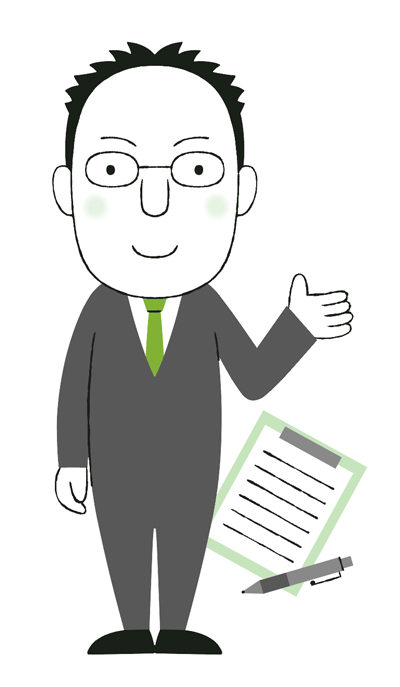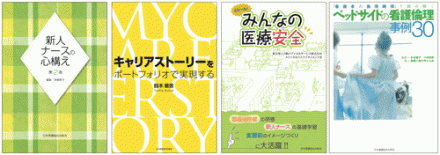訪問看護ステーションの管理者が地域のニーズを的確に捉えて健全
な経営を行い、その理念を実現するために行うべきことを、公認会
計士・税理士・看護師の資格を持つ筆者が解説します。
1時間でできるエリアマーケティング(後編)
渡邉 尚之
前回は、エリアマーケティングの必要性や資料活用のポイントなどについてお伝えしました。
簡単におさらいをすると、エリアマーケティングは新規事業立ち上げのための需要予測のみならず、すでに事業を展開している場合でもその地域の需要・方向性等を踏まえて経営戦略を検討する上で必要です。また、それに活用する資料は公表されている官公庁の統計資料や業界団体のデータを活用すると効率的であるという内容でした。
さて、皆さんは自身の地域の人口や高齢化率、人口当たりの訪問看護ステーション数・1ステーション当たりの従事者数、実際の利用者数などをご存知でしょうか? 今回はこれらの調査と活用方法を示したエリアマーケティングの実践例を紹介します。