
看護師のバイブル『看護の基本となるもの』を著したアメリカの看護理論家ヴァージニア・ヘンダーソンは、弊社ととてもゆかりが深い方です。そこで弊社では、ヘンダーソン氏の没後20年(2016年)、生誕120年(2017年)を記念して、著作3冊と映像DVDを収めたコレクションBOXを刊行しました。ここでは山あり谷ありだった制作秘話(?)をご紹介します。

看護師のバイブル『看護の基本となるもの』を著したアメリカの看護理論家ヴァージニア・ヘンダーソンは、弊社ととてもゆかりが深い方です。そこで弊社では、ヘンダーソン氏の没後20年(2016年)、生誕120年(2017年)を記念して、著作3冊と映像DVDを収めたコレクションBOXを刊行しました。ここでは山あり谷ありだった制作秘話(?)をご紹介します。
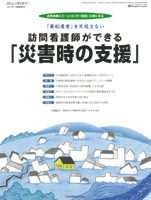 「災害への備えについての本はあるけれど、災害の発生時・発生直後に看護がどうかかわればよいかが書かれたものがあまりない!」と思っていた佐々木裕子さんの企画提案から『「コミュニティケア」2017年11月臨時増刊号・訪問看護師ができる「災害時の支援」』が誕生しました。ここでは佐々木さんに本書のおすすめポイントをうかがいます。
「災害への備えについての本はあるけれど、災害の発生時・発生直後に看護がどうかかわればよいかが書かれたものがあまりない!」と思っていた佐々木裕子さんの企画提案から『「コミュニティケア」2017年11月臨時増刊号・訪問看護師ができる「災害時の支援」』が誕生しました。ここでは佐々木さんに本書のおすすめポイントをうかがいます。
福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。
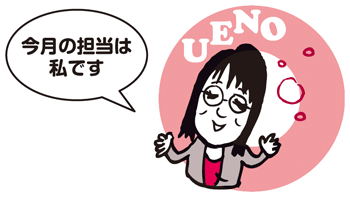
AIが活躍する新たな社会とは
文:上野まり
最近、「AI」(Artificial Intelligence:人工知能)という言葉を頻繁に目や耳にするようになりました。AIの定義はあいまいですが、コンピューターを進化させて人工的につくられた人間と同様の知能のことです。目的を設定すると多大な情報を統合して分析し、その結果に基づいて行動するため、最近ではプロの棋士と将棋の対戦をしたり、車の自動走行に活用したり、時には人間の能力を超える力をさまざまな場で披露し、とても頼もしい存在になりつつあります。