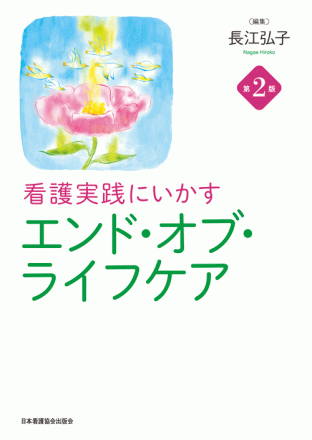
人生100年時代といわれる現在、生きることを身近な大切な人とともに考え、その人の生きるを支えるエンド・オブ・ライフケアの必携書籍が改訂されました。編者・長江弘子さんと執筆者・内田明子さんに本書の読みどころや込められた思いをうかがいました。
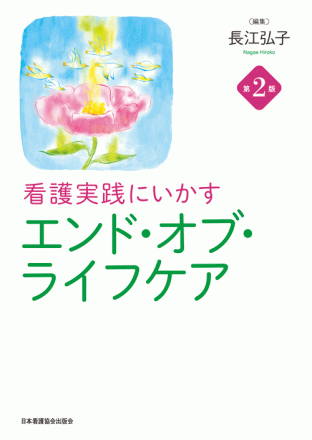
人生100年時代といわれる現在、生きることを身近な大切な人とともに考え、その人の生きるを支えるエンド・オブ・ライフケアの必携書籍が改訂されました。編者・長江弘子さんと執筆者・内田明子さんに本書の読みどころや込められた思いをうかがいました。
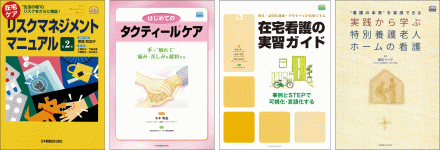
訪問看護師や特別養護老人ホームの看護職など「在宅・施設」領域で頑張っているナースのための月刊誌が『コミュニティケア』です。その『コミュニティケア』で人気のあった臨時増刊号や連載記事をまとめて書籍にしたのが「C.C.MOOK(Community Care MOOK)シリーズ」。今月は「在宅・施設の看護」の知識を学ぶのにもってこいの4冊をご紹介します。
福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。
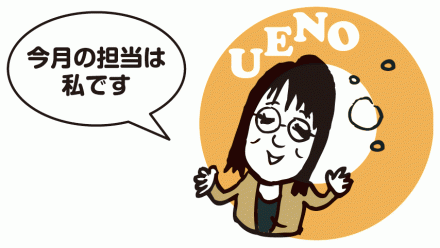
SDGsについて考える
文:上野まり
最近は、新聞をとらない人が増えているようです。私は子どものころから新聞がある生活を送っており、大人になってからは、仕事に行く前に朝刊の大きな見出しの記事や天気予報に目をとおし、帰宅してから朝刊・夕刊をざっと斜め読みすることが習慣になっています。そんな私にとって新聞のない生活は考えられません。新聞はさまざまな情報を毎日提供してくれて、時折、とても興味深い記事に出会うことがあります。先日もそんな記事を見つけました。
SDGsを自分事として捉える
仕事で公衆衛生関連の情報をインターネットで調べていたときに、「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals、以下:SDGs)を知りました。2030年までに誰もが住みやすい世界をつくろうと、2015年に国連で採択されたものです。
訪問看護ステーションの管理者が地域のニーズを的確に捉えて健全
な経営を行い、その理念を実現するために行うべきことを、公認会
計士・税理士・看護師の資格を持つ筆者が解説します。

給与の正しい知識を
身につけよう(前編)
渡邉 尚之
皆さんは、自分がもらう、またはスタッフに支払う給与について、どのような認識を持っていますか? 訪問看護ステーションの管理者が給与についての知識を習得する機会は、あまり多くありません。しかし、給与の支払いは経営者・管理者とスタッフの信頼関係を維持する上で大変重要な要素です。そのため、給与計算を社会保険労務士などに委託しているステーションであっても、経営者・管理者は給与についての基本的な知識を理解しておくことが必要です。
福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。

介護現場における
ヒヤリハット報告をめぐって
文:鳥海房枝
介護事故を減らすことを目的に、多くの介護現場でヒヤリハット報告書の提出が奨励されています。その根拠とされているのが、1:29:300のハインリッヒの法則です。これは重大な事故1件の背景には、軽微な事故が29件あり、さらにその背景には事故寸前の案件が300件あるという、米国の損害保険会社の社員・ハインリッヒが提唱した労働災害における経験則です。これを基に「ヒヤリ」としたら、あるいは「ハッ」としたら報告書を作成することで軽微な事故や事故寸前の案件に目を向け、重大な事故の発生を予防しようとする考え方です。