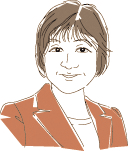古川 久敬さん (ふるかわ・ひさたか)
日本経済大学大学院経営学研究科教授、九州大学名誉教授 教育学博士 1972年九州大学大学院教育学研究科修士課程修了。1972〜86年日本国有鉄道 鉄道労働科学研究所社会心理研究室。1980〜81年米国ニューヨーク州立大学(ビンガムトン校)経営管理学部 客員研究員。1986〜2000年九州大学教育学部 教育学研究科 助教授、教授。 2000〜2012年九州大学大学院人間環境学研究院 教授。2003〜2012年九州大学ビジネススクール教授併任。2012年より現職。



.jpg)