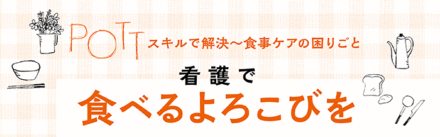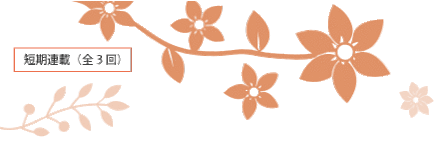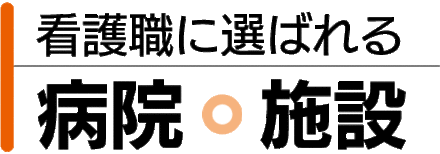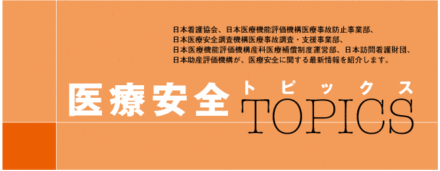誤嚥性肺炎や窒息のリスクが気になる食事ケア。
でも、嚥下障害と姿勢アセスメントの基本的な知識と技術があれば、利用者が安全に食べることを継続して支援できます。
筆者らが提唱するPOTT プログラムの基本スキルを基に、現場で遭遇する問題の原因やケアの方法・根拠を紹介します。
執筆
定松 ルリ子 さだまつ るりこ
株式会社ケアライフエナジー
訪問看護ステーションアスレ
摂食嚥下障害看護認定看護師
知りたいこと その❽
誤嚥性肺炎を繰り返す人のポジショニングは
どうすればいい?
ポジショニングによる
誤嚥性肺炎の予防
食べ物や唾液などが声帯を越えて気管内に流入することを誤嚥と言います。誤嚥性肺炎は誤嚥を繰り返すことで生じる肺炎で、誤嚥物による侵襲が多くなり、炎症に対する免疫力・抵抗力が低下することにより発症します。誤嚥性肺炎による日常生活や社会活動の制限は、精神的なストレスやQOLの低下にもつながってきます。
看護ケアにおける誤嚥性肺炎の再発予防は、嚥下訓練や口腔ケアだけでなく、生活援助の視点に立った多角的な対応が必要となります。食事のポジショニングはその一例で、以下のような予防効果が期待できます。