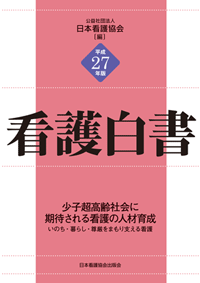
今年度の看護白書は4章構成から成り、地域包括ケアシステムで活躍できる人材づくりについて、多角的に考察し、提案する書となっています。資料編を除く全体の内容を紹介します。
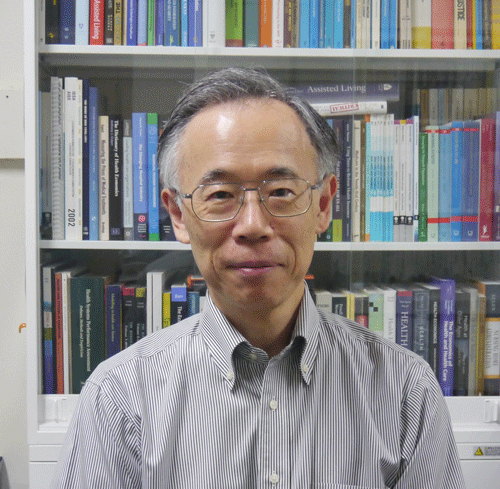
尾形 裕也さん(おがた・ひろや)
東京大学政策ビジョン研究センター特任教授
(九州大学名誉教授)
1952年兵庫県神戸市生まれ。東京大学工学部・経済学部卒業後、1978年厚生省入省。年金局、OECD事務局(パリ)、厚生省大臣官房・保健医療局・保険局・健康政策局課長補佐。1989〜2001年、在ジュネーブ日本政府代表部一等書記官、千葉市環境衛生局長、厚生省看護職員確保対策官、国家公務員共済組合連合会病院部長、国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長を歴任。
2001〜2013年、九州大学大学院医学研究院教授。2013年より現職。
地域包括ケアシステムの構築をめざす制度改革の中で、質の高い看護を提供し、地域で選ばれる医療機関となるためには、看護管理者がその経営に参画することが重要です。医療制度の概要と経営理論をわかりやすく解説した新刊『看護管理者のための医療経営学 第2版』の著者・尾形裕也氏に、本書で解説している内容と看護管理者への期待などについてうかがいました。
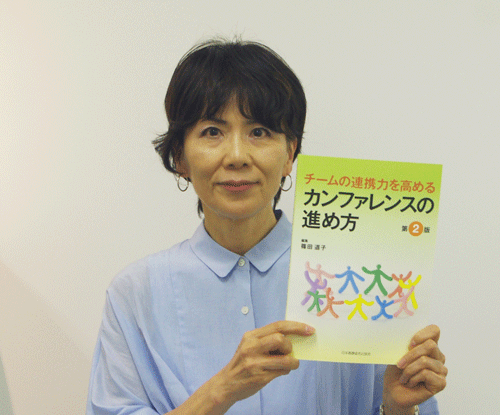
篠田 道子さん(しのだ・みちこ)
日本福祉大学社会福祉学部 教授
看護師免許取得後、筑波大学大学院教育研究科
リハビリテーションコース修了。筑波大学附属病院、
東京都養育院、シルバーサービス会社勤務を経て1999年に日本福祉大学赴任、2008年より現職。2011〜2012年、慶應義塾大学大学院経営管理研究科訪問教授。

地域包括ケアシステムが推進される中、患者・家族を含めた多職種・他機関が参加するカンファレンスが連携・協働の重要なツールとなっています。豊かなカンファレンスを運営するための基本技法を丁寧に解説した『チームの連携力を高めるカンファレンスの進め方 第2版』の編著者・篠田道子さんに、改訂のポイントなどをうかがいました。
岡本 充子(おかもと・じゅんこ)さん
近森会グループ統括看護部長
桑田 美代子(くわた・みよこ)さん
青梅慶友病院看護介護開発室長
戸谷 幸佳(とや・さやか)さん
特別養護老人ホームくやはら
西山 みどり(にしやま・みどり)さん
有馬温泉病院ケア開発室室長
山下 由香(やました・ゆか)さん
東太田リハビリ訪問看護ステーション
吉岡 佐知子(よしおか・さちこ)さん
松江市立病院地域医療課課長
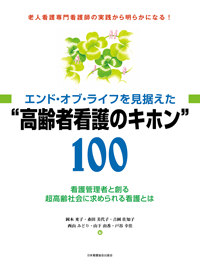 高齢者看護のスペシャリストである“老人看護専門看護師”は、看取りを見据えた看護の“キーパーソン”として期待が高まっています。そのような中、32人の老人看護専門看護師が自らの実践を基に“高齢者看護のキホン”を導き出した書籍
高齢者看護のスペシャリストである“老人看護専門看護師”は、看取りを見据えた看護の“キーパーソン”として期待が高まっています。そのような中、32人の老人看護専門看護師が自らの実践を基に“高齢者看護のキホン”を導き出した書籍
『エンド・オブ・ライフを見据えた“高齢者看護のキホン”100』が発刊されました。

東京海上日動メディカルサービス株式会社
メディカルリスクマネジメント室の皆さん
同室は、病院やクリニックで発生する事故やインシデントを受け、コンサルティングや研修を通してサポートする組織。看護学、薬学、心理学などの視点で医療現場から寄せられるさまざまな相談に応じ、医療安全の取り組みを支援している。
『病院で働く みんなの医療安全』をご執筆いただいた、メディカルリスクマネジメント室(MRM室)の皆さんに、本書のおすすめポイントについて伺いました。