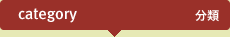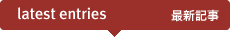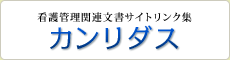訪問看護パリアン看護部長・川越博美氏のエッセイ「訪問看護師ががん患者になって考えた 死にゆく人に寄り添い支えること」が大幅加筆の上、本になりました。闘病、介護・看取り、まちづくり……当事者として向き合ってきた著者ならではの、真摯な言葉に溢れた1冊です。
■連載に大幅加筆!
小社発行の月刊誌「コミュニティケア」は、主に地域ケア・在宅ケアに従事する専門職の方々を対象とした月刊誌です。本書は、「訪問看護師ががん患者になって考えた 死にゆく人に寄り添い支えること」というタイトルで、同誌2013年9月号〜2015年12月号に連載されたエッセイがベースとなっています。
書籍化に当たっては、全28回分をテーマで分類し、再構成。連載で書かれたエピソードの「その後」も交えながら、大幅加筆を行いました。連載時の読者の方々にも、新たな気持ちでお読みいただけますし、1冊にまとまったことで、著者の思いがより強く伝わるものとなっています。
■当事者ならではの、説得力のあるメッセージ
著者は、制度化以前から訪問看護に携わり、自宅で最期の時間を過ごす人々(主に、末期のがん患者)と向き合い続けてきました。一方で、看護大学で教鞭を執り、さまざまな公的な職務も歴任。
現在は、「訪問看護パリアン」(東京都墨田区)の看護部長として現場で奔走しながら、他職種や市民と協働し、「誰もが当たり前に家で老いて死ねる地域」づくりに取り組んでいます。
そうした中、タイトルにも示されているように大病を患い、さらには、義母・実母を自宅で介護し、看取るという経験も……。
医療職、患者、介護者。当事者としての、説得力のあるメッセージに溢れています。
■生き続けたい。でも、かなわないかもしれない
―「患者になって考えた」より
働き盛りに病の宣告を受け、仕事や生活を中断し、治療に専念することを余儀なくされる。2人に1人ががんになるといわれる今の時代、誰にとっても他人事ではない事態ではないでしょうか。
すべての職務を投げ打たねばならない心痛、激烈な副作用の苦しみ、周囲からの理解や思いやりへの感謝、うれしかったお見舞い、そして改めて考えた、今後の生き方……。第1章では、そうした自身の闘病経験が綴られます。
■自分はどう生き、どう最期を迎えたいのか
―「訪問看護の現場で考えた」より
現場で出会う患者たちの事情はさまざま。一人暮らしで経済事情もよくない、家族と同居していても関係が良好ではない……それでも、住み慣れた家で最期まで過ごしたい。
そんな彼らの希望をかなえるために必要なこととは何か。家族、そして遺族にはどのように対応し、支えるのか。
第2章・第3章では、豊富な事例を基に、自身の実践を紹介します。「訪問看護パリアン」の1日を追った箇所もあり、「訪問看護師とは、日々、どのような業務を行い、どのような役割や使命を担っているのか」といった、具体的な姿が描き出されます。退院支援などの場面における、円滑な連携のヒントとしてもお読みいただけるのではないでしょうか。
さらにここでは、著者自身が家族を自宅で介護し、そして看取った経験についても語られます。自身の生活を営みつつ老親の行く末を思うこと、きょうだいとの関係、住み慣れた地域から親を離してしまうことへの葛藤……。読む側も、自身の状況と重ね合わせ、これからの生き方を考えるきっかけとなる箇所です。
■余命が限られている人に、今必要なことは何なのか
―「これからの在宅ケアを考える」より
そして第4章・第5章では、よりよいケア提供のために、病院や他職種とどのように連携していけばよいのか、実践を通して考えたこと、現状の制度や仕組みに関する問題提起や提案が示されます。病院・在宅を問わず、ケアに当たる専門職として、自分たちに何ができるか、ともに考えていきましょう、という願いが込められています。
また、ここでは、他職種や市民との協働による、まちづくりの取り組みについても紹介。
住み慣れた場所で、誰もが当たり前に老いて死にゆくことができ、地域の人皆でそれを支え合うまちをつくりたい。患者たちとの対話を通して抱いた思いを具体的な形とするべく、さまざまな立場の人とともに考え、行動を起こしていきます。
その中から生まれた、在宅ケアを支える「小さな宿泊所」の構想。在宅での療養を選んだ人も、家で過ごし続けることに不安や葛藤、疲れを感じることがある。そんなとき、気軽にひと休みできる「ひなん所」のような部屋があれば、患者も家族も、より安心していられるのでは……と考案されたものです。
制度上の困難さや、運営面での課題を検討しながら、地域に開かれた医療の場、ケアし合う場として、小さいながらも暖かな場を、ボランティアとともにつくろうと、準備を進めている最中とのこと。この号が出るころには、なんらかの形で動き出しているはずです。
川越博美 著
●四六判・296ページ
●定価(本体1,600円+税)
ISBN978-4-8180-2032-0
発行 日本看護協会出版会
(TEL:0436-23-3271)
〈主な内容〉
患者になって考えた(人生の危機は突然に/患者として思ったこと/他)
訪問看護の現場で考えた
—「最期まで家で過ごす」を支える(訪問看護師の使命/一人暮らしの最期を看取る/他)
— 在宅ケアは家族ケア(私の介護経験/見えない家族/「悲しみをともに悲しむ」遺族ケア/他)
これからの在宅ケアを考える
— 連携の現状に感じるもどかしさ(退院時のタイムラグ/他)
— 誰もが家で老いて死ねるまちに(「家で死ねるまちづくり」/他)
-「看護」2017年4月号「SPECIAL BOOK GUIDE」より –