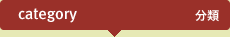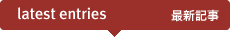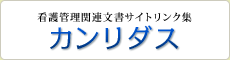語りは重層的です。ある人のものがたりが語られるとき、記憶される経験が時を経て感じ方や考え方を変え、時にその人のものの見方を新たな視野へ、次の成長へと導いていきます。
嶋守 さやか しまもり さやか
桜花学園大学教育保育学部 教授
金城学院大学大学院文学研究科博士後期課程修了、社会学博士。著書に『孤独死の看取り』『虐待被害者という勿れ 虐待サバイバーという生き方』(新評論)などがある。2025年11月、研究テーマ「生ききるケアを生きる──よい訪問看護とは何か」を基に書き下ろした、『訪問看護ものがたり ご在宅の力』(同)を刊行。
看護とことば「ちょっと、やっぱり」
看護師たちの“語りの揺れ”
昨年の11月に『訪問看護師ものがたり ご在宅の力』を上梓しました。6人の訪問看護師へのインタビューをもとにしたこの書籍には、「人として生ききる」ことを最期まで諦めない人々に「沿う」ことで生まれた訪問看護師の語りが収録されています。社会学者として現象学的質的研究に取り組む私にとっては、一人の語り手によって語られる内容の順序や繰り返し、癖や言い淀みなどの“語りの揺れ”が、分析のための重要な手がかりとなります。それらを丁寧に追うことで、一人ひとりの看護師によって生きられる経験世界のかたちが見えてくるのです。
本稿では、そんなインタビューの中で、ある病棟の看護師が自身の看護についてどのように語ったのかを示したいと思います。その看護師をここではEさん(50歳代)と呼びましょう。彼女が過ごしてきた病棟での日常で何を目にし、どのように心に留め、自身の看護観に連動させていったのか。それを「ものがたり」、つまりEさんのナラティブ分析として描いていこうと思います。
「ちょっと、ちょっと、やっぱり」
Eさんは、私が住む県にある病院の外来化学療法センターで看護師長を務めています。ある看護師の方がEさんのことを、「看護の本筋がそこにある」けれど「ガチガチでない」人柄であり、自身が影響を受けた「よい看護師」だと言って、紹介してくれました。そしてより詳しく話を聴くうちに、「もしかして」と、ふとあることに気づきました。4年前、私はこの病院で抗がん剤治療を受けました。医師にがんと宣告された際に同席していたのが、まさにEさんだったのです。
Eさんの語りには、「ちょっと、ちょっと、やっぱり」という、特徴的な言葉のリズムが見られます。この「ちょっと」の語られ方から、言葉は文脈で読んでこそ意味をなすのだなと感じます。文脈ごとに「ちょっと」は表情を変えて現れ、語の意味、語りの構造を変動させるのです。看護師をめざすまでの語りの中で、その語の使われ方を注意深く追っていくことで、Eさんの看護師への憧れが夢の実現へと思いの濃度が深まっていくプロセスを解釈できます。「ちょっと」と語られるほのかな思いが「やっぱり」という確認になっているのです。
→続きは本誌で(コミュニティケア2026年冬号)