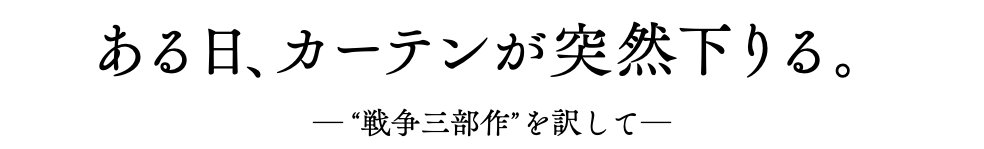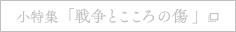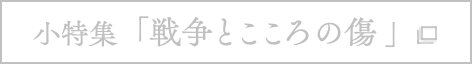内戦で爆撃を受けたシリアの街を避難する親子。(2015年)
ジャーナリストが命がけで伝えようとしたこと
シリアの現状を世界に伝えるためにその国へ赴き、捕虜となり殺されたジャーナリストは、2017年の時点で94人に上っています。日本人ジャーナリストの山本美香さんが2012年に亡くなったこともいまだに忘れられません。銃弾に倒れるその姿がテレビで繰り返し放映されたせいでもあります。同じ女性ジャーナリストとして、シリア国内の暴力と貧困の状況、過酷な状況で人の命を救おうと奮闘する医師や看護師の姿を伝えているのが、『シリアからの叫び』です。
独裁政権を批判した学生がどのような拷問を受けたか、政府軍と反政府軍の戦いがどのような経緯で泥沼化していったか、「アラブの春」から始まった民主化運動がシリアでどのような結末を迎え、都市と遺跡がどのように破壊されていったのか。これは、遠い中東の独裁制国家だけに起こりうる話ではありません。独裁的な政権が軍隊を動かし、市民の口を封じると国は人々はどうなるのか、医療や教育はどうなるのかといった問題は、どこの国家に所属していようと真剣に考えなければならないものです。
『シリア・モナムール』(シリア・フランス合作、2014年)というドキュメンタリー映画があります。シリアに暮らしている大勢の人々が、自分たちの置かれた現状を携帯電話で撮影し世界に向けて発信した1001の映像を、シリア人監督が一つにつなぎ合わせた作品です。死の気配が立ち込めるその衝撃的で鮮烈な映像は、観ている者に自分がどこにいるのかわからなくなるほどの強い印象を残します。
『シリアからの叫び』が伝える過酷な現実にもまた、読んだ者はみな言葉をなくすしかありません。わたし自身、本書の翻訳に関わることで精神的な衝撃を受けました。書かれた内容自体の酷さはもちろん、訳している自分が置かれている場所と、シリアの人々を取り巻く環境があまりにもかけ離れていたからです。彼らの置かれた状況の痛ましさに対する自身の無力さに、なす術もありませんでした。
しかし、そうした無力感に最も苛まれているのはシリアの医師や看護師たちです。2015年、政府軍と反政府軍が歴史あるアレッポの町をどちらが征圧し支配するかを賭けて戦っていました。そしてそこに暮らす市民たちは、銃撃と爆撃で死傷し、町が戦場になってからは、そこから逃げる手段がありませんでした。
アレッポでは赤ん坊が死ぬのはあっという間だ。十分もしないうちに死んでしまう。医師クレハドと看護師が手当をしていた。必死になってその小さな命を生かそうとしていた。難しくはない呼吸器の感染症で病院に来たのだった。ひどい怪我などしてなかった。銃で撃たれたわけでも、爆弾の破片で動脈が切断されたわけでもなかった。
医師たちがその子の上に群れ集まっていた。まるでオリンピック競技を見ているみたいだった。クレハドの顔が緊張と競争心に満ち、そのそばにはヒジャブを被ってスニーカーを履いた女性看護師たちがいた。彼らの競争相手は時間だった。死だった。
だが、彼らは負けつつあった。(略)赤ん坊は死んだ。
赤ん坊が死んだとき、百万人が住むアレッポにはたった三十一人の医師しかいなかった。クレハドは経営者側の要請で(略)研修医からいきなりこの病院を率いる医師となった。(略)
──『シリアからの叫び』187〜188頁
政府軍は病院を狙って爆撃を仕掛けてきます。そこに市民が集まっているために、効率よく殺せるからです。そのため、病院は1週間おきに場所を移さなければなりません。戦時中に公共の場を攻撃するのはジュネーブ条約違反です。でも、そのような条約に関心を向ける者はひとりもいません。「ジュネーブ条約を気にしながらおこなわれた戦争があっただろうか」と著者ジョヴァンニは書きます。そして若き医師クレハドは「問題はあの子が呼吸器感染で死んだことです」と、無念さを滲ませます。
呼吸器感染は、ほかの国では抗生物質の大量投与をすれば何の問題もない。深刻な病気でもないし、治療ができないものではない。戦争中でなければ。
赤ん坊の両親は、命が危ぶまれるまで赤ん坊を病院に連れてこなかった。あまりにも大量の砲弾が町に降ってくるので、家から病院に行く途中でロケット弾で殺されるのではないかと思ったからだ。
クレハドが求めているのは救急車だ。一台四万ドル。それがあれば負傷者や重病患者を早く病院に運び込める。「贅沢な望みじゃないでしょう? 救急車一台ですよ」と彼は言った。
──『シリアからの叫び』189〜190頁
多数の難民がトルコを経てヨーロッパに向かったことから国際問題になったのは2015年のこと。2012〜2019年までの間に犠牲となった人はおよそ37万人。560万人が難民として周辺の国に逃れ、家もなく粗末なテントで難民生活を送っていると言われています。難民キャンプではレイプ事件も多く、女性はさらに危険な立場に置かれています。
当たり前の日常は、いとも簡単に失われる
これら「戦争三部作」を訳そうと思った理由は、『帰還兵はなぜ自殺するのか』を出版した直後、国会で「安全保障関連法」を強行採決した2015年に、政権が戦争ができる国へと舵を切ろうとしているのを目の当たりにし、若者が戦争に駆り出されるかもしれない、という危機感を持ったからです。戦争体験者が減っていき、語り継ぐことが難しくなってくれば、その悲惨さを実感として感じられなくなり、国のために死ぬことを理想化したり美化しようとする人々が登場してきます。戦争がもたらすリアルな悲惨さは物語で描ききれるものではありません。『兵士は戦場で何を見たのか』『シリアからの叫び』を出版することで、戦場とはどういうところなのか知ってもらいたいと思ったのです。
このようなノンフィクションに必要なのは読者です。長い時間をかけ、命を危険に晒してまで伝えようとしたジャーナリストの言葉を受け止める人々です。そうした意味で、この三部作は医療従事者はもちろん、教育や政治に携わる人々、保護者のみなさん、そしてなによりも女性たちに読んでいただきたいと思っています。
ジャニーン・ディ・ジョヴァンニはこう書いています。
普通の人々にとって、戦争は何の前触れもなく始まる。娘たちのために歯医者の予約をし、バレエのレッスンを手配していたのに、突然カーテンが下りる。ATMは機能し、携帯電話も繋がり、日々の習慣は続いていたのに、突然、何もかもが停止する。
バリケードが築かれる。徴兵がおこなわれ、近隣では自警団ができる。政府高官が暗殺され、国は混沌に向かっていく。父親が消える。銀行は閉鎖され、富も文化も生活も一気に消滅する。(略)
戦争がどれくらい速く動いていくか、わたしは知っている。わたしが取材したあらゆる戦争——ボスニア、イラク、シエラ・レオネ、リベリア、チェチェン、ソマリア、コソボ、リビア、さらにもっと——において、普通の状態から極端に異常な状態へとすべてが変わっていく瞬間というのは、まったく似た特徴がある。(略)
1992年4月の初旬、サラエヴォにいる友人が、ミニスカートとハイヒール姿で勤め先の銀行へ歩いていくと、戦車が通りをやってきた。そして発砲が始まった。彼女は大きなごみの缶の後ろで身を屈め、震えていた。彼女の生活は一変した。数週間のうちに、彼女は自分の赤ん坊の安全を願い、異国の見知らぬ人に預かってもらうために、バスに乗せて送り出した。そして何年も自分の子に会えなかった。
こうして戦争は始まる。
──『シリアからの叫び』219〜221頁
ふるや・みどり
翻訳家。主な訳書に、エドワード・ケアリー『おちび』(最新作:2019年11月)、〈アイアマンガー三部作〉『堆塵館』『穢れの町』『肺都』(以上東京創元社)、近著にデイヴィッド・マイケリス『スヌーピーの父 チャールズ・シュルツ伝』(亜紀書房、2019年9月)。その他、ラッタウット・ラープチャルーンサップ『観光』(ハヤカワepi文庫)、イーディス・パールマン『双眼鏡からの眺め』(早川書房)、M・L・ステッドマン『海を照らす光』(早川書房)、ダニエル・タメット『ぼくには数字が風景に見える』(講談社文庫)など多数。