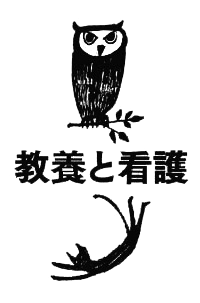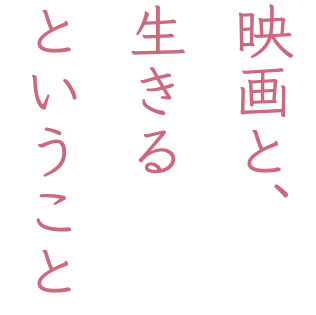
月刊「看護」好評連載「映画と、生きるということ」特別編
執筆者3人によるリレーエッセイ。おすすめの映画を1作品取り上げ、その魅力を伝えるとともに、さまざまな場面・セリフ・背景にあるものから、「生きるということ」について考えたこと・感じたことを語ります。
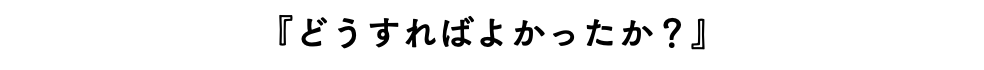

©五十嵐大/幻冬舎 ©2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
-動画配信サービスにてレンタル配信中-
監督:呉美保
原作:五十嵐大
編集協力:秦岳志
配給:ギャガ
出演:吉沢亮、忍足亜希子、今井彰人、ユースケ・サンタマリアなど
2024年/日本/105分
映画のあらすじ
宮城県の小さな港町で、耳のきこえない両親の元に生まれた男の子、大(だい)。耳がきこえる大は、いつの間にか手話を覚え、母と買い物に行くときには通訳をしてみせ、店の人に「偉い」と褒められます。しかし、小学校に入学し、思春期を迎えるにつれ、周囲から特別扱いされることや、「普通」の親と同じように三者面談で話し合ったり、将来の相談ができない両親に対して、いら立ちを募らせるようになりました。
「自分だけこんな家に生まれたのが不幸」「耳がきこえない親を持つかわいそうな子だというレッテルを張られたくない」と、大は、逃れるように東京へ。そこでは、苦労をしながらなんとか職に就き、そして、偶然に知り合った耳のきこえない人との交友関係も生まれます。やがて、耳のきこえない両親に育てられた自分の生い立ちや、母親との関係を冷静に振り返るようになっていきます。

text by 渡辺 裕子
わたなべ・ひろこ / 看護師。NPO法人日本家族関係・人間関係サポート協会 理事長。長年、家族看護の発展に注力し、
近年は「かぞくのがっこう」の開講など市民にも家族看護のエッセンスを伝え、広げている。趣味は鉛筆デッサン。
2025.5.22
※一部本編の内容に触れているところがありますので、あらかじめご了承ください。
子と親の間に引かれたバウンダリー
舞台は1980年代の宮城県の港町。耳のきこえない両親の元に、きこえる赤ちゃんが生まれ、両親、祖父母、叔母共ども安堵するシーンから物語は始まります。昭和を感じさせる懐かしい家のたたずまい、方言が交じる祖父母の遠慮のない会話、耳がきこえない母親の子育ての困難と喜びがとても丁寧に描かれ、前半はほほえましく明るいトーンで進行していきます。
それが徐々に変化を見せるのは、大が中学生になったころから。そして、一つのクライマックスは、受験に失敗した大が、母親にひどく感情をぶつけるシーンです。
「こんな家、生まれてきたくなかったよ!みんなお母さんのせいだよ!障がい者の家に生まれて、こんな苦労して、バカみたい!」
青ざめた表情であぜんと立ちすくむ母親を残して階段を駆け上がる大。「友だちはみんな相談してるよ。お母さんは無責任なんだよ。何も助けてくれなかったじゃないか!」という言葉も、母親の胸に突き刺さっていたことでしょう。

©五十嵐大/幻冬舎 ©2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
このとき、大が望んでいたのは、進路や進学先について、とことん話し合える両親、困ったときにはアドバイスもしてくれる友だちの家のような「普通の親子」だったのでしょう。しかし、両親ともにろう学校を卒業し、受験の経験もない母親には荷が重かったに違いありません。そんな頼りない「無責任な母親」のせいで、自分が不合格になったのだと大は唇を震わせ、にらみつけました。そして、考えてみれば、そもそもこの家に生まれたこと自体が不幸の始まりだったと大は詰め寄ります。この瞬間、母親は動くこともできず、もちろん、言葉もないままでした。
画面いっぱいに広がる緊張を振り切るように、すぐにシーンは入れ替わり、母親が父親の職場で帰りを待つ場面となりました。家まで自転車を押して歩く父親に母親も寄り添って歩き、「障がい者の家に生まれたくなかったって……。さすがにキツイね」と手話でつぶやきます。父親は、「まぁ、でも、それぞれどんな家にも悩みがあると思うよ、たぶんね」「大は、大丈夫だよ」と応えるのです。
父親の発言は、「障がい者の家に生まれたくなかった」と息子に言われ、障害を持つ自分を責める母親を、「こういうことはどの家族にもあること」と普遍化したものでした。ろうの親を持ちながら、自分は耳がきこえるという境遇の子どもはコーダ(Children of Deaf Adults:CODAs)と呼ばれますが、本作はコーダの青年の物語のみに閉じられたものではなく、広く、思春期から青年期の子どもと親の物語として考えることができるのではないでしょうか。というのも、映画を見ながら、筆者自身の思春期や両親の記憶が呼び覚まされ、また、息子の一言に怯むまいと唇を噛んだ瞬間がよみがえってきたからです。
思春期・青年期は、親の世界で育てられてきた自分から、何とか自分自身の世界を見つけようともがき、格闘する時期です。その過程で、「親のようにはなりたくない」「親の生き方なんか絶対イヤだ」と批判することが、子どもにとって「新たな自分の世界」を見いだす原動力になることが少なくありません。子どもからの批判によって親は身を切られるようなつらさを感じることもあるでしょう。だとしても、子どもを信じ、子どもなりの奮闘を見守ることが親の仕事ではないでしょうか。親も不安にかられる時期ですが、子どもとの間に一定のバウンダリーを引いて、少なくとも、自分の不安を子どもに投影しないようにすることが親の課題でもあります。
真の関係性を築くために必要なプロセス
さて、父親が倒れ、東京から初めて実家に戻った大。このとき、実に8年の月日が流れていました。大は、東京で、生きていくことの厳しさ、世の中の現実を知ると同時に生きていく自信のようなものも身につけました。また、耳のきこえない人との交流を通じて、知っているようで知らなかった「ろう者」の世界を知り、両親を客観的に、そしてより深く理解することができたようです。
実家はいつもの日常が流れ、台所に立つ母親はあの日のままです。夕食の準備をする母親に、突然大が手話で「ごめん」と言うシーンがありました。「何が?」と不思議そうにする母親。「いろいろ」と大。「こんな家に生まれたくはなかった」と激しく反発していた大が、一回りも二回りも成長し、母親と「再会」を果たした瞬間でした。

©五十嵐大/幻冬舎 ©2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
人が大人になっていくためには、ある場合において、本人にも親にとってもかなりの痛みを伴うことを思い出させてくれる作品でした。それでも、その過程で、親とは異なる世界を自分の力で生きてみることはとても尊いことではないでしょうか。親を傷つけ、その経験を思い出して罪悪感に苦しむこともあるでしょう。遠く離れて子を思い、親を思って涙することもあるでしょう。それでもなお、一度精神的な意味で親を捨て、子に捨てられる過程なしには、得られない真の関係性があると思うのです。親は、反発し、離れていく子どもに戸惑う時期ですが、子どもにしがみついたりせずに、子どもの「親を捨てる力」を奪ってはならないのではないでしょうか。
「親とともに生きた世界」と「自分が築いた世界」、誰もがこの二つの世界を内在化し、再統合して自分の世界を生きていくのでしょう。本作品は、障害のある両親と健常な青年の物語を通して、普遍的な親子のあり方を語りかけているような気がしました。
自らの思春期にタイムスリップし、大に自分を重ねる方も多いと思います。そして今、思春期の子どもの子育てに悩んでいる方にもぜひ観ていただきたい映画です。