文・西尾美登里/挿画・はぎのたえこ
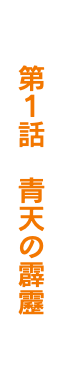
──太郎は飛ぶように車を降りた。扉前に立っていた守衛が西野先生に「ご家族の方ですか」と尋ねている。太郎は西野先生にひょっこりと頭を下げ、小走りで救命センターの中に入っていく──(本文より)
特集:ナイチンゲールの越境 ──[ジェンダー]
< ● ●
僕、未成年なので……。
そこから九西大学のゲートまで、一度も信号にかからなかった。救命センターのゲート前にいる守衛に声をかける。
「救命に家族が運ばれたと聞いてきました。どこに車をつければいいですか」西野が尋ねると、守衛よりも前に太郎が告げた。「突き当たって左のロータリーに入ってください。駐車場の手前の分岐を左いくと駐車場があるけど、まず救命センターの入口前までお願いします」
「そうか。お前のお母さん、ここの看護師やったもんな」
青いボードに赤い文字で「救命センター入り口」と書かれた場所には、一台の救急車が到着していた。どうやら患者はすでに搬入されたらしく、サイレンが鳴らないまま警光灯だけがクルクルと回っていたが、その警光灯もすぐにオフになった。救命センターから空のストレッチャーが搬出され、救急隊員がブランケットを畳んでいる。西野先生はその救急車から2メートルくらい後方に車をつけた。
太郎は飛ぶように車を降りた。扉前に立っていた守衛が西野先生に「ご家族の方ですか」と尋ねている。太郎は西野先生にひょっこりと頭を下げ、小走りで救命センターの中に入っていく。
通路左手にある受付には、オレンジ色のストラップに緑色のネームホルダーを首から下げ、紺色のベストを着た男女3人がパソコンの前で黙々と作業をしていた。幼い頃から何度も来たことがあるこの場所。小学校の低学年だった頃、太郎は学校が終わると母が勤務するこの病院へやって来て、待合室をいくつも探検し母親の仕事が終わるのを待った。
相変わらずこの救命センターの待合室は待人が少ないが、前を行き交う人の数は多く、そのわりに静かである。
太郎が宿題をするための「穴場」は、白く光るまっすぐな廊下の途中を右に曲がった場所にある。扉を押すと、左手には公衆電話を撤去したのだろう小さな白い棚が残っていた。ノートを広げたりランドセルを置く場所として重宝したのを憶えている。あれから10年ほどたつがあの頃のままだ。以前から見慣れた場所のはずなのに、なんだか初めて来るような感じもする。不思議な気持ちで足元がふわふわしていた。
「すみません。東尾といいます。母が運ばれたと聞いて来ました」
受付と書かれた窓際に座る男性の事務職員が、少し面食らっているように見えた。
「東尾さん、下の名前は何とおっしゃいますか?」
太郎に向けられた瞳は透き通るように薄い茶色でくりっと丸い。視線が合わないことに違和感を覚える。頬はぷっくりとして赤いが、血色のよい感じではなくかさかさとした質感で、首には数本の深い皴が見えた。体格は人形のように小柄だ。太郎とあまり年齢が変わらないようにも見える。
「そちらの椅子でお待ちください」
母の名前を告げると彼は慣れた様子で奥の椅子へ視線と手のひらを差し出しながら、感情のない表情で太郎にそう伝えた。窓際の後ろには、髪をひとつに束ねた化粧気のない黒縁めがねの女性事務職員が座っている。インターフォンを持つ手の親指と人指し指には、ピンク色の指サックがついている。
「東尾さんのご家族がお見えです」
太郎は薄い緑色の椅子に座り、前かがみで膝の上に両手を組みながら扉が開くのをじっと待つ。そこへ西野先生が慌てた様子でやって来て、何も言わすに太郎の横に座った。救命ユニットの中から細くて背の高い若手医師と、色白のベテランぽい医師が出てきた。
「息子さんですね」若手の医師が声をかける。
「はい」太郎がうなづく。横で西野先生もうなづく。
ベテラン医師が太郎を見てニコリと笑った。親しみを込めたような表情だ。以前にどこかで会っただろうか……。
ベテラン医師は、すぐに肩越しの西野先生に視線を向ける。
「あ、高校の部活の先生です。僕、未成年なので」
「そうか。じゃ一緒に説明していいのかな……うーん」
ベテラン医師が腕組みをして若い医師のほうを振り向き、「今からすぐにソーシャルワーカーの田村さんに電話してよ。立ち会ってもらおう」と指示をする。若い医師は軽くうなづくと、左胸の赤いストラップに手をかけ院内PHSを取り出した。
「救命センターⅠユニットです。家族が未成年の息子さんなので説明に立ち会ってもらいたいんですけれど、今から来てもらえますか?」
ベテラン医師は、太郎に再び視線を向けると「いくつになったの? 太郎君」と声をかけた。
「17歳です」
「大きくなったね。君は僕のことを覚えていないだろう?」ベテラン医師は、返事を返せない太郎の肩をぽんと叩く。首を縦に振りながらも、太郎は昔の自分を知っている医師がいたことを心強く感じた。
ベテラン医師が救命センターのユニットに向かって歩き出すと、その歩調に合わせて太郎と西野先生も進んだ。「高校の先生の立ち会いは、多分だめなんだけれどね……。説明するから中にどうぞ」すりガラスの扉に近づくと自動扉が左側にスライドし、そのとたん室内から「ピッピッ」というモニタリング音とアラーム音があふれてきた。
白い壁と白い蛍光灯の部屋の中で、細く高く鋭い音が四方八方から太郎の耳を容赦なく突き刺してくる。ここに母親がいるのかと思うと、血圧がスーッと下がるような感覚を覚えた。
第2話 につづく
< ● ●
いま男性たちの身に起きていること……
西尾 美登里
世の男性の多くは、普段から「家族を・女性を介護する」なんて想像もせずに生活している人がほとんどではないでしょうか。毎日部活動に明け暮れる健康な男子高校生なんて、まさにその代表者のようなもの。そんな太郎くんがもし本当にお母さんを介護することになったらいったい何が起こるのか……というのがこの物語のテーマです。
1人っ子の高校3年生で、主人公と名前も同じ私の息子である実在の「たろう」に男性介護者の話をしたところ、「他人事じゃないよ。もしかすると自分も“親を介護する男性”になる可能性が高いぞ……」と思ったらしい彼は、介護を経験していない社会人もしくは退職後の既婚男性49人を対象とした自記式質問紙調査を独自に実施しました。
その結果によると、「自分が妻や母親を介護することになるかもしれない」と想像したことのある人は全体の32.65%でした。また、現在の生活で「料理に困っていないか」という質問に対し「困っている」人は4%のみ。その理由は「妻が料理をするから」でした。また、男性が女性の介護を開始すれば、おそらく日々の買い物にもさまざまな苦労が予想されるでしょう。そこで男性がふつうしない買い物について尋ねてみました。回答をみると「化粧品売り場に行くことに抵抗がある人」が38.8%、「下着売場に行くことに抵抗がある人」は80%でした。
内閣府による2017年の調査では、わが国の人口の27.7%以上が65歳以上に達しており、加齢に由来するさまざまな問題(病気や怪我の増加などに伴う医療費の高騰、認知症の増加、介護負担、高齢者の生きがい喪失など)が、社会のいろいろな場面で懸念されています。そんななかで、男性介護者の割合は1999年に18.6%だったのが2016年には34.0%と、15年あまりで50%近く増加しました(厚生労働省)。そして彼らの多くが慣れない介護にさまざまな問題を抱えていることが明らかになってきています。たとえば厚生労働省の高齢者虐待の調査(2011年度)では、加害者のうち40%は息子でした。一方、2006~08年の間に起こった介護に関連する殺人事件の新聞報道件数のうち、加害者の71.8%が男性だったことからは、社会的な関心の高さをうかがうことができます。
©2019 Taeko Hagino
