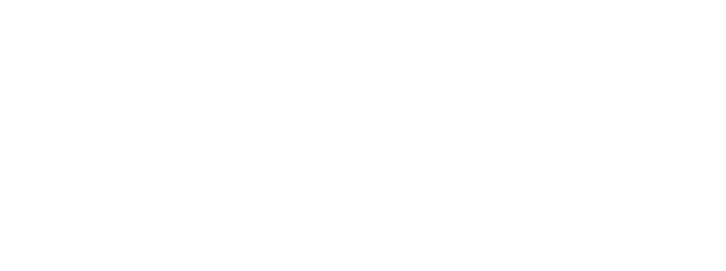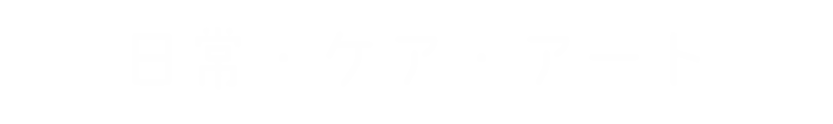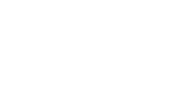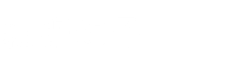被災者が抱える深く複雑な苦悩
しかし、被災から長い月日がたち、その後の日常が人生の多くを占めるようになった今も、人々の心の傷が完全に癒えることはない。住民たちの心の奥深くには3.11にまつわる「記憶のレイヤー」が眠るように存在しており、かつて暮らした場所の記憶が呼び覚まされることに強烈な拒否反応を示す人もいるのだという。
また、地震や津波によって直接大きな被害を受けなかった人々も、故郷が存在しているにもかかわらずそこに住むことができないという「曖昧な喪失」を今なお経験している。住み慣れた町や家の面影が時間とともにじわじわと変質し失われていく中で、彼らは「真綿で首を絞められていくような感覚」とともに生きているのだ。
懐かしさや愛着の思いに浸れるだけではなく、大切なかつての記憶の扉を開くことには苦痛がつきまとう。中筋さんはそんな一人ひとりの気持ちをできるだけ見きわめながら、自分の写真を見せるかどうかを決めているという。
表現活動の“もやい”
福島原発事故への関心が社会から徐々に薄れていく中で、原子力災害のもたらす破壊の現実を五感で感じ取ってもらいたいと考える中筋さんは、効果的な展示方法を検討する中で写真以外のアートの存在に注目した。彫刻、絵画、音楽、漫画、短歌など福島の惨状を見聞きしながら創作された作品が、今も数多くの作家たちによって生み出されている。そうした多様な表現を「もやう(共同作業する)」ことで、原発事故をめぐるさまざまなリアリティが渾然一体となった空間をつくり上げることはできないかと考えたのだ。
この中筋さんの願いはやがて「おれたちの伝承館」となって実を結んだ。被災による喪失、哀しみや恐怖を、色や形、音など人々の感覚に訴えるさまざまなアート作品へと昇華させて展示する場所だ。いまだに現実を直視することが困難な人であっても、これらのアート作品であれば向き合えるかもしれない。そうすれば、帰ることができない大切な故郷に対して自分なりに思いを馳せることもできるだろう。被災で受けた傷を持つ人々や町に触発されて生まれたアート作品は、その傷を優しい色や形に変えられるかもしれない。もしかするとそれは故郷の未来に小さな明かりを灯し、この先を歩んでいくための足元を照らすかもしれない。
「おれたちの伝承館」で見たもの
筆者は、東日本大震災の2カ月後から被災地の現実に触れるのため宮城県と岩手県に向かい、現地の被災状況を直接目にしてきたが、福島県に初めて入ったのはその2年後だった。当時、整地され復興が進む隣県と異なり、家屋が倒壊したまま残されていた町の姿に驚いた。とりわけ福島第一原発から10km圏内の警戒区域では、メインストリートの道端から青々とした草木が空に向かって伸び、持ち主が戻らない駐輪所の自転車にツル草が巻き付いていた光景が強く印象に残っている。町に生い茂る植物たちは、生活が停止した人々の時間を象徴しているようで胸が痛んだ。筆者には、中筋さんのようにそこにある「美しさ」を見てとることまではできなかったけれど、深く傷ついたこの地域を放っておけない気持ちになって、以後毎年のように通うようになった。


人がいなくなった街を覆い始めた植物たち
(筆者撮影)
2024年8月、酷暑のなか筆者は「おれたちの伝承館」を訪れた。地元の人に紹介され、連れて行ってもらったのだ。館内に入ると、警戒区域のいたるところに置かれていた立ち入り禁止ゲートが展示されており、初めて福島に訪れたときに現地を走る車窓から見た殺伐とした物悲しい景色がありありと蘇った。次に目に入ったのは、透けた和紙で創られた酪農牛の像だった(小林桐美「強制避難区域に取り残された牛たち」2019年)。世話をする飼い主が去り、食べる物がなくなって齧った柵の間から力尽きた体を横たえている。薄い和紙で表現された儚げな表情が、牛たちの苦しみ、大切に育てた人の苦悩、原発事故というものの罪深さなど、さまざまな思いを誘う。

安藤榮作「鳳凰」
(「おれたちの伝承館」ホームページより)
館内にはほかにも、天に向かって何かを掴もうと手を伸ばしているように見えるオブジェ(安藤榮作「鳳凰」2015年~)、人びとの願いを携え空に向かって高く跳躍するかの如く描かれた馬(山内若菜「命煌めき」2023年)などがあり、筆者は一つひとつの作品の前で立ち止まり、発せられるメッセージに耳を澄ました。「あ、こんな表現の仕方があるのか」と素朴に感心し、これまで自分なりに感じとってきたこの地域の人々が抱える痛みが、さまざまな色や形、音や気配に変容してそこにあることが新鮮だった。
汗を拭いながら館内を見て回る筆者らに、館長である中筋さんは警戒区域の町並みを撮った絵巻物のように長い何枚かの写真作品を広げて見せてくれた。それは自身が継続的に撮影している原発事故後の町の定点記録だった。これらのアーカイブは原子力災害の影響を時間軸で切り取り可視化することを可能している。人の手が及ばない町並みが自然にもてあそばれながら、徐々に経年変化してく様子がそこには収められている。これらもまた館の展示を構成する作品の一つであり、同館が福島原発事故の表現共同体として放つエネルギーをいっそう厚く強いものにしていた。
「美しさ」がもたらす“あそび”
地震・津波・原子力事故という未曽有の大災害に見舞われた福島の人々の痛苦を、さまざまなアートの表現を通じて昇華する「おれたちの伝承館」の作品群は、震災後の日常を生きながら抱え続ける人々の悲しい現実を和らげ、捉えどころのない苦悩の存在を認め、苦悩の中に潜む変容の兆しを見いだすための支えとなることを願う人々の手でつくられている。終わりの見えない苦しさが続く日常の中でさえも、「美しさ」がもたらす優しい“あそび”がそこにはある。
● 参考文献:中筋純:おれたちの伝承館, 図書, 891, p.22-27, 2023.
なかすじ・じゅん
1966年和歌山県生まれ。八王子市在住。東京外国語大学中国語学科卒業。出版社勤務と平行して写真技術を習得。1995年中筋写真事務所設立。ファッション、舞台、映画、ドキュメンタリーの雑誌&広告企画で撮影を担当する傍ら日本の産業遺構にスポットを当てた作品を制作。2007年10月以降6度にわたってチェルノブイリ原発を取材。2011年の福島原発事故後には被災町の許可を得て無人と化した街々の発する静かなメッセージを季節の変化に寄り添って記録している。2017年より、さまざまなアーティストたちが各々の手法で原発事故後の福島を表現した作品を展示する「もやい展」を主宰している。