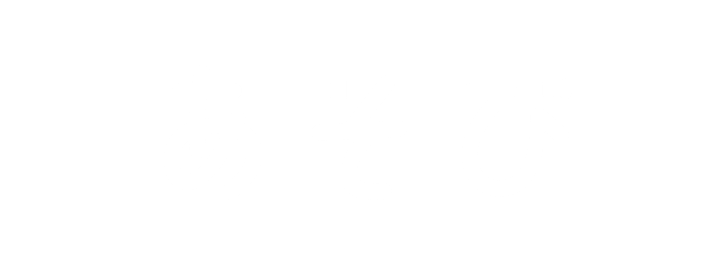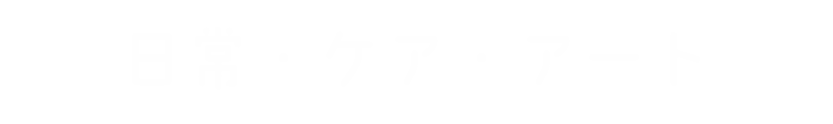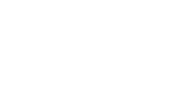突然中断された日常生活
今回は福島原発事故後の町を写真カメラで撮影し続ける中筋純さんにインタビューを行った。中筋さんはファッション・舞台・映画・ドキュメンタリー雑誌・広告など幅広い分野のプロ・カメラマンとして活躍する一方で、日本の産業遺構に焦点を当てた作品制作に取り組んできた写真家である。
2007年、中筋さんは原発事故で廃墟化が進むチェルノブイリの町を取材し、20年以上も沈黙を続ける都市空間を目の当たりにして大きな衝撃を受け、以後繰り返し訪れることになった。そして4年後の2011年3月11日に東日本大震災が発生し、翌日に起きた福島第一原子力発電所の事故で多くの住民が長期に渡り避難生活を余儀なくされてしまう。中筋さんは誰もいなくなってしまった町に一人で足を運び撮影を続け、2016年から全国各地で写真展を開催し、そこで見た風景を紹介してきた。さらに、撮影活動と並行して2023年に福島県南相馬市小高地区に「3.11&福島原発事故 伝承アートミュージアム おれたちの伝承館」(以下:「おれたちの伝承館」)を開館した。同館は福島原発事故を題材として表現活動をするアーティストたちの作品を現地に集め、放射能災害が人々の暮らしにもたらしたものを「伝承」していくことを目的としている。
それまで、中筋純さんが産業遺構の撮影に取り組んできた理由は、捨てられたものの中にある美しさに惹かれたからだった。全国の廃墟をめぐり、歴史的な役目を終えた人工建造物が植物に覆われ「自然に呑み込まれていく」過程を数多く目にしてきたが、その中でもチェルノブイリでの経験は特別だった。人々が営む暮らしが突然中断されたままの状態で遺棄された町や村は、これまで見てきた廃墟と同様、植物や動物などの「野生」がどんどん侵入していたが、20年を経た今も「人が住んでいてもおかしくないように」見えたのだ。そこに確かに残る生活の気配が、失われてしまったものの存在を際立たせていたのである。
大学時代、原子力発電所とその場所に住む先住民の関係を研究していた文化人類学者の先生に学んだ経験を持つ中筋さんは、チェルノブイリの町で起きたこと、そしてそれが今も続いていることを切実に受け止めた。そしてカメラマンの自分にできることは何かを考えた末、「これは時間がかかるぞ」と、現地に足を運び続けることにしたのだ。
放射能災害の「その後」を撮り続ける
そんな中筋さんが、事故を起こした福島原発から10km圏内の町にカメラを向けることは必然だった。2012年より双葉町、富岡町、大熊町、浪江町など帰還困難区域となって人がいなくなった町に入って写真を撮り始めた。
それらの町には、地震・津波により建物が倒壊した状態のまま、チェルノブイリ以上に生々しい生活感が残っていた。激しい揺れで商品が散乱したままのスーパーマーケットでは、獣が食べ物を食い荒らし、凄まじい匂いが立ち込めていた。誰もいない静寂の中でシャッターを切る中筋さんの背後でガサガサと動物が動く音がすることもあった。かつての人の賑わいを失い、たった一人、自分だけがいるその場所で耳にするその音に、同じく生ある自身とのつながりを否が応でも感じさせられた。
「自分が今まで何を撮ってきたのかっていうのを、1回なんか、廃墟を撮ってきた人間として総括しないと駄目だっていうような気持ちになった──」
中筋さんが撮影してきた写真は、未曽有の傷跡を残す町の貴重な記録として、50年後、100年後の社会を変える力となるかもしれない。浪江町長だった故・馬場有氏は、一介のフリーランスである中筋さんに町内を自由に出入りするための許可証を与えてその思いを託した。「放射能災害は1回撮って終わりにはできない。時間を写し込むっていう作業がいるんだ」と中筋さんは言う。チェルノブイリと福島の「その後」を記録し続けることは、放射能災害の全貌を捉える上で欠かすことのできない「時間」に焦点を置いた表現活動と言えるのだろう。
「記憶の扉を開けるための装置」
「被災した街を撮る写真は美しくあらねばならない」と、中筋さんは考えている。そこにかつていた人への「リスペクトの念」がまずあるからだ。14年の時を経て、しだいに風化していくこの町を虚しいものとして眺めるのではなく、今もそこにある「この土地の季節ごとの光の違い、風の向き、空気の感じというのを読む」。例えば、朽ちかけた家屋の上に広がる空を「思いっきり入れてあげる」。そんな中筋さんの写真を見る人びとは、悲惨な生活の残骸という現実を突きつけられながらも、「この空、懐かしいよね」「この日差しの感じ、ちょうど今頃だよね」というように、目にした途端にそれぞれの人が持つ「記憶の原点」に連れ戻されるのだ。
双葉町では、秋になるといたるところに植えられたセンダンの木が一斉に黄色い実をつける。変わり果てた故郷とともに映しとられた馴染み深いその風情は、昔どおりの晩秋の双葉町が今も変わらずそこにあることを実感させてくれる。福島の出身ではない中筋さんだが、生まれ育った場所でなくても、地元の人が懐かしく感じられるものを写真に収めるために必要なヒントが必ずどこかにあるという。例えば小学校の校歌には、土地の人々が愛する美しい四季折々の姿が描写されていることが多い(ちなみに、中学・高校の校歌では教訓めいた内容が増え、“懐かしい光景”が描かれることが少ないという)。
最近では、この町を離れた住民たちが中筋さんの写真を見て「ここに住んでいた○○さんは、今、何やっているのかな」と話すところを見る機会が増えた。作品たちの「美しさ」は、被災から10年以上も地元を離れて暮らす人々の記憶を呼び覚まし、互いに故郷を語らう懐かし時間をもたらしていた。中筋さんは「人々の記憶の扉を開けるための装置」としての写真による“ケア”を実践していたのだった。
チェルノブイリ原発(撮影:中筋純)
チェルノブイリ原発の背後に佇む集合住宅の光景。「一つひとつの部屋にあった暮らし」を思うと心が曇る。


流転 チェルノブイリ 2007~2014(中筋純:二見書房, 2014より)
チェルノブイリの大地で育ったジャガイモを手にして空を見上げる女性。放射能に汚染されたとしても、愛おしい土地で暮らす誇らしさのようなものを感じる。
なかすじ・じゅん
1966年和歌山県生まれ。八王子市在住。東京外国語大学中国語学科卒業。出版社勤務と平行して写真技術を習得。1995年中筋写真事務所設立。ファッション、舞台、映画、ドキュメンタリーの雑誌&広告企画で撮影を担当する傍ら日本の産業遺構にスポットを当てた作品を制作。2007年10月以降6度にわたってチェルノブイリ原発を取材。2011年の福島原発事故後には被災町の許可を得て無人と化した街々の発する静かなメッセージを季節の変化に寄り添って記録している。2017年より、さまざまなアーティストたちが各々の手法で原発事故後の福島を表現した作品を展示する「もやい展」を主宰している。

双葉町のセンダン(撮影:中筋純)