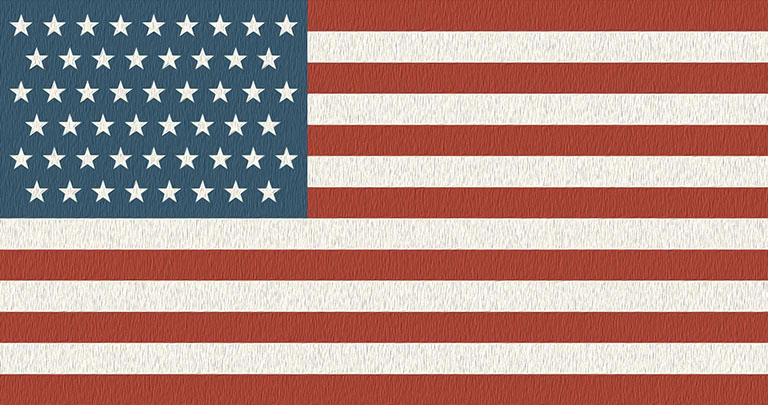
生きて帰国できても、それはハッピーエンドではない
2004年から2006年まで、約5,500人の陸上自衛隊員がイラクのサマーワに派遣され、戦闘で一人の犠牲者もだすことなく全員が帰国した。サマーワは「非戦闘地域」だと当時の小泉純一郎首相は強弁していたが、それでも正直なところ、日本の国民の多くは彼らの無事にホッと安堵の胸をなでおろした。
しかし、2007年11月の防衛省の発表によると、イラクに派遣された陸上自衛隊員のうち7名が2007年10月末までに自殺した1)。さらに新聞報道によると2012年3月末までに19名が2)、そして2015年の国会での質問書では2015年3月末までに21人がみずから命を絶ったことが明らかになった3)。2015年4月以降の数字は、残念ながら資料が公表されていないため把握できない。ともかく、生きて帰国できてもすべての隊員にとって必ずしもハッピーエンドではなかったのだ。
約5,500名の集団のうち21名が約9年間に自殺している現実。この確率は高いのか低いのか。直接比較できる統計資料がないため、正確なところはわからない。ただ、イラクに派遣された陸上自衛隊員の死亡率を10万人あたりに換算すると38.3人となり、自衛官全体の33.7人や、一般職である国家公務員の21.5人と比べてもとりわけ高い数字だ4)。さらに、派遣されたのが自衛官の中でもとくべつに選抜された強壮な隊員であることを踏まえれば、その自殺にいたる割合がより深刻な意味をもつような印象を与える。
イラクの駐屯地サマーワは、銃弾が宿舎に飛び込んでくるような場所だった。隊員たちは常に生死にかかわる緊張を強いられることになった。
人はあまりにも強いストレスに遭遇すると、PTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)を発症することがある。それは現在ではよく知られている。そしてこのPTSDによってもたらされる最悪のケースの一つが自殺である。とすれば、イラクに派遣された陸上自衛隊員の何人かは、みずからの命を絶つ背景にPTSDがあったであろうと考えるのが自然だ。だが、2015年5月の国会答弁では、イラクへの派遣と自殺との因果関係を特定するのは「困難な場合が多い」としている5)。ただし政府も、それを認めてはいないが、完全には否定していない。
ここで注目すべきは、そもそもイラクへの自衛隊員派遣と自殺との因果関係が証明しにくい点だ。また、隊員のなかには帰国後およそ6~10年後に自殺した者が3人もいた点だ。これらはPTSDの特徴をよく表している。
PTSD
PTSDは、1980年に米国精神医学会が認めた比較的新しい疾病である。ベトナム戦争(1960~1975年)には、米軍の兵士約260万人が投入され、戦死者約5万8千人、負傷者約15万人の犠牲をだした。そのうえ、生きて帰国したが心にひどい傷を負った兵士も多くいた。
心的外傷をもつ元兵士は、帰国後の日常生活に再びうまく適応できなかった。たとえば不眠に苦しんだり、感情がコントロールできなくなったり、離職し失業したり、離婚したり、引きこもったり、薬物やアルコールの中毒になったり、犯罪を犯したり、最も不幸な場合には自殺することもあった。より最悪のケースでは、帰国後に妻を殺害したあとみずから命を断った例もある6)。
1970年代に入ると、心が傷ついた元兵士たちの奇行や反社会的ふるまい、自殺の多さに世間の関心が集まり、臨床医や元兵士たちの活動もあって、その原因は戦争によるストレスに関係することが認められた。そうして、PTSDという病名が発明された(のちに戦争によるものだけでなく、鉄道事故や自然災害や性暴力などによるストレスから生じた心の傷もPTSDと呼ぶようになった)ことで、治療もやっと本格化した。
つまりPTSDという病名は、戦争のストレスと心の失調との因果関係が直接証明されて生まれたのではない。現実に眼の前で苦しんでいる元兵士を救済するために名づけられたものである。だからそもそも、PTSDという症状と戦場でのストレスとの因果関係に根拠を求めるのは無理な注文なのだ。
また、PTSDの恐ろしいところは、ストレス経験直後に発症するだけではない点にもある。精神科医のジュディス・ハーマンは、激烈な戦闘を経験した者は、15年後においても36%がPTSDと診断されると語っている7)。また同じく精神科医の斎藤学は、根拠を示していないが、ベトナム戦争帰還兵は「いずれも(PTSDの)発症まで平均15年ぐらいはかかっています」とまで語っている8)。
数年間なんとか日常生活を営んでいながら、ある時突然、PTSDの症状が目に見えるかたちで顕在化し、極端な場合には前触れもなく自死を選ぶことがあるのだ。帰国から6~10年後に自身の命を絶った自衛隊員のなかには、防衛省がイラク派遣との因果関係を認めていないこともあり、謎めいた唐突な死として処理されている場合もあるだろう。もしそうだとしたら、ひどい話ではないか。しかもなかには、自殺にまでいたらずとも、PTSDに伴うさまざまな困難や苦しみ、悩みに直面しているより多くの隊員がいるはずだ。私たちはそうした彼らの存在に関心を向け、彼らの身に起こったことを理解する必要がある。今後も決して忘れるようなことがあってはならない。
「シェル・ショック」と第一次世界大戦
戦闘や戦場を経験したあと、心が傷つき、その後の日常生活に支障が生じる。この事実は、もちろんベトナム戦争以前から知られていた。すでに紀元前8世紀の叙事詩『オデッセイ』にも、兵士のフラッシュバックや「自分だけが生き残ってしまった」という罪悪感が描かれている。しかし、戦闘や戦場の経験が生むストレスが一般の関心を引くようになったのは、第一次世界大戦(1914~1918年)以降のことである。
第一次世界大戦は、歴史上初めてプロの軍人だけではなく、徴兵制度で集められた多数の一般人が戦った戦争だった。ヨーロッパ全土で4年間もつづいたその戦闘の結果、直接負傷してはいないが、心身の失調をきたす兵士が多く現れた。彼らの症状は「シェル・ショック」と呼ばれた。炸裂するシェル(shell=砲弾)によるショックで脳震盪や脊髄震盪が起き、心身の不調が生じたと考えられたのだ。もちろん現在からすればその理解は誤りである。ちなみにShell Shockという単語は、開戦から約半年後の1915年2月には、有名な医学雑誌『ランセット』に掲載された記事のタイトルに使われている9)。
このシェル・ショック症状を示す兵士が多数生じたため、米国政府は1919年と1921年に帰還兵士のための専門治療施設を新たに設立している10)。しかしシェル・ショックはあくまで症状を示す一般的な呼び名であった。正式に認められた病名ではなかった。そこがPTSDとの違いだ。つまり「病気」ではなかったために、結果としてそれらの症状に苦しむ人は、臆病者・意思薄弱者・社会生活不適応者・作病者などとみなされがちだった11)。そうしたこともあり、シェル・ショックは世間の広い関心を引きつづけることはなかった。

