
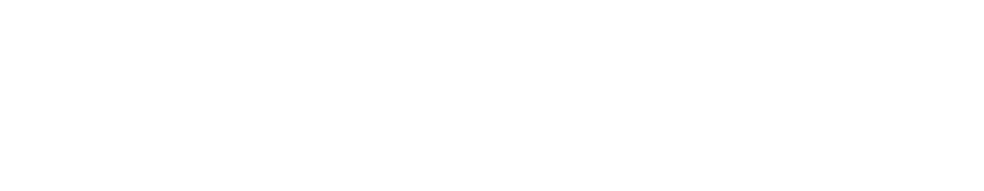
戦争で心に傷を負った人たちがいることを知ったのは、今から約40年前、精神科医になったその年からだった。
しかし、当時はそのことが、私にとって重要な課題になるなどとは考えもしなかった。私の精神医学の根幹を支える重要な課題であると決定的に考えるようになったのは、ここ10年ほどだ。戦争が人々の心に傷を負わせ、そのことが世代を超えてさまざまな形で伝搬され、後の世代に精神症状として表出されていることを知り始めたとき、目の前にいる患者さんたちの理解がもっと深まってきたと考えている。
ここでは、私のささやかな精神科医としての歩みを辿りながら、戦争による心の傷に触れてみたい。
加害者の苦しみ
大学を卒業し、精神科医局に入局した年の秋だった。遠戚の叔父が脳梗塞で倒れ、意識が回復した直後に呼び出された。彼は、父方の遠戚(遠戚ではあったが、なぜか父とは仲がよかった)の人で、戦前に大学を卒業し、大企業に就職したものの召集を受け、満州で過ごしたことを子どものころから知らされていた。
病室を訪れると、彼はほかにいた見舞客に席を外してもらい、私1人だけになったところで、回復直後の滑舌が悪い状態で話し出した。「部隊長の命令で、自分の部下に罪もない中国人や満人を殺させた。今もそのときの断末魔の声が耳に残っている。こういったことがどれだけ苦しいか、精神科医であるお前にはわかるだろう。お前が精神科医になったことを聞いて、お前にだけには伝えて逝きたいと思っていた。皇軍の兵士がこんなことしてはいけないとずっと思っていた……」
話はあちこち飛びながら、あっという間の30分だった。疲労困憊しているように見えたので、できるだけ話を聞きにくるから今日はこれだけにしようと話を打ち切った。その後、折に触れて呼び出され、話を聞くことになった。あの温厚な叔父さんが、こんな大変な過去を背負っていたことを知り、人というのは表面だけではわからないものだとつくづく思った。
患者さんの中に見る戦争体験
研修医として入った病院は、1922(大正11)年、山形県内初の精神科病院本院の分院として1956(昭和31)年に閑静な田舎に建造された。当初は40床弱で始まったが、ライシャワー事件●1 を機に、しだいに病床数を増やし、私が入局したときには460床にまで拡大されていた。私が配属された病棟は86床、開放型男女混合慢性社会復帰病棟だった。
まだ2年目の研修医だった私には、未熟な精神医学の知識しかなく、患者さんと一緒にさまざまな活動やリクリエーションに参加し、タバコを吸い、温泉入りやラーメン食べに出かけ、上司に指示されて往診に出かける日々だった。
病棟の家族会があり、病院会議室で総会の後、近くの温泉旅館に泊まり、総会の打ち上げがあった。新人の義務と言われ参加したが、患者さんのお母さんたちに散々お酒を飲まされ、私は早々と寝入ってしまった。翌朝、露天風呂に入っていたところ、1人のお母さんが入ってきた。
よく晴れた蔵王山を見ながら、「戦時中に妹と2人で満州に渡った。戦争が終わり逃げてくる途中で妹がロシア兵に捕まり、凌辱され殺された。そのときの「おねえちゃん助けて」という声が今も私の耳に残る。娘が20歳になって発病した。しだいに自分がわからなくなっていくときに、「お母ちゃん助けて」って叫ぶ。その声が妹の声にそっくり。私は、2人の人間を救うことができなかった」と涙声で語った。私は、適切な言葉が見つからず、「大変でしたね」と、つぶやくように声を出すしかなかった。
朝食後、病院に戻っていつものように病棟業務についていたところに、そのお母さんがそっと近づいてきて、「さっきの話は、私と娘が死んだらしてもいいけど、それまでは先生の心の中に収めといてね。病院で初めて山形弁を話す精神科医に出会って、墓場まで持って行こうと思っていたことをついつい話してしまった」と苦笑された。「とても大切な話を聞かせていただき、ありがとうございました。自分の中で深く考え続けたいと思います」とだけ返事をしたときには、彼女は颯爽と廊下の角を曲がっていた(今はもう、ふたりとも亡くなっている)。
そのころから、私の病棟にいる慢性統合失調症の患者さんの中には、戦争に傷ついて統合失調症になった人が結構いると気づけるようになっていった。
砲弾の中を生き延びて発病し、通信兵として巡洋艦に乗り込み、爆撃が隣の兵士に直撃し、モールス信号を打つ手に肉片がこびりつき、それを機に発病した人など、事例は1つや2つではなかった。しかし、それをどう表現すればよいのか、私にはその手立てがなかった。
内地留学を終えて―外国人花嫁たちの背景にある日本―
病院での研修の後、北九州市立デイケアセンターの所長だった坂口信貴先生のもとに4年間、内地留学をした。個人精神療法や家族療法、薬物療法、チーム医療、地域医療などを学び、私は研修医として1年間過ごしたもとの病院に戻り、しかも同じ病棟を受け持つことになった。
時々来院する家族にお願いして、3世代から4世代にわたる家族歴と成育歴をていねいにとり始めた。父親がシベリア抑留中に生まれた子ども、元憲兵だった患者の家族否認妄想、南京虐殺事件の1937(昭和12)年に確かに南京にいた兵士……戦争の爪痕がしだいに私に明確に意識できるようになっていた。
しかし、その当時、私には心的外傷後ストレス障害(post traumatic stress disorder:PTSD)の知識はなく、まだ私の心には重く受け止められていなかった。そんなとき、平成に入って間もないころ、ある晩友人がやってきて、「山形にも難民がいる」言ったことがきっかけになり、いわゆる山形に来た外国人花嫁の定着支援に、ボランティアとして関わることになった。
あるとき、山形に来て境界例●2のような状況に陥っていた外国人女性に会った。私に出会うまでに、彼女は山形県内のすべての支援者と争いになり、今日の夜を精神科病院で過ごしてもらうしかなくなっていた。そのことをやんわりと彼女に話したところ、「日帝支配40年、そしてまた私を支配する気か」としっかりした日本語で言い放ち、私を平手打ちした。彼女の祖父が日本兵に尊厳を傷つけられ、そのことを彼女は小さいときから聞かされていたということを後で知った。
このことをきっかけに私は、日本にやってくる外国人花嫁の母国と日本の近現代史を調べるようになった。彼女たちの母国の歴史教育の中で日本はどのように語られているのか。フィリピン、韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、オーストラリア、カンボジアといった国々が日本をどう見ていたか、知れば知るほど自分の無知に気づかされた。同時に、日本の歴史教育が、近現代史をすっ飛ばして教えていることに驚かされた。
いじめた者はいじめた過去を忘れ、いじめられた者はいじめられた過去の事実を子子孫孫まで伝えるということを、「者」を「国」に置き換えて考えなければいけないと痛感した。しかし、私はその当時でもまだ心の傷についての理解は不十分だった。
PTSDの理解と心の傷を抱えた病院職員の発見
外国人花嫁対応にモデルを探していたころ、同じように外国人労働者や移民を扱っている精神科医が全国にいることにようやく気づき始め、1993(平成5)年、社会精神医学会の際に多文化間精神医学会●3が設立された。全国からの外国人情報が流れてくるようになったことは、山形のような田舎に住む人間にとっては大きな資源となった。
そして1995年、阪神・淡路大震災が発災。その翌年に翻訳出版されたジュディス・ハーマン氏の『心的外傷と回復』●4によって、私はようやくPTSDの全貌が見えるようになってきた。同じ時期に、県警の依頼より外国人犯罪に関与するようになり、にわかにPTSDが私に集中するようになってきた。薬物療法の効果が期待できないために、TFT●5やEMDR●6、ブレインジム●7など、学べるものは何でも学ぼうとした。学んできては、職員にお願いして被験者になってもらった。
あるとき、EMDR中に居眠りしてしまう職員がいた。協力できなくて申し訳ないと深々と頭を下げる彼女に、まだ初心者でわけもわからずやっているので、こちらこそ申し訳ないと謝罪した。
それから1か月ほどたって、その彼女が「時間をとってほしい、話を聞いてもらいたい」と言ってきたので、早速話を聞くことにした。「自分は18歳まで父から犯されてきました。先生はそのこと知っていたから、私を被験者に選ばれたのではないでしょうか」ということだった。話をよく聞いてみると、中学生のころから、父親から犯され続けていた。それが嫌で18歳で上京し、住み込みで看護師の資格をとったと言う。どの患者にも優しく接する彼女の姿勢にいつも感心していた私は、誰にも言えない過去があることなど想像することすらできなかった。私は唖然とした。
当時私は、副院長になり、病院の産業医になっていた。職員の中にも心に傷を負っている人たちがいることがぼんやり見えてきた。DVに苦しむ人、アルコールやギャンブルなどの依存症を抱える配偶者のいる職員。しかも、彼や彼女は、自分が傷を抱えていることさえ自覚していない。それをどうやって自覚させていけばいいのか、それを侵襲的にならないように気づかせるにはどうしたらよいのか。
職場の健康診断に引っかかった職員に一人ひとり、家族のことなど話を聞いていくと、さまざまな問題を抱えていることがわかった。何とかしなければと思ったものの、その時点で私自身がオーバーワークになっていた。妻が癌の末期状態であることが発覚し、約7か月の闘病生活で他界した。喪失体験は、私が駆け出しの精神科医だったころからのライフワークの一つだった。心的外傷と喪失体験は、紙の裏表のようなもので、PTSDの患者さんを診療するたびごとに、私自身が多大なストレスを抱えることを身体で感じるようになっていた。
そのストレスを身体が受け止め、その身体の疲弊を感じ取る力を無視して生きている自分に気づくようになったころ、サテライトクリニックへの異動を命ぜられた。組織に縛られて働く体力は自分には残っていないことを自覚し、再婚したことを機に、2007年から小さなクリニックを開業し、無理のない生活をしようと考えるようになった。そこで病院職員の心の傷の調査は、そのままになってしまった。
病院職員、とりわけ看護者の中には人知れず心の傷を抱えている人たちが少なからずいることについて、私はもっと配慮が必要なのではないかと、今でも考えている。
開業後―傷跡を今に引き継いで生きる―
初診には1時間をかけ、できるだけ薬を使わない医療をと考え、身体療法なども多用することにした。特に妻は、TFTやEMDRなどさまざまな身体療法を使えたので、女性の患者で解離やPTSD傾向の認められる患者は、妻に治療をお願いした。
東日本大震災のあった2011年3月11日以降、1週間以上、患者さんは来なかった。抗不安薬を極力処方しなかったこと、睡眠薬も可能な限り減らす努力をしていたことが起因したのだろうと思う。
震災は、近所の老健施設から通う陳旧化した統合失調症の人たちにさまざまな影響を与えたようだった。その中の一人の患者さんは、ハロペリドール15mg分3、就寝前に100mgのヒルナミン、そのほかにいくつかの薬剤を服用していた。戦争中に満州にいたということから、私が対応したことのある外国人花嫁の出身地である内モンゴルやモンゴルの草原の話などをして、月に一度、10分程度の話をしていたが、震災からほどなくして、彼は付き添いを外して聞いてほしいと言った。それから毎週30分の時間をとって、彼の話を聞いた。
彼の幻聴は、満州で上官の命令で殺してしまった中国人の泣き叫ぶ声だった。その中に女や子供の声もあった。日本に戻ってきてたまたま一流企業に採用された。しかし、上司に無茶苦茶なことを言われているときに、中国でしてきたことがフラッシュバックしてきて、夜も眠れなくなった。うつむきながら話す彼の目からは滂沱(ぼうだ)の涙が流れ、ティッシュではなくタオルを置かなければならなかった。聞く私も涙を禁じ得なかった。
処方は、最終的にハロペリドール1mg就寝前で落ち着いた。彼は、これ以上減らすと過去の映像が蘇って眠れなくなると言った。しかし日中フラッシュバックが起きてきても、それは自分が向き合わなければならない仕事だからと言い切った。自分の話は、自分が死んだら誰にでも話してよいが、死ぬまでは先生の心の中に収めてくれと言われた。彼が満足しきるまでには、半年の歳月が必要だった。
そして再び月に一度の診察に戻った。受診最後の日に、自らの死を自覚したかのように「戦争は絶対にしてはいけません。それを若い人たちに伝え続けてください」と安らかな顔で握手を求められた。それからほどなくして肺炎のために亡くなった。彼の話から加害者のPTSDも大事に扱わなければと考えるようになった。また、戦争による傷痕は、その時代を生きた人のみならず、世代間連鎖としてその傷を引き継いで今を生きる人たちがいることを忘れてはならないことを肝に銘じたい。
過去の事実と向き合う
「一億総懺悔」という言葉は、日本人全員が戦争を起こした責任を懺悔することだと私は思っていた。たまたま辺見庸氏の『1★9★3★7』●8を読んだ。一億総懺悔は、戦争に勝てなかったことを天皇に詫びることだということを初めて知った。極東国際軍事裁判●9 で外国人によって戦争責任の裁判が行われた。しかし、日本という国は、国民が自ら自国の戦争責任を問うことをしなかった。東久邇首相によって一億総懺悔にすり替えられ、いまだに戦争責任を追及する者もなく、マスコミも触れようとしない。
いじめのために自殺した子供、その家族は、悲痛の声を上げる。しかし、いじめた者は顔も出さず、自責の念さえ語らない。戦争のために上官の命令で罪のない無辜(むこ)の民を殺し、戦後何十年も苦しみ続け、統合失調症患者としての人生を送り、しかも「皇軍に1人も戦争神経症はいない」として、彼らは戦争の犠牲者として日本という国に受け入れられることはなかった。戦争を引き起こした責任者は、その責任を恥じもせず戦後を生きている。いじめられて自殺した人間をいじめた人間は、責任もとらずに何食わぬ顔で生きている、日本という国は、責任を受け止める文化のない国なのではないか。
かつて人権問題にうるさかった精神科医は、精神疾患と戦争について語ることは少なかった。医師も看護師も、あの戦争に関わってきた歴史があるはずである。
ヴァイツゼッカー●10は、「荒れ野の40年」の中で語る。若者にあの戦争の責任はない、しかし、過去に目をつぶる者は未来に対して盲目になると。過去の事実と向き合うという作業は、心の傷を抱える人にも、それを扱う治療者にも避けては通れない営みである。
[ 註 釈 ]
●1=ライシャワー事件:1964年、駐日米国大使・エドウィン・O・ライシャワーがナイフで刺され、重傷を負った。犯人が精神疾患患者であったこと、大使が輸血後肝炎を発症したことから、精神衛生法の改正(緊急措置入院制度の新設など)、売血制度の廃止へとつながった。
●2=境界例:境界性パーソナリティ障害(borderline personality disorder;BPD)とも。対人関係、自己像、感情などに著しい変化が見られる。
●3=多文化間精神医学会:海外駐在員やその家族の適応問題、帰国子女の再適応、日本国内における外国人労働者の適応問題、外国人花嫁問題、国家間・民族間の紛争、それに伴う難民問題、宗教・民族問題などを多方面から専門的に探求するために設立された(同学会ウェブサイトによる)。
●4=『心的外傷と回復』:中井久夫訳、みすず書房、1999年(増補版)。
●5=TFT®(thought field therapy ; 思考場療法):米国の心理学者・ロジャー・キャラハン博士が1970年代の終わりに発見し、発展させてきた心理療法。ツボをタッピングすることで心理的問題の症状改善を図る(一般社団法人日本TFT協会ウェブサイトによる)。
●6=EMDR(eye movement desensitization and reprocessing ; 眼球運動による脱感作と再処理法):1989年に米国の臨床心理学者・Francine Shapiroが発表した心理療法。8段階、3分岐の過程によって、健常な情報処理、統合の再開を促す(日本EMDR学会ウェブサイトによる)。
●7=Brain Gym® : 米国の教育学博士・ポール・デニソンにより開発された、「ブレイン」(脳)を活性化させるための「ジム」(体操)。この体操を「ブレインジムエクササイズ」といい、26種類の動きを学ぶことで、運動能力の向上、精神面の安定を図る(公式サイトによる)。
●8=『1★9★3★7★(イクミナ)』:辺見庸著、角川文庫(上・下)、KADOKAWA、2016年。
●9=極東国際軍事裁判:東京裁判とも。1946年5月~1948年11月、東条英機らA級戦犯28名に対し、連合国が審理。
●10=第6代ドイツ連邦大統領・リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー。「荒れ野の40年」は、1985年5月8日のドイツ終戦40周年演説。
いがらし・よしおヒッポメンタルクリニック院長、精神科医。1983年、岩手医科大学卒業。北九州市立デイケアセンターなどを経て、2007年、山形市にて開業。現在に至る。統合失調症のリハビリテーション、精神療法、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を専門とし、特に、帰国者や外国人労働者、日本人配偶者をもつ定住者(外国人花嫁)の心のケアに、長年にわたり積極的に取り組み続ける。戦争体験で心に傷を受けた患者・家族との出会いを通し、海外派遣後の自衛官らへの医療支援にも注力。共訳:『トラウマからの回復 ブレインジムの「動き」がもたらすリカバリー』(2013年、星和書店)共著:『心の健康を育むブレインジム―― 自分と出会うための身体技法』(2017年、農山漁村文化協会)
お知らせ
五十嵐善雄先生は、2019年8月17日にご逝去されました。ご冥福をお祈り申し上げますとともに、当サイトへ貴重なご寄稿を賜りましたことに心よりお礼を申し上げます。
(編集部)


