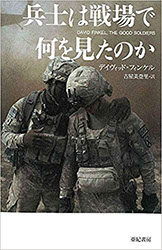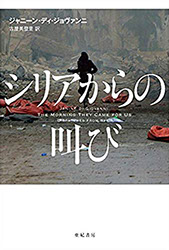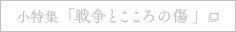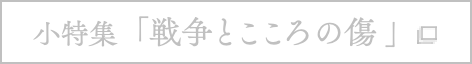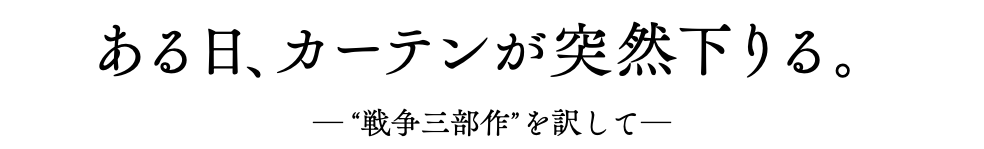
シリア内戦が起こる前のダマスカス。マルジェ広場近くのメイン通りを人々が行き交う。(2008年)
翻訳という仕事
翻訳を生業にしてから35年が経ちます。ノンフィクションとフィクションを車の両輪のようにして、さまざまな作品を訳してきました。
同業者からは珍しい仕事の仕方だと言われます。確かに、翻訳業界はわりあいジャンルによる棲み分けが進んでいて、フィクションのなかでも、文学、ミステリー、SF、ファンタジー、ヤングアダルト、ロマンス、児童文学など専門によって仕事は分かれていますし、ノンフィクションでも、医療、自然科学、経済金融などさまざまなジャンルに分かれています。
ミステリー専門の訳者が経済金融や民族学の本を訳するようなことは滅多にありませんし、自然科学専門の訳者がヤングアダルトに手を出すということもあまり見かけません。耳鼻科の医師が婦人科医になったり、内科医が外科医の仕事をしたりしないのと同じで、フィクションとノンフィクションではそもそも文体も世界観も知識の多寡も違うため、分野を決めてしまったほうが仕事がやりやすいのは事実です。
でも、わたしはどういうわけか気が多くて、面白いものならジャンルにこだわらずに訳していく、というちょっと変わった仕事の仕方をしています。また、そういう者がいてもいい、というのが出版界の大らかさだと思っています。おかげさまでこれまで、とても興味深いけれど訳すには覚悟がいるような問題作に取り組むことができました。
いちばん最初に訳したノンフィクションは、『日曜日のコンピュータ読本』(マイク・エーデルハート他著、ダイヤモンド社、1985年)で、原書は1984年にアメリカで出版されたものでした。当時の日本は、まだオフィスにPCが行き渡っていないような時代で、これからコンピュータを使ってなにができるかを多方面から調査し報告したものでした。訳文はワードプロセッサーではなく、紙と鉛筆で記していましたので、今とは隔世の感があります。一般的に、ノンフィクションではその時代ごとに最も必要とされたり、多くの人が求めていたり、興味が抱かれている作品が翻訳されます。したがって時間が経てば自然と古くなっていってしまうのは仕方がないことかもしれません。
2015年から2017年にかけて、わたしが個人的に「戦争三部作」と呼んでいる過酷な作品が、亜紀書房から刊行されました。『帰還兵はなぜ自殺するのか』『兵士は戦場で何を見たのか』(いずれもデイヴィッド・フィンケル著)、そして『シリアからの叫び』(ジャニーン・ディ・ジョヴァンニ著)です。
左から『帰還兵はなぜ自殺するのか』(2015年)、『兵士は戦場で何を見たのか』(2016年)、『シリアからの叫び』(2017年)。いずれも亜紀書房より刊行。
前者の2作は、ピューリッツァー賞を受賞したこともあるワシントン・ポスト紙の記者がイラクに派遣された師団に従軍し、そこで見聞きした兵士と戦争について克明に伝えたノンフィクションです。後者は、女性ジャーナリストが入国困難なシリアへ潜入し、そこでおこなわれている残虐な行為や、戦争の犠牲になっている女性や子ども、一般市民の日常の様子を女性の視点から報告したものです。平和な時間を過ごしている私たちには想像もつかない地獄のような戦場で、人々は日々の生活を営んでいる。そうした事実を伝えています。
衛生兵たちの体験
戦場には兵士だけでなく、ジャーナリストや料理人、そして医師と看護師が必ずいます。イラクの米軍基地には外科医はもちろん精神科の医師も従事しており、心身ともに傷を負った兵士の治療にあたっていました。フィンケルの著書には、ハンヴィーという装甲車に乗って、簡易爆弾が隠されている道路を進む兵士たちのことが書かれています。塵やバケツの下に隠されている爆弾は、ハンヴィーが通るときに爆発するように仕掛けられているのです。アメリカ軍がイラクに送ったハンヴィーで生き残った車両は皆無だった、という報告もあります。いずれも、ことごとく爆弾によって破壊されました。ということはつまり、それに乗っていた兵士の多くが死傷したのです。
『兵士は戦場で何を見たのか』には、ハンヴィーの車中で被爆した兵士が救護所に運び込まれる場面が生々しく描かれています。
ひとりの兵士が泣き喚いていた。ハンヴィーの運転手だった。EFP(簡易爆弾)の一部がハンヴィーの下に入り込み、破片が車体の床を通って彼の片足の骨を砕き、もう片足のかかとを切り刻んだ。カウズラリッチ中佐(大隊指揮官)が救護所の中に入っていくと、やはり駆けつけたブレント・カミングズがその兵士のところにいき、彼の手を握りしめ、大丈夫だと話しかけていた。「リーヴズはどうしました?」とその兵士が訊いた。カミングズが答えずにいると、さらに「彼の様子を教えてください」と言った。
「いまは自分のことだけ考えろ」とカミングズは言った。
ジョシュア・リーヴズという二十六歳の特技兵は、地面に描かれた一筋の血痕の先にいた。カウズラリッチが向かっていたのはその兵士のところだった。EFPが爆発したとき、リーヴズは前部座席の右にいた。爆弾のほとんどが彼の横のドアを通って入り込んできた。救護所に運ばれてきたときには、意識不明で脈もなく、医師たちはすぐに彼の処置を始めた。呼吸がなく、目は動かず、左足は失われ、背中はぱっくりと開いて、顔は灰色に変わっていた。腹部は血だらけで、裸で横たわっていたが、血まみれの靴下はまだそのままだった。(略)
「三分経ったら教えて」いま起きていることをすべて把握し、監督している主任医師が大声で言った。彼女の声がいくつかの機械の音を押し分けて聞こえてきた。部屋には血とアンモニアの目眩のするような臭いが満ちていた。リーヴズは十人ほどの医師に囲まれていた。ある者は彼の顔に酸素マスクを押しつけ、ある者はエピネフリンというアドレナリン注射を打ち、ある者は、おそらく衛生兵だろう、彼の胸を、肋骨がすべて折れるのではないかと思うほどの強さで押していた。「もっと強く速く」と主任医師が衛生兵に言った。衛生兵はさらに強く押し始めたので、リーヴズのずたずたになった足の肉片が少しずつ床に落ち始めた。
──『兵士は戦場で何を見たのか』204〜206頁
これが戦場での現実でした。そして爆発のときに居合わせた仲間の兵士は、「どうして彼を救うことができなかったのか」「なぜおれは生きているのか」と自分を責めるようになります。イラクに派遣された兵士の平均年齢は20歳。皆若い未経験な青年たちで、帰還した者のうち多くがPTSDを患っているという報告もあります。
兵士は確かに命の危険な状況に置かれ、不安と恐怖を抑えながら戦場にいますが、任期を終えれば母国に帰って手厚い医療を受けられます。アメリカには帰還兵のための傷痍軍人病院がいくつもあり、そこではさまざまな負傷に対応していますが、イラク戦争後は、病棟に入れない兵士も増えています。そこにはすでに第二次世界大戦やベトナム戦争、アフガン戦争、湾岸戦争で負傷した兵士たちがいて、いまだに治療を受けているからです。アメリカは実に多くの戦争をおこない、その都度たくさんの死傷者を出してきたのです。
とはいえ、兵士は職業であり(つまり補償や年金が受けられる)、充実した医療設備のあるアメリカは、ある意味では恵まれていると言えます。しかし、戦場でずっと暮らさなければならない人々、つまり仕事も食べ物もなく、どうやって子どもを育てたらいいのかわからずに苦しんでいるような、たとえば内戦が続くシリアに留まり、国から逃げられずにいる人々はどんなことを考え、どんな思いを抱いているのでしょう。
ふるや・みどり
翻訳家。主な訳書に、エドワード・ケアリー『おちび』(最新作:2019年11月)、〈アイアマンガー三部作〉『堆塵館』『穢れの町』『肺都』(以上東京創元社)、近著にデイヴィッド・マイケリス『スヌーピーの父 チャールズ・シュルツ伝』(亜紀書房、2019年9月)。その他、ラッタウット・ラープチャルーンサップ『観光』(ハヤカワepi文庫)、イーディス・パールマン『双眼鏡からの眺め』(早川書房)、M・L・ステッドマン『海を照らす光』(早川書房)、ダニエル・タメット『ぼくには数字が風景に見える』(講談社文庫)など多数。