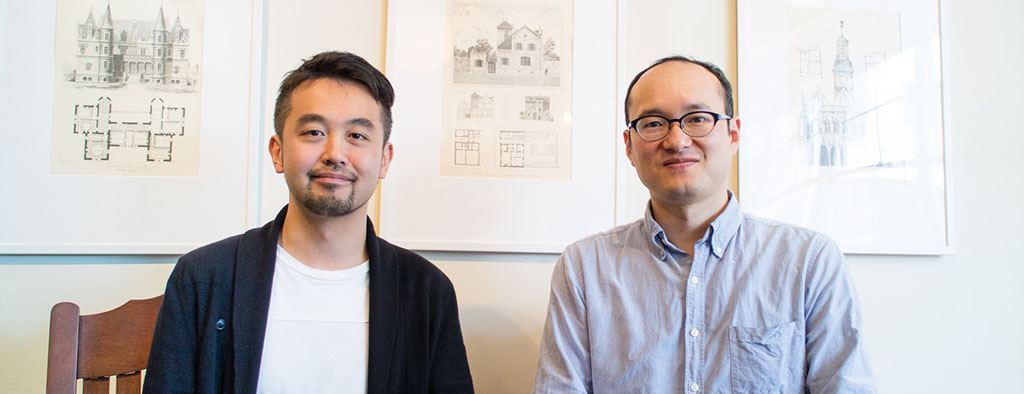チェン 僕は、痛みというものがその人の志向性を理解するうえで大きなヒントになると思っています。人はストレスを感じたり嫌だなと思う感受性の中に、その痛みを修正したり解決したりする創造性を、当事者意識として持つことができるからです。僕が教える大学の授業で、学生たちに最近ストレスだったり苦痛だったことをひたすら書いてもらい、互いに交換させるとすごく話が盛り上がります。そこで「自分だったらどう解決する?」というお題を出し、たとえば存在しないテクノロジーをSF的に考えてもらったりすると、その考えるプロセス自体に治癒的な効果が見いだされることがあるのです。
ただし僕は医療の専門家ではないため、人の痛みに踏み込むことには慎重であらねばと常に考えています。痛みはどんなものでも安易に共有できるわけではなく、本人にも語れないがゆえに恢復できない苦痛もある。社会的弱者と呼ばれている人たちの多くはそういう問題も抱えていますよね。だからこそ、痛みの共感・共有について考えることが、多様な人間の寛容さを満たす1つのスタートポイントになるのではないかと思います。
孫 痛みのケアは医療従事者の専売特許ではなく、社会的な痛み、たとえば社会的弱者のケアなどは、福祉の専門家や社会のさまざまな人によって考えていくべきですね。そもそも、そのように周縁化された人々は声を上げることができない。彼らの声をどうやってアドボケイトするのか。そういう意味では、やはりフィンランドで行われていた「対話(ダイアローグ)」の取り組みには大きな可能性があると思っています。
この対話の哲学の一つに、ドストエフスキーの研究者である言語学者のミハイル・バフチンが芸術批評に応用した「ポリフォニー」(多声性)という概念があります。ドストエフスキーの小説では登場人物を介して作家の思想が語られるのではなく、多様な価値観や考えを持つ人物を対等に扱い、それぞれの語りを錯綜させることで対話的に物語が積み上げられていく、とバフチンは指摘しています。オープンダイアローグに取り組む専門家たちは、現実の対話の場もこうした視点でとらえることを重視しています。
ポリフォニーとは、もともと多声音楽やその技法を表す言葉ですね。各声部ごとに異なる詩や旋律が割り当てられた複雑なカノン様式のことですが、人と人の対話も同様に、合目的的な統一した結論を前提とするのではなく、各人ごとの音程やリズムを尊重しながら全体として不協和音が生じない世界をともにつくりあげていくことなのかもしれませんね……。話が尽きないので、これについてはまたぜひ、じっくりお話する機会があれば嬉しいです。
今日はウェルビーイングを始め、痛みや感情の可視化、共感など、いま僕がとても関心をもっている事柄について、テクノロジーや情報学分野の取り組みに今後どのような可能性があるのかを知ることができ、大きな希望を感じる対談でした。これからの医療や福祉、教育など多くの分野におけるケアのあり方は、人工知能やテクノロジーの発展によって大きく変わろうとしています。ややもするとネガティブな論調も多い中、チェンさんのお話から明るい未来予想図を少し描けたような気がします。どうもありがとうございました。
チェン 孫さんと対談ならぬ「共話」させていただいたおかげで、僕の研究にとってもたくさんのヒントを得ることができました。オープンダイアローグとバフチンのポリフォニーの相関、フラヌールの無目的な遊歩の効能など、何らかのかたちで自分の活動にも取り入れたいと思います。
また、今日お話した「自発的な価値の生成」と「自律性」については、アートと能舞台の観点からも考えています。どちらも自律的な存在と対面し自らの価値を生成するためのきっかけを与えてくれるものですが、これは僕たちが「問い」や「謎」と呼ぶことの一形態なのではないか、といったことを、7月に刊行される松岡正剛さんとの共著『謎床』(晶文社)に書いていますので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。また、この対談記事を読んでくださった読者の方からも、ご指摘やご質問をTwitter(@dominickchen)でいただけると大変幸いです。
今日はどうもありがとうございました。