老いと病と死
1963年のことです。ボーヴォワールの一人暮らしの母親ががんで倒れます。70歳になるところでした。彼女は「死そのものは怖くないのだけれど、とぶのがこわい」と言います。つまり、死は怖くないが「死ぬ瞬間」が怖いのです。
やがて、がんに蝕まれている母の身体に、さまざまな不調が来し始めます。死と拷問の苦しみとのあいだの葛藤とでも言うのでしょうか。愛する者が「助けて!」という叫びを発しても、自分が何もできないとき、一体どのような向き合い方をすればよいのでしょうか。必ずしも母親とは良い関係ではなかったものの、ボーヴォワールはなんとか寄り添おうと努めます。しかし、わずか1カ月ほどで母は亡くなってしまいます。
ボーヴォワールは「母が自然に死ぬのをそのままにしておいてください」と医者に言いたかったのですが、それは言えませんでした。結果、苦しみながら母は手術を繰り返します。強がりを言ってみたり、すねてみたり、母はこれまで見せたことのないような「弱さ」をさらけだしてゆきます。モルヒネも使って痛みを緩和させるものの、それは病人の死のスピードを「緩めている」だけで、むしろ、苦しむ時間を延ばしているだけの「拷問」ではないのか、とボーヴォワールは悩みます。
もちろん、まわりの人たちは誰もが、母が死なないで生きていてほしいのですが、かといって、生きさせていることが、本当に「良い」ことなのかどうか、誰にもわからず、苦しむことになります。その人の死は、無数にある死のうちの1つにすぎないというような代替可能なものではなく、立ち直ることができないほどの打撃であり、それ自体がかけがえのないただ一つの存在であったことを、生き残る側に突きつけ、悲しみや悪夢をもたらし続けるのだと、ボーヴォワールはとらえます。
しかも、ボーヴォワールには母親に対する「後悔」が残っています。しなければならなかったことを怠ったのではないか、省いてしまったのではないか、放棄したのではないか……。そうした気持ちも含めて、最後に結論として何よりも死とは「事故」であり、もし本人がそのことを知っていたとしても「不当な暴力」であることに変わりはないのだ、と自らに言い聞かせます。
ただなんとなく、無配慮に時間の流れのなかに埋没するような「現在」ではなく、絶えず「今、ここ」であることへの自覚をもち、自己ならびに他者と真剣に関わってゆく「現在」において、「老い」や「死」もまた、いつかやってくる漠然としたものではなく、「現在」そのものとしてボーヴォワールはとらえようとしています。なぜなら人は、サルトルが強調していたように、全面的に自由でなければならないからです。あるときは自由で、あるときは不自由ということはありえないのです。この点が、ハイデガーのような、死の不可避性を厳然たる事実としてとらえる思想との決定的な違いです。
ボーヴォワールもサルトルも、ハイデガーとは異なり、「死」に幻想を付加してはならないと考えていました。もちろん人が「死すべき」運命にあることを否定はしません。しかし、あくまでも人の死は「事故」に等しいとするのです。自然的な出来事ではなく、不当な暴力なのだと。一般論的には、ハイデガーの言うことのほうが納得できますが、2人の「意地」のようなものも、わからないではありません。2人は「生きる」ということに、とにかく真剣だったし、特にそれは、近親者の死を前にして、より一層強い思いとなって表れていると言えるのではないでしょうか。
このように『おだやかな死』では、ボーヴォワールの母親が余命幾ばくもない状態で入院しているなかで体験した様子が詳細に描かれています。結果としてわかるのは、治療行為は医師(と看護師)と患者との間で交わされるものの、患者の家族からは隠されている一方で、看護行為はそのまま家族の目にさらされている、ということでした。少なくともボーヴォワールは、母親が看護師によってなされていることには好意的でした。仕事であるにもかかわらず病人と結ばれており、友情的なつながりがあると考えたからです。ただし、その仕事の内容については、ある種の悲惨さを感じ取っています。病人にとっては屈辱的であり、看護師にとっては不快極まりないことであることは避けようがないととらえられました。
これは、医療処置が、あくまでも専門的な能力や技術によって行われるものであるのに対して、看護行為が、自分たちでも行いうるものとみなされていたからでしょう。自分でもできることをわざわざ他者にまかせているという「負い目」が、看護行為を見つめる目を厳しくさせているのではないでしょうか。
1981年に発表された『別れの儀式』という作品は、1970~80年にかけてサルトルが死に向かうプロセスを綴った日記と、1974年8~9月に行われた2人の対話をまとめたものです。ボーヴォワールの立場(患者ではなく患者の家族の目)からすれば、医療現場の中に入った患者は常に侵襲にさらされることになります。ボーヴォワールにとって、病も老いも死も不可避であるがゆえに、「生」の側からすると暴力にすぎないのです。
こうした不条理さを自分が受け止めるためには、それぞれの死へのプロセスを自分が見たままに書き記すことが必要だったのでしょう。ただしボーヴォワールも、自分の母親のときと比べると、サルトルの末期には、もう少し冷静になっています。この「暴力」を少しずつ受け入れているように思えます。
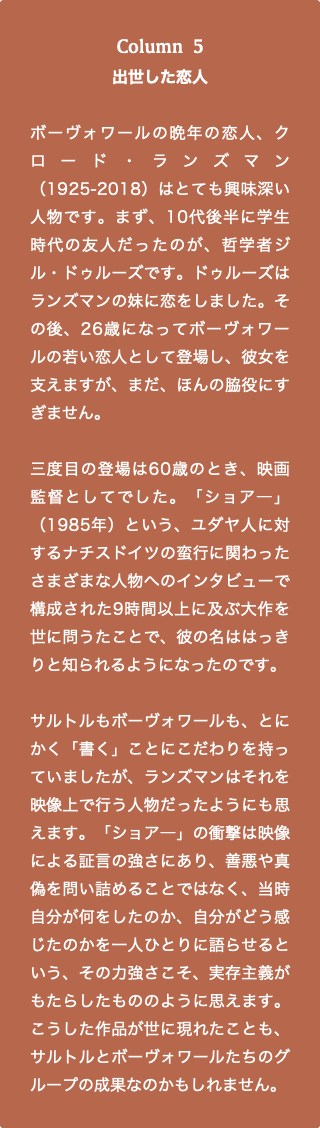
注目したいのは、ボーヴォワールが自分の母親を看取り、サルトルを看取ったその姿、もしくはその姿を描写しようとする彼女の「意志」です。ごく普通の日常をていねいに描いているのです。これこそ、これまでの哲学者が表現してきたものと、決定的に異なるものだと言えないでしょうか。孤高であったり、高みに立っていたり、根源的な問いを突きつけたりするというよりも、身近な人に寄り添い、ともに生きる(そして、ともに老い、ともに死に向かう)という姿勢が全面に出ています。
これは言い換えれば、看護や対人援助に差し向けられた哲学とも言えます。日常の喜びや悲しみ、不安や苦悩とともに向き合う哲学は、派手さや新奇さはありませんが、とても大切な問いかけの仕方、他者とのかかわり方を示唆しているはずです。
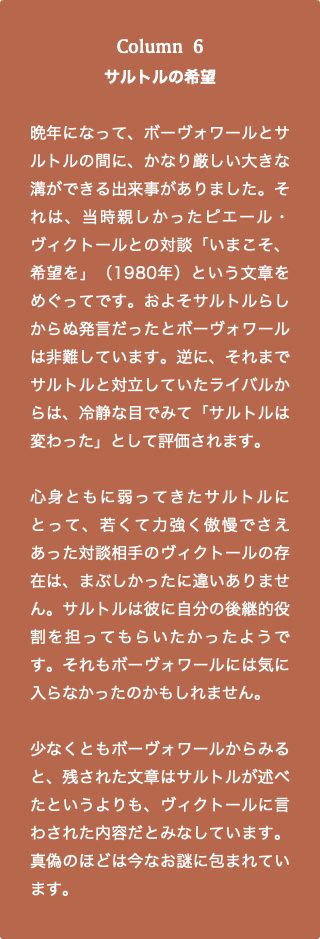
シモーヌ・ド・ボーヴォワールSimonne de Beauvoir1908-1986 フランス 第二次世界大戦後、世界的に知られた女性哲学者。サルトルとともに生きた。個人の名前では「第二の性」によって、女性解放運動の先駆者として常にとりあげられる。書き残した作品は、これまでの哲学とはスタイルが異なるが、常に他者と向かいあう姿が描かれ、対人援助の現場にかかわる人にとって重要な示唆がある。
ジャン・ポール・サルトルJean-Paul Sartre1905-1980 フランス 第二次世界大戦後の世界を生きる指針を提示し続けたフランスの哲学者。ボーヴォワールとともに生きた。自由を追求し責任を問いかけた彼らの実存主義は、狭いアカデミズムを抜け出て、多くの市民や労働者の心に響いた。学者や専門家というよりは、行動的知識人という名にふさわしい。
***
ナイチンゲールは「すべての女性はナースである」と述べ、「看護」が「女」と不可分なものととらえました。これは、ボーヴォワールから言わせれば少し不正確な言い方です。つまり、単純に「すべての女性は(生まれながらに)ナースである」のではなく、「社会的、文化的、さらに言えば、歴史的にナースになる」ということ、「ナースであること」を引き受けて生きているということになるでしょう。
ナースは、社会のなかで、他者との営みのなかで「ナースになる」ものです。「看護」を「女性」にとって当たり前の行為、単純に「自然=本能」的な行為とは考えず、「看護をする」「看護師になる」ことを意識して生きること。ナイチンゲールも、そうした考えのもとで、あえて「すべての女性はナースである」と述べたのではないでしょうか。
哲学者が登場する連載は今回のボーヴォワールでおしまいです。次回は最終回として、哲学と看護(理論)との関係性について、総まとめをします。
──────────────────────自己紹介 | イントロダクション | バックナンバー──────────────────────