
フーコー Michel Foucault1926-1984 フランス 第二次世界大戦後、サルトルに続く大哲学者として終始注目を浴び、時代的には実存主義を批判した構造主義者の一人とみなされたが、本人は自身のことを「歴史家」「爆破技師」と考えていた。サルトルが個人の内面を生々しく描き出そうとしたとするならば、フーコーは社会や文章に表出してしまっている「嫌なもの」をていねいに拾い上げ人々の目の前につきつけた人物、という見方もできる。一度は就職先を日本にしようかと迷うも恋人との関係で断念、その後の来日では座禅を組むという体験をする一方で、新宿2丁目にも出没していたというエピソードも残されている。 〈フーコーをめぐる人物相関図〉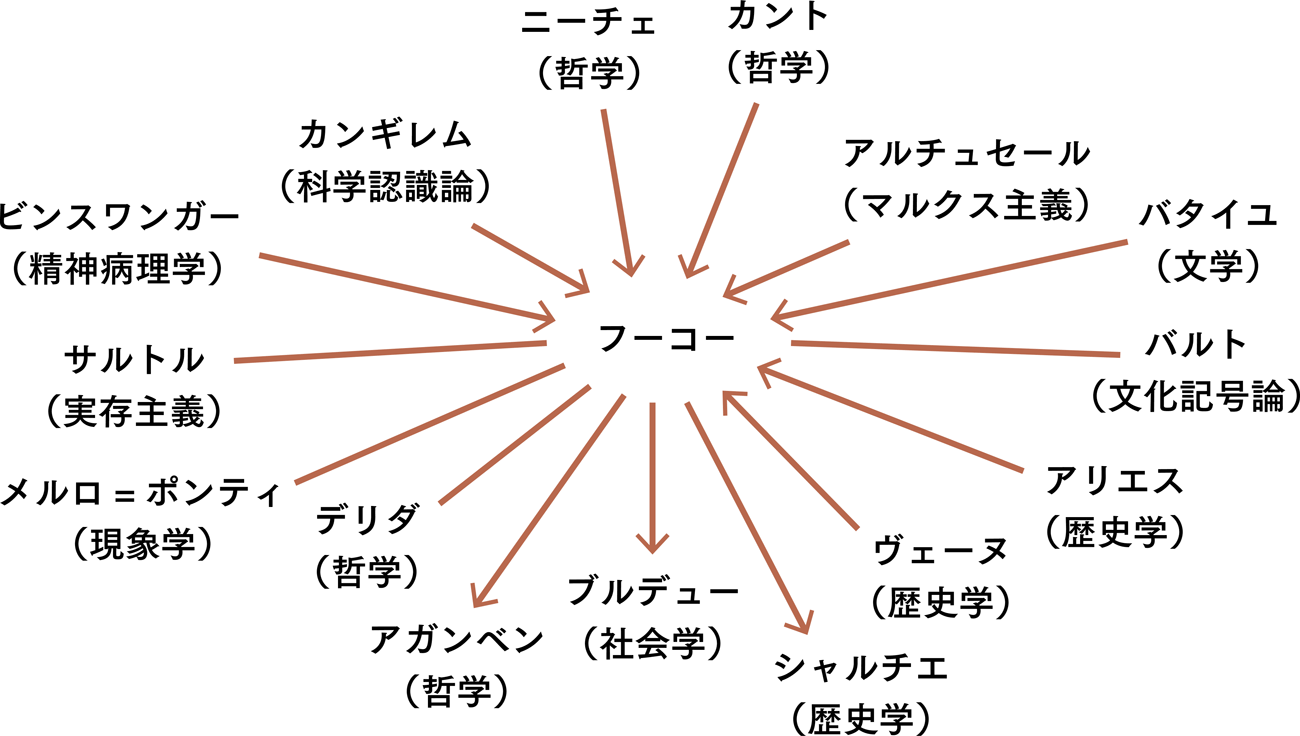
正常と異常、健康と病気
フーコーが見つめていたのは、目の前の医者と患者の人間関係の軋轢であったり、現存する病院や体制の欠陥にとどまりませんでした。そうした現実をつくりあげるに至ったこれまでのプロセスをたどることに力を入れ、歴史の厚み、言葉の深みから要点となる部分を半ば強引に引っ張り出して、独特なやり方で再構成しようとしたと言えるでしょう。
すなわち、現代社会と医療の常識では、人には皆違いがあるということと、正常ではなく異常だということと、そして健康ではなく病人だということが、すべてひとまとめにされてしまっていることに、フーコーは驚きを感じたのでしょう。これがその後の大作『狂気の歴史―古典主義時代における』(1961年)の中心モチーフとなります。つまり、一人ひとりの生き方や考え方、外見その他の違いを理解してその相手とかかわるということと、医者もしくは「医療的な知」が患者を前にしてその人の症状をとらえ、ある病気を認定し、治療行為を行うことと、さらにはそうした行為を境にして世間では人間を「正常」と「異常」とに区分けしているということは本来それぞれ別物であるにもかかわらず、医療実践と知はこれらをひとまとめにしてしまっている、とフーコーは主張しているのです。
すなわち、正常と異常、健康と病気という二項対立で多様な人々を識別・判定・評価することの危険性(とされることの影響)を訴えている、ということになるでしょうか。こうした、正常や健康という枠組みに入らないものに対して、価値のないもの、価値が低いものと見なす、矯正や調教を行って正しい道に進ませようとする流れに対するフーコーの批判精神は、その後『監獄の誕生─監視と処罰』(1975年)で「訓育=調教」を行う権力と見なされるに至ります。つまり医療(従事者)もまた、患者に対してそうしたことを行っているのではないか、という問いかけがあるのです。
そのほか、さまざまな理由でさまざまな人たちが幽閉された施療院や貧窮院から、「狂人」だけが収容された病院が、特別な社会的役割を担っていった経緯にも焦点を当てています。しかもただ収容することだけを意図していた施設が治療を目的とし、かつ、その治療を実践する医者(さらには看護実践を行う人)がそこに常駐するところに変わっていったととらえます。もちろん、深淵なるテーマとは別に、フーコーの内面的な動機として言えば、『狂気の歴史』は、なぜ自分が医者になりたくなかったのかを歴史・社会の文脈で掘り下げた本とも言えるかもしれません。
───────────────────────────────────
![]()
「先日、看護技術論の講義においてロールプレイを行った。ロールプレイでは、患者役と看護師訳とそれぞれを観察する役とに分かれ、場面と患者役のみ、今の心境や体の状態などが細かく設定されている。看護師役はコミュニケーションを通して今後の援助に役立てるためにいかに患者の情報を収集するかを演習し、その後グループ内で演習について思考する内容であった。しかし、私は「看護師」という与えられた役割にとらわれすぎてしまい、患者を病・ケガを負っている「患者」としてしか見ることができなかった。さらには「今後の援助に役立てるための情報収集」ということばかりに重点を置いたコミュニケーションしかとることができなかった。つまり、私は患者を異常とみなし、自分と同じ一人の人間としてかかわっていなかった。自分は正常であり、患者は異常として、無意識のうちに線を引いてしまった。このことに、フーコーを学んで気づかせてもらった」
以上は、看護学生が私の授業の感想として書いたものの一部です(少し手直しして使わせていただきました)。どのようにフーコーの思想を受け止めたのか、その一端が垣間見られるかと思います。
───────────────────────────────────
医療のまなざし、看護のまなざし
『狂気の歴史』を書き上げたフーコーは、さらに『臨床医学の誕生』(1963年)という本も書いています。ここでは、解剖医学(外科学)に対して内科のもつ独特の話法やレトリックに焦点を当てています(ほかにも医療施設や法整備など、多層的な分析が行われていますが、ここでは省略します)。フーコーは、身体内部に入り込むことなく皮膚の表層で病や死の「しるし」を示し出すことへの特異性にとても興味を覚えたようです。
内科は、皮膚の内側で何が起こっているのかをあくまでも外側から症候を集め、これまでの類例を参照にして「病」を探り当てるという、不思議なことを行っている、とフーコーはとらえます。他方で外科学は、特に死体の解剖をめぐって、豊饒な知や言葉を生み出します。デカルトのところで説明したような、単に内部の仕組みや部位を図に落とすという次元を超えて、死に至る細やかなプロセスを内部に見るという実践をします。つまり、人間の死にゆくさまを内側から綿密に明瞭化させる(=インテリジビリティ)ということを成し遂げたのです。
ともあれここでは「まなざし」という言葉がクローズアップされています。これは「医学」のまなざしであり「医者」のまなざしでもあり、今ならばおそらく「看護(師)のまなざし」でもあるはずですが、残念ながらフーコーは看護という次元までは対象としませんでした。しかし今ならば、看護実践の現場で行われていることを、ナイチンゲールの時代からひもといて、歴史的な変容を記述することも可能でしょう。看護学も今や、単なる経験則や精神的なケアという側面よりも科学性、客観性、学問性などが求められており、場合によってはエビデンスに基づいた看護知というものを生み出しています。それらが一つの権威となって医者や患者と対峙しているという言い方もできるでしょう。
行き過ぎた医療化という文明の病
おそらくここでフーコーが感じたことは、特に医者との関係、患者との関係について、看護に携わっている方がこれまで感じてきた違和感や不満などとも重なっていることでしょう。とはいってもフーコー自身の記述の中で看護の役割や人についての言及はほとんどありません。1974年にブラジルで行った「医療化」にかかわる内容の講演録が目立つくらいです。18世紀になってヨーロッパでは初めて、豊富な経験をもつ医者が専属でいる病院が現れ、それとともに医者にこれまでにない力が帯び始め、そのまわりに医療関係者が付帯しはじめた、と説明するくだりです。病院の規律化が進み、規則などに、看護師が医者の後に病室に入ることなどを定めはじめた、という説明をフーコーは行っています。
現場の医者とその関係者たちは、患者とのやりとりにおいて科学的裏づけ(知)の援護射撃を受けながら自分たちの言動を正当化して治療を行い、その繰り返しをフーコーは「知/権力」つまり知と権力は一体化したもの、密接な相互関係をもったもの、としてまとめています。
フーコーが医療界に与えた衝撃としては、近代の社会が「医療化」したという指摘が第一だと思います。この言葉自体はイバン・イリイチの『脱病院化社会─医療の限界』(1975年)によって広く知られるようになったものですが、そのイリイチ自身がフーコーの影響を強く受けています。この「医療化」についてフーコーは、端的に、私たちが「出産」「病気」「死」にかかわる際には病院や医者なしにはありえない、と疑いもなく考えてしまう現実を指しますが、先に述べたようにフーコーがブラジルで講演を行った内容の影響は当時メキシコにいたイリイチにも届いていたと考えられます。
大雑把に言うと、病院や医者や薬や手術などが、絶対的な正しさをもっているわけではないにもかかわらず、私たちはついそれらに依存や従属を行ってしまうという批判が「医療化」という言葉にはこめられていました。看護実践はおそらくそうした医療化の強化というようなまとめ方ができると思いますが、同時に、医療化の柔軟化という側面もあるように思います。「柔軟化」というのは、私の勝手な造語で、医療化の悪い側面を和らげるとともに、場合によっては医療の制度化、固定化、膠着化を突き崩す可能性もあるのではないか、という意味合いを持たせたくて使いました。おそらく現在の看護学の内部においては、そうした議論はしにくいことでしょう。しかし、フーコーの思想の重要な意味はむしろ、こうした本来内部にいる者が分からなくなっていること、言いにくいことを外部からではなく内部から見つめなおすことだと思いますので、どうか耳を傾けていただければありがたいです。
───────────────────────────────────
![]()
フーコーの著作のなかでも学術書としては珍しくパリのベストセラーとなった『言葉と物』(1966年)という代表作があります。ここでは直接医療には触れていませんが、近代知の大きな3つの枠組みの一つとして「生命」が「労働」「言語」とともに取り上げられています。『臨床医学の誕生』も『言葉と物』も、当時流行した「構造主義」の影響を受けていると言われ、無数の書物や考え方を、半ば強引にある道筋の裏付けのために当てはめたところがあります。しかし同時に、時代の雰囲気やその根底にある自明視されていたものへ向けられた、ダイナミックかつ想像力豊かな独特のまなざしがとても興味深いです。特に「生命」という考え方が、必ずしも古くからあるものではないという指摘があります。それ以前の博物学は「生き物」を対象としているという意味では、その後の生物学と連続性があり、あまり変わらないように見えるのですが、博物学と生物学では、全くその知の基本が異なっており、「生物」という概念は生物学において主要なものとなったものであって博物学には重要なかかわりをもたないとされています。
───────────────────────────────────
────────────────────────
────────────────────────


