───
───
───
特集:ナイチンゲールの越境 ──[戦争]

2階展示室(常設展)
![リポート「しょうけい館」 [第1回]戦傷病の実態 text by 林田悠紀子(編集部)](../images/u17207-20.png?crc=114796850)
< ● ●
⑥帰還後の労苦
内地に還送された傷痍軍人が、臨時東京第三陸軍病院(現・国立病院機構相模原病院)でリハビリを受けているようすが紹介されています。下の写真は実際に使用されていた義足です。


背後には社会復帰の訓練を受けている場面を写した写真が展示されています。アルミの外骨格を本革で包んだ義足は、足の断端部にはめ込みショルダーベルトを肩からかけて外れないようにしていました。
重さが3kgもある上、歩くたびに装着部分に全体重がのしかかり、肩にはベルトによる擦れが生じます。しかし、その痛みをこらえて歩けるようにならないと、退院(除隊)できませんでした。

<義指> 戦時中、義肢は「御賜」の品として、「皇后陛下の思召」をもって下し給うとの文言が入った御沙汰書が添付されていました。
戦時中は「お国のためにがんばってくれた」傷痍軍人をみんなで応援しようと、「護れ傷兵」と訴えるポスターもつくられていました。そして実際に、除隊した傷痍軍人には日常生活上の障害程度に応じた恩給が支給され、社会復帰も含めてケアをする体制も整っていました。
⑦戦後の労苦(常設展順路では「箱根療養所」)
昭和20(1945)年8月15日の終戦以降、戦後の日本を統治したGHQは軍人への優遇措置を撤廃していきます。その一つが恩給の打ち切りでした。陸海軍病院は国立病院と名称変更され、入院していた傷病兵は退院させられました。それと同時に、世の中が軍国主義から民主主義へと180度変わったことにより、世間の反応も変化しました。陸海軍病院から退院させられた傷病兵が、帰省中に「お前らのせいで戦争に負けたんだ」と、子どもに石を投げられたこともありました。

<恩給廃止・街頭募金> 昭和26年(1951)年、大阪の心斎橋で行われた街頭募金の様子。両足切断の重傷者が前に立ち、彼よりは軽傷の仲間が後ろで音楽を演奏して同情を誘い、お金を乞います。
戦後、軍人だけでなく軍属(軍の施設で働いた人等)、準軍属(国の命令で動員された人等)も含め、戦争中の公務により戦傷病を被った人は、総括して「戦傷病者」と称されました。
昭和26(1951)年のサンフランシスコ講和条約調印以降、日本傷痍軍人会が発足して恩給も復活しました。同会は「恩給が支給されている以上は自活できるように」と指導を行い、街頭募金の一掃運動を行うようになりました。それでも、昭和50(1975)年くらいまで街頭募金の姿を見かけることがありましたが、そのほとんどは戦傷病ではない「ニセモノ」が行っていました。
戦後のこの時期が、戦傷病者にとって長い困難の時期であったといえます。

<質札> 昭和30(1955)年以降は高度経済成長期に入り、右肩上がりの時代でした。しかし、戦傷病者とその家族は戦後の恩給がない時代に借金を重ねていた人もいました。彼らの恩給はそのまま借金の返済に流れ、服だけではなく布団まで質入れしなければならないような状況でした。また、復活後の恩給は生活保護世帯の給付額よりも低く、生活は厳しいものでした。

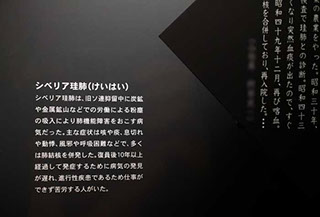
<トロトラスト> 戦時中のX線撮影時に使用されていた造影剤のトロトラストは、肝機能障害を引き起こすことが後に判明し、社会問題となりました。戦争で怪我をし、さらにその治療のために使用した薬剤で肝機能障害が引き起こされるという二重の苦しみに戦傷病者は直面しました。その他にも、旧ソ連抑留中の炭鉱などでの強制労働の際に粉塵を吸い込んだことが原因で、復員後に肺機能障害を発症する人もいました(シベリア珪肺)。

<箱根療養所> 戦時中、脊髄損傷を負った傷痍軍人が入所していた傷痍軍人箱根療養所(現・国立病院機構箱根病院)に関する展示で、写真は昭和40(1965)年代頃、妻が夫の乗った車椅子を押して坂を上がっている場面。昭和39(1964)年の東京パラリンピックで選手宣誓を行った青野繁夫さんも、ここに入所されていました。
⑧ともにのりこえて
戦争により左腕を肩から10cm部分で切断された男性や、両足を切断された男性、沖縄戦で右腕と顔面を負傷した女性など、証言映像を収録した4人の人物についての資料が紹介されています。戦後、妻や家族の支えによって重い障害を克服し、社会で懸命に働いてきた姿が写真に収められています。彼らのひとりは映像の中で「自分たちは障害者だけど、手足がなくても健常者以上にがんばっている」と話されています。
身体に障害を受けながらも、戦後を生き抜いてきた戦傷病者だからこそ、彼らの多くが平和のありがたみを強く訴えています。
「ある兵士の足跡」
──傷痍軍人たちの手記より
<徴兵>
二十歳をむかえる夏 徴兵検査を受けた
甲種合格となり
入営の日を待つばかりとなった
昭和十二年に盧溝橋事件が起きてからすでに三年
中国での戦線は拡大の道をたどった
<入営>
明日はいよいよ入営だ
正月祝いもそこそこに
家族や知人に見送られ故郷を後にした
新兵としての訓練がはじまった
<出征>
数か月の訓練を経て
出征することになった
大勢の兵士を乗せた汽車は港へ向かった
出航して数日後 船は大陸に着いた
<戦地>
昭和十六年十二月八日 日本軍が真珠湾を攻撃
米英との戦闘状態に入ったとの大本営発表があった
戦域は中国大陸から南方へと拡大した
部隊は南方に向かうことになった
昼はジャングルに潜み
夜は重装備で道なき道をゆく日々が続く
もう何か月も満足に食べていない
行軍に耐えきれない戦友が次々と斃れてゆく
<受傷>
夜襲命令で突撃したその瞬間
全身に激痛が走った
うすらぐ意識の中で
衛生兵にはげまされながら
応急止血をしてもらう
翌朝には仮繃帯所に運ばれた
<救護>
野戦病院に移された
受傷した手と足が悪化し
切り落とされることになった
麻酔もなく
身体をおさえつけられて
激痛に耐えた
いま 壕の中にいる
<搬送>
病院船の中は 傷病兵でいっぱいだ
故郷の家族は今 どうしているだろうか
片足を失った私をどう見るだろうか
そう思う一方で
今も戦地で戦っている戦友の姿が頭によぎる
<療養生活>
再び故国の土を踏んだ
しかし 自分の身体は以前のものではない
病院で再び手術を受けた
義足で皮膚を痛め 歩行訓練がつらい
<終戦>
昭和二十年八月十五日
戦争が終わった
<戦後復興>
やっと退院して故郷に戻った
誰もが生きることに精一杯だった
国の支えを失った私も
生きていけなければならなかった
<経済成長と暮らしの変化>
良縁に恵まれ 子どもも生まれた
家族を支えるため
傷の痛みに耐えながらも懸命に働いた
身体が思うように動かないため 職場を転々としたが
ようやく自分に適した仕事が見つかり
ひとまず生活のめどがたった
<傷病とともに生きる>
家と職場の往復で 無我夢中の毎日だった
だが時折傷口がうずく
前のような元気な身体であればと思う
くじけそうにもなったが
そんな時 いつも妻が支えてくれた
<さまざまな戦後と労苦>
かつて戦争があった
今となってはその面影はない
しかし私は癒えることのない傷を抱えながらも
家族や良き仲間に支えられ
戦後を生き抜いてきた
もう二度とこのような戦争のない
平和な世界であることを祈りたい
──取材を終えて──
毎年8月になると、新聞やテレビで戦争についての報道が多くなります。それを見るたびに、「もっと戦争について、知らなければいけないのでは?」と思っていました。そんな中、しょうけい館のことを知り取材をさせていただきました。
戦争で怪我をするとはどのようなものなのか、銃で撃たれた人はどうなるのか、どうやって手当されたのか。手や足がなくなってしまった後はどのように生活してきたのか。実際に展示されている品々を見ると、本を読むだけではわからなかったことが見えてきたように思えます。
戦場では、包帯の代わりに日章旗で手当された兵士がいて、麻酔もない状況で銃弾を身体から取り出されていたりしました。爆弾で四肢を失い義足や義指をつける練習をする人もいました。そして敗戦後の彼らは補償もなく社会に放り出されて、布団までも質に入れるような生活を余儀なくされました。
ですが、そのような苦難が続いた人生でも、戦傷病者たちは妻や家族と労苦を「ともにのりこえて」毎日の生活を重ねてきました。そうしたひとり一人からなるたくさんの人々が、戦中も戦後も確かに生きていた……。展示されている寄贈品のすべてがその証でした。
文責 = 編集部
取材協力 = しょうけい館学芸員 木龍克己
───────────
※第2回「労苦を語り継ぐ(仮)」は、2019年9月頃に公開予定です。
< ● ●