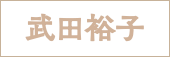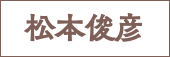弊社より4月に刊行された『格差時代の医療と社会的処方:病院の入り口に立てない人々を支えるSDH(健康の社会的決定要因)の視点』が話題を呼んでいます。キーワードのSDH "Social Determinants of Health"とは、健康を左右する、個人に起因しない構造的な要因であり、格差が広がる中で医療者や学生がその考え方を学び始めています。最前線で独自の実践に取り組む編著者らが、医学生(武田ゼミのみなさん)を前にSDH的なアプローチとその意義について語り合いました。
好奇心に訴える
武田:では次はHさん。
学生H:はい、漠然とした質問なのですが、いま日本では社会的な格差が健康的な格差につながっている現状があり、何もしなければこのままそれがどんどん広がっていくんだろうなと思います。私は日本が好きで、もっとみんなにとっていい国になるようにしたいと思っています。社会全体を変えるためには大きな動きが必要だと思いますが、その前に自分の近くにいる人にどう伝えていけばいいのか……。自身もこのゼミに入って初めてさまざまな現状を知ったように、まだ知識のない同級生たちに理解してもらうことに難しさを感じています。何かよいアドバイスをいただけると嬉しいです。
山中:「?=クエスチョンマーク」をもつことです。「どうして?」って知りたい欲求は誰にもあると思います。私の場合、最初に話したように「どうして寿の人たちはここにいなければいけないんだろう」でした。この人たちがそこにいる経緯が知りたかった。今日ここにいるみなさんがどうしてここへ来たんだろう。それってまあ縁みたいなもので、たぶん私の「?」と武田先生がイギリスへ留学してSDHを修得することになった「?」、それと松本先生はじゃんけんで負けたとおっしゃいますが(一同:笑)、そこへ至るまでにきっとさまざまな「?」があったはずだと私は思います。
人間の好奇心はとめどないもので、みなさんがこのゼミを選んだのは、何かを欲していたからなんだろうと。そこに気づくチャンスがあるかないかが個人的な差だと考えれば、他者に問いかけることによって、すごく大事なチャンスをつくることになる。例えばビーガンの人たちの活動方法もいくつかあって、家畜の殺戮を見せることで心を痛める仲間を増やすやり方もあるだろうけど、そういうことに拒否感を示す人も少なくないでしょう。ならば、どうして自分たちがそうした活動をしているのかを考えることで、もう少し深みのあるアプローチが可能になっていく気がします。私の場合は、好奇心に訴えることを重視すれば暴力的な刺激を与える必要性はないと思っています。まだ本人が見たいとも思っていない路上生活者に会わせようとして誘うのは、それこそ暴力なんですよね。そうじゃなくて、話題の中で相手に「?」をもってもらえるような問いかけをつくることを覚えるゼミであっていいと思います。私が患者さんをずっと見てきた中で、自分の進路を決断する分かれ道に来たときには「?」が点いていたんですよ。そこで行ったさまざまな選択の総和で、いまここにいるわけです。
松本:私はいまの若い人たちはちゃんとわかってくれると思うんですが、そうでもないのかな……。いろんな情報をSNSなどで発信したりして、自分たちの同級生の何割を変えるとかいう発想だと難しくなってくるけれど、学校を超えて医学生全体でそういったことに関心をもつ人たちの絶対数を増やすと考えれば、食いついてくる人はいると思います。それがムーブメントになったときに、それまで反対していた人も振り向いてくれる気がします。むしろ一番難しいのは、人口の層が大きくて選挙にもせっせと行くような世代を変えることだと思います。若い人たちはリベラルでいい考えをもっているのに、選挙へ行かないよね。
武田:そう。選挙には行きましょう!(笑)。
患者によって医者は変えられる
学生O:私もHさんと同じことを考えていました。SDHについて同級生とにディスカッションをしたいと思ったとき、「自己責任だ」という人に加えて、私たちのように考える者に対して「思想が強い」などの偏見をもたれていると感じることが結構あるんです。
松本:なるほどね(笑)。
山中:「あいつヤバいぞ」とかね。
学生O:そのせいで発信することに怖気づくこともあります。私の弟も、別の大学の医学部にいるのですが、自分とは正反対の考え方で完全な自己責任論者なんです。女性に対しても下に見るところがあって……。私は昔からセクシャルマイノリティについて関心を寄せていたので、家でそういう話をすると「気持ちわるっ。そんなこと考えて意識高い系でマジ嫌だ」みたいなことを言われます。それに私には松本先生のような経験があるわけではなく、人から聞いた話などから考えることが多いため、自分でも頭でっかちになっちゃってる部分もあるなと思い、発信することがおこがましいんじゃないかと考えてることもあって葛藤しています。どうやったらそういう気持ちに打ち勝って、自分の正しいと思うことに向き合えるでしょうか。
松本:実は恥ずかしながら、私も医師になってから3年目くらいまでは、その弟さんと似ていたかもね。ちょっとマッチョな考えをもっていた気がします。ただ患者さんとの出会いなどが否応なく自分の価値観に楔を打っていった。患者によって医者は変えられるんですね。また、いまの研究所に来てから、国際保健などにも取り組むようなさまざまな研究者がいて、いわゆる「意識高い系」の感じがする言葉が周りに飛び交っているんですね。そういうものを聞きかじっているうちに、最初は「格好つけやがって」なんて思いつつ、自分がこれまで臨床の現場で経験してきたことにつながりはじめたんですよね。モヤッとしていたものを表現する言葉があったんだと。まあ、つまり人は変わると思うんですよ。
山中:私も同じ意見ですね。時間と経験。自分は若いときにものすごくチャラチャラした研修医で、ずーっと遊ぶことばっかり考えていました。振り返ればそれがあったから逆に今がある、とも言えるのです。逆にいまあなたのように真面目に考えている人がとんでもない遊び人になるかもしれないしね。わからないものですよ。
一同:笑。
山中:タレントになってTVでコメンテーターなんかやったりして(笑)。まあ、どうなるかなんてわからないから面白い。とはいっても今すごくいろんなことを考えたり戸惑ったりする気持ちも、すごくよく理解できますよ。
居場所をつくる
松本:じゃあKさん。
学生K:私はまだゼミに入って短いのですが、今日のお話で自分の世界観や価値観が変わっていくことを実感しています。ゼミでも少年院について学んでいるのですが、今日のお話のように自分のおかれた境遇から入らざるを得なかった人が、少年院にいる間にようやく自己肯定感を得て社会に出たときに、それを受け入れる体制がないことをすごく感じています。社会そのものを変えることがすごく難しい中で、自分たちにできることは何だろうと思っています。
松本:それはとてもいい問題意識ですね。家庭の中で暴力を受けて過酷な体験をしながら、不良グループの間でお互いを出し抜き合ってそこでも暴力を受けたり逆に与えたりと、油断も隙もない、常に警戒を解けない生き方をしてきた子どもが少年院に入ってくると、最初はすごい顔をしているんだよね。目がつり上がってさ。でも半年もするととてもいい顔に変わってくる。それが院から出てクリニックで会ったりするとまた怖い顔に戻ってるんですよ。つまり少年院には一定の効果があるし前科もつかないから社会復帰の可能性もある。でも地域の中に彼らがいる場所がないところに問題があるんですよね。
かつてはね、そんな彼らを受け入れてくれていた場所があったんですよ。トラウマや精神障害、あるいは知的なハンディキャップや発達障害があり普通に仕事に就くことがうまくいかず、かつ安心して帰る家もない。そんな若者を受け入れていたのが暴力団だったんですね。親を知らない子たちが親分や兄貴を慕って生きることで一種の疑似家族を体験していた。それが暴対法で社会がクリーンになってきている中で、とくに男の子たちの居場所がなくなった。女の子たちには、いろいろと問題はあるものの、住み込みの風俗というかたちでまだそれがある。すぐに仕事をくれて調子悪いときには休めるし、最近では託児所付きの風俗なんかもある。
ただトラウマを抱えていることでその仕事によってさらに傷がつく経験をすることもあるし、男性からひどく理不尽な搾取を受けているという事実もあります。その結果メンタルをやられて仕事ができなくなり、さあ生活保護をというときに、2つの理由でそれができないんです。まず就業証明ができないかたちで給料をもらっていることがあるから、役所に説明ができない。それから金遣いが荒くなって生活保護での暮らしに馴染まなくなってしまっているんです。コロナがなければいわゆる“パパ活”で生きている子たちもいましたが、いまはそれもなくなっている。
だから社会が「クリーン」になればなるほどそうした子たちの「かろうじての居場所」さえ消えていっているんですよね。その代わりになる、もっとちゃんとした場所をどうやってつくっていくのか。でもお上や大人が考えた制度や施設ではおそらく誰も入りたがらないでしょうね。絶対に厳しくてうるさそうじゃないですか。それよりももっと若者たちの価値観でつくれるかどうかが大事です。
いま政府には、少年法を引き下げて18歳を大人にして刑罰を与えようとする動きがあり、与党議員の間で絶対的多数で通過しているわけです。そして少年の加害による深刻な事件が起こるたびに世論が盛り上がる。実際には少年犯罪はこの数十年の間に激減しているんですが、報道が重なることで「増えている」という誤った認識が広まって、その結果少年たちが更生したり生き直しをするチャンスが奪われている。そうした事実や状況を若い学生たちでシェアしてもらって、同じ若い自分たちで何ができるかを考えてほしい。大人がつくるものではなく自分たちの価値観で、そこへ行くことが格好悪くないような場所をね。そのためにどのようなヘルスプロモーションを行えばいいかを考えてほしい。ぜひNPOを立ち上げください(笑)。
待つことしかできない
武田:次はSさん。
学生S:松本先生が「自己責任論を振りかざす人自身の立場についても思いを馳せる必要がある」とおっしゃいましたが、自分が医師になったときにそのように相手の立場を知ること、変化に気づくことがうまくできるのだろうかと感じています。自分のことをなかなか話してくれない人もきっといるでしょうから。私は昨日、地元の生活困窮世帯の子どもたちを対象にした学習支援に参加していたんですが、その子たちと接した感じは普段から知っている他の子どもとそれほど変わらない印象でした。彼らにそうした背景があることは事実ですが表面的には何もわかりません。問題に気づくためにどうアプローチをすればいいのでしょう。
松本:端的に言えば、まず相手をジャッジしないこと。良い悪いといった価値判断を決めずに素直に話を聞くというのが、技法としては一番大事だと思います。山中先生や武田先生がいる前で私が言うのは恐縮なのですが、そのためには経験というものがすごく大事なんだなと思うんです。長く医師を続けることはそれだけで意味がある。これまでいろんな人たちの物語を現場で耳にしてきたけれど、すべてを話してもらうことはオペで大きな傷を開くことに似ていて、開けたら開けたで大騒ぎになることもあるのです。
つまり大事なのは、少しずつの情報でもそれが時間をかけて頭の中に堆積してくれば、あまり語られなくてもその人の物語をぼんやりと想像できるようになってくるんです。いわば、小さな切開でもオペができるようになってくる。それは駆け出しで身につけることは無理でしょう。困っている人のお話を浴びるように聞く。その過程で、よせばいいのにしつこく聞いちゃって患者から嫌がられたり、フラッシュバックが起きて大暴れされてしまい、看護師さんから「先生が話を聞きすぎるからですよ!!」って怒られたりとか(笑)……嫌な思いもたくさんしてください。
一同:笑。
山中:いいお答えですね。私からもアドバイスするとすれば、まずあなたが自分の悩みを相談するときにどんな人に声をかけるでしょうか。
学生S:私もなかなか人に悩みを人に言えない性格なんですが、「この人には」と思えるのは何を話しても受け入れてくれる人ですね。
山中:それが答えですよね。子どもたちも自分の言うことを聞いて受け止めてくれる人に本音を言う。例えば看取りの現場であるホスピスにも自分の人生の最期にいろいろな話をしたい人がいます。それまでの経歴や成し遂げたこと、さらには告白や懺悔もしてしまいたい。だけど、それは「そのとき」「その人」に向かってしか言わないものです。私たちは無理やり引き出すのではなくそのタイミングを待つことしかできない。精神科医の先生はそういう仕事をしていて、循環器内科医の私は非常にせっかちですぐに答えが欲しい人間なんだけど、今日はそんなぜんぜん違う二人が話をしているわけですね(笑)。
でもそんな精神科医の待ち方のようなものが、私もようやく最近になってわかってきました。他にも、小児科医なら一人ひとりの子どもたちが育っていく過程を何年も見ています。自我形成を経て大人になっていくまで観察を続け、その子がその人なりの人生を歩んでいくことを支援していくんですね。そうしたゆっくりとした時間の中に医師としての醍醐味を感じる人もいる。
武田:先ほど山中先生が「伴走する」とおっしゃいましたが、そのためには「聞かない」ということも大事かなと思います。相手に踏み込みすぎて言いたくないことを言わせてしまい敬遠されることもある。だから「話さない」というのもその人のメッセージなんだなって思いながら待つことを、路上生活者の方との会話や外国人支援の現場で学んでいます。
さて、この会も予定を大幅に過ぎ、すでに2時間にもなろうとしていますので、そろそろ終わりにしなくてはなりません。
山中先生の診療所では、コロナ禍が始まる前年まで当ゼミの学生たちを受け入れていただいていました。そこでは、「虫になって木をみるミクロな視点、鳥になって森をみるマクロな視点」、すなわち「患者さんを診察すること、社会的な制度と生活環境を整えること」を、学生たちに教えてくださっていました。患者さんへの接し方はもちろん、在宅医療の導入にあたり、訪問看護や介護の担当者が入れるように、簡易宿泊所の経営者に建物のリノベーションを提案するところから始めて地域づくりに取り組まれたと伺ったのがとても印象に残っています。まさにSDH(健康の社会的決定要因)の実践者です。
一方、松本先生には、ハームリダクションの講演会で一参加者としてお話を伺ったのですが、自分の視点がぐるりと変わるのを感じました。そして、医療者として、気づかなかった、知らなかったことが申し訳ないという思いになりました。その後は、先生の編著である『「助けて」が言えない──SOSを出さない人に支援者は何ができるか』(日本評論社)という書籍に、助けられることが多々ありました。松本先生には、SDHのレンズを通して患者さんを診ることを教わった気がします。
本日は、そのような私にとっては特別なお二人をお招きして直接にお考えを伺うことができ、至福のひと時を過ごすことができました。ゼミの学生の皆さんにも、専門家間の対話によって化学反応が起きる様子を目撃してもらえて、何よりもの教育の機会となりました。山中先生、松本先生、そしてこのような機会を提供して下さった日本看護協会出版会の編集部の皆様に感謝を申し上げて、本日の会を終了したいと思います。ありがとうございました。
おわり

2021年6月9日、於:順天堂大学武田研究室、撮影:浦田圭子