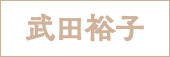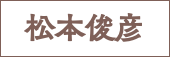弊社より4月に刊行された『格差時代の医療と社会的処方:病院の入り口に立てない人々を支えるSDH(健康の社会的決定要因)の視点』が話題を呼んでいます。キーワードのSDH "Social Determinants of Health"とは、健康を左右する、個人に起因しない構造的な要因であり、格差が広がる中で医療者や学生がその考え方を学び始めています。最前線で独自の実践に取り組む編著者らが、医学生(武田ゼミのみなさん)を前にSDH的なアプローチとその意義について語り合いました。
コロナ禍で起きていること
武田:ところで、依存の背景には社会的な格差で深刻な問題を抱えている状況があると松本先生もおっしゃいましたが、この「格差」は確実に広がっていますよね。コロナ禍も2年目に入り、路上生活者の炊き出しへ行くとリーマン・ショック時を超える数の人々が集まっています。驚くのが「え? こんな若者が?」とか「女性が?」など、以前には見かけなかったような人が増えていること。本当にどうなっていくのか……。私たち医療者は何を思ってこれからの社会と向き合い、患者さんを診療していけば良いのでしょう。
松本:コロナ禍になってから、子どもや女性の自殺がよく話題になっていますね。それは私自身、精神科の診療科でいろんな人を診る中ですごく納得のいくことなのです。「ステイホームで家族のつながりがわかるようになった」と言われたりしますが、家庭が「密」になることであおりを受けている女性もいる。とくに首都圏の住宅事情ではお父さんが書斎をもっていないことも多く、ダイニングやリビングの真ん中でパソコンを開いてテレワークをしているわけですよ。でも日本の女性の雇用状況では飲食店などのサービス業が多いことから自宅待機が増え、場合によっては収入が途絶えてしまい、家庭内の経済的な関係から夫の発言力が強くなる。さらに子どもの世話もあり女性ばかりがしんどくなっていく。つらいのは子どもたちもです。学校が嫌で命を断ってしまう子がいる一方で、反対に家にいるのがつらい代わりに学校があることで救われ生き延びている子たちもいるんですね。
あと依存症をもつ人にとって自助グループの役割はとても大きい。しかしその多くは公民館などを利用しているため、今は閉鎖されて使えない。ミーティングがなくなったことをきっかけにまたお酒やクスリを始めてしまうのです。つくづく思うのだけど、依存症からの回復に必要なのは「三密」と「不要不急の外出」だなって(笑)。もちろんオンラインで実施するところもありますが「ミーティング後に本名も知らない仲間と雑談しながら駅まで歩く時間、あれがよかったのに」と言う患者さんもいる。あと対面の集まりだと「その場の空気が震える」と表現する人もいます。他の依存症者のそばで体験を聞くことで「自分と同じなんだ。独りじゃないんだ」と肌で感じられるんですね。
一方でオンラインにもポジティブな面があって、地方の僻地にいて参加したくてもできなかった人の居場所ができたし、子育て中のシングルマザーは家からアクセスできるようにもなりました。対人恐怖症の人はカメラをオフにして参加できるし、家族に聞かれたくないならイヤホンでずっと誰かの体験を聞いていればいい。そうやってどうにか欲求を抑えている人もいる。おそらくコロナの問題が終息した後も、ミーティングはリアルとオンラインの両方が残っていくでしょう。
武田:私も同様に、訪問診療の中で高齢者の方が月に一回、唯一の楽しみにされていたコーラスや詩吟の会に行けなくなり、運動不足にもなってフレイル(frailty=虚弱:健康と要介護のはざまにあり、身体的機能や認知機能の低下がみられる状態)につながるようなケースを目にしています。山中先生もまたそうした「居場所」とそして「生きがい」「自己肯定」がすごく大事だとおっしゃっていましたが、寿町ではコロナはどのように影響しているのでしょうか。
山中:実は全く影響を受けていないんですよ。寿町では皆さんもともと三畳か四畳一間の部屋に独りで住んでいますから、社会的なコミュニケーションがあるのは病院やデイケアへ行くとき、もしくは65歳以上で介護を受けていればヘルパーや訪問看護師が来るときくらいしかありません。あとは飲み屋が何件もありますが、休業補助金のほうが売上より多いためか、ほとんどの店が閉じてしまっているんですね。それで行くところがなくなったおじさんは、家飲みしているので感染機会がほぼない。それくらいこの街はもともと「個」の世界なのです。
それからうちの診療所ではもともと結核対応を行っていたので、スタッフが感染しないよう空気の流れがきちんとつくられているし、特別待合室もあって疑いのある患者はそこに入ります。コロナでも既存システムをそのまま利用できるのです。
武田:なるほど。
山中:おかげで役所からは「あそこへ行くと診てもらえる」と紹介されるようになり、当初は連続して20人くらい感染者が見つかりました。でも最近は非常に減っていて、いま話したように街自体ではクラスターが起きないし、時々現れる感染者はすべて病院でウイルスをもらってきた人なのです。
コロナにメリットがあったとすれば、これまで平和すぎた国内で誰もが「自分は平均寿命まで生きるんだろうな」と思っていたのが、テレビで志村けんさんが亡くなるのを目の当たりにし、医療崩壊によって助かる命も失われる可能性を実感するようになり、危機感をもつようになったこと。これはある種の革命ですよね。健康や命に対する意識が大きく変わったと思いますから。
武田:自粛生活でさまざまな不自由がある日々を過ごしていると、戦時中の暮らしはこれに似ていたのかなと思うのです。より厳しい外出制限や衣服・髪型まで国家と社会の空気にコントロールされ、「個」が認められていなかったような状況を、私たちは少しだけ疑似体験している気がして。これがきっかけで平和の大切さを考える機運につながればと思いますが……。
じかに体験していることから受ける影響は大きくて、以前、国会議事堂の前で安全保障関連法案に対する反対デモがあったとき、友人に誘われ医療班として出かけたことがありますが、来られていた人の多くが70代後半から80歳を超えた戦争体験者でした。いろんな持病を抱えならも「当時、自分が大変な思いをしたので再び繰り返してはいけないという思いで来ました」とおっしゃっていました。だからこそ伝えたいという気持ちになるんですね。
もちろん今の状況はそれとは比較にならないし、共通点なんてほんのわずかかもしれないけれど、だからこそ「戦争になったらこんなものじゃないんだよ」っていうことを共有できたらいいなって思うのです。
依存症者の孤立感
武田:ここからは、学生さんに感想や質問をお聞きしましょう。
学生M:お二人に一つずつご質問したいことがあります。まず松本先生、薬物の規制を強化し厳罰化するほどかえって状況が悪化するケースがみられ、そのため欧州ではハームリダクションが広がっていると。しかし日本ではまだそれが進んでいない現状があるとおっしゃいましたが、この違いの原因はどこにあるのでしょうか。
松本:一つは日本が島国で民族構成が他国に比べてそれほど多様ではなく、移民の数もまだまだ少ないため、薬物をタブー視する国民の同調圧力が強いこと。また取り締まりも厳しく警察官や麻薬取締官の捜査能力も高いせいか、違法薬物の生涯経験率が相対的にとても低いのです。例えば米国では現時点で違法とされる薬物を一生に1回以上使用する人の割合は、国民の49%を占めます。これだと、むしろ使わないほうが非社交的と思われたりするかもしれませんね。でも日本の場合は2.3%しかいないとされています。ともかく、こうした事実をもとに「厳しくすることでうまくいっているじゃないか」と認識されているのです。
ちなみに、一方で日本は海外の常識からすると恥ずかしいほどアルコールについては寛容なのです。例えば米国だと州によってはカフェやレストラン以外の公道での飲酒は厳しく取り締まられていますし、酒瓶を持って歩くだけで罰金を科せられるところもあります。21時を超えればスーパーでアルコール飲料を買うこともできません。日本では24時間コンビニで買えるし、忘年会シーズンにはあちこちで酔っ払いが歩いてますよね。
ひとつ理解しておいてほしいのですが、先ほど民族構成がそれほど多様でないと言いましたが、日本にもさまざまなマイノリティがちゃんと存在していて、あるコミュニティのなかではすごく薬物が行き交っているんです。それはセクシャルマイノリティです。とくにゲイの人たち。例えば私のところには薬物で検挙され免許停止になった医師が研修を受けに来ますが、その多くの方がセクシャルマイノリティなんですよ。どうして医者が? って思うかもしれないけれど、なかなかカミングアウトができない中でようやく大事なパートナーを見つけ、相手から「一緒に使う?」って言われたら、医者であろうとなかろうと、なかなか断れないと思いませんか? それに「ダメ。絶対。」教育では、まるで薬物を使う人がモンスターのように描かれているけれど、依存者はそんな顔してないですから。どっちかというとEXILE TRIBEのメンバーみたいにかっこよかったりするんだよね。
一同:笑。
松本:恐ろしいどころか、むしろ「自分もああなりたい」ってタイプの人なんですよ。しかも若者にとっては、これまで出会った大人の中で一番優しく自分の話をていねいに聞いてくれ、初めて自分の存在価値を認めてくれた相手なんですね。「お前面白いじゃん」「お前イケてるよ」「友だちになろうよ」って言ってくる。こうして学校や家庭の居場所のない若者、あるいは、社会から疎外されているセクシャルマイノリティのなかで薬物が広がっていき、そこに属している有能な人たちも次々に職を失っている。それは国家的な損失と言ってもいいでしょう。
武田:じゃあMさん、もう一つの質問を。

自分の価値観を押し付けない
学生M:山中先生、私たちは明日、三鷹市でワクチン接種の予約をする高齢者のお手伝いをさせていただくのですが、寿地区でのワクチン接種はどのような状況なのでしょう?
松本:それはとても重要な質問ですね。
山中:ワクチン接種については私の中で明確な基準をつくっていて、自分の意志が明確な人つまりテレビなどいろいろな情報をもとに自分で判断ができる人たちも当然普通にいますので、希望があればうちで接種を行っています。ネットで予約できる人は非常に少ないですができる人もいます。問題は認知症や寝たきりの高齢者です。彼らは意思表示ができないから打つべきではないと私は考えます。その代わりに、その人の部屋に行く人がワクチンを打つようにお願いをしていて、なるべくヘルパーさんたちはうちで接種するようにしています。
これは、路上生活者の人たちにどう相対するかということなんですが、自分の価値観で彼らにアプローチをしていくと、それを押し付けてしまう。それが本当にその人にとって必要なことかどうかが見えなくなる場合がある。私の価値観は「居場所」であり「生きがい」であり「自己肯定感」です。だからもし「あなたも居場所をもってください」「生きがいはなんですか」「自己肯定感をもてていますか」ってやり始めるとズブズブとその人との関係に入り込んでしまう。そうではなく、本当に大事なのはその人らしい意思を最大限に尊重した支援の仕方です。それも、彼らとお付き合いをするようになって学んだことです。だからワクチンも同じで、医師としての自分の価値観で勝手に打つものではないんです。そんなふうに線を引いています。
武田:私が活動に参加させていただいている団体が、炊き出しの現場で「ワクチン接種を受けられることを知っているか」「受けたいか」「どこで打てるか知っているか」「接種券をもらうための住所があるか」といった内容のアンケートを行いました。すると、少なくない数の方が受けたくないか、もしくは迷っておられたんです。その理由に「今までずっと健康で生きてこれたけど、接種してもし具合が悪くなったときに自分は医療を受ける立場にないから」というものがありました。また「ずっと社会のことが信じられない状況に置かれてきたのに、ワクチンを打てと言われても受け入れられない」といった主旨の回答もありました。そこから考えたのは、やはり社会に対する信頼という基盤がなければ、人々へのワクチン接種は進まないんだなということです。
例えば米国のように潤沢にワクチン製剤が用意され、何の予約をしなくても会場に立ち寄れば接種ができる仕組みがあるのに、まだ多くの人が受けていない。しかもそれはエスニックマイノリティなどによく見られる傾向だということ。そこに共通するものを感じるのです。
松本:エスニックマイノリティの人々は、おそらくいろいろなトラウマを抱えてきていますよね。さまざまな差別や排除、迫害の経験を通じて、基本的に世の中は敵意と危険に満ちているものととらえている。さまざまな公衆衛生的な政策もそうした人たちの心の傷や、社会から排除されてきた歴史を考慮する必要がありますよね。
武田:そうですね。米国ではそうしたマイノリティごとに同じ立場にある医師が彼らに話をすることを行っているようです。
松本:みなさんが医師になったときに、なぜか服薬をしてくれない患者さんがいた場合、中にはそうした背景をもつ人がいると思うんです。良いとされている治療をなぜか拒んでしまうとかね。
武田:それに関連して山中先生から学んだ大切なことがあります。私が路上生活者に対する医療相談を始めたとき、自分の役割がわからなかった時期があったんですね。相談時にいちばん言われるのは「風邪薬をください」とか「マスクがほしい」といったようなことで、普通の外来のように「今日はどうしましたか?」から始まって「実は○○が調子悪くて…」というのではなく、求められるものを「はい」ってただ渡すだけなのです。なので、そこで社会資源などを紹介してつなぐことが自分の役割なのかなと思い、お薬などを手渡しながら「そろそろ生活保護はどうですか」などの声がけをしていたのです。でもそうすると相手の方々は苦笑いしながら「まだいいよ…」っておっしゃったり、中にはすごく怒って「自分はまだそこまで落ちぶれていない!」と強い口調で言われたりして、それでいいのか、何かが良くないのかも理解できずにいました。
そんな折に山中先生の外来へ見学に伺ったときに、ある若い方が来られたのですが非常に暗い表情で、そばにいることがいたたまれないくらいのうつ状態にあることが窺えました。その人が部屋を出られたあとに先生が「彼は最近、生活保護を受けることになって、この町に来たんだよ」っておっしゃったんですね。「いま本当にどん底で、自分には価値がないっていう気持ちでいるんだ」と。それを聞いて初めて「生活保護を受けるというのはそういうことなんだ」と知り、自分はこれまでなんて失礼なひどいことを言っていたんだろうと気づいたのです。
それからは、求められるものを渡すだけでもいいと考えて接しています。そのようななかで、本当に今すぐに医療が必要だという人がいた場合、あるいはすごく頑張ってきたけど高齢でこれ以上は働けないと言われたときに、「医療を受けるために生活保護を考えませんか」、「生活相談されてはどうですか」と声をかけるようになりました。そうすると「じゃあ」って言ってくださるんですね。その限られた瞬間を逃さないために、自分はこの活動をやっているんだなと思えるようになりました。これは本当に山中先生のおかげです。
山中:駅伝の伴走みたいにね。一番早いのは車に乗せてゴールまで走っていけばいいんだけど、そのルールは通用しないんですよね。その人が己の力で自分にあてがわれた20数キロを走っていくことが大事で、伴走する者はその人のその日の顔色、息づかい、走る速さなどをじっと見ながらいろんな声をかける。でもある限界を目にして「これはダメだぞ」と思ったときには手をかけますよね。それがいま武田先生がおっしゃった瞬間のことです。普段からずっと見続けているから「もうダメだ」というタイミングがわかる。この伴走の感覚というのは医師でも看護師でも、往診なり外来で一定期間長く見続けることで得られるものです。そんな変化に気づいて対処できることが臨床医の能力なんですね。