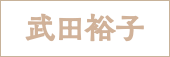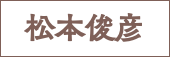弊社より4月に刊行された『格差時代の医療と社会的処方:病院の入り口に立てない人々を支えるSDH(健康の社会的決定要因)の視点』が話題を呼んでいます。キーワードのSDH "Social Determinants of Health"とは、健康を左右する、個人に起因しない構造的な要因であり、格差が広がる中で医療者や学生がその考え方を学び始めています。最前線で独自の実践に取り組む編著者らが、医学生(武田ゼミのみなさん)を前にSDH的なアプローチとその意義について語り合いました。
医者は何をする存在なのか──これまでの道のり
武田:では最初にそれぞれのこれまでの道のりをご紹介いただきましょう。まず松本先生から。
松本:私は精神科の医者で、とくに依存症を専門としています。依存症にはアルコールや薬物、ギャンブルなど色々ありますが、私がとくに力を入れているのは薬物です。
きっかけは医局の人事でじゃんけんに負けたことなんです。それで誰も行き手がなかった横浜市の依存症専門病院に着任したんですが、1995〜96年当時は、第三次覚醒剤乱用期*1に当たる頃で、横浜でも十代の若者たちが学校のトイレで覚醒剤を焙っていたりする状況でした。ちなみに、病院の近所には後に有名になるある学校教師──今では「夜回り先生」として知られている水谷修先生がおられて、いろんな子たちを連れて来られて大変だったりもしました(笑)。でもそのおかけでいろいろと教わることも多かったです。
*1「第三次覚醒剤乱用期」:我が国における覚醒剤乱用期は大きく3つに分けられる。まず終戦後に「第一次覚醒剤乱用期」があり昭和30年代にいったん沈静化するが、昭和40年代半ばから再び増加し、昭和59年には警察による検挙者数が約2万4千人に達する「第二次覚醒剤乱用期」を迎える。その後減少傾向を示し、平成に入ってからの検挙者数は年間1万5千人前後で推移してきたが、平成7年以降は2万人に迫る勢いで再び増加しており、この時期が「第三次覚醒剤乱用期」と呼ばれている。「第三次」の特徴として中・高校生をはじめとする少年の乱用が目立つほか、初めて覚醒剤取締法により検挙される者の占める割合が高いことが挙げられる。
その病院では、服役を繰り返すような患者さんも多くて、私は20年くらい前から刑務所や少年院などに出入りするようになりました。彼らは世間的には犯罪者ですが、一方で医学的な問題も抱えており、社会から排除されるだけでなく医療からもネグレクトされがちなんですね。同じ依存症でも「薬物」というだけで精神科で診てもらえなくなったり、救命救急センターの医者から通報されてしまったり……。こうした状況に対して「医者は何をしなきゃいけない存在なのか」ということを絶えず考える領域なんです。そこでは法律や常識という観点からだけでは本質を見ることができません。
実は、世界各地のあらゆる民族ごとに、それぞれ「お気に入り」の薬物があります。例外的にそれがないのは、私が知るかぎり北米先住民のイヌイットだけでした。植物が育ちにくい寒冷後に住む彼らは、もともとどんな薬物も嗜んでこなかったんですが、後にヨーロッパの人がお酒を持ち込んで、一気にアルコール依存症が広まったんです。世界各国に薬物をめぐるさまざまな規制やタブーがありますが、見方を変えれば実は薬物文化の争いからくる異民族排除の問題であったりもするわけです。つまり「薬物戦争」というのは人類と薬物との戦いではなく薬物同士の戦いであり、そしていつも最後に勝つのは「アルコール」なんですよ。

法律とか常識とかではなく、こうしたニュートラルな目で「薬物」というものをとらえる必要があると私は思うのです。今日聴いてくださっている学生さんたちも、中学や高校のときに学校で薬物乱用の「ダメ。ゼッタイ。」教育によって偏った価値観を押し付けられてきているだろうし、医学部教育では薬物依存について学ぶのは6年間のなかで一コマ・90分しかないですよね。こうした不適切かつ不十分な教育状況を日々憂いています。と、こんなことを言って同業者の中でも孤立しながら働いています(笑)。
武田:(笑)ありがとうございます。
山中:次は私ですが、話すと長くなるんだけどいいのかな……
一同:笑。
山中:順天堂大学を卒業したのが1980年ですが、いま思い返すと徹底的に自己完結型の医療を目指してきたんだなと思います。実は私は医者のくせに血液が大嫌いで、自分の血を見ると今でも倒れちゃうかもしれないくらいです。当初は亡くなる人を見るのも怖かった。とはいうものの、この仕事を選んでしまったのだからしょうがないよなと思って、最も人が急激に亡くなっていちばん多く血を見る循環器内科を選びました。また若気の至りもあって、目の前にいる患者さんを誰かに託すことを嫌い、自分で診断し自分でカテーテル治療をしたり、ペースメーカーも入れたりしたかったんです。
あと、患者さんを診ることは大好きだけど、セクショナリズムにはまりやすい大学にいることが大嫌いで、附属静岡病院や越谷病院あるいは浦安病院などをぐるぐる回っていたところ、横浜市の国際親善総合病院から話があり、そこの循環器内科の部長になったわけです。しかし、そこで研修医を教えるうちにだんだん疑問が湧いてきたんですね。彼らは患者さんの蘇生行為を学ぶ中で、亡くなったご遺体から相当な勉強させてもらっているはずなのに、だんだんその患者さん一人ひとりに対する敬意を失っていくのです。亡くなることが当たり前のように手袋を脱ぎ捨て、踵を返してその場から立ち去っていく。そんな様子を繰り返し見るのが徐々に許せなくなっていったのです。
卒業してみるとわかると思いますが、循環器内科の医師はわりとAggressive(好戦・攻撃的)、Active(活発)、 Ambitious(野心的)という「トリプルA」な人が多くて、そうした姿勢のためにどうしても見失っていくものがでてくる。自分が患者の命の尊厳を生業としていくことを常に反芻するという、そういう気持ちをなくしてしまいがちなんです。そのようなジレンマを感じていたある日のこと、当時の妻だったポーラさんが「寿町に毛布を持っていく」って言うんですね。私は「やめなさい。あそこは怖いところだよ。あなたが入っていくようなところじゃない」って言ったんだけど、どうしてもって言うから私もついて行ったんです。
彼女とは米国オハイオ州のクリーブランドクリニックに留学した際に知り合ったんだけど、日本に来て、ある意味では適応障害を起こしていたんですね。ちなみに、本書で松本先生がご執筆されたところを読んでいて「ああそうだな」と思ったのは、人間というのは肯定される居場所をとにかく欲するというメッセージでした。これは私が寿町で学んできたことと同じです。つまり人間に必要なのは「居場所」と「生きがい」と「自己肯定」を感じられる毎日だということ。
その頃、ポーラさんは日本に自分の居場所がなくて、何をしていいかわからないという焦燥にかられていました。困り果ててさまざまな精神科医などに診てもらってもいたけれど、寿町と出会って救われた部分があった。そのことに私は非常に興味を持つようになり、やがて「なぜ寿町の人たちはここにいるんだ?」と強く思うようになったんですね。それでボランティアとして関わり始め、毎日曜日にホームレスや街のおじさんたちと話すチャンスをつくるようになりました。4年間そうやって過ごすうちに「よし、ここで病院をやろう」となったわけです。
当時の寿町は今とはずいぶん違い、社会的な差別もまだまだ大きく、危険と言われて外から人がなかなか入らない場所でした。そこで気づいたのは「この人たちを看取る者が誰もいない」ことでした。それを自分がやろうと。つまり寿町と知り合ったのは自分の意志ではなかったわけ。人の人生とはわからないものです(笑)。
寿町で目指したこと、そこに起きている変化
武田:山中先生に質問ですが、「毎週日曜日に話すチャンス」というのはどのようにつくられたのですか?
山中:まず場所を決めて、ボランティアのみんなでカレーをつくるんですよ。それを寿町の人々に振る舞う。私はヴィオラを弾くんですが、仲間にはギターやピアノができる者もいて、食べながら歌を歌うんです。とにかくここに来ればなにか楽しいことがあるんだと思ってもらおうと。そして、あちこちで小さなグループをつくってお話をする。そこからいろんな産物が生まれるんです。それが「さなぎ達」*2というNPOの活動で、まずそこから始めたんですよ。
*2「特定非営利活動法人さなぎ達」:若者によるホームレス襲撃事件をきっかけに「路上生活者の現状を知ろう」と1984年に始まった夜回り活動「木曜パトロール」のメンバーら(代表は山中氏)によって設立された、横浜市寿地区を拠点とするホームレスや、ホームレスに至るおそれのある人の「自立自援」を支える団体。「医、衣、職、食、住」を5つの柱としながら、憩いの場である「さなぎの家事業」や食堂の運営を行う「さなぎの食堂事業」、独居高齢者のみまもりを行う「寿みまもりボランティアプログラム(KMVP)」、生活・就労・メンタルケアを行う「寿JUMP事業」など、さまざまな取組みを行う。2018年に活動を終了した。
この街の人たちの孤独死を防ぐためにどうすればいいのか、仮説的なゴールを設定したうえで、そこに近づいていくためにどのようなプロセスを歩めばいいのかという計画を立てました。これは実は医学論文を書くのと同じなんですね。仮説の結果を置いてロードマップを立て、データを集めて検証していく。そのゴールというのは「この場所で看取れる社会=組織をつくること」。そのためには看護師が必要だし、ヘルパーもいる。まわりで手伝ってくれる人も欠かせない。そうしたグループをつくれば看取りは可能だ。とにかく人が必要なので、NPOをつくって楽しいことをやればたくさん集まってくるし、注目もされてお金も集められるだろうと。それで当時はテレビや新聞にも出たりしました。
すると慶應や立教の大学生たちが寿町への理解を深めようと、ゼミの活動でやってくるようになったので、孤独死の心配がある人を学生たちが定期的に訪問できるような環境をつくりました。訪ねられたほうも人好きであれば喜んでくれる。こうして、医療者や支援者などさまざまな人々が安全に入れる街づくりを目指したのが、この頃の活動でした。
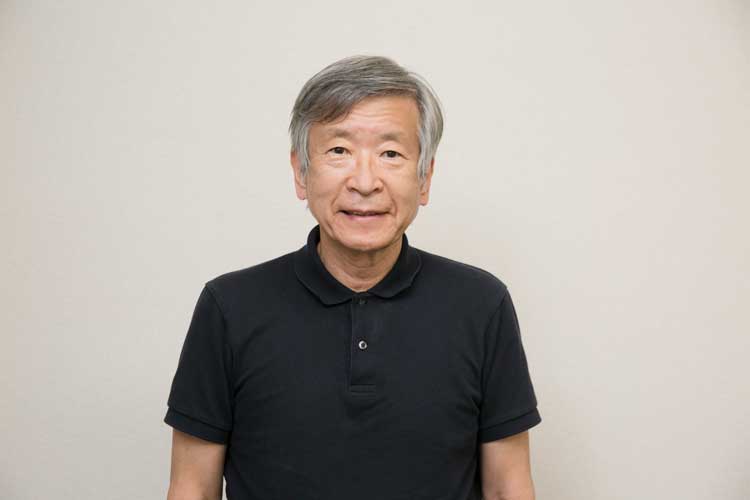
武田:最初はどのように仲間を集ったのですか?
山中:ポーラさんが通っていたバプテスト教会の人たちを核にしていました。また、路上生活者で私の親友になった人がいて──もう亡くなってしまったんですが、彼はもともとカナダで事業をしていたような人だけど、当時は元町のそばの川にあった廃船に住んでいて、私は毎晩そこへ行き2人で「何をやろうか」「どうしようか」と計画を練っていました。NPOをつくって一旗揚げようって。楽しかったですよ。いまはそのゴールに届くまでになってきたなと思っています。
でも気がかりなことがあって、寿町の人口構成を考えたときに、「第1世代」は美しく言えば自身を日本の高度経済成長のために捧げてきた労働者たちで、年金を払って来なかっために年老いて生活保護を受けながら人生の終焉を待っているような人々です。彼らをイメージして私たちは看取りの仕組みをつくってきました。しかしその次の世代は誰なのか。どのような人を活動の対象としていくのか。それはアルコールや薬物の依存症をもつ人たち、犯罪を犯して服役した人たち、そして精神疾患のために社会に居場所のない人たちであり、まさしく松本先生が対象とされている人々なんです。
NPOの中で、私は「そうした人々のために、あなたたちは汗を流すことができるのでしょうか」と問いました。つまり「第1世代」の人々に対しては、今の豊かな社会を実現してくれた、いわばお返しとして彼らを看取ることで、自分たちは生きがいを感じられるが、犯罪などで社会から弾かれ居場所を失い寿町にやってきた人々に対して医療や看取りを気持ちよく提供できるのか。実際に街でそうした人から酷い扱いを受けることもあるのです。たとえ「この野郎! どうせ金儲けでやってるんだろう。とっとと帰れ!」みたいな悪態をつかれても、それを受け止めながら看取りやNPO活動を続けられるのか……。
さまざまな考え方があり、中には「第1世代のおじさんたちで十分だ。自分は離脱する」という者や「そういう人たちは自業自得。どういう生活を送ろうと自己責任だ」としてNPOを去っていく者もいました。
その後、さまざまな複雑な経緯があってNPOは2018年に閉じたのです。私個人は世代の性質がどのように変わろうとも「決めたことだからやりきるんだ」と、看取りの活動を続けていますが、サスティナビリティを考えれば「変わった医者がいたね」と、私の時代で終わってしまうのかもしれない……。
生き延びるための薬物とウソ
武田:なるほど。松本先生が対象とされている領域の人々が重なるというお話ですが、お聞きになっていかがですか?
松本:山中先生は、きっと私の患者さんや、同業者たちが診ていない人たちを支えてくださっているんですね。また、NPOの方の反応はある意味で当然だと思います。「だらしなく酒やクスリに溺れているからそういう場所へ流れ着いたんだ」と普通の人は考えるし、おそらく医師や医学生だってそうでしょう。でも、まずわかってほしいのは、世界中に共通する依存症問題が深刻なエリアとはどのようなところなのか。それは貧困からくる格差が偏在する場所です。皆が貧困であればむしろ依存や自殺の問題は拡大しません。人は他人との比較や以前の自分自身との落差によって心が傷つき、それがDVや虐待といった暴力にも向かう。
私たちが3年前に法務省法務総合研究所とともにまとめた「覚せい剤事犯者の理解とサポート2018」では、全国の刑務所で受刑している覚醒剤取締法事犯者の子ども時代の逆境的な体験についての調査を行いました。すると一般人口とは比較にならないくらい、子どもの頃に虐待やネグレクトを経験していたり、親がアルコール問題を抱えていたり、刑務所に入っていたり、自殺していたり、あるいは統合失調症でケアをしてもらえなかったりしている人が多かったんです。女性の場合はさらに悲惨で、そうして育ったうえ成人してからは性暴力を受けたり、パートナーからの暴力も受けている。
そんな人々がなぜ覚醒剤を使うのか。つまり彼らは逆境体験によるPTSDのフラッシュバック、過覚醒、不安といった精神症状への対処として用いているのです。クスリを使うと楽なんですね。例えば性暴力を受けた経験のある人の場合、昔受けてしまったレイプの場面が繰り返しありありと浮かんできて、そのたびに当時の年齢に逆戻りする。そのフラッシュバック体験の最中は1分1秒という時間が信じられないほど長く感じるのです。それが覚醒剤を使うとあっという間に時間が過ぎていく。しかし一方、クスリのせいで朝起きるたびに体調が変わってしまうため、どうにか身体が動くときもあれば、全くベッドから出られないこともある。それでも自分でどうにか生計を立てていかなければいけないし、暴力を振るう男からもなんとかして逃げたい。そのために一人暮らしをするにはお金も必要なんだけど、日々変わる体調に合わせて働ける仕事って、風俗業くらいしか考えられないんですよ。でも性暴力のトラウマを抱えているからそんな仕事をすれば、せっかく固まりかけた“心のかさぶた”がまた剥がれて血が出てしまう。そんなときに、またクスリやお酒が役に立つんです。
アルコールや薬物は、長期的には自殺やさまざまな健康問題による死亡リスクを高める危険因子である一方、短期的にはむしろ自殺には保護的に作用し、皮肉にも“今日一日だけ”死ぬことを回避するのに役立っているのです。クスリで問題に対処することは決してベストな方法だとは言えないけれど、死ぬよりはマシという意味では最悪ではないんですね。「だらしがない」とか「不摂生の成れの果てだ」とか「それは医療の問題ではなく自己責任だ、あえていえば司法の問題だろう」といった解釈の仕方でほんとうにいいのか、考えてみてほしいのです。
私自身が20年間、刑務所や少年院に通い彼ら・彼女らと付き合っていて思うのは、暴力というものはやはり人から「学ぶ」ものであり、被害と加害の連鎖が世代や地域を超えて広がっていくんです。それでもお金があればまだ幸せで、経済的に恵まれている人はそうでない人と同じくらい違法薬物を使っていても捕まらないのに、貧困にある人はなぜか逮捕される。そして服役を重ねるほどクスリはやめづらくなる。なぜならそのせいでどんどん社会から孤立していき、家族からも見放され、友だちに電話しても着信拒否。戻れる職場もなくなる。かろうじて雇ってくれる人といえば、昔一緒に覚醒剤をつかっていたアニキだったりするわけで、そこでまた依存を繰り返す。
仮にそうした過去と決別し、空白部分のある履歴書を書いて就職できたとしても、ウソをついている罪悪感は人の生活をとても窮屈にします。新しい職場でいろんな人と出会い「今度遊びに行こうよ」と言われてもつい距離を置きがちになる。これ以上親しくなれば自分の「空白部分」についての話をしなければいけないだろう。そうするとみんな引いてしまう。だからさらにウソをつくことになる。そうして偽りを重ねていくことで生じる孤独・罪悪感が、また次のアルコールや薬物への欲求へとつながっていくんですよ。
そう考えると、依存症者の実態について私たちがもっと正しい情報発信をしていかなければならないなと思うのです。少なくとも自己責任論や「健康に悪いとわかっていながら言うことを聞かない人」という見方からの脱却が必要です。とくに医療者は「タバコを吸っちゃいけない」「食事療法をちゃんと守りなさい」など、健康にとって正しいことを言えば人は従うものだと思いがちです。それって、なんて傲慢なことだと思いませんか? 「健康な人」なんてどちらも従っていませんよね。あるいは内科に通う患者さんのうち、もらった降圧剤をいったい何割の人がちゃんと飲んでいるでしょう。医師が期待しているほど患者は言うことを聞かないものです。
多かれ少なかれ、患者はウソをつく。そして医師は患者にウソをつかれると裏切られた気分になります。でもそのウソは「生き延びるスキル」じゃないですか。例えばDVを受けている女性が、男から「正直に言え、あの男と会ったのか?!」と問われ「怒らないから答えろ」と言われて正直に話すとひどく殴られたりする。そのときに「会ってないわ」とウソをつけば怪我や死から身を守れるわけです。子どもの頃から「正直に言えば怒らない」と言われながら裏切られてきた体験を重ねている人には、生き延びるためのウソが必要になるんです。
「私はあなたの命を守ろうとしているのだから、正直にならなければダメだよ」と正論をぶつけてくる医療者の姿に、かつて自分を支配していた加害者の影がかぶってくる。一所懸命に診ているのに、ある日突然失踪して来なくなったりする患者さんにはそういう事情があるのかもしれませんよね。でも、医学教育の中でそうしたトラウマに関するメンタルヘルスの問題がしっかりと教えられていませんし、社会の中でどのようなかたちで格差が生み出され、そのために暴力の被害者・加害者になることに加えてセルフケアができず自分の健康や命を大切にできなくなる、といったことを想像するのは難しいことなのだと思います。

武田:先生のお話を聞いていると少年院に入る少年少女たちはむしろ被害者であり、そうならざるを得ない状況に置かれてきたのだということをすごく実感します。でも報道などでは「もっと責任を感じられるような教育が必要だ」という論調も見かけます。
松本:少年法の適用年齢も20歳から18歳へと引き下げになりましたしね。「殴ってわからないやつは、もっと強く殴ればいい」という発想をもつ人たちもいるけれど、そこには「殴ってわからないということは、そのやり方が間違っているかもしれない」と考える余裕がないんです。
山中:これはクリニックに来る学生に毎年言っているのですが「人生はその人の起承転結である」というのを私は寿町で学びました。一人の人間の「起」とはつまりオリジンのことで、誰もがそれをもっている。つまりどんな親の元に生まれたのかといったことです。しかし寿町には親がわからないまま生きてきた人もいっぱいいて、そのことに「自己責任論」は存在するのか。
もう一つ、エピジェネティクス(DNAの配列変化によらない遺伝子発現を制御・伝達するシステムおよびその学術分野のこと)という分野は今後10年の医療を大きく変えるインパクトをもつものですが、精神科でもそれを前提とした考え方をするようになってきていますね。例えば、ナチスドイツの占領下で飢餓(オランダの飢餓*3)を経験した人を25年間追跡調査した研究によると、その8割が後に肥満になっていたことがわかっています。より注目すべきなのは、飢餓の期間を経て出生した子どもたちの追跡調査でも、成人後に糖尿病や高血圧の発症率が有意に高くなったという疫学調査結果です。彼らは生まれ出た後の食糧不足に順応しようとして、栄養を貯め込みやすい体質になってしまったのです。
*3「オランダの飢餓」:1944年9月、ナチスドイツ占領下のオランダ西部地域で、港の封鎖や食料補給路の寸断によって住民が深刻な飢餓に陥り、翌年5月までに22,000人が餓死した。
遺伝学では長いあいだ、遺伝子そのものが人の目や髪の色のみならず、キャラクターも規定するのだと受け止められていました。でもよく考えてみると、一卵性双生児が違う価値観をもち別の人生を歩むことをみんな知っているし、クローンの羊や牛たちにもそれぞれ異なる個性があることもわかっている。ということは遺伝子だけでその個体を説明できない何かがあるわけです。それが近年の研究によって、遺伝子(gene)自体に違いはないけれども、子が母親の子宮にいるときに一生を左右する体質や性質に関わる情報を遺伝子の表面に刷り込まれることがわかってきた。
次の「承」ですが、私たちが小学校の頃は悪いことをすると親に「ご飯あげないからね」なんて言われたものでした。子どもはそれに「Yes」と言っておかなければ自分は生きていけないことを学ぶんです。松本先生がおっしゃったことと非常に共通しますね。だから人間は本能的に「承る」ことで生きていると言える。そして「転」は反抗期。「承」をよくも悪くも転じるんです。例えば大変な苦学をして東大などに入り成功した人、つまり自身で努力して転じた人は、いわゆる「負け組」の人に対して努力が足りないんだと思いこむ。医者が傲慢な理由はそこにあるのでしょう。でも広い視野でさまざまな人の転じ方を観てきた人は、それぞれの「転」のありようを受け止めることができると私は思うんです。
ここにいる学生さんたちは、いま「転」の真っ最中ですが、次に来る「結」はまだずっと先の終活に当たります。看取られる医者を決めたり、身辺を整理してどのような最期を迎えるのか。それなりに大事な時期ですが、自分ではその死をコントロールすることはできません。弱った身体を誰かに任せていくしかないわけです。私たち医師は患者さんの希望を読みとりながら、施設に送るべきか、夜中は誰かついていたほうがいいかなど、その人の最期の時間についてずっと考え続けているのです。
こうした起承転結の話は格差の問題と深く関わってきます。武田先生のゼミでもDevelopmental Origins of Health and Disease(DOHaD)について学ぶかもしれませんが、発達におけるオリジンのありようが健康と医療に大きく関与してくるという意味で、まさしくSDHと関連するのです。
武田:なるほど。では、ここで司会も自己紹介させていただきます。私は、患者さんが抱える問題を一緒に考える医師になりたくて、プライマリ・ケアの道を選びました。「自分の専門以外のことはわからないから、他へ行ってください」と言いたくなかったのです。一緒に考えて、自分の守備範囲であれば対応し、必要があれば専門医にお願いして問題解決を図りながら、患者さんと共に歩む医療者を目指しました。そのために、米国へプライマリ・ケアの専門的な研修を受けに行きました。
帰国して呼吸器の専門研修をしたのち、琉球大学に5年半勤めることになりました。そこで地域医療部に所属しましたが、当時(2000年頃)はまだ「地域医療」という枠組みはあまり知られていなくて、地域で提供される医療、すなわちプライマリ・ケアのことかと考えていました。でも沖縄の歴史について知ったり、離島で仕事がないためにお酒を飲んで時間を過ごす依存症の患者さんに出会うなかで、病気の原因には生物医学的に説明できるものとは違う次元の「何か」があることに気づきました。本書にも書きましたが、その後東大に異動してアフガニスタンの医学教育プロジェクトに関わるようになって、WHOが唱える健康の定義において「身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態」と「社会」が含まれている理由が、本当に腑に落ち、理解できました。
アフガニスタンでは、タリバン政権時代に女性は教育を受けられませんでした。字も書けず働いたこともない女性は、夫を紛争で亡くし生活の糧を得られなくなると物乞いをして暮らすしかなくなる。日本のような生活保護という福祉制度もないところで生きていくために、車通りの激しい道路に座り込んでお金を恵んでもらう女性たちがいました。教育に限らず様々な制約がある生活を送り、さらに紛争により街が破壊され人々が犠牲になる、そうした境遇が健康や生死に直結していると肌で感じました。
それからしばらくして留学したイギリスでSDHの概念を知り、沖縄やアフガニスタンで自分が見たのは「これだったんだ」とわかりました。そこで、それを学生に知ってもらう教育がしたいと思って帰国しました。と同時に、本日のゲストのお二人のようにすでにSDHの視点でさまざまな現場で実践をされている方々の活躍も知っていましたので、そうした最前線の取り組みを執筆者にご紹介いただきたいと本書を編纂しました。より理解がしやすいものにできたと感じています。
まつもと・としひこ
1967年生まれ。佐賀医科大学医学部卒業後、神奈川県立精神医療センターでの勤務などを経て、2015年より現職。精神科医として薬物依存症や自傷行為に苦しむ患者と向き合う。
依存症治療には単なる自己責任論では片づけられない背景への視線が欠かせないことや、依存症からの回復を支援する社会づくりの必要性について、著書などで広く訴え続けている。
やまなか・おさむ
1954年生まれ。順天堂⼤医学部卒業後、⽶オハイオ州の病院に勤務。横浜市泉区の国際親善総合病院循環器内科部⻑などを経て、2004年に現クリニックを開業。
横浜市中区・寿地区の簡易宿泊所に住む独居⾼齢者の訪問診療や看取り医療に尽⼒する。2016年第4回日本医師会赤ひげ大賞受賞。
たけだ・ゆうこ
筑波大学医学専門学群を卒業後、1990年米国へ臨床留学。1995年米国内科専門医資格取得。帰国後は筑波大学で卒前・卒後教育に従事。琉球大学に異動し「地域医療」に触れ、東京大学で国際協力、三重大学でへき地医療を経験してロンドン大学衛生・熱帯医学大学院に留学しMSc(修士号)を取得し、2014年より現職。
専門は、医学教育、プライマリ・ケア、国際保健。地域の活動の中で、病気の「原因の原因」も含めたSDHの視点を学生たちが学ぶ教育を実践している。また、外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」を医療者に広げる活動を行っている。