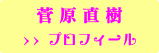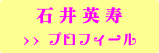考えること、学ぶこと。
ち

第 一 幕
「いしいさん家」(千葉県)
石井英寿さん
すがわら・なおき●青年団(平田オリザ氏主宰)に俳優として所属。2010年より介護福祉士として特別養護老人ホームで働く。介護と演劇の相性のよさに気づき、岡山県和気町を拠点に地域における介護と演劇の新しいあり方を模索する。2014年より認知症介護に演劇の手法を生かす「老いと演劇のワークショップ」を全国で開催している。主宰する劇団OiBokkeShiを取材したドキュメンタリー番組「よみちにひはくれない〜若き“俳優介護士”の挑戦」が、第24回FNSドキュメンタリー大賞優秀賞を受賞。

いしい・ひでかず●1975年生まれ。淑徳大学社会学部卒業後、介護老人保健施設に8年勤務する。介護福祉士として、認知症専門病棟で認知症の方たちとのかかわりを持つ。2005年有限会社オールフォアワンを設立、2006年千葉市に宅老所いしいさん家を立ち上げる。2017年には訪問看護事業もスタート、2020年には新プロジェクト「52間の縁側」(>>こちらで動画にて紹介中!)に挑む。
>> 「soar」インタビュー “子育ても介護も一人で抱えず、「お互い様」と声をかけあって。高齢者も子どもも集まる宅老所「いしいさん家」”

おかじい:菅原さんが主催する劇団OiBokkeShiに所属する俳優・岡田忠雄さんの通称。1926年香川県高松市生まれ。定年退職後、夢であった俳優を志し、今村昌平監督『黒い雨』『カンゾー先生』にエキストラ出演。2014年妻の認知症介護に悩み、「老いと演劇のワークショップ」に参加。以後、OiBokkeShiの全作品に出演する。
感情失禁:わずかな刺激に対しても過度な感情を示し、感情の表出を抑えられない状態。
石井──あ~なるほどね。そういえば、何年もお風呂入っていないおじいちゃんがいて、いろいろ試したことがありました。そのとき昔の人にとってお医者さんは絶対的な存在だから、「白衣を着て行ってみよう!」って思いついたんです。「僕、医者なんですよ。診察したいけど、ここでは脱げないからちょっとついて来てください」って言ったら「あっ、はいー!」って来てくれて、チャンスとばかりにそのままお風呂場まで行って、「ここに聴診器当ててますから、洋服を脱いでください。全身を診ますからね」って服を脱いでもらって、そのまま僕も一緒にお風呂入ったことがありました。
菅原── ノリのいいお医者さんですね(笑)。

石井──ついて来た時点でこっちの勝ち。次はどうしようかなっていうわくわく感があって、面白かったです。今思うと、医者を演じていたのかもしれないね。
編集部──最初に「“介護”じゃないよね」と言われていた意味はそこで、経験上、何かをしてあげている、奉仕しているんじゃなくて、ケアを与えている側も楽しんでいるということが石井さんの中では大切なのかなと思いました。
菅原──デイサービスに来たがらない人を説得する行為を、言葉でやっていたらお互いうまくいかないわけで、そんなときに石井さんは演じて状況をつくってしまうわけですよね。それって、すごくクリエイティブな行為ですよね。
石井──そのときは、演じているっていう意識はないよね。ほかにも、施設内を歩き回ることで、前の施設から「問題行動あり」と申し送られて来た人がいました。それで、過去を紐といていったら警備員をしていたとわかって、「だったら道路交通調査員をやってもらおう!」って思いついた。「うちの前を車や自転車、犬や猫が通ったら正の字で書いていってください」ってお願いしたら、「はい、わかりました」ってちゃんとデイサービスに来てくれて、仕事をしてくれました。そういうときは、うれしくて楽しくて(笑)。
菅原──介護者にとっては問題行動でも、その人は警備をしているのであって、それは徘徊じゃない。いしいさん家の考えともつながると思うのですが、あまりプログラムを決めない。お年寄りが「帰る」と言ったときに寄り添えるように、なるべくこちらのストーリーを薄くすることが大切なんだと思います。うまくいくと、ものすごく怒っていた人が、またいい表情をするわけです。それがこの仕事の楽しみですね。それで、私は共演者なわけです。
石井──主人公と共演者、なるほどね。そこは演劇と似てるのかもしれません。
常識を疑え!
編集部──そのようなアイデアは、その方とお話をする中で思いつくのですか。
石井──何をしてきた人なんだろうか、どんな性格なんだろうかとは考えますが、ひらめきみたいのものかな。とりあえずアプローチしてみて、だめだったら次を考えようと。
菅原──その人が大切にしてるものをこちらも大切にしながら進んでいくような感じですね。
石井──そうそう。ただ、同じことが次もうまくいくとはかぎらない。
菅原──そのときの石井さんのわくわく感も大切なのかもしれないですね。マニュアル化して、ほかの人がやってもうまくいかないかもしれない。
石井──あーそうかもしれない。医療は因果関係が成り立つじゃないですか、でも介護って相関関係なのかなって感じます。こちらが変われば相手も変わる、というより元々その人が持っているものなんですが……。

菅原──こちらが問題視すると、いつの間にか問題が悪化していることもありますよね。信頼関係が築けていない状態でいくら働きかけてもできないものはできないというか、信頼関係が築けたときにどんどんできることが引き出されて増えていくのは面白いですね。僕は今、93歳のおかじい*と芝居をつくっているんですが、出会った88歳のときはもうおじいさんだしセリフも覚えられないだろうなと思ってかかわっていたんです。でも、信頼関係が築けてくると相手がやりたいことがわかってくる。そして、こちらが望むと応えてくれる。結果、93歳になった今はセリフ覚えもすごくよくて、1時間半の芝居に出ずっぱりです。
石井──すごいよね!
菅原──信頼関係が築けて、こちらが望んでることと本人がやりたいことが重なったらミラクルが起きるのは当然なんです。
石井──ミラクルが当然!(笑)
菅原──僕が取り組んでいる「老いと演劇のワークショップ」*で面白いなと思うのは、演劇の場合、舞台の上は何もないから現実も虚構も等しくなるんです。例えば、特別養護老人ホームの設定になっている何もない舞台に認知症の人役がやって来て、「ここはビジネスホテル」というふうに演じ始めるとします。そこには介護職員が2人いて、「いやいや、ここはビジネスホテルじゃなくて、老人ホームですよ」と言ったらそっちが正しくに思えるけれど、もう1人、2人宿泊客やホテルマンが登場したら、今度はこっちがリアルに思える。そこで、認知症の人の世界をほかの人にも見える形にできるんじゃないかと思っています。
石井──だまされちゃうよね、「常識はどっちなんだ?」って(笑)。
菅原──常識を疑う気持ちも、介護の現場では必要ですよね。
石井──それは大事! 僕らの世界が正しいというわけじゃない。違ったことをする人が1人だと非常識だけど、それが2人、3人と増えていくと常識のほうが変わっていくんです。

身をもって演じる最後の演劇
菅原──僕が介護の仕事場に入ったばかりのころ、脳梗塞で片麻痺、失語症の人のモーニングケアをしていました。ある日、いつも通りある人の着替えの介助をして、カーテンを開けたらいいお天気だったんです。で、僕が「いい天気ですね」って言ったら、その人が号泣し始めたんです。そのとき、僕は感動しました。人生いろいろあって、こうしてなんとか生きていて、朝を迎えて、まるでこれまでの人生を祝うかのような快晴だと思ったら、「確かにこれは泣くべきことだ!」と思ったんです。それで、申し送りのときに「泣いていました」と伝えたら、「ああ、それは感情失禁*ですね」って看護師から軽く言われたわけです。でも、そのときに僕とその人が感じたことは本当なんですよね。今この瞬間が一番いい状態かもしれない、明日には病に倒れて亡くなる可能性もある。今この瞬間を生きていることの尊さを、僕は介護の仕事から教えてもらった気がします。認知症になると昔のことは忘れるかもしれないけれど、今この瞬間を楽しむことはできる。それは大きな希望だなと思います。
石井──そう、「今」でいいんだよね。そういうことにちょっとでも気づければ、もうすこし生きやすい世の中になるのかもしれない。
菅原──演劇の最大の特徴も、「今ここにいることをともに楽しむこと」です。まさに一緒に歩くということは、「今、ここ」をともに生きるということですね。
石井──いきなりダッシュしないかとか心配もあるけど(笑)。あと、一緒に歩くって同じ方向を向いていることが大切な気がするんです。縁側に誰かと座っていると、別に何をするわけでもなく同じ方向を見ていることで、「今、ここを共有する安心・信頼が生まれる。だから、僕が新しくつくる宅幼老所「52間の縁側」*にも長い縁側をつける予定です。
菅原──同じ方向を向いているときは、気持ちも一緒なんですよね。うまくいかないときはベクトルが逆を向いている。もう1点、認知症って、社会の常識からすると異常としてとらえられがちなんですが、介護者も家族介護者は価値観やコミュニケーションの方法を変える必要があって、その振る舞いが時に演技になるんじゃないかな。演劇の特徴は、「社会生活の役を脱ぎ捨てて、虚構の世界で出会い直すこと」なんです。介護の人は、結構そういうことをしてますよね。
石井──やってますね。あちら側に合わせてあげられたら、みんな一緒に暮らしていけるのに。
菅原──本人にしたら長年暮らしていた家から、突然、特別養護老人ホームに1人で行かされるわけで、これって、不条理ですよね。アートって、不条理をそのまま受け入れることが特徴なのかなと思います。これからは、効率や合理性からだけではなく、芸術文化の中で老いとボケと死をとらえ直す必要が出てくると思うんです。石井さんはそれを介護の現場で実践されていて、ここでの取り組みがまさに演劇になっていて、僕はこの場が理想の演劇なんじゃないかと思っています。僕はここに足を踏み入れただけで感動して、「こういう場があるんだ!」って鳥肌が立ちました。
石井──最後の演劇じゃないけど、お年寄りって子どもや孫たちに人間はこうなっていくんだよって身をもって表現し、教えているのかなって思うんです。だから生産性がないなんてバカなこと言っているけど、すごく必要なことなんだよね。
菅原──誰しもこういう道をたどっていくわけですよね。もしかしたら、その価値観や生き方に触れることで若い人が生きやすくなるかもしれない。
石井──このままでいいんだ、生きていていいんだって感じられるのってすごいことだよね。
菅原──現代社会のそれとは真逆の価値観を発信しているわけで、これはすごく意味がある。
石井──介護っていい仕事だよね。だから、これからもその魅力を発信していきたいと思います。
(おわり)

●参考文献
菅原直樹監:特集 ようこそ!老いと演劇の世界へ,Bricolage, 増刊6, 2018.
老いと演劇のワークショップ:菅原さんが取り組んでいる「認知症ケア」をテーマに、身体を使った遊びからぼけを受け入れる演技までを体験するワークショップ。演劇体験を通じて、認知症の人とのコミュニケーションに意識的になることを目的に行われている。
52間の縁側:赤ちゃんからお年寄りまでさまざまな人が集い、生活する場をつくりたいと言う石井さんの新プロジェクト。千葉県八千代市内に新たな宅幼老所をつくり、長い縁側をつける。設計は山崎健太郎氏(山崎健太郎デザインワークショップ)。(>>動画で紹介中!)