interview

page 2
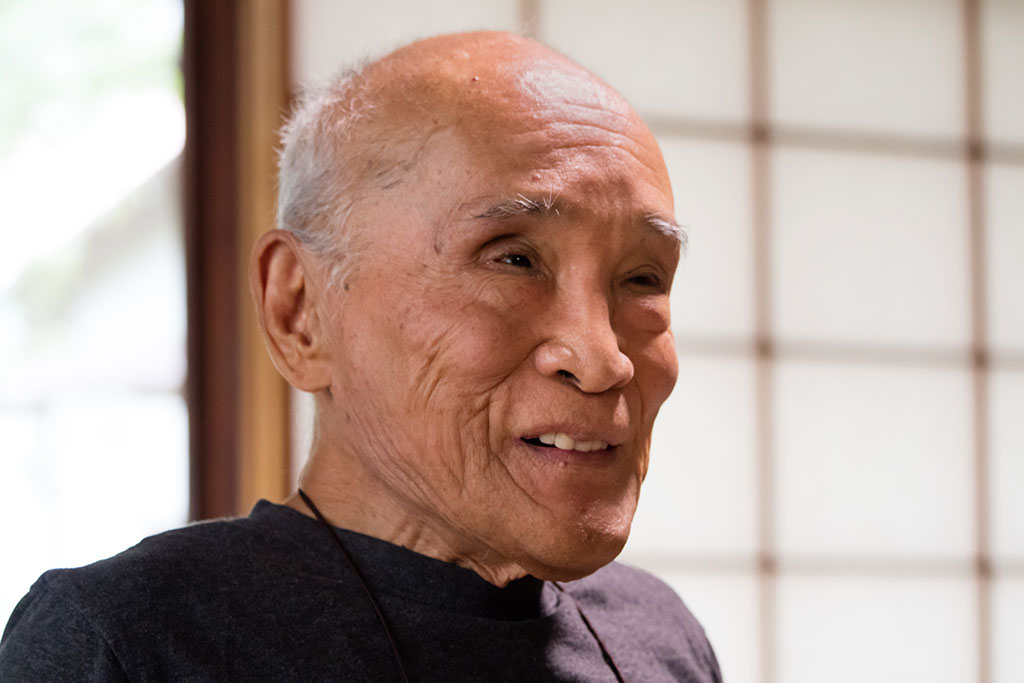

『ことばあそびうた』福音館書店/1973年
身体を面白がってみる
西村 医療では命を預かっているためか科学的な根拠を求める傾向が強いのですが、実際の臨床現場で看護師や患者さんが経験していることは矛盾だらけですから、いろいろな条件下でそこを表現していくことが重要だと私も考えています。
谷川 そうでしょうね。
西村 たとえばこのご本、『子どもたちの遺言』。
谷川 ああ、遺言。
西村 大人が亡くなるときに遺言を残していくのではなく、今から生きようとする子どもたちそれぞれの成長時点のつぶやきが詩になっています。私にはそこがすごく響くんです。子どもたちに向けて何かを言っているというよりも、私たちが生きていく現実に対して詩が語りかけてくる。「前世」についても結構書かれていて、それにもすごく関心を持ったんですが…。
谷川 現代の科学ではぜんぜん証明ができないところだから、非常に怪しげで危ないでしょ。僕はそういうものに何か未来に通じる道があると思っているんです。だから今の医学のどらかというと「デジタル」な方向よりも、たとえば漢方とか身体術のような曖昧な形での身体への関わり方のほうに僕は傾いているんですよね。定期健診なんて行ったことないんですよ。検査をすると何かの「病気になる」んじゃないかと思って怖くて(笑)。
西村 探すと「何か」が見つかっちゃいますものね。
谷川 うん。それと、病気というのはその人にとっては常に全身的なものでしょ。だけどたとえば目が痛くても、眼科の先生はそれが何か全身的なことに関係しているという視点では診てくれない。一事が万事でそれだったら、肩を揉んでもらうことのほうがまだそこには「身体の面白さ」みたいなものがあると思うんですけどね。
西村 たしかに、現代医療はうまくいかないところを治すことに注力したり、より良い状態になることを目指しますが、「面白さ」という方向になかなか関心が向かないものです。
谷川 そりゃそうですよね。本人はすぐにでも痛みをとりたいし、お医者さんも患者が心配だし治さなくちゃいけないと思うからね。面白がってちゃいけないよね(笑)。
西村 そうです(笑)。あ、それで思い出したんですけど、私が大学の教員になって最初に担当したのが感覚器という科目で、目や耳の治療を受けている患者さんにどういうケアをするかを教える授業だったんです。そこで、目の見えない人たちがどんな世界を生きているのか、耳の聞こえない人の「ろう文化」がどんなものかという話をしたところ、ある学生さんが、生まれた頃から谷川さんの詩を子守歌のように両親が読んでくれていたエピソードを語ってくれたんです。
谷川 へえ。
西村 たとえば、私も大好きなんですが「かっぱ」(『ことばあそびうた』福音館書店、1973年に所収)とかを…。
谷川 ああ「かっぱかっぱらった/かっぱらっぱかっぱらった」っていうやつね。それをご両親が声に出して読んでいてくれたわけ?
西村 ずっと、そうだったらしいんです。
谷川 素晴らしい両親ですね(笑)。
西村 本当に。それがきっかけでしばらく「谷川さんの詩を詠む会」をして、いろいろな詩から刺激を受けたことを学生たちと話し合いました。「目が見えないからこそ感じられることがあるんじゃないか」「こういう詩のリズムは、見えない人のほうが面白く感じられるんじゃないか」って。あのときの学生さんたちとの授業だったら「身体を面白がる」ことを楽しめる気がします。
谷川 そうかもしれませんね。
西村 この詩集を開いていると、つい「かっぱらった」って声に出しちゃいます(笑)。ひらがなだけで詩をつくる遊び心のようなものがとても素敵ですね。
谷川 きっかけはね、幼稚園児ぐらいの子どもを相手にした絵本を考えていたときに、編集者から社会をテーマにしたものをつくりたいと言われたんです。でも「社会」という言葉はもちろん幼い子どもには使えないから、どう言い換えれば伝わるのか散々考えたんだけど、それはないんですよ。つまり大和言葉として時代を超えて人々の身に染みこみ、暮らしに根づいた日本語のなかに「社会」という言葉はなかったのね。
今のわれわれは漢字仮名交じりの言葉を平気でしゃべったり書いたりしているけれども、その大部分が外国語なんじゃないかという気がしてきたんです。まず中国から入ってきた漢字があって、明治維新以降は西洋から輸入されてきた思想・概念に多くが移し変えられてきているんだから。一方で、詩の言葉というのは身体に根ざしたものこそが力強いわけで、それでひらがな表記という発想も出てきた。
また「かっぱ」の場合には、日本語の音韻についての考え方があります。伝統的な七五調で書くとどうしても時代錯誤的で何だか古臭い詩になっちゃうのね。それとはちょっと違うものと考えると、もう韻を踏むことしかないわけなんです。だけど日本語というのは全部母音で終わります。ローマ字を見ればわかるけど、すべて子音プラス「あいうえお」でしょ。だからいくら脚韻を踏んでも耳に入ってこない。
たとえば、戦後まもなく中村真一郎さんや福永武彦さんらがマチネ・ポエティクという文学運動でずいぶんたくさんの押韻詩を書かれていて、詩としてはいいんだけれども韻は耳に入ってこないんですよ。ならば、どこまでしつこく韻を踏めば日本人は喜ぶのかな(笑)みたいなことを突き詰めると、結局ダジャレのようなものになるんですよね。だから子どもたちが長く口ずさんでくれるような楽しいものが書けたんです。この漢字・漢語については今でも現代の日本語が抱えているすごく大きな問題だと思うんです。
西村 そうですね。私たちも日常的に言葉を使うなかでは、ひらがなだけっていうわけにもいかないですから。そうすると谷川さんは、大人が知っているような概念や意味をまだはっきりと知らない子どもたちに、日本語のひらがながもつリズムを介してそれらを伝えようとされたわけでしょうか。
谷川 散文の場合には意味を伝えなきゃいけないけど、詩は伝えなくてもいいというのが僕の立場でね。もちろん意味はどうしても伝わってしまうわけだけど、でも目指すものとしては道端の草花みたいに、言葉がなくても存在しているものを言葉でつくりたいっていう野心があるんです。なかなかそうはいかないんだけど。
(中編につづく)

『子どもたちの遺言』写真:田淵章三・詩:谷川俊太郎/佼成出版社/2009年
page 1 2
コメント:


