ニーチェ F. Nietzsche
1844-1900 ドイツ(スイス)
本人はポーランドに出自を持つと言っていたが、生粋のドイツのプロテスタント信仰の家に生まれ、早熟の天才として25歳にして大学の教員(古典文献学)となるも、病によって早々と引退、欧州各地を放浪しながら執筆活動を行う。それまで懇意だったワーグナーを攻撃するなど、容赦ない批判を展開する。しかし晩年は精神が崩壊し家族の介護のもとで静かに暮らす。「神なき時代」をどう生きるのかを模索する思索を展開するが、死後は妹の手によってナチズムに利用される。
「病気」と「狂気」
以上、ニーチェの中でもとりわけよく知られた4つのキーワード、「権力への意志」「価値の転換」「永劫回帰」「超人」を見てきましたが、正直、ニーチェの考え方がうまく伝わったのかどうか、とても心もとないです。そもそも「ニーチェの考え」というものは、論理的、合理的な説明がしにくいです。「認識としての知への意志」にあったように、彼はそうした枠組みに入れられたくないのですから。その結果、こうした回りくどいような説明とたとえ話のようなものが増えてしまいました。でもニーチェならこうして書いていることに対して、きっと「然り」と言ってくれることでしょう。そこがニーチェの良さだからです。
それでは最後に、簡単にではありますが「病気」をめぐるニーチェの考えをもう一度まとめておきます。
ニーチェにとって「病気」は「健康」の対立概念ではありませんでした。「健康」が「正常」な状態であり「病気」は「異常」な事態であるとか、「病気」にかかってしまったらとにかく「健康」に戻さなければならないとは考えませんでした。強いて言えば「病気」であることこそ大事であり、「病気」によって世界や自分や他人がよく見える、とまで言っています。「健康」であるうちは、ただその日常に埋没してしまうだけだというのです。なんとひねくれた考え方でしょうか。しかし、ニーチェにとって大事なのは「価値の転換」です。「病気」であってこそはじめて、生きる意味が見えてくる。健康であることをありがたがる人はいますが、ニーチェは病気をありがたがっているのです。なんというのか、「病気」のほめ殺しみたいなことをしているわけです。
つまり、健康であるときには、病気にならないように気を遣うあまりに、健康であることのありがたみも、健康であることによって自分が求めているものも、むしろ、ぼんやりとしてしまうのです。健康であるほうが健康にとらわれてしまい、健康を楽しめず、そうした考えにいるうちは病気になっても早く健康になりたいと思うばかりで、病気であることを「楽しめない」のです。「楽しむ」という言葉が不適切であれば、「享受」もしくは「受け止める」「向かい合う」と言えばよいでしょうか。
ところで、デカルトが見いだした「思考する私」に拠点を置くという考え方は、おそらくニーチェにとっても重要なものです。このこと自体はなかなか否定のしようがありません。しかし、カントやヘーゲルのところで説明しましたが、「理想」や「観念」というものは、常に現実(現象界)に対する「否定」(批判)を前提とします。対立や否定があってこそ世の中も良くなり人間性も高まるのであり、そうした力こそ人間の持っている才能だとされました。
しかし、ニーチェからみると、ここに働いている思考プロセスが、これまでの哲学のダメなところのようです。現実の否定からはじまって(つまり課題を抽出して)、未来をよりよくしてゆく(つまり解決してゆく)、そういう発想をニーチェは「ルサンチマン」(怨恨)がまとわりつくものとして、ダメ出しをします。「ルサンチマン」とは、正直わかりにくい言葉です。一般的によく言われるのはイソップ童話にある「酸っぱい葡萄」というものです。狐がおいしそうな葡萄を見つけるのですが、手が届かず食べられません。そこで、自分が食べることのできなかった葡萄は「酸っぱい」ために、自分は別に食べなくてもかまわない、と言い訳をします。
この考え方からすると、病気がちなニーチェが「健康より病気のほうが健康だ」みたいなことを主張すること自体がルサンチマンであるように思えてしまいます。しかしニーチェは、自分はそうではないと言い張ります。重要なのは「病気」は「健康ではない」と否定形で説明するのではなく、「病気」は「病気」なのだ、ということです。「病気」であることを何ら卑下することなく、そのものとして肯定すること、受け入れること、そこからはじまります。
つまり「病気」は否定ではなく肯定である、と言いたいのです。そして否定からはルサンチマンが生まれ、肯定からは超人が生まれます。否定したあとには「〜ねばならない」という強制がもたらされますが、肯定したあとには「いずれも良い」「これで良いのだ」という多様性の共生がもたらされます。
こうしたニーチェの考え方で言えば、医療や福祉の現場で「病気」や「老い」に苛まされている人たちとともにいる看護職のみなさんは、率先して相手の「病気」を肯定する立場の人であり、ともに「病気」であることを肯定的に分かち合う人物ということになるでしょう。もっと言えば、病人の「苦しみを分かち合う」のではなく「喜びを分かち合う」ということでしょうか。
さらに繰り返しますが、私は、今なおこうしたニーチェの肯定の哲学とは、結局のところ究極の形の「ルサンチマンの哲学」ではないのかという、少々の疑いを持っています。しかし病人(患者)が弱気になって病と闘えず、生きる意欲や希望を見失っているとすれば、是非ともニーチェのこうした肯定の哲学から学んでほしいと思いますし、看護職の方は、そうした視点から患者を支えてほしいとも思います。
こうした意識を持った地点でようやく、ニーチェの「永劫回帰」の発想が生きてきます。すなわちそれは、単に自分の人生すべてが単に永遠に繰り返されるということを言っているのではありません。そうではなく「永劫回帰」へと「意欲」を肯定的に持つことが重要なのです。病気の自分、最高、上等。そんな自分の毎日こそが人生というもの。ならば、もう一回寸分なく繰り返されても、何も恐れることはない。受けて立とうではないか、ということなのではないでしょうか。
実際、看護・福祉・医療職を目指す学生のみなさんに、こうしたニーチェの考えを説明してみると、直感的に反発する人もいますし、少し考えてみてどうにも理解しがたいと思った人もいます。また一方でニーチェに対し「強い人」という印象を抱く人もいました。弱音を吐かず、現実に立ち向かうという点においては共通していたようです。そもそもニーチェは「共感」や「共鳴」を望んでいるわけではないので、見かけだけだと思いますが、ニーチェの強がりに敬意を表してもらえれば、それだけでかまわないように思います。
ニーチェに対する学生たちのコメント
- 「神は死んだ」や「超人」といった概念や言葉を生み出した人、「異端児」というイメージがありました。ですが彼がなぜその言葉や概念を残したかを学ぶうちにイメージが変わりました。ニーチェは自分にとって「よい生き方」を目指すためにはどうすればいいか、という問いに対する答えを考えていたのではないでしょうか。
- 意見を述べても解釈の一つとして受け流されそうだなと思いました。晩年のニーチェは崩壊した精神の中で何を考えていたのか気になりました。
- 彼の言っていることがすべて正しいとは思わないが、でも確かに的を射ている。現在の社会の風潮などにも言えることだが、メディアの情報や断片的視点からの意見に流されている人が多く、正しいことを言っている人が少数派だった場合にその人たちが非難されたりすることについてなど、私たちはもう少し考えるべきことがあると思う。
- 人間はいろいろなことを自分の都合のいいようにとらえている生き物のような気がしてきました。今まで人生が一度限りであると意識したことがなかったので、もう少し自分も人間として質の高い生き方をしようと思いました。
- 宗教や他者に依存しながらなんとなく生きているだけの人々に、危機感を抱かせてくれる。私自身「あの時、ああすればよかった」と後悔ばかりしながら生きているため、今この瞬間を一生懸命に生き、言い訳しない人生を歩みたいと思った。ニーチェのように自己を全面的に肯定し自らですべてを創造して生きる自信はないが、自らの意思を持ち自分で自分を肯定することで、今を自立して生きることができると思った。
- けっこう偏屈でとっつきにくい性格のような印象を受けましたが、共感できるところもありました。
- 考え方が難しく、よくわからないものが多かった。
- 永劫回帰とか、人間は動物と超人とのあいだに渡された一本の綱であるとか、根拠もないのにきっぱりと言い切っていて面白い人だなと思いました。でも、あまり共感はできませんでした。
- その口調などが今までの哲学者と異なっていて凄く強いと感じた。
- 永劫回帰の考え方は今まで自分にはなかったものでした。これに基づくと自分の人生に関して誰かに責任転嫁することはできないし、ニーチェはすごく強い人であると感じました。私も後悔しないようにこの人生を生きようと思いました。
- 永劫回帰という考え方は面白い。ニーチェのようにどのようなことも受け入れて前向きに生きて行くということは難しいが、大切なことだ。
- ニーチェの永劫回帰が今まで聞いたことのない考え方で新鮮でした。人間は前世を言い訳にしたり、来世があるからと堕落したりすると思うけど、ニーチェは割り切った考えを持っていて、芯の強い人間だなと感じた。同じ人生がまた繰り返されて、今が1回目の人生だとしたら、私は今できること、やりたいことに全力で取り組み、またこの人生に戻って来た時に楽しめるように努力したい。
- ニーチェは過激な考え方をする、と最初は思いました(価値についてなど)。同じ人生が繰り返されるという考え方はすごいと思いました。私も後悔しないように生きたいです。
- 畜群道徳批判では、群れていることにネガティブでした。人は孤独であることに恐怖を覚えることが多い。1人ではないことにより、心身や生活が保障され、安全に豊かに暮らすことができるのは事実である。しかし、孤独を知らないということに対してニーチェは問題視しているのではないか。一人でないとわからないことも重要であると言いたかったのでは。
- ニーチェがもし今の時代に生きていたら、早々に精神がやられてしまうのではないか。人が生まれて死んでゆくのは確かに当たり前のことだが、中には神や宗教などに頼らなければ押し潰されてしまう人もいる。ニーチェは感情的であり意思が強いところがあるが、それは言葉をオブラートに包んでいないだけで、案外言われてみればそうかもしれないと納得してしまった。「本当はパラレルワールドがあるかもしれない!」と考えれば、それはそれで、できなかったことがそこではできるのかもしれない、という希望を持つが、何度も同じ人生を繰り返すならば自分で人生を努力して生きなきゃいけないと思った。
夏目漱石と看護師
文豪、夏目漱石がニーチェに強い関心を寄せていたことはよく知られており、作品にもその影響があると言われています。漱石は晩年に伊豆で吐血し、生死をさまよったときのことを「思いだすことなど」という随想にしたためています。これが1910年のことですから、ニーチェ亡きあと10年が経過しています。
漱石は自分のことを支えてくれた家族や医者、看護師への率直な感謝の思いを書きあげています。そこに、自己主張ばかりする世知辛い世の中に対する不満を述べるとともに、ニーチェの名前が挙がっています。彼を「弱い男」「多病な人」「孤独な書生」と形容していて、それ以上は踏み込んでいませんが何となく自分とニーチェを重ね合わせているようです。また、病気から快復しかけていることに、これまでにない喜びを感じているさまが読み取れ、その勢いで、漱石は看護していた人たちを「神」や「雛」と呼びます。それまでの漱石の作品には見られない「弱さ」が率直に記されていて、ある意味、痛々しさを感じます。おそらくニーチェにも同じような心境があったのではないかと想像してしまいます。
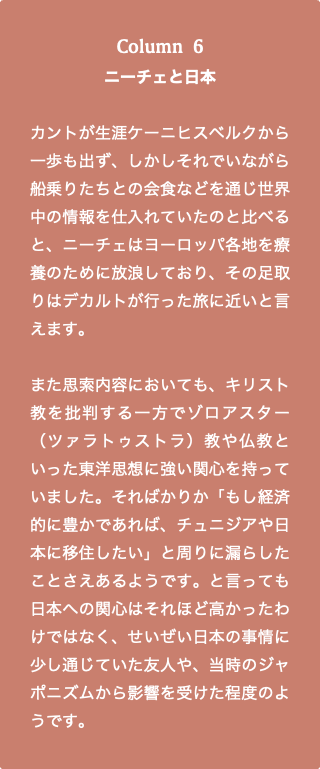
いずれにせよ、ニーチェの言うことは極めて過激であるとともに、極めて繊細です。文字どおりに受け止めるべきものであるとともに、かなりこねくり回して理解すべきものでもあります。漱石の言うように、ニーチェは「弱い」人間であったわけですが、「弱い」からこそ「強い」のであり、強く「肯定」を強調したがゆえに、極めて「批判」的にも見えます。そして、あまりにも「超人」を強調したばかりに、「あまりにも人間的」であったと言えます。そこで少なくとも言えることは、ニーチェによって「人間」を見つめるまなざしが「超人」として無限に解放されたのだ、ということです。実のところ「超人」とはあくまでも「人間」の一類型なのです。
対人援助職にかかわる読者の方々にとって、こうしたニーチェの考えは一体どういった意味を持つのか。残念ながら私にはまだうまく咀嚼できないまま、ここまで来てしまいました。どうか何らかの考える手がかり、生きる手がかりを新しく発見してもらえれば幸いです。
次回はサルトルとボーヴォワールを取り上げる予定です、第二次世界大戦後に世界中の多くの人を魅了したこの2人こそ、20世紀最大の哲学者カップルであり、とりわけボーヴォワールの存在とその生き方について、是非とも皆さんにご紹介したいと思っています。
──────────────────────自己紹介 | イントロダクション | バックナンバー──────────────────────