───
───
───
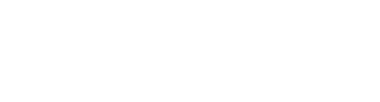
「無いこと」にされてきた、日本兵の戦争神経症
日本社会の中でトラウマやPTSD(post traumatic stress disorder;心的外傷後ストレス障害)に関する社会的共有知が形成されたのは、1995年の阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件がきっかけだったと言われている。
世界史的に見ると、第一次世界大戦期の兵士の「シェルショック」(shell shock;砲弾ショック)や、第二次世界大戦後のホロコースト・サバイバーの「強制収容所症候群」、PTSDという診断名を生み出したベトナム戦争など、戦争と関わってトラウマが注目される契機は何度かあり、欧米の医学史や文学・映画などでは比較的メジャーなテーマと言える。
しかし、近代日本の戦争をトラウマという観点から考える試みは、近年始まったばかりである。
2018年1月に刊行した拙著『戦争とトラウマ』(吉川弘文館)では、現在のPTSDの先行概念と位置づけられている「戦争神経症」が、総力戦期の日本軍においてどのような処遇を受けていたのかを明らかにした上で、なぜこの問題が戦後50年以上も「見えない問題」になってきたのかを考察した。

『戦争とトラウマ──不可視化された日本兵の戦争神経症』(中村江里著・吉川弘文館・2018年)
アジア・太平洋戦争期に軍部の関心を集めた戦争神経症。恐怖を言語化することが憚られた社会で患者はどのような処遇を受けたのか。また、この病の問題はなぜ戦後長らく忘却されてきたのか。さまざまな医療アーカイブズや医師への聞き取りから忘却されたトラウマを浮かび上がらせ、自衛隊のメンタルヘルスなど現代的課題の視座も示す一冊(吉川弘文館ウェブサイトより)
第一の要因として指摘できるのは、記録/記憶の不在と制約である。精神疾患を発症した軍人の多くは戦地に取り残され、軍事精神医療の対象として記録が残されたケースはごく一部にとどまった。また、言語化困難なトラウマを抱えた生存者の多くも戦後沈黙することとなり、圧倒的な資料的空白が存在するのである。
第二に、軍事精神医療の対象となった少数のケースに目を転じてみても、軍医たちは戦争神経症の原因が戦場・兵営の暴力性ではなく、恩給や兵役免除に対する願望という患者個人の逸脱性であると解釈し、戦争神経症の解釈の枠組みそのものが戦争神経症を不可視化する構造を有していた。
第三に、当時の日本社会の様々な文化・社会的規範の影響である。まず、「皇軍の精神的卓越」が強調され、「お国のために死ぬこと」が絶対であった当時、精神疾患になることは「国賊」であるというのが多くの患者の自己認識であった。また、恐怖心を核とする戦争神経症は、強靭さを求められた当時の男性のジェンダー規範にも反するものであった。
このように、日本軍における戦争神経症の問題は、戦時中から軽視・不可視化される構造があり、さらに戦後においては軍隊・戦争への強い忌避感がある中で忘却されていったのである。
史料としての診療録
上記のような史料の制約の中で、筆者が注目したのが陸軍病院等の診療録である。戦時精神医療の中核を担ったのは、1938年以降、精神神経疾患の特殊治療施設となった国府台(こうのだい)陸軍病院(千葉県市川市)と、1940年に精神障がいのため兵役免除となった人々の長期療養施設として設立された傷痍軍人武蔵療養所(東京府小平市)であり、これらの施設の診療録は、戦後、後継医療機関や関係機関で保存されてきた。
戦時中に精神疾患となり、内地に還送された患者の多くは、小倉・大阪・広島の基幹陸軍病院を経て上述の国府台陸軍病院に入院したが、中には全国各地にあった一般の陸軍病院に入院したケースもある。
これらの一般の陸軍病院の診療録は、戦後の復員処理業務や援護事業で利用されたため、患者の原籍となる各都道府県が管理してきた。その後、非現用となった資料群が地方自治体の公文書館に移管され、新発田(しばた)陸軍病院(新潟県)や、小倉陸軍病院(福岡県)の診療録など、氏名等の個人識別情報をマスキングした上で公開された事例も存在する。
また、神奈川県の民間の精神病院の入院記録の調査では、戦時中陸海軍病院だけでなく民間の精神病院に入院したり、自宅療養を行う元軍人の患者が存在していたことを明らかにした。
1980年代以降の「新しい医学史」の流れの中では、それまで医師中心で行われてきた医学史研究の担い手が人文社会科学研究者にも広がり、医師、疾病とともに、患者が医療を構成する重要なエージェントと位置づけられるようになった(鈴木 2014)。診療録はその3者が交差する史料として、近年の日本における精神医療史でも注目されるようになった。ここでは、軍事精神医療の歴史を社会史的に研究する上で、診療録が持つ重要性を2点、指摘しておきたい。
第一に、公的な医療機関で作成された診療録には、大規模かつ質の高いデータが集積されている。敗戦前後の組織的な公文書の焼却と隠匿のために、戦後の軍事史研究には大きな史料的制約が存在し、例えば、日本軍の戦傷病の全体像を示す体系的な統計すら残されていないという問題がある。その中で、医学的に貴重な資料として軍医たちの尽力で残された診療録は、戦争が国民の心身にもたらした広範な被害や、兵力動員や治療の実態が詳細に記された貴重な記録であると言えるだろう。
第二に、診療録には、患者の言葉や表情、行動などについての詳細な記録が残されている。診療録は基本的に医師や看護婦・看護人が記録したものであり、陸軍病院に関して言えば、軍医―患者の関係は、同時に将校―兵士の関係であることが多いため、二重の権力関係が存在したことは確かであるが、これらの記録は、入隊前の生活史に関する情報や、家族との手紙のやり取りなどとあわせて、一人ひとりの患者を取り巻く構造や実態を理解する上で非常に重要である。
看護日誌が伝えるもの
第二の点に関して、傷痍軍人武蔵療養所の診療録には、医師が書いた病床日誌だけでなく、看護婦が書いた看護日誌も残されており、日々の患者の変化が綴られた貴重な記録である。
筆者はこの看護日誌を用いて、1945年8月15日の「玉音放送」で敗戦を知ることとなった日の入所者の反応を分析したことがある(後藤・中村・前田 2016)。激しいショックや動揺を示す者がいる一方、楽観的な反応の者もいるなど様々であったが、意外なことにその日の多くの人々の記録は「変化なし」であった。しかしよく調べてみると、戦争末期から栄養失調や結核のために衰弱する者が激増しており、特に1945年とその前後1年の死亡者が多いことがわかったのである。
戦争末期の民間の精神病院での死亡率の高さは岡田(1995)も指摘しており、同様の事態は第一次世界大戦でも生じていた。民間病院に比べて食糧が優遇されていた軍関係の医療機関でさえ、戦争が終わった後にもこうした「戦病死」が生じてしまったのである。
戦争が再び身近になることへの懸念
拙著『戦争とトラウマ』は、博士論文をベースにした研究書であるにもかかわらず、幅広い読者の方に読んでいただくことができ、著者としては望外の喜びである。
しかし、このテーマが現在関心を集める背景には、集団的自衛権の容認(2014年)や安全保障法制の制定(2015年)が、多数の国民の反対を押し切る形で拙速になされ、「戦争」が身近になることへの懸念があると考えられる。今後の安全保障政策の方向性次第では、自衛隊員のストレスが飛躍的に増大することが予想されるが、政府・防衛省・日本社会はそのような事態を受け入れる準備ができているのか●1、そもそもそれを望むのかという議論が必要だろう 。
戦争の代価
筆者の研究対象はアジア・太平洋戦争期の日本であるが、同時代的には、学生時代に起きたアメリカ同時多発テロ事件(9.11テロ)とその後のアフガニスタン・イラク戦争の経緯を観察する中でも、トラウマについて関心を持ち続けてきた。
日本が引き起こし、あるいは支持したこれらの戦争がもたらしたトラウマも十分に検証やケアをしないまま、日本の再軍事化が進むことを強く懸念している。これらの戦争がもたらした「戦争の代価」を私たちはきちんと理解しているだろうか。
戦争は、兵士や戦場となった地域で暮らしていた市民の心身に破壊的な暴力を加えるだけではない●2 。軍事偏重の医療・福祉は、「知る権利」や科学研究の自律性の制限、社会的弱者のケアへのしわ寄せにもつながる。また、筆者が聞き取りを行った元日赤看護婦のある女性は、敗戦前後の過酷な状況の中で十分な救護活動を行えなかったことへの悔恨をくり返し語っておられた。戦争遂行が最優先される軍隊の論理のもとでは、時に人命や人権が軽視されてしまい、医療・福祉関係者にも大きな葛藤を引き起こしたのではないだろうか。
復員兵と家族の戦後
今後の研究の課題として残された点は数多くあるが、現在は年々少なくなりつつある戦争体験者に加えて、復員兵の子ども世代の人々への聞き取りを進めている。
戦争で精神障がいを負った元軍人の戦後史については、吉永(1987)や清水(2006)が、家族の受け入れ拒否などの理由で、戦後も国立療養所で長期にわたって療養を続けた「未復員」への聞き取りを行ったが、心身の不調を抱えながら、家族のもとで生活した人も相当数いたと考えられる。
戦後、復員兵たちは家族に自らの戦争体験をほとんど語らなかったとよく言われるが、入隊前の彼らの様子を知る家族は、トラウマやPTSDに関する知識がなかった時代であっても、その変化に気づいていただろう。辺見庸『完全版1★9★3★7(イクミナ)』(KADOKAWA、2016年)や、村上春樹「猫を棄てる―父親について語るときに僕の語ること」(『文藝春秋』、2019年6月号)など、復員兵の子ども世代の作家たちが、父親の「ただならぬ雰囲気」に戦争の影を鋭敏に感じ取り、長い間の葛藤を経て、父の戦争体験に向き合う作品を近年相次いで発表したのは、注目すべきことである●3 。
暴力・トラウマの世代間連鎖
また、復員兵の子ども世代の経験は、暴力の連鎖や、トラウマの世代間伝達を考察する上でも重要である。トラウマの世代間伝達は、第二次世界大戦後のホロコースト・サバイバーの研究の中で注目されるようになった。
昨年、筆者がオランダのCentrum'45財団を訪問した際に、戦争トラウマのケアについていろいろとお話をうかがう機会があったが、同財団も、1971年設立当初はホロコーストを生き延びた人々の「強制収容所症候群」や、ドイツ占領下でレジスタンス活動を行っていた人々のトラウマケアから出発した。その後、日本軍に抑留された人々を含む第二次世界大戦の犠牲者全般も対象となり、現在は第一世代の戦争体験者から第二世代・第三世代のケアへとシフトし、難民や児童虐待の被害者などの精神的ケアも行っているとのことであった。
このように国立のセンターが、軍人も民間人も含め、何世代にもわたるトラウマのケアを行っているオランダの事例は、日本の状況とは大きく異なると感じられるが、日本でこの問題を考える際には、戦争という国家間の公的な場での暴力と、虐待という私的な場で起きる暴力とのつながり(この2つは、ハーマン〔1999〕が整理したように、トラウマ研究の2つの大きな潮流でもある)に注目することが重要であると考える。
これは、DV(ドメスティック・バイオレンス)や性暴力のサバイバーのケアを行ってきた信田さよ子氏に教えていただいたことだが、信田氏が原宿にカウンセリングセンターを設立した1995~2000年の初期の頃に話を聞いた女性たちは、ちょうど復員兵の子ども世代であり、彼女たちが父から受けた虐待や母へのDVは、2000年代以降のカウンセリングで語られた暴力とは質が異なる壮絶なものであったという●4。
戦争や軍隊は、古参兵から初年兵へ、日本軍将兵から侵略・占領されたアジアの民衆へ、復員兵から家族へと暴力の連鎖を引き起こす可能性がある。新たな戦争への支持を表明する前に、国境や世代を超えて生じるトラウマの破壊的な影響について、私たちはまだまだ多くのことを知る必要があるのかもしれない。
[ 注 釈 ]
●1=2017年2月には、海外派遣に伴うストレスに関する情報提供や民間での医療サポートを目的として、「海外派遣自衛官と家族の健康を考える会」が設立された。
●2=アフガン・イラク帰還兵のPTSDや自殺率の高さについては、反戦イラク帰還兵の会(2009)などで日本でもよく知られるようになったが、高遠(2019)は「対テロ戦争」が生んだ暴力の連鎖はイラクの人々に大きな心の傷を残し、ケアが圧倒的に不足する現状を指摘する。同様に、アジア・太平洋戦争でも、国内外の市民が受けたトラウマは、軍人よりもさらに医療ケアが不足し、記録に残りにくいという問題がある。
●3=また、2018年1月には「PTSDの復員日本兵と暮らした家族が語り合う会」が設立された。
●4=同じく子どもや女性への暴力について、日本では早い時期から問題提起をしてきた森田ゆり氏の近著『体罰と戦争』(かもがわ出版、2019年)も、両者の共通点について示唆に富む本である。
[ 参考文献 ]
- 岡田靖雄「戦前の精神科病院における死亡率」南博編『近代庶民生活誌 第20巻 病気・衛生』三一書房、1995年.
- 後藤基行、中村江里、前田克実「戦時精神医療体制における傷痍軍人武蔵療養所と戦後病院精神医学―診療録に見る患者の実像と生活療法に与えた影響―」『社会事業史研究』第50号、2016年9月、143-159頁.
- 清水寛編著『日本帝国陸軍と精神障害兵士』不二出版、2006年.
- ジュディス・L・ハーマン(中井久夫訳)『心的外傷と回復【増補版】』みすず書房、1999年.
- 鈴木晃仁「医学史の過去・現在・未来」『科学史研究』269号、2014年、27-35頁.
- 高遠菜穂子『命に国境はない』岩波書店、2019年.
- 中村江里「精神科診療録を用いた歴史研究の可能性と課題―戦時下の陸軍病院・傷痍軍人療養所における日誌の分析を中心に―」田中祐介編『日記文化から近代日本を問う―人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』笠間書院、2017年、139-162頁.
- 中村江里『戦争とトラウマ―不可視化された日本兵の戦争神経症』吉川弘文館、2018年.
- 反戦イラク帰還兵の会、アーロン・グランツ(TUP訳)『冬の兵士―イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実』岩波書店、2009年.
- 辺見庸『完全版 1★9★3★7』上・下(角川文庫)KADOKAWA、2016年.
- 村上春樹「猫を棄てる―父親について語るときに僕の語ること」『文藝春秋』、2019年6月号.
- 森田ゆり『体罰と戦争―人類のふたつの不名誉な伝統』かもがわ出版、2019年.
- 吉永春子『さすらいの〈未復員〉』筑摩書房、1987年.
なかむら・えり博士(社会学/一橋大学)。専門は日本近現代史。一橋大学大学院社会学研究科特任講師を経て、2018年4月より日本学術振興会特別研究員PD。主な著書に『戦争とトラウマ―不可視化された日本兵の戦争神経症』(吉川弘文館、2018年)、『資料集成 精神障害兵士「病床日誌」』第3巻、新発田陸軍病院編(編集・解説、六花出版、2017年)などがある。 研究者情報データベース(※この記事へのご感想や、情報提供・インタビューにご協力いただける方は、研究者情報データベースに記載のメールアドレスにご連絡いただければ幸いです〈中村〉)。