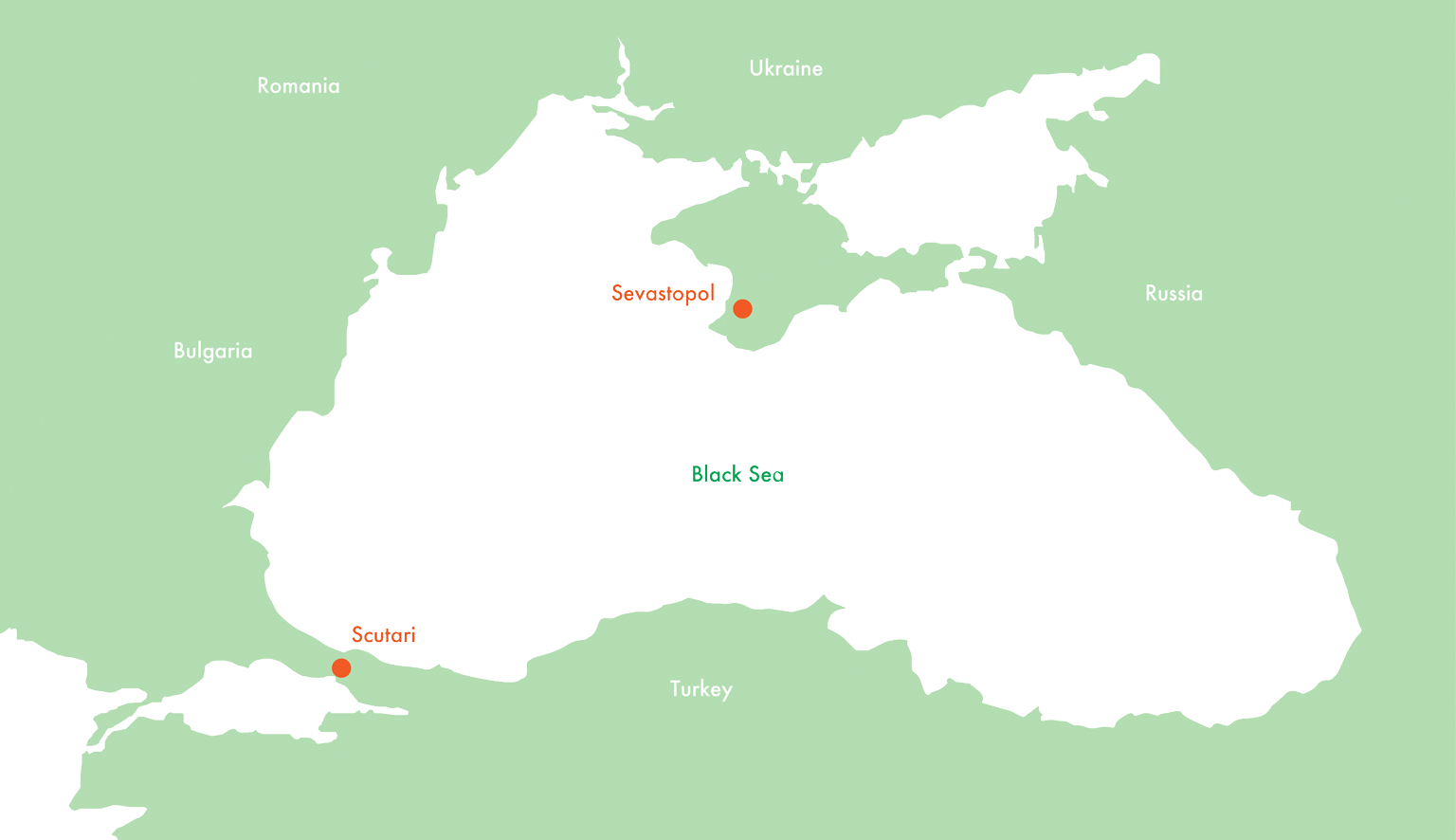特集:ナイチンゲールの越境 ──[戦争]
クリミア戦争とトルストイ
作家という残酷な生き物
金沢 美知子
『12月のセヴァストーポリ』★3
★3:1854年末から55年にかけて執筆され、55年6月に雑誌に発表。
クリミア戦争の激戦地セヴァストーポリを舞台とする3つの物語は三様の表情を示している。題名からもわかるように季節は冬から初夏、そして秋の気配を感じさせる時季へと移行し、戦況も変化していて、移りゆく時間の中に登場人物の心理が映し出されている。また主人公の設定や叙述の形式も異なっており、さまざまな差異の中で、3つの「セヴァストーポリ」はそれぞれに「生と死」をめぐる物語を織り上げているのである。
3作の最初、『12月のセヴァストーポリ』は2人称で叙述された、すなわち名前を持たない「あなた」「きみ」を主語にした文章で書き綴られた物語で、この手法は作品の大きな特徴となっている。「きみ」という言葉が最初に登場するのは物語の冒頭に近い、次のような場面だった。
── きみは埠頭の方へ歩いていく、と、石炭や肥料や湿気や牛肉の異様な臭いが鼻を刺す。埠頭の辺りには薪、肉、堡塁の資材、穀粉、鉄など、何千もの多種多様な物が山のようになっている。さまざまな連隊の兵士たちが、背嚢と銃を持っている者も持たない者も、そこに群がってタバコを吸ったり、罵り合ったり、煙を吐きながら桟橋に停泊している汽船に重い荷物を引き摺っていったりしている。あらゆる人々、兵士や水夫や商人や女たちで満載の小舟が気儘に埠頭に寄ったり離れたりしている。
「グラフスカヤ(埠頭)かね、旦那さん? どうぞ」と、水夫あがり2、3人が小舟から立ち上がって、きみに自分の舟を薦める。
きみは近くの一艘を選び、その小舟の傍らで泥の中に倒れている、腐りかけたどこかの栗毛馬の屍を跨いで、舵の方へと通り過ぎていく。そしてきみは岸を離れた。きみの周囲はもう朝日に輝く海だ。
こうして「きみ」が船上からの眺めに心を奪われているうちに、突然、遠方に敵の艦隊が姿を現し、水を伝って響いてくる人の声やセヴァストーポリを狙って発射された砲撃の爆音が聞こえた。その時語り手は「きみ」にこう問いかけるのだ。
──自分がセヴァストーポリにいると思えば、おそらくきみの心にも勇気や誇りといった感情が湧いてきて、身の内で血の流れが速まるのを抑えられないだろう。
いわゆる「2人称で叙述された小説」は皆無ではないが、比較的珍しいジャンルでもある。「きみ」や「あなた」を主語に据えた叙述に関しては、「あなた」に語り手自身の「わたし」を見ている場合、「あなた」に「わたし」と対峙する特定の「誰か」を想定する場合、「あなた」に不特定の読者を重ね合わせている場合などが考えられるだろう。
『12月のセヴァストーポリ』では、セヴァストーポリに足を踏み入れたトルストイ自身の遠からぬ過去の記憶が「きみ」に移し込まれている。しかし同時に、読者を「きみ」と同じ地点に立たせ、埠頭へ向かい、小舟に乗り込むという一連の動きの中に誘っている。読者の前に、「きみ」の視線を通して対岸の町並みや水平線の上に浮かぶ敵の艦隊が現れ、「きみ」の耳を通して砲撃の音が響いてくる。読者は「きみ」の感覚と心情をいつの間にか自分のものとしている。したがって語り手が、「自分がセヴァストーポリにいると思えば、おそらくきみの心にも勇気や誇りといった感情が湧いてきて、身の内で血の流れが速まるのを抑えられないだろう」と述べる時、読者は自分が祖国への義務を果たしたいという熱い思いでセヴァストーポリにやってきた兵士であるかのような気持ちになってしまうのだ。
このように『12月のセヴァストーポリ』はスケッチの風貌を持ち、そこでは特定の主人公ではなく、名前のない兵士や水夫や商人や、子供や女たちや、その他さまざまな人々が行き交い、ひとつまたひとつと風景が通り過ぎていく。作家トルストイの筆はまだ生と死の意味を掘り下げる作業を本格化させておらず、戦場の現実はもっぱら「恐ろしい予感」として登場している。
『5月のセヴァストーポリ』★4
★4:1855年に執筆され、同年9月、検閲下での書き換えのもと雑誌に掲載。初出時の作品名は『1855年セヴァストーポリの春の夜』で、翌1856年に作品集が編まれた際に『5月のセヴァストーポリ』の題名で収録された。
この予感は次作以後で、具体的な主人公を得て目に見える形をとることになった。トルストイがセヴァストーポリの戦闘に加わってすでに半年が経っていた。『5月のセヴァストーポリ』では、語り手の「わたし」が二等大尉ミハイロフを中心に、虚栄心の強いカルーギンや些か小心者のプラスクーヒンたちの従軍生活を描写している。戦争という特殊な状況にありながら、他愛もない社交の光景が登場し、敵国の言葉であると同時に当時ロシアの社交界ではまだ不可欠であったフランス語での会話の場面が長々と描かれる。★5とりわけプラスクーヒンが砲弾を受けて戦死するくだりで、トルストイの描写力は一段と冴え渡る。
★5:18世紀末から19世紀半ばにかけてのロシアではフランス語が社交界の常用語であり、セヴァストーポリ物語でも将校たちの会話を中心に、フランス語がたびたび登場する。『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』などトルストイの作品に限っても、上流階級がフランス語で会話する場面は数多い。
──「伏せろ!」と誰かが驚いて声をあげた。
ミハイロフは腹ばいになった。プラスクーヒンは思わず地面に屈み込んで目をつぶり、砲弾がどこか非常に近いところで固い地面にぶつかる音だけを聞いた。1時間とも思える1秒が過ぎたが、砲弾は破裂しなかった。
プラスクーヒンには多少の心の余裕が生まれ、近くで地面に伏しているミハイロフの姿を見て優越感さえ覚えた。しかしその直後再び砲弾に襲われる。
── さらに1秒が過ぎた―感情、思考、希望、記憶の世界が丸ごと彼の脳裡に閃いて消えた1秒であった。
プラスクーヒンはこの1秒の間に、借金のこと、夕べ唄ったジプシーの歌、昔愛した女性、まだ果たしていない復讐のことなどを思い出した。そして爆音を感じて駆け出したが、転倒してしまう。プラスクーヒンは自分が怪我をしただけのような気がし、傍らを通り過ぎていく兵士達に助けを求めて叫ぼうとしたが、かなわなかった。
── 彼は石を押しのけるために懸命に身体を伸ばそうとしたが、もはやなにも見えず、聞こえず、考えることも、感じることもできなかった。彼は胸の真ん中に砲弾の破片を受けて即死した。
このぞっとするような見事な描写はプラスクーヒンが即死するまでのほんの「2秒間」についてのものである。生き延びたミハイロフが過ごした時間も同じ「2秒間」だった。彼もまた地面に伏したまま、砲弾が破裂するまでの2秒間に果てしなく多くの事柄を考え、感じたのである。
2人の人間が戦場で死と向き合い、1人は砲弾に倒れ、1人は生き延びた。2人が体験したのはほんの一瞬のできごとだったが、トルストイはそれを果てしなく長い時間として捉えた。彼の代表作のひとつ、有名な長編小説『アンナ・カレーニナ』★6 にヒロインのアンナが自殺するくだりがあるが、彼女が列車の下に身を投げる場面にはプラスクーヒンの死とまったく同じ描写方法が使われている。
★6:『アンナ・カレーニナ』は1873年から数年をかけて執筆、完成された長編小説で、トルストイの代表作のひとつである。1870年代ロシアの上流社会を舞台にした物語で、同時代のロシアに内在する社会的な問題と人間の心理についての卓越した描写で普遍的な評価を確立した。主人公アンナが鉄道自殺する場面は、8編構成のこの作品の第7編の最後に登場する。
アンナは車両の下に身を投げた瞬間に、もう取り返しのつかないことをしたという思いにとらわれた。そして「彼女が不安と欺瞞と悲哀と邪悪に満ちた書物を読む時に明かりをとっていた蝋燭が、いつにもまして明るく燃え上がり、それまで闇に包まれていた全てのものを彼女に照らし出して見せ、それからぱちぱち燃えて暗くなり、永久に消えてしまった」のである。
作家トルストイは、死の瞬間を全人生に匹敵する凝縮された時間、内面における永遠の時間として捉え、消滅する直前の生命の輝きを言葉を尽くして描き出した。そこでは人が「死」を前にして「生」と向き合うさまが冷ややかに、そして詩的に語られている。