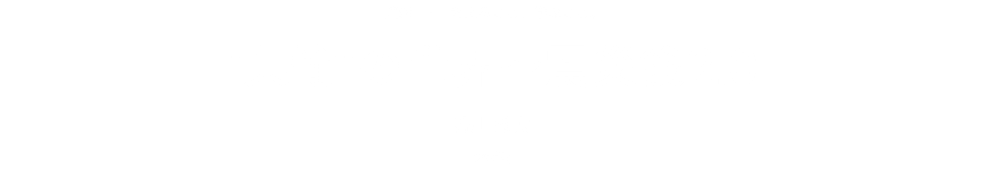第2回 共に愉しみ、創り、生きる社会 [後]
1 | 2
学び方:共同学習から共精(きょうせい)的な創造へ
第1回で述べたことは、同時に「教え、学ぶ」の「教授─学習」の定義や学び方の変革にもつながっていきます。自ら自然環境や社会環境の発達につながる仕事を新たに開拓し、創っていく場合、これまで以上にクリエイティブな作業が必要になります。
特定の組織や会社の中の文化や慣習に馴染んでいったり、そこで望ましいとされる、あるいは期待される知識やスキルを身につけるだけでなく、既存の常識や枠組みを時には破壊し、積極的に逸脱したりして枠を超えていく必要があります。単に「何かグループで一緒に創る」という意味での共同創造ではなく、間接的・無意識的であろうとも「既存の前提や常識の枠を超える」ことを伴う共同創造です。
既存の枠からの越境は、ある組織に属す異端者が批判をものともせず引き起こしていくものというよりも、むしろそもそもが特定の組織に固定・固執しない流動的なネットワーク型の活動だからこそ、よりしがらみが少ない状態でより自由かつ複数人により進められていくはずです──むろんそれでも、現実にはそのチームはまたさまざまなしがらみや既存の枠、あるいはメンバー間で生じる齟齬や葛藤と関わらなければいけませんが──。
ただ、上記は「知識習得が不要になる」という意味ではまったくありません。むしろこうした生き方のプロセスにおいては、より多くの学習の必要性を人々はより自然に感じるようになります。また、学習の意欲も教え込み型の教育(教授主義)下よりもはるかに自然に(かつそれとは質の違う形で)発生します。実際、この連載でご紹介する予定の新しい生き方、働き方を開拓している方々は読書や新しい知識の習得を好み、学ぶことを愉しんでいる方が少なくありません。「学ばないといけないから」「教わるから」ではなく、「もっと知りたいと思うから」「自然環境、社会環境をより良い方向に変えたいと思うから」自然に学んでいくのです。
そしてそのうえで、各々の文脈や自らの関心に合わせて、彼らは知識を上手に工夫して加工し、変化させ、発達させていきます。そのまま学んだ知識を用いるわけではありません。ゴールがはっきりしないこと、より事の本質に近づきたいと思うこと、経済依存の状態をより脱して、より社会を面白くする活動を生み出したいと思うこと。こうしたことが自然に彼らを「探究的な学び」へと向かわせるのです。
何が必要な知識かはわかりません。学習や教育に特化した人工的なテスト空間や授業空間よりも、はるかに複雑で予測困難な、しかし面白い「野生の世界」に向き合い関わるからこそ、異なる知識を結び付け創造的にアレンジしていく必要があります。そして自然や他者とともに新しいsomethingを共同で創り拡張させていく。このプロセスや結果は、個々人の能力に還元できない独特で唯一の「関係的な」プロセスでありプロダクトです。
心理学では、個体主義的な発想つまり「精神(こころ)とは個人内(頭の中)にあるもの」という考えを前提としてきたがゆえに、学習とは「個人が頭の中に知識を取り込む過程である」と考えられ、創造的なアレンジは基礎的な知識を身につけた後の(個人による)知識の応用と考えられてきました。看護教育でもしばしば「基礎が先で、応用はそのあと」といったことが常識に近い形で言われてきたのではないかと思いますし、実際、私自身が担当させていただいた看護職者向けの研修や授業にて何度もそのような言葉を耳にしてきました──ではどういったやり方が別に考えられうるか、この点もいずれ言及したいと思います──。
しかし野性的な学習においては、そうではなくむしろ共同的な創造こそ学習の基盤でありベースです。それは個々人に分断された精神ではなく、他者や自然と切り離せない、関係的・共同的な精神、つまり「共精(きょうせい)」から成り立つものです──ただしいずれ言及したいのですが、個々人の特異性が集団や関係性に溶け込んで無くなることはありません──。
これこそ、むしろ『本来の学びの姿!』です。
実は「次の社会」の創造とは、単に「未来への前進」なのではなく、同時に産業主義的・集権組織的な教育の拡大によって「いったん失われた人間本来の生き方」を回復するという、「過去への回帰」でもあります。未来へ進む動きと過去へ戻ろうとする動きとのダイナミズムが、次の社会を創造していきます。
ちなみに、アクティブラーニングが盛んに教育業界でも言われるようになりましたが、仮にそれを単に「グループ学習」という意味で解釈したり、グループ学習の後に参加した個々人の知識習得状況をテストして個人の能力の向上を測定すればよい、という発想に置き換えてしまうと、従来の教え込み型、知識習得型の個体主義的学習観(枠組み)と実は何ら変化がなさそうです。個人学習をグループ学習に挿げ替えただけで、結局は知識習得が目的化しているのであり、個人の能力に還元してしまっているからです。尺度も結局は単一であり多様性がありません。それゆえ、本稿ではこの種の「個体主義的な共同学習」と区分して、「共精的な学習」と呼んでみたいと思います。
心理学者のイアン・パーカー(2008)は、互いにリソースを奪い合うよう人々を個に分断してきた資本主義と、心理学の個体主義的な発想とは同期している、あるいは、後者の心理学は前者の資本主義体制に奉仕してきた、とすら述べています。
従来の学習観は「自己がいかに貨幣や利益を獲得していくか」という、資本制における獲得メタファと同期して、「個人がいかに知識を獲得していくか」といった、個人単位の分断された学習観を採用してきました。したがって、雑音を極力排除するようデザインされた、あのちょっと奇妙な、個人の能力を図るきわめて人工的なテスト場面において優秀な成績を収めれば収めるほど、その点数が将来における収入の良い職に就くための交換価値を有し、それでもって大企業に勤めることができ、社会的な成功にもつながっていくわけです。
お金をより多く稼げる人間や集団が力をもつという考えと同様、より多くの得点──学校に限らず、上から定められた基準で点数化される指標は基本的に全てこれに該当します──を稼げる人間がより力をもつ。金と標準化された点数。これらの間には、尺度や規格の統一とそれが適用される領域の拡大という実践が同期しています。
そして、個人単位の学習は管理職者や教師や講師あるいは国など、誰か特権的な地位にいるレイヤーが正解あるいはより妥当な解を定めて、それにより試験によって個々の能力を評価するような仕組みに合致しています。それは単に知識の内容面だけでなく、生きる姿勢のようなものの再生産も含まれます。組織のルールや資本家の指示に的確に従い大きく逸脱せず円滑に動いてくれる人材、効率よく商品の生産や販売に貢献してくれる人材、集権的な社会や組織を生きていく態度やアイデンティティの再生産(学習)です。
しかしながら、「多様性を軸にしたコミュニティ」においては、複雑で曖昧で面倒な、そして生々しく荒々しくすらある、生きた野性の環境を生き抜く学びが要求されます。野生環境では、唯一の正解のないものに向かって、あるいは向かうべきものそれ自体を探求しながら、個々の「特異性」(ネグリ&ハート、2005)の有機的で創造的な連結、言い換えれば相手の特異性と自分の特異性とをその都度、柔軟に結び付けていくグループの力、即興的な相互行為の力が要求されます。
それは唯一の存在である相手と、唯一の存在である自分とが「出会ってみて」「話してみて」「工夫してみて」ようやく可能になる「固有かつ集合的な知識」です。
たとえば、Aさんは設計士で設計や絵を描くことが得意で、Bさんはロックバンドのミュージシャン、CさんはWEBデザインを専門とする人だとしましょう。彼らが一つのチームになって、公園の再開発について市が考えた案よりも魅力的なモデルを一緒に創っていくことを試みるとします。ここでは専門分化されて同じ領域の人たちが集まりことをなす普段の仕事では、あまり関わることのなかった三者が接点を見つけ、互いの特異性を生かし合う必要があります。どのような形が正解で妥当かは誰も(先生も上司も本人たちも)知りません。
そうした場合は普段どおりのやり方ではなく、新しいアプローチをその都度編み出していく必要があります。うまくいけば単にWEBデザインの技術と音楽技術とを融合させるということ以上の意味をもつ、AさんとBさんとCさんの間ならではの新しい知識(創造的で特異な集合知)が、生まれていきます。
このような共精的な学習においては「個人がどれくらい成績を伸ばせたか」「利益を獲得できたか」ではなく、たとえば「チームとして、特異性を互いに生かし合って、いかに魅力的なものを創れるか」「共愉的な時間や空間が生まれているか」「世の中(環境)がどのように発達していくか」「環境とチーム・ネットワークとが、どのように相互に絡み合いつつ(相互反映的に)、共変化が起こっていくか」が焦点になってきそうです。たくさんうまくいかなかったとしてもそれ自体をチームで愉しみ、それをまた別の機会に資源として、創造的に活用していけばいいのです。
もっと言えば、上で挙げたものより尺度はさらに多様になってくるでしょうし、そもそも尺度から離れるという選択肢も当然にしてあり得ます。尺度はある意味で他者にわかりやすく説明するための道具の一つにすぎません(つまり尺度を全否定するわけではなく、何が一番大事なのかの問題だということ、いつの間にか手段たる道具側が主役になってもよいのだろうかということです)。本当の「評価」(なるもの)は、自分たちが関わっている目の前の具体的な事柄や人に敏感であれば、当事者の方たちにはよくわかるものであり、互いの関係を通してその都度創っていくものでもあります。そうした野性的な敏感さは、野生の実践を重ねる過程でますます鋭敏になっていくことでしょう。
具体的な経験、創造的な経験は、毎回が唯一無二のものであり、そもそも共通の物差しでは推し量ることはできません。物差しで測られたものが無意味だということではなく、多様にありうるうちの、一つの可視化された側面にすぎないということです。人間がつくった物差しに逆に支配されてしまうようでは、本末転倒なのかもしれません。
こうして、先に述べた「働き方」と「学び方」がつながってきます。
1 | 2