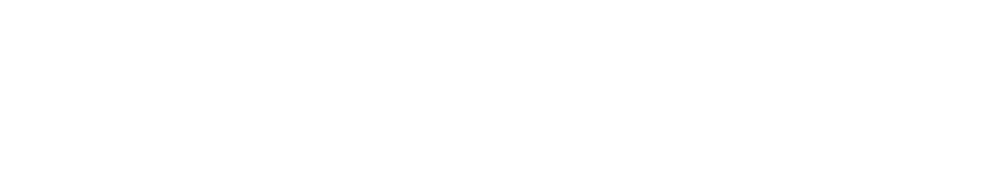第1回 共に愉しみ、創り、生きる社会 [前]
1 | 2
従来型社会と次の社会
1回目と2回目は、イントロダクションとしてこれからの社会のあり方について、大ざっぱな見取り図を示していきたいと思います。図1をご覧ください。これは、半ば実際の事例に基づき、しかし半ば予測的にモデル化したものです。したがって、まったく絵空事というわけではありませんが、100%こうなるというものでもありません。起こりつつある現在進行中の変化です。
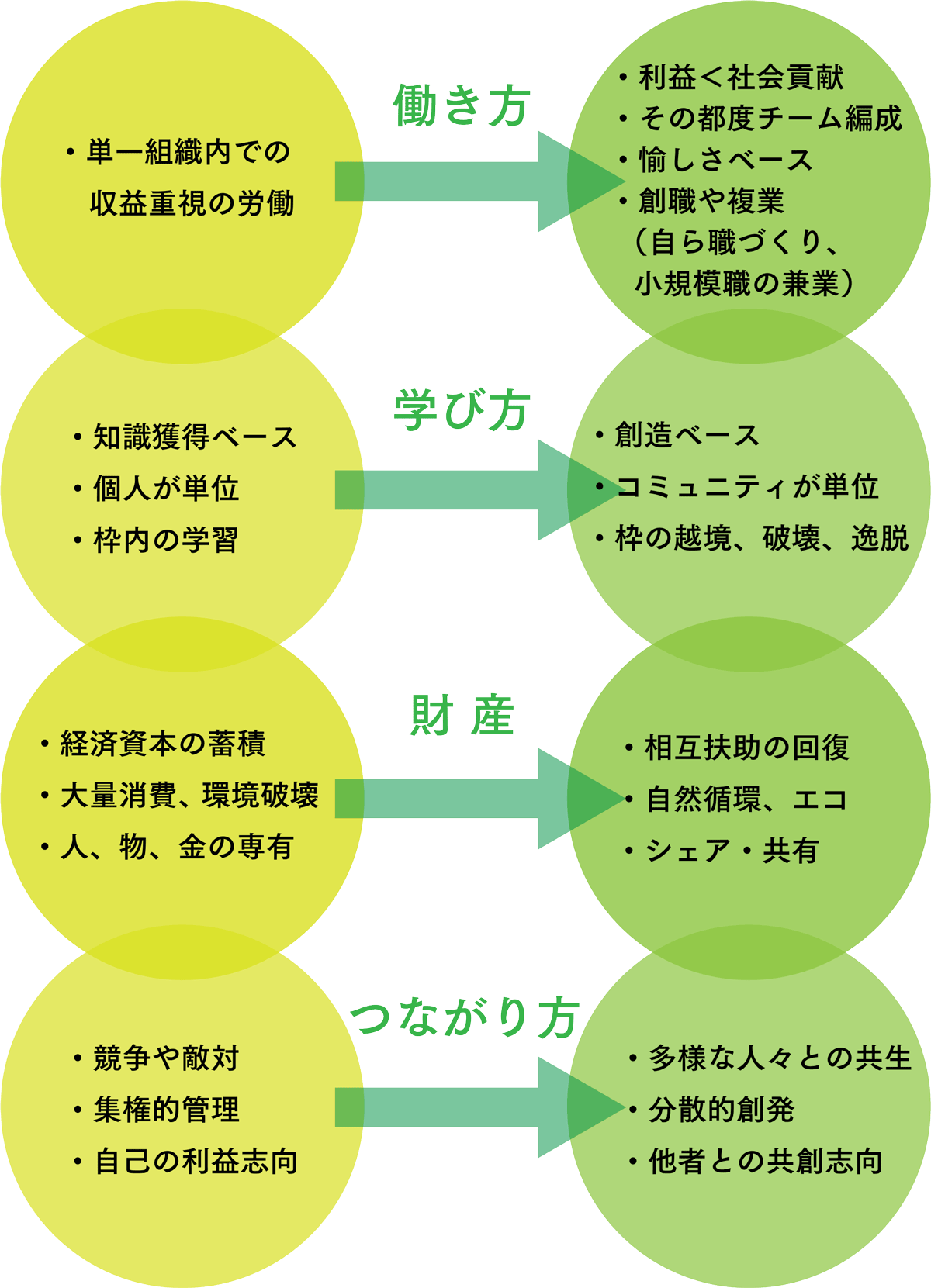
図1「次の社会」の暫定モデル
働き方はこうなる?
上から見ていきましょう。まず働き方で言えば、従来の社会では労働者は「(転職はすれども)一つの組織」に属し、主に「経済的な収益」を会社にもたらすべく働き、その一部を給与として得ていたのが当たり前だった時代から、次の社会では経済的利益を軸にするよりも、何らかの「社会(貢献)活動」が軸となります。これは、単に企業として収益を上げる活動を行う傍らで副次的・二次的なものとして行うような社会貢献ではなく、むしろ社会貢献が主軸になって、その「手段」として収益を上げるという、経済と社会貢献の地位の転換が含まれます。
すでに、社会課題を解決する社会起業家の台頭や非営利団体の拡大がみられたり、営利企業でもCSR(corporate social responsibilit:企業の社会的責任)やCSV(creating shared value:共通価値の創造)が叫ばれて久しいわけですが、こうした動きは次の社会への転換の萌芽といえ、今後いっそうじわじわと強化・拡大していくでしょう──ただ、もちろん現実にはそれらの活動の中でさまざまな課題が生じていますし、本当に既存の在り方からの脱却に相当する活動なのかといった点での検討や議論も必要になってきます──。
なぜこうした動きが起こっていくのでしょうか。
哲学者の柄谷行人(2014)によれば、資本制社会は「三つの無限」に立脚することで持続的な経済成長を果たしてきました。それは、無尽蔵ないし無限の「自然資源」「消費者」「産業革命」です。たとえば、自国で収益が上がらないとみれば他国に進出し各企業が経済成長を図っていくグローバル化は、二番目の「無尽蔵な消費者」という前提を象徴しています。むろんこの「三つの無限」は幻想であり、実際はどれも有限ですから、いずれこの「矛盾は爆発」します。貧困格差、環境破壊、戦争や紛争リスクという、資本主義の三大問題です。
また、経済評論家のジェレミー・リフキンは、資本制は「企業間競争を通して生産性を向上させ価格を下げるという、新しいテクノロジーのイノベーションを随時起こしていく」ことで、最終的には財とサービスの大半がほぼ無料となり、利益が消失して所有権が意味を失い、ついに市場は不要になるとさえ主張します。彼はオスカー・ランゲの言葉を引用してこう述べます。「資本主義体制は自らの首を絞める」と。
そして、70年代にすでに哲学者のイヴァン・イリイチは、産業資本主義では人間の労働が次々とマシーン(機械)に置き換わっていくと主張しました。たとえば飛行機のパイロットは、機械がまだ開発されていないから、そこにいるだけにすぎないといったラディカルな主張をしています。まさに今、AIなどの新しい技術が従来の人間の仕事を侵食していくといった議論がありますが、これは何も今に始まった話ではなく、産業資本主義の必然的な結果でありプロセスであるといえます。人間のための労働や技術発展のようで、実は資本の蓄積と資本制の維持や拡大のためのそれらだからです。人間ではなく、資本制の仕組み自体が巨大な生き物のように人間を動かしているのです。
こうした諸矛盾に直面する中、貨幣経済中心の社会(財の獲得中心の社会)は立ち行かなくなりつつあるという認識が、さまざまな人々の間で広がってきています。ある意味、必然的に社会はNPO法人や社会貢献団体だけでなく、従来の営利企業であっても新しい組織の在り方や働き方──ひょっとすると「労働」という概念すら変わりうるのですが──への転換を模索せざるを得なくなってきているのです。
ただし、経済的利益の獲得という活動からまったく離脱するということでありません。それでは、良くも悪くも長きにわたって発達させ、過去の狩猟採集社会から現在の資本主義社会を生んできた、人類の文化的、歴史的発達──後の回でご紹介する予定です──を無視することになってしまいます。あくまで持続的な経済的利益の獲得が優位で主目的であった状態から、後者の社会環境・自然環境の発達が主目的になり、経済面は副次化ないし社会貢献の「手段」に置かれるようにならざるを得ないということです。
また、すでに波は訪れておりますが、一つの会社や組織に属し、その中で階段を上るように出世していく働き方から、複数の会社への転職が当たり前になり、さらには社内に限定されず多様なジャンルの人との繋がりを生かして、その都度、共通の関心をもとに多様性を生かした小さなチームを(ある意味で即興的に)つくり、プロジェクト単位で活動し、一つのプロジェクトが終わればまた新しい別のチームを編成していくような働き方、生き方がますます増加していきそうです。
それは、特定の地域の異なる企業間や組織・団体間だけでなく、北海道と沖縄というかなり距離の離れた地域の人たち同士、さらには国外の人たちとも、流動的なチーム編成を繰り広げていくことになるはずです。
1 | 2