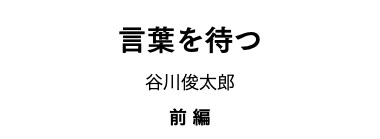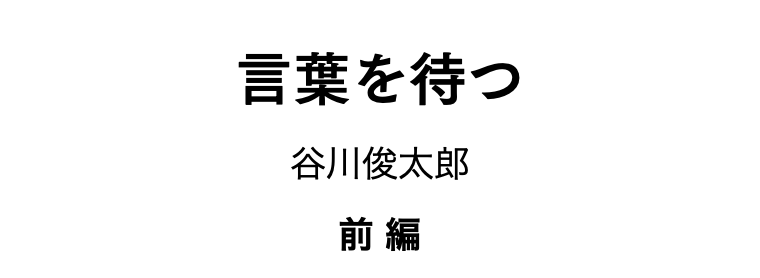interview

page 1

お風呂の中でおならをする感じ
西村 看護師が意識のはっきりしない患者さんに話しかけたときに、「うん」とか「うー」といった応答しかなくても、相手が何かを感じたり、何かを言おうとされたりしているのを感じ取れることがあります。自分の言葉にすべて置き換えることはできないですが、言葉にならない世界でのやりとりが確かにあって、私には何かそこに谷川さんの詩の世界につながるものがあるという気がしています。
谷川 以前、河合隼雄さんと対談した際に、自分の書いている詩と心理療法の共通性に気づいたんです(参考①▶)。それをきっかけに意識の表面にある言語と、そうではなくもっと未分化な何かの動きとして意識下にあるものについて考えるようになったんですよ。まあ、考えてもどうにもならないんだけれども。
日常的に使われている言葉の組み合わせから外れたところで、普段気づいていないことが突然言葉として現れたときに、詩は面白いものになるのだとその頃から思うようになりました。また、僕の母が認知症になり言葉があまりうまく通じなくなったことなども一つのきっかけとなって、福岡で「宅老所よりあい」という老人たちのケアホームをつくった人と知り合いになりました(参考②▶)。
そこへ行って詩を読んだら、入居者の人に「いいかげんにしろ!」って怒鳴られたりするんです。普段われわれはスムーズに言葉を交換しているけど、そういう言葉が全然通じない世界があることがだんだんわかってきた。しかもそれが自分の書く詩と関係していると感じて面白くなってきたんですよ。
西村 そうなんですね。
谷川 詩と、言葉にならないものごととの問題というのは、長年ずっと考えてきたことなんです。言葉自体の根っこや、言葉が発生する源がそこにはあると思っています。だから今は詩を書く時も「待っている」ことが一番大事です。最初から理詰めで書き始めたらどうしても散文的になるから、それを避けて自分の中から何かがポコッと出てくるような詩の始まりが面白いんです。
西村 ポコッと、っていう感じですか...。
谷川 「お風呂の中でおならしてるみたい」って言ってるんですけどね(笑)。いや、本当に自分でも思いがけない言葉が出てくると面白いんですよ。
西村 なるほど(笑)。私の場合は遠回りかもしれませんが、現象学という哲学の知識を借りながら、同じように意識の手前の層の、まだ言葉として生まれてくる前の営みにこだわりを持ち続けています。たとえば谷川さんのお仕事への関心で言えば、「二十億光年の孤独」(『二十億光年の孤独』創元社、1952年に所収)という詩の中に「万有引力とは/引き合う孤独の力である」という箇所がありますが、この「万有引力」という言葉などは、あの詩全体のリズムに浸って読んでいると、テンポの違ういろいろな句に、身体ごと引き寄せられたり押しのけられたりという、なにか働きかけのようなものを感じさせられます。
谷川 あの詩を書いた頃、僕はまだ今言ったようなことは何も考えてなかったんですけど、詩の言語というのがそもそも論理的な言語とはちょっと次元が違うところで成立しているということなんでしょうね。言語というのは我々の立場からすると非常に困ったものなんです。
西村 困ったもの?
谷川 はい。我々が何かこう、言語に頼らずに直観的にある全体を感じているとしますよね。でもそれを言葉に書こうとするとき、どうしても言語がものごとを分割していくわけじゃないですか。「正しい/正しくない」「美しい/醜い」みたいなかたちで、基本的に2つに分けていく。そういう言語をどうにかして一つに統合して、まずは言語以前の存在のようなものに迫ろうというのが詩のわけですから。
たとえば“万有引力”という語も物理学の辞典を引けばサラッとそれが何であるか教えてくれるわけですよね。我々はそういうふうに普段言葉を使っているんだけど、それをうまくコノテーション、つまり存在と言葉の結びつきの含意によって科学的な定義ではないところへ曖昧に広げていきたいわけです。だから普通なら散文の世界では許されない曖昧さというものが、詩の場合にはすごく大事だと思っていますね。
西村 なので、あえて矛盾した表現もみられるわけですね。
谷川 「矛盾だけが現実のすがたであり、現実性の基準だ」と、たしかシモーヌ・ヴェイユが書いています(参考③▶)。あの言葉にはすごく目が開かれましたね。日常生活ではどうしてもつい「矛盾しているのはだめだよ」となっちゃうわけでしょ。だけど詩の場合は矛盾してないものはみんなリアルではない。基本的にそう思います。
page 1 2