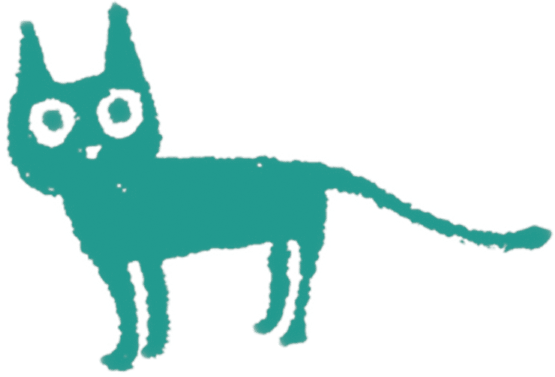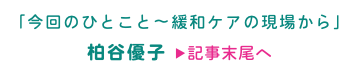───
───
───

イラストレーション : : 楠木雪野
連 載

>> この連載について/予定

< ● ○
できなかったことではなく、できていることに目を向けたり、
弱さや苦手なことも認められる関係を築く
医療だけでなくこれまでの専門職教育・マネジメントの特徴は、だれもがオールマイティな能力があることを前提とし、できなかった点に目を向け改善していく「欠乏・問題モデル」※2で考える傾向が強いと思われます。自分たちの不足点に目を向けるのは、専門職としての責任感の表れだと言えますが、特に看護については、あるケースにおいて、何がよい看護なのか、答えが一つに決まることは少なく、誰からも文句の出ない完璧な看護を毎回実践することは難しいと思います。その中で、できなかった点に目をむけてばかりいると、自分やスタッフがバーンアウトしてしまうこともあるかもしれません。
※2 手島恵編『主体性を高めチームを活性化する!看護のためのポジティブ・マネジメント』、医学書院、p.18-20.
対話的な関係とは、互いのできていないところだけを見るのではなく、それと同時にできていることも認める関係であり、意見の違いだけでなく、弱さや苦手なことも違いとして認められる関係だと筆者は考えています。そして、看護のスタッフ養成においては、特にこの点は重要だと考えています。
筆者が関わっている緩和ケアの領域では、医療職同士の「デスカンファレンス(デスカンファ)」というものがあります。緩和ケアでは、患者さんの死に直面することが避けられません。医療職にとっても患者の死はつらいものですから、患者さんが亡くなった時に医療者同士で、その患者さんについて振り返りをするのがデスカンファです。ところが、ある緩和ケアナースから「デスカンファがつらくなって、やめることにした」という話を聞きました。詳しく聞くと、その方の施設では、デスカンファでも、普段のカンファレンスの調子で、行った看護が適切であったか、こうもできたのではないかと反省ばかりしてしまい、患者さんの死を受け止めるどころか、かえってスタッフがつらくなってしまったということでした。そこでこの方の施設では、業務時間内のデスカンファはやめ、業務外で希望する人だけが参加し、亡くなった患者さんに対しての思いを、ただシェアするだけの集まりを設けるようにした、ということでした。
患者さんの死は極端なケースですが、患者さんからクレームが来たりして「うまくいかなかった」ケースを振り返る際にも、まずはそのことで、自分たちも「悲しい」「傷ついた」という気持ちをシェアすることは大切なのではないかと思います。そして、できていなかったことだけでなく、できていたこともスタッフで振り返り、それを「このような看護をしたい」というしたい看護の姿を共有できるきっかけにすることができれば、うまくいかなかった経験を活かしつつ、よりよい看護を行なっていこうというスタッフのエンパワメントになると思われます。
もう一つ、専門職として難しいのは、専門職であってもそれぞれの得意・不得意があることを許容することではないでしょうか。しかし、だれもがオールマイティな能力があると考えるのではなく、それぞれの得意・不得意を認め、補い合う関係を築くことも協働の条件である、と筆者は考えています。先の事例の患者Yさんの例でも、話し合いの参加者のなかに、「自分も気持ちを言葉にするのが苦手なので、この患者さんの気持ちはわかる。このようなタイプの方は、言葉にならないことをあれこれ聞かれることがしんどい場合もあるので、身体面でのケアを会話を交わしながら丁寧にすることを先にしてはどうか」と意見を述べられた方がいて、他の方は「自分は無理に話させようとしていたのかも、と気づいた」と話されてしていました。
ケアの対象となる患者さんにも、いろいろな得意・不得意を持った方がいるため、それを理解し、対応するためには、専門職の側も自分たちの多様性や得意・不得意を認め合い、生かせる関係性を築くほうがそのチームの強みになると筆者は考えます。そして、医療現場のコミュニケーションでは「欠乏・問題モデル」だけでなく、自分やスタッフの実践を肯定し、エンパワメントするコミュニケーションも重要ではないかと思います。
ケアを重視する組織には、対話・ケア的な組織風土が必要
筆者が医療者同士のコミュニケーションにも対話的な関係が必要だと考えるのは、それがスタッフへのケアやエンパワメントにもなるからであり、さらにスタッフのケア的態度の教育にもなるからです。この連載で言うケア・ケアリングとは、看護師の業務としての「看護ケア」のことではありません。ここでいうケアとはもう少し広く、人と人との関わりや話し合いの目標として何を置くか、についての考え方や理念を指しています。医療者のみなさんに馴染みがある言い方では、「キュア(治療・効率や結果)重視の考え方」に対置して、「ケア(その人らしさ、QOL)重視の考え方」も必要と言われる時の「ケア重視の考え方」のことです。
医療現場において、これまではキュア中心で、効率・結果重視の考え方が強かったため、問題解決思考で、一つの答えに早く到達することがコミュニケーションにおいても重視されていました。ところが現在は、多くの場面で患者の価値に沿った生活の実現やQOLが重視されるようになり、ケア的なアプローチがナースだけでなく、医療現場全体のアプローチとして必要となっていると言えます。そして、患者に対しても、スタッフに対しても、キュア志向で一つに答えが収斂する場合には、専門家やリーダーのように、答えや知識を知っている人が一方向的に「決める」「教える」ことが可能ですが、それぞれの人が自分の価値観に基づいて主体的に動くことが重要な場合は、相手が誰であれ、その人なりの方向性を「引き出し」「育てる」ための、相手を中心に置いたコミュニケーション、すなわち〈対話的態度〉が重要になってきます。
さらに、それぞれの人が自分らしく、主体的に動くことができるようになるためには、その場がそれぞれの人の違いをお互いに認めあう場であることが必要ですし、違いのなかには、不得意や弱さもあり、それを認め補いあう場があるからこそ、それぞれの得意なことや〈主体性agency〉※3も引き出されると考えるべきでしょう。対話・ケア的態度や主体性に関しては、専門職やリーダーの個人のスキルやそれによって引き出されるものというよりも、患者であれ、スタッフであれ、その人が置かれている場そのものに〈対話的環境〉が浸透していること、その場にいる多くの人が対話的態度にある程度コミットしていることが重要だと筆者は考えています。
※3「主体性」については、session7の後半を参照
そして、自分自身の周りとの違いや主体性が尊重される対話・ケア的環境にあることによって初めて、その人自身が他者を尊重し、相手の主体性を引きだす対話・ケア的態度を取れるようになるのではないでしょうか。すなわち、医療スタッフが患者を尊重し、その人の主体性を引き出すための関わりができるようになるには、その人自身が、ケア的・対話的環境を経験しているということが重要ではないかと思われます。
ビジネスシーンにおける対話的態度とは、時として組織の生産性を上げる、リスクや事故を減らすための単なる「手法」として捉えられることがあります。しかし、医療現場において、患者の主体性を引き出すというケア的な考え方が重視されるのであれば、医療の組織自体に互いの違いや主体性を尊重するケア的な考え方や対話的態度・環境が、ミッションに合致する組織のあり方として取り入れられる必要がある、というのが筆者の考えです。
![]()

医療組織内の多職種協働に課題を抱えていない現場など、ないのではないでしょうか。私が大学病院で所属横断の緩和ケア専従看護師として勤務していたときには、地域連携よりも院内連携のほうがよほど難しいとさえ思ったことがありました。そしていま現在、看護管理専従職として聞く各部署の報告からも、自身が会議などに参加していても、連携場面で少なからず感じているのが“通じ合うって難しい”ということです。なぜこうもわかり合えない、あるいは、わかりあえるようなコミュニケーションが取れないのでしょうか。
本文の中で高橋さんも、専門職教育・マネジメントの特徴として『欠乏・問題モデル』で考える傾向があることを指摘していますが、臨床では私たち医療従事者は、常に問題解決思考が優位になって行動してるということが“通じ合えない”ことに関係していると思っています。臨床では、医療従事者は誰もが役に立つことを価値として行動する傾向があるため、正しくありたいと思うあまりただ一つの正解を探しがちです。しかし、人は常に矛盾を抱えて生きています。
たとえば「苦痛緩和治療と自由度の高い暮らし(治療に時間は割けない・器材は使いたくない)を両立させたい」などです。このような場合、もちろんどちらも考慮すべきなのでしょうが、主にCure(治療)の視点で思考する医師と、主にCare(ケア・生活)の視点で思考する看護師とでは、方針決定の場で意見がかみ合わなくなることもしばしばです。職種・業務が形成する価値観というのでしょうか、そうしたものに縛られて柔軟性を欠いているということなのかもしれませんね。また、圧倒的に時間がないということも、さらに“わかり合う”ことを難しくしているのだと感じます。もう一歩踏み込んで話し合いたいと思っても、時間が決まっている診療やナースコール等に阻まれてしまうようなことが、皆さんにも経験があるだろうと思います。
もうひとつ、検査室採血後の止血不良に関わるインシデントレポートを受けて、医療安全担当から聞いた話も、臨床ではありがちなことだと思いました。同じようなインシデントを生まないために、看護側から採血後の止血手技について、検査室でもうひと手間、少しの配慮を加えてはどうか、との提案をしたところ、検査室側は「新たな手間を増やすことはできない」という考えを譲らず、話にならなかった(わかり合えなかった)そうです。臨床で各職種・各部署は、少しずつ重なり合った業務をしているのが通常です。診療の流れを見直したりする際には、どちらがその業務を担うのかといった駆け引きがあるのが常で、ややもすると自部署の損得で考えがちです。止血インシデントの件も、患者の安全や診療の質を共に担う立場という前提で、望ましい解決策について話し合えればよかったのでしょうが、一方が業務の質について話し、他方は業務の量でその話に応じているという、すれ違いが起きていました。
互いの価値観や視点の相違によるすれ違い、問題・課題に対する取り組み姿勢の違いを超えてわかり合えるように努力できるようでありたいですね。今回のSession8をヒントに、それから先に紹介されているSession5もエンパシー(共感的理解)について書かれていて、「他人の靴を履いてみる」といったような思考の練習についての提案がありました。理解と納得を得て協働するほうが働く人のストレス度は低いでしょうし、アウトカムの質も高くなる、そんなふうに思います。
< ● ○
>> この連載について/予定