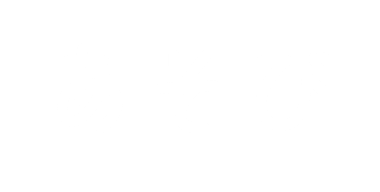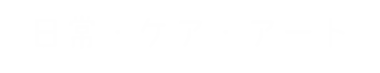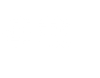───
───
───
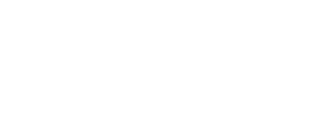

すぎもと・まさたけ
東京衛生アドベンチスト病院内科医師。糖尿病臨床を専門とする。ナラティヴ・アプローチと出会い、病い体験や病いの意味を尊重した糖尿病診療をめざしている。主な著書「医師と栄養士と患者のためのカーボカウンティング実践ガイド」「2型糖尿病のためのカーボカウント実践ガイド」「糖尿病でもおいしく食べる」など。
日常はナラティブによって紡ぎ出される
その人の日常や人生に入り込んでいく杉本さんの診療スタイルは、Narrative based medicine(以下、NBM)との出会いが大きく影響している。Evidence based medicine(以下、EBM)で分類される“糖尿病患者さん”は、NBMにおいてはその人が人生の物語の主人公であり、一人ひとりの物語の中で糖尿病という病いがさまざまに意味づけられる。病いの意味は単線の因果論的アプローチではとらえられず、複数のストーリーが絡まっていて、その網の目をほどいていかなければ理解ができない。
また、その人ならではの修辞的な表現は、物語独自のフレームワークをつかむ手がかりとなる。医学的な枠組みを当てはめるのではなく、その人の物語の中から検査値の意味を考えようとすれば、援助する側の私たちは知らず知らずのうちに相手の日常に巻き込まれ、その人がどんな薬をどうやって使うのか、生活のうえでどう工夫をしたらいいのかという検討が生き生きとしたものになる。だから杉本さんは、患者さんが人生や日常の物語を豊かに語れるように質問を重ねていくのだ。「それって、どういう意味なのですか?」と。
冒頭の患者さんとの会話は、そのようにして紡ぎ出されたものだ。医師としての正論を振りかざすことなく、叱ったりすることもなく、体重が増えた理由を徹底してフラットに対等な姿勢で聴く杉本さんの声かけは、診察室でその人の日常の風景を描き出し、その中で何ができるかを一緒に考える場を生み出している。体重増加、糖尿病の指標であるヘモグロビンエーワンシー(HbA1c)や血糖の値上昇は、糖尿病の診察ではいわゆるバッドニュースだが、この結果だけをみて「食べ過ぎです」と一蹴するのではなく、そこに連なるいくつかの物語を紡ぎ出して一緒に入り込みながら、あれやこれやと実践する糖尿病診療や看護が〈おもしろい〉のである。
名料理人?!糖尿病治療のいい匙加減
食事をとても楽しんでいるある糖尿病の患者さん。食事制限ありきの“非人道的”な栄養指導に憤慨し、自分なりの運動療法で対処している。おいしいものを食べれば、それに見合うウォーキング(驚くほどの歩行量である!)をし、糖尿病であっても自分の食べたいように食べている。日焼けしたその人にエピソードを聞かせてもらいながら、杉本さんは診察を進める。妊娠糖尿病の患者さんであれば、妊娠期間中の治療が大半であり、限られた時間でタイムリーかつ濃密な支援が必要になる。インスリンを適切なタイミングで打てば血糖値を下げることができるからだ。
昨今は持続して血糖測定が可能なモニタリング器機(Continuous Glucose Monitoring:CGM)が普及し、たとえば血糖値の推移を読み取りながら、インリンの打ち方を決めていくことができる。患者さんから杉本さんに「先生、Wチーズバーガー食べちゃったらこうなっちゃった……」とSOSが届く。炭水化物に加えて脂質が多い食事となると、通常のインスリン投与では血糖値の下がりが悪くなる。そこで、杉本さんは、複数のインスリンを時間差で使い分け、血糖値の上昇カーブを緩やかにする方法をとる。持続モニタリングで描かれる血糖値曲線とにらめっこしながら、あれこれと戦略を立ててうまくいったのかどうかを診察室で患者さんと一緒に確認するのである。
また、このようにその人の日常の中に入り込んで行う診察にはSNSがとても役に立つ。互いにフォローし合った患者さんが投稿する家族や仲間との食事のひとときから、その人の物語を知り、その人の身体で起きている血糖値の上昇をできるだけ緩やかにするための匙加減をみるのだ。
なんだか杉本さんの診察室がキッチンのように思えてくる。たとえば今夜の食事はおいしいカレーライスだ。玉ねぎをじっくり炒めて甘みを出し、お肉を叩いて塩コショウで下準備、隠し味のスパイスをちょっと入れてじっくり煮込んで……。大切な人にじっくり味わってもらいたいという、そんなイメージと重なるのである。その人の今の身体に合わせた匙加減ができる料理人……ではなく医師がそこにはいる。

杉本さんは、2型糖尿病の疾患分類が変わっていく可能性に期待している。現在、糖尿病は1型と2型のほか、妊娠糖尿病やその他の特定機序および疾患によるものに分類されており、2型以外のタイプに分類されないものはすべて2型糖尿病とされている。しかし、最近、2型糖尿病の中に4つのクラスターが同定され、インスリンの働き具合によって細分化された●1。
たくさん食べても、多少体重が増えても、インスリン分泌が十分なタイプならHbA1cは上昇しない。一方、インスリンの分泌力が落ちているタイプだと、たくさん食べればHbA1cは上昇する。2型糖尿病という一つの括りが、その人のインスリンの働き具合に合わせて括り直されれば、それぞれに合わせた治療やアドバイスが可能になる。杉本さんは、画一的に「食べ過ぎです」と注意するステレオタイプで傲慢な医療者の指導が減っていくことに期待している。
レシピどおりにしか料理をつくれないのでは、楽しみは広がらない。今日の食材の特徴や食べる人の好みに合わせて、臨機応変に匙加減を変えられる料理人の料理はおいしい。その人のインスリン分泌力、その人のインスリン抵抗性、その人の物語が調和するような薬の処方や生活アドバイスを、杉本さんのようにいい塩梅でできる医療者が増えたらいいと思う。
糖尿病物語の語り口を変えていく
私は、看護研究者として糖尿病である人たちにたくさんインタビューをしてきた。その経験から、糖尿病であることを語るときの当事者には、特有の語り口があるように思う。多くの人がポロっとこぼす「つい食べちゃうね」というセリフはその代表格だ。このフレーズが口にされるのは、がんばってきた糖尿病マネジメントの語りが綻びを見せたときであり、それは苦笑いが伴うちょっと切ない瞬間だ。これほどまでに食べることが自己責任化されており、そのことを本人は自覚していない。私自身も臨床にいた頃、患者さんにこう言わせる言葉がけをしていたと思う。そして社会そのものにも“生活習慣病”の呼び名が引き連れてくる疾患管理を自己責任化する固定観念が根深く浸透していることを痛感する。
「糖尿病の人が食べていけないものは毒物だけです!」「糖尿病の人はおいしいものを食べなければならないんです」と繰り返す杉本さんは、スイーツが好きならスイーツを、お酒が好きならお酒を楽しみながらマネジメントしていくことを粘り強く説明していく。驚いて半信半疑で杉本さんの言葉を聞く患者さんの固定観念を、そうして毎度の診察で塗り直していく。しかし「制限してこそ患者さん」と刷り込まれてきた患者さんを変えるのは難しい。診察室に入ってすぐに今回のHbA1c数値を聞いてくる人には、「僕はあなたの話を聞くまで診ませんよ!」と伝える。今回の結果だけで判断するのではなく、まずはあなたがどういう生活を送ってきたのか、その物語を聞かなければ診察は始まらないのだ、という姿勢を相手に見せるのだ。
生活には楽しいこともあればつらいこともある。毎日摂る食事との向き合い方はその時どきで変わっていくものだ。そのような日々の物語のなかで、一つひとつの結果を患者さんとともに意味づけすることにより、杉本さんはその人らしい食事、その人が実現したい食事に向けて、たくさんある引き出しからうまいやり方を提案する。
「糖尿病である人はおいしいものを食べなければならない」と患者さんに話す杉本さんの診察室ではスイーツ談義にも花が咲く。リンゴのスイーツに目がない杉本さんは、「そのアップルパイ、どこのお店?」と目を輝かせて一緒にインターネットで検索する。「このお店のものだと糖質は○gだね。間食の糖質は20gを超えないほうがいいから、ご夫婦で半分ずつにしたら?」と提案したり「レアチーズケーキは一番血糖が上がらないよ」と情報提供したりする。そんな会話を続けるなかで、患者さんのほうから「昨日○○を食べたけど、先生どうかな?」と率直な質問が出てくるようになると安心する。もしこれが一般的な糖尿病指導にありがちな問題解決型のコミュニケーションだったなら、アップルパイを食べたエピソードは語られないだろう。
生きていくこと。老いていくこと。それは、個人だけの営みではない。身近な人たち、身近な世界の中で連綿と続く営みだ。その人生や日常に糖尿病は練り込まれている。その糖尿病の語り口が自己責任化してしまうのは、寂しい。そして、その語り口は、医療者や社会の言葉がけと対になっていることを忘れてはならない。糖尿病治療のフレームワークではなく、その人の物語のフレームワークで語ることができるような問いかけ方がもっと浸透したら、糖尿病であることの語り口はもっとその人固有のものになっていくだろう。杉本さんはご自身の仕事ぶりを「人生の伴走者」と語る。それは長年EBMとNBMをいい塩梅で融合させてきた実践に裏づけられた、味わい深い表現だった。
●1:Wesolowska-Andersen, A., Brorsson, C. A., Bizzotto, R., Mari, et al. : Four groups of type 2 diabetes contribute to the etiological and clinical heterogeneity in newly diagnosed individuals: An IMI DIRECT study. Cell reports. Medicine, 3(1), 100477, 2022. doi:10.1016/j.xcrm.2021.100477