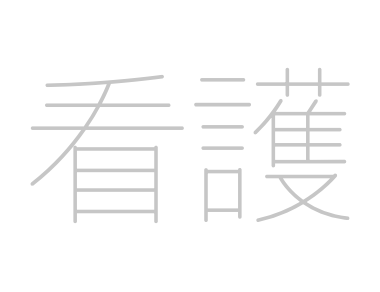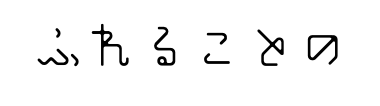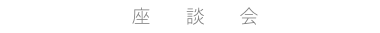───
───
───

当社では2021年5月に、コロナ禍における看護の状況を医療人類学の視点から検証したNursing Todayブックレット『「コロナ」と「看護」と「触れること」』を刊行しました。看護師が手を使い患者に「触れること」がままならない現状をめぐるその議論をきっかけに、その名も「て・あーて(TE・ARTE)推進協会」の発起人である川嶋みどり氏と、「熱布バックケア」の普及活動に取り組む茂野香おる氏・内山孝子氏をお迎えし、看護職自身の立場から「触れること」のもつ普遍的な意義について語り合っていただきました。(編集部)
看護師にはやはり手が必要
川嶋 まさに世の中では感染への恐れから「手で直接触れないで」としきりに言われている最中ですから、私もこのブックレットを読んでみました。すると本書の中に、現代の医療技術が非常に複雑かつ臨機応変な対応が求められる昨今では、看護に求められる知識と技術が幅も量も膨大なものになっており、今一度、そもそも看護師がすべき仕事の割り当てを考え直す必要があるだろう、という記述が見られました。またそこには、救命知識や医療的技術の重要性に目を向けた場合には、従来的な看護の役割そのもの──コロナ禍で患者との接触がままならない中で、患者に手を触れたり直接言葉かけを行ったりということの意義──も改めて問うべきだという主張があり、私はそのことがとても気になりました。
もちろん、論者の波平恵美子先生(医療人類学者・看護教育従事者)は、「医療者ではない立場で見聞きしてきた限られた情報に基づいている」といった前提を述べておられ、テーマの渦中にいる看護の当事者とは違った立場から、あえて学者的な姿勢で「そもそも」の看護のあり方に対し疑問を呈されたのでしょう。でも、だからこそ、私たち看護師も個々に自身の考えをきちんと言葉にしておかねばならないと思ったのです。
私は看護にとって「触れること」は、昔も今も、そしてこれからも変わることのない普遍的な本質だと考えています。ウイリアム・オスラー博士●1は 「洗練されるべき技術として、また従うべき専門職としての看護は近代的なものである。しかし実践としての看護は、洞窟に住む人たちの間で母親が病める子どもの額を小川の水で冷やした漠とした過去に遡る」●2と述べています。
●1 William Osler(1849‐1919)カナダと米国、英国を代表する内科医、医学研究者。医学教育の基礎を築いた人物として知られ、『The Principles and Practice of Medicine』(医学の原理と実際/1891)など多くの名著を残しており、日本でも『平静の心―オスラー博士講演集』が刊行されている。 ●2 引用文献(Osler, W. : Aequanimitas: With Other Addresses to Medical Students, Nurses and Practitioners of Medicine, 1932)
この時代のことは想像するしかありませんが、人間が直立二足歩行を獲得し、前足を手に解放して共同体の仲間たちとともに男性は狩りを、女性らは植物を採取して仲間たちの飢えを満たし、いのちをつないだのです。つまり原始時代からヒトの営みには社会性が組み込まれていて、自分以外の人の役に立つために手を使い始めたとも言えるわけです。看護実践の基礎はそこから始まったものであり、互いに傷の手当てをしたり熱した石で痛むお腹を温めたりといった、みんなで助け合うケアの行為が現在まで続いているのだと。
一方、「触れる」という言葉は、目や耳の知覚を通したやりとりのほか、人格同士の交流においても用いられ、例えば「折に触れる」「事に触れる」など、より抽象的なレベルでも使われます。ここでは主に直接的看護師スキンシップの意味で患者さんの身体に看護師が触れることと、全人的に対象の人格と向き合い、そばに寄り添いながら相互作用していく看護の重要なアプローチのツールとして注目したいと思います。
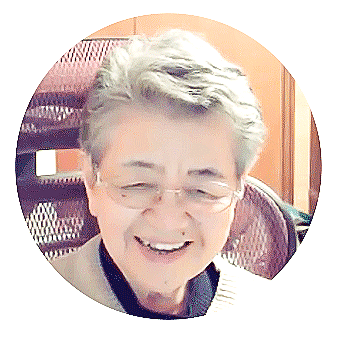
川嶋 みどり(かわしま・みどり)看護師。健和会臨床看護学研究所所長、日本赤十字看護大学名誉教授。1951年日本赤十字女子専門学校卒業、1971年まで日本赤十字社中央病院、日赤女専、同短期大学に勤務、1984年健和会臨床看護学研究所創設、2003年日本赤十字看護大学教授、2011年日本赤十字看護大学名誉教授。2007年第41回ナイチンゲール記章受章。2013年一般社団法人日本て・あーてTE-ARTE推進協会代表理事に。
川嶋 個人的に私自身が手を触れることに重きを置き始めた理由は、長く看護師を続けてきた中で次第に看護師たちがそれをしなくなったと気づいたからです。およそ20年近く前からその兆しはありましたが、とくに実感したのは私の夫が舌がんの末期に入院した緩和ケア病棟での出来事でした。私は夫の思いを尊重して大学の仕事を続けていましたが、ある日様子を見に行くと、夫の足が氷のように冷たくなっているのに、看護師たちはそのことに気づきさえしていませんでした。身体に触れていないから、わからなかったのです。
そこで、朝夕、私が足浴で温めたりしていたのですが、ある日、友人の村松静子さん●3がお見舞に来こられたときのことでした。病室に入ってくるなり、さっと夫の首筋に手を入れて「こんなに肩が凝ってる。大変ね、つらかったでしょう……」と、ほとばしるように声をかけながら、襟元から手を差し入れて肩を擦ってくれました。私の夫は気の強い人であまり弱音を吐かなかったし、手術で舌を全部取ってしゃべれなかったので筆談でしたが、そのとき大粒の涙をポロポロっと流しながら、紙にペンで「ありがとう、気持ちよかった」と書いたんです。
●3 むらまつ・せいこ1947年秋田県生まれ。日本赤十字社医療センターICU初代看護師長を経て、1986年在宅看護研究センター創立。2010年、メッセンジャーナース認定協会を設立。2011年に「フローレンス・ナイチンゲール記章」受章している。著書に『「自主逝」のすすめ』『メッセンジャーナース:看護の本質に迫る』などがある
結婚して50年、元気な頃は2人で手をつないで歩いたことなど一度もなかったけど、病室にいる夫は私の手をギューッと血流が悪くなるぐらい強く握り続けるんです。そうしたこともあったし、村松さんの行為を見て「看護師はもっと手を用いなければいけない」と本当に感じました。
そのような体験もあって、私は看護の基本となる「手当て」の重要性を広めるため、文科省の研究費で看護師の手の有用性に関する研究を続けるなどして、看護師が患者に手で触れるケアの価値付けを、折りに触れて書いたり話したりして来ました。日本の看護の状況は先ほど述べたとおりですが、「手で触れるケア」からますます遠のいている現状があります。例えば患者さんが「足が腫れて赤い」と訴えても、看護師は「先生に話しておきましょう」あるいは「明日、湿布薬をもらっておきますね」と答えるのみで、自身で触れて熱いか・冷たいか、どこが発赤しているかなど見ようともしない。そうした危機的状況が以前からありました。
今はさらに新型コロナウイルスの感染予防という理由から、ソーシャルディスタンシングが定着しつつあり、「離れましょう」「そばに近寄らないでおきましょう」「できるだけ短時間にしましょう」と、ますます触れないことが正当化されています。ですが、私は、コロナの時代だからこそ、看護師が本来の看護の本質を改めて見直し、手で触れることの大切さを見つめ直す機会じゃないかと思うのです。
現場の変化〜数値ではとらえきれないもの
茂野 学生を通して臨床の現場を見ていると、「触れる」ことから「機器に頼る」ことに変化していると感じています。例えば脈拍測定の場面では、1分間きちんと患者さんの脈を手で触れて観察し、その後呼吸をみていくことを期待しますが、学生は看護師が脈を触れずサチュレーション・モニターに示される値をそのまま記入しているのを見て、「学校で習ったようなことを臨床ではしていませんでした」と平気で言ってしまうのです。

茂野 香おる(しげの・かおる)看護師。淑徳大学看護栄養学部/大学院看護学研究科教授。千葉県救急医医療センターにて臨床経験後、千葉県立衛生短期大学助手・講師・助教授・教授、天理医療大学教授など経て2014年より現職。2015年日本赤十字看護大学看護学研究科看護学研究科博士課程修了 博士(看護学)。熱布バックケア普及プロジェクトメンバー。
このようなことが日常的に起きてきています。本当に看護師が患者さんに直接触れることに執着しなくなったと感じるのです。医療者が患者さんに触れる機会が少なくなったという意見もあるようですが、確かに、月に1回定期受診で訪れる外来患者さんなどはそうかもしれませんが、それは多様な現場の一面です。患者さんそれぞれの病状やADLなどの状況によっては触れることが不可欠な場合が多くあるのです。
内山 私は5年ほど前まで臨床で働いていました。例えば具合の悪い人が目の前にいて血圧計やパルスオキシメーター、聴診器がなかったとしても、手を使い脈に触れれば、脈拍の数だけでなく患者さんの脈の緊張から、およそどれくらいの血圧があるかなどもわかります。また皮膚の湿り具合や乾き具合から「この人は脱水では?」「ショックの前兆では?」などの兆候もつかめますし、胸に手を当てれば痰の位置や呼吸状態も当然知ることができます。腹部なら触れた場所によりその痛みがどのような疾患や徴候から起こる反応なのか、また張りの状態で便がどこにありそうかも手を通してすべてわかるのです。

内山 孝子(うちやま・たかこ)看護師・保健師。東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科准教授。1989年藤田保健衛生大学 衛生学部衛生看護学科卒業。諏訪中央病院、医療法人財団健和会:みさと健和病院・柳原リハビリテーション病院で勤務。2013年日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修士課程修了、2016年日本赤十字看護大学大学院 看護学研究科博士後期課程修了後、日本赤十字看護大学助教を経て現職。熱布バックケア普及プロジェクトメンバー。
確かに道具を使って状態を数値に置き換えることも大事ですが、数字では表現できないこともたくさんあり、そこにこそ看護がある。看護師同士の情報共有として血圧や体温などを知る必要はありますが、患者さんそばに立てば、やはり川嶋先生がおっしゃったように、「先生に言っておきますね」ではなく、看護師としてどこがどの程度どのように痛くて、どのように困っておられるのかを知る必要があり、それにはまず触れてみないことには何もわからないのです。
現場の変化〜数値ではとらえきれないもの
茂野 学生を通して臨床の現場を見ていると、「触れる」ことから「機器に頼る」ことに変化していると感じています。例えば脈拍測定の場面では、1分間きちんと患者さんの脈を手で触れて観察し、その後呼吸をみていくことを期待しますが、学生は看護師が脈を触れずサチュレーション・モニターに示される値をそのまま記入しているのを見て、「学校で習ったようなことを臨床ではしていませんでした」と平気で言ってしまうのです。このようなことが日常的に起きてきています。本当に看護師が患者さんに直接触れることに執着しなくなったと感じるのです。医療者が患者さんに触れる機会が少なくなったという意見もあるようですが、確かに、月に1回定期受診で訪れる外来患者さんなどはそうかもしれませんが、それは多様な現場の一面です。患者さんそれぞれの病状やADLなどの状況によっては触れることが不可欠な場合が多くあるのです。