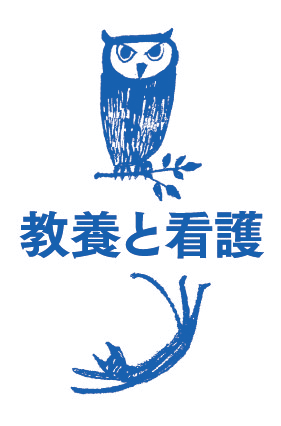写真提供:東京都立千早高校演劇部
──高校生たちは、自分たちの問題意識や考えていることを表に出す行為に対し、どんな思いやおもしろさを感じているのでしょうか。
青柳 私は今までさまざまな学校で演劇部の顧問をしてきましたが、「自分たちを表現する」というのをほとんどやってこなかったように思えます。しかし、ここ数年の本校の作品は、今この場にいる部員にしか表現することのできないオンリーワンの芝居がつくれているような気がします。もちろん、100%自分たちの話というものではなく、一部にフィクションを織り交ぜてはいますが、彼女たち(演劇部員)の心情としては自分たちの話をしているような感覚になっているようです。“虚構じゃない迫力”を出せているのではないのかと思います。
柏木部員にとって、自分たちの話を集団創作で演劇にしていく意味はあるのでしょうか。青柳先生はずっと部員のそばにいて、何か感じますか?
青柳 ある部員の話によると、自分たちの生活を見つめなおしたり考えたりするきっかけになっているようです。演劇のテクニックが上達するとか、俳優として成長するとかではなく、生き方や考え方が変わり、人としての成長につながっているのです。役を自分と重ね合わせて演じているため、「思い入れが強くなってどう演じればよいかわからない」といったことを口にする部員もいますが、そこを乗り越え、人間的に間違いなく成長できていると思います。
寺﨑 彼女たちの姿を見ていると、特に演劇がやりたくて演劇部にいるわけではない、演劇を仕事にしていきたいわけでもない、正直、演劇がそこまで好きなわけでもないかもしれません。それでも自分たちの話を演劇にしていくことで、安心感みたいなものが彼女たちに広がっているようにみえます。演劇部が彼女たちにとっては居場所になっていたり、子どもとして過ごすことのできる唯一の空間になっていたりする気がします。今回の作品をつくるにあたり、彼女たちは“主張すること”を選びませんでしたよね。
柏木 そうですね。集団創作という手法では、演劇部員が自分たちでどう作品をつくっていきたいかを考えながら進めていくのですが、「どう観客に伝えたいか」と尋ねると、彼女たちは「ただ会話をし続ける」ことを選びました。「この問題が大変なんだ!」と主張する演劇になる可能性もあったし、そっちを選んでもよかったのですが、彼女たちは「自分たちの会話をみせることで伝える」ことにしたのです。
青柳 彼女たちの性格もあるかもしれませんが、思いっきり主張することはせず、さまざまな問題がある状況を受け入れたうえで、「でもね……」と思いを伝えていくかたちですよね。作品のなかで、彼女たちの抱える問題を解決しようとはしていません。それに、上演時間の1時間で解決できるような問題でもありません。
柏木 彼女たちは、自分自身の問題や、学校を続けられない友だち、大変そうにしている周囲の同級生をみて、「きつい」とは思っているけれど「だからこうなってほしい」とも思っていないようにみえます。だからこそ、彼女たちが抱えている問題は根深いのだと思うのです。彼女たちは運よく全国大会に進めたことで、この作品と1年以上向き合うことができたので、練習や上演を通して、「どうやらこの問題は私一人で受け止めなくてもいいっぽいぞ」とわかってきています。けれど、演劇のテーマにしていなかったら、誰かに助けを求めてもよいことに気がつかなかったでしょう。今は仕方ないからこの状況を受け入れているけれど、「嫌だ! と言ってよかったんだ」「しんどいと言っていいんだ」と演劇をつくりながら認識していった部分があります。
青柳 彼女たちが練習をしているときに、「私が何を言いたいかわかりますか?」と聞いてくることがあります。観ている人にどう捉えられるかが気になるみたいで。
柏木 自分たちがこの作品を発信することにどんな意味があるのかという問いに、彼女たちが一番意識的になっているのだと思います。自分たちがヤングケアラーであり、それに関する芝居をつくっているからこそ、社会の動きに関しても「これって私たちがいま演劇で取り組んでいることにかかわることですか?」と意識できるようになってきて……この作品を上演する責任を負えるようになってきたのかもしれません。
「部活」という居場所だからこそ、
自分をさらけ出せる生徒たち
──集団創作という方法は、ヤングケアラーの問題を発信するためだけではなく、教育においても意義のある方法に思えます。ほかの学校でも採用されているのですか。
青柳 本校のような方法で作品をつくる学校は少数です。高校生自身の問題意識をぶつけてくる作品には結構頻繁に出会うのですが、「自分たちをほぼ演じる」というのはあまりないように思えます。
柏木 恐らく皆さん、「演劇というものは他人を演じることだ」という固定観念をもっていると思うのです。
青柳 以前、ほかの大会で審査員が「自分たちのことを演劇にするとつらくなるよ」と話していたことがありました。確かに、演劇部員が役への思い入れが強くなりすぎて演じられなくなると困るので、大会という場面ではあえて集団創作という方法を選択しないという道もアリだと思います。
寺﨑一般的に、演劇とは舞台の上で偽りの自分(役)になりきることですよね。けれど、日常的に我慢をしていたり、素の自分を出せなかったりする彼女たちの姿を見ていると、逆に舞台の上だからこそ本当の自分を出せているようです。そう考えると、彼女たちにとって集団創作という方法は合っているのだと思います。演じることで自分のこれまでの選択を客観視し、何かに気がつくきっかけになると、さらによいのですが……。
──高校生たちが抱えている問題を、演劇部だからこそ見つけられることもあるのでしょうか。
柏木 よく部活は居場所だと言われますよね。生徒たちにとっての「居場所」ってなんだろうと考えたときに、自分らしく振舞える、好きなように表現ができる、誰かに甘えられる、自分の好きなことに没頭できる環境だと思います。本校の演劇部では、「舞台で作品として自分の状況を見せる」「登場人物の言葉に自分の心情をのせて発する」ことができます。演劇を通して自分自身を表に出し、自分を振り返り、気持ちを整理する機会になっていることが、少なくとも今の彼女たちにとってはベストな居場所になっているようです。
青柳 そうですね。部員たちが「授業を受けずに、ずっとここにいたい」と話しているのをよく耳にします。また、集団創作という、自分たちで考え、認め合ってつくっていく方法だからこそ、部員の自己肯定感が上がっているように思います。
柏木 本校に限らず、家庭や学級、それ以外にも居場所がないという生徒は学校生活を続けられませんよね。
青柳 誰もがそうです。やっぱり勉強とは別に、友達や部活など1つでも居場所がないと学校生活は続かないですね。生徒によってその場所は違いますが、勉強とは関係のない居場所が見つかれば3年間頑張れるという子は多くいます。「家庭が居場所ではない」という子はたくさんいますから、ほかのところに居場所を見つけるのが本当に大切ですね。コロナ禍でオンライン授業になっていたときは、居場所が家庭しかないため、「しんどい」と話している生徒はたくさんいました。
柏木 コロナ禍に東京で暮らす高校生は、特にそこが大変だったかもしれません。大人たちも、リモートワークがキツくなってきていましたよね。コロナ禍の家庭のトラブルも結構多いと聞きます。
青柳 親からすればずっと家に子どもがいるのが大変だし、子どもからすればずっと親がそばにいるのがしんどい。学校に来ているほうが楽しいことはありますからね。
柏木 もともと私は「学校は勉強するところ」というよりも、「社会性を身につけていくために必要な場所」と思っていたのですが、コロナ禍でそこがより強調されたと感じます。現場の先生方が日々苦心されているところ(生徒に社会性を身につけてもらう)と、社会的な学校のイメージ(勉強する場所)って相当なズレがあるんだなと改めて思いました。
青柳 もちろん学校の指導方針などによっても違いがあるので、一概にも言えないですけどね。
ヤングケアラーを題材にした劇を上演する意味
──全国大会で、本作を上演する意味をどう考えますか。
寺﨑 “2022年の東京で暮らす高校生”が、演劇を通して全国に向けて発信するということにどんな意味があるのかと、ずっと考えてはいました。作品と向き合う中で、実感を伴って意味を認識・意識できるようになったのは、全国高等学校演劇大会に出場するための2021年11月に行われた都大会で、上演中に社会とのズレを感じた瞬間でした。最初、何気ない会話をしている高校生たちの演技を見て、「馬鹿だな〜」と客席から笑いが起きたのですが、次第に笑い声が減っていきました。客席がだんだんピリピリした空気に変わったのです。上演後に客席にいた人に聞くと、「笑えなくなってきた」「そこは笑うところじゃないだろ、と思った」「笑っている人に腹が立った」と話していたのが印象的でした。
柏木 東京の公立校の高校生が、東京で行われる全国大会で発信することの意味を考えると、ほぼ今の話につながるのだと思います。ヤングケアラーや貧困の当事者として生きている高校生が実際にどれくらい日本にいるのか詳しい数字はわかりませんが、「笑えないよ、それ」と思う人が客席に複数人いるというぐらい東京の状況は逼迫しているのでしょう。本校が全国に発信していく意味は“今の高校生が抱える問題を伝える”ことです。案外、高校生のほうがリアルな状況がわかると思うのです。
青柳「笑えないよ、それ」と思う観客は、自分の話として捉えている場合だけでなく、友だちに同じような状況の子がいるとか、頭に浮かぶ人の顔があるはずですよね。別にこの作品の話は、ものすごく変わった高校生の話をしているわけではなく、ありふれたどこにでもいるような高校生の話をしていますからね。
柏木 これまで上演してきた際の客席の反応を観て、ヤングケアラーや貧困を抱えている高校生たちの話がよりリアルなものとして伝わるよう、準備はしてきたつもりです。
恐らく全国大会では各地域の人たちがそれぞれの課題やその地域から見えているものを劇の題材にして発信することでしょう。そのなかで、「7月29日午前9時集合」という作品は東京の高校生の今を伝えるものとして上演する意味があると思っています。
寺﨑 作品の中で、東京の地域性を表現できていますよね。
柏木世の中で起きているほとんどの社会問題は、多くの人に「この程度で問題視するの?」と考えられていることばかりだと思うのです。それくらいフワっとしていて、ヤングケアラーの問題も、多くの人が「そんなの大したことないじゃん!」と思うかもしれないけれど、生徒たちの将来が潰れていく可能性があります。周囲がなんてことない問題と捉えていたとしても、取り返しのつかない出来事に発展していくことだってあるのです。しかし、きっとほとんどの当事者はこの作品の登場人物のように、なんとかやり過ごしている状況です。だから、当事者はしんどいのですよね。当事者も周囲の人も問題解決をあきらめている状態、これこそ一番危険なのではないかということが伝わるといいですね。
この作品を観ても問題だと思わない人には、また違ったアプローチをしていく必要があります。
青柳 1年間この作品に向き合ってきて、より壮絶さを感じるようになったシーンもあるし、もはや救いようがなくなったと感じるシーンもあります。それは作品のなかだけに留まらず、実際に演劇部員だった生徒が学校を続けることができなくなり、辞めてしまったことが影響しています。観ていただければわかると思いますが、彼女たちの取り組みがすべて無駄になってしまったような感覚をもちます。この1年で、フィクションとしか思えないような状況にどんどん現実が変わっていっていることに、正直、自分も驚きながら作品と向き合ってきました。
柏木 もしかしたら、全国大会に進み1年間同じ作品に向き合うことができるというのは、問題に対して変わらない社会を実感する意味があるのかもしれませんね。語弊もありますが、この作品で伝えている大きな問題(ヤングケアラー)は1年経っても何も変わらなかった。誰も高校生たちを助けに来なかったし、何一つ社会が変わることのないまま1年が経ってしまった。今回の作品に「原案」として名前を残した前述の生徒は、この1年を乗り越えることができませんでした。作中でも彼女の行方について触れていますが、何も変わらない1年だったけれど、高校生の彼女たちにとってはあまりにも長すぎる時間でした。恐らく、そこまで細かくくみ取っていただける方はいらっしゃらないかと思いますが(笑)。
──2022年夏の全国高等学校演劇大会での上演前は、どのような気持ちでしたか?
寺﨑 以前、ヤングケアラーを支援されている栃木県那須塩原市の社会福祉協議会の方から話を聞きました。今、ヤングケアラー当事者である子どもと、これから当事者になり得る子どもでは、支援の視点がまったく異なるそうです。特に前者は、今までの生活や行動が当たり前になっていて、時間を費やしてきたからこそ誇りにもなっているため、大人が介入しすぎると、自尊心を傷つけたり、これまでの人生を否定したりすることにもつながるとのことでした。その子自身が助けを求めたときが介入のタイミングであり、大人はそのときのために最大限の準備をしておけばよいという意見をいただきました。
部員たちを見ていても、必ずしも全員が自分の状況を苦痛だとは思っていないようです。良くもあれば悪くもあるのですが……。どちらにせよ、いつか必ず、自分の人生を客観視できる瞬間が訪れるでしょう。そのときに彼女たちを支えられる社会を整えておくのが大人の責務です。そのためにも、この作品を通して「高校生が過ごす日常」を届けられたら嬉しく思います。そして、自分のことを誰かに一所懸命伝えようとした経験が、彼女たちの人生の糧になってくれるとよいですね。
柏木 演劇は1回の公演で、多くても1,000人ほどにしか届けることができません。そのため、マスに対して作品を届けることにはあまり意味がないと思っています。演劇の作品をつくることの本当の意味は「つくっていくことで何を得られるか」「インパクトが社会にどれほど広がるか」だと思うのです。観た人が新たに作品や社会をつくっていく、ということに大きな意味があると考えます。本作を観た人が、高校生の会話から何に気がつくのか、もしくは気がつかないのかとても楽しみな部分でもあります。
また、舞台に立つ高校3年生の部員たちは、コロナの影響で中学校の卒業式、高校の入学式が行われず、学校行事もほぼないまま3年間過ごしてきました。だからこそ、全国大会の舞台に立てる、それだけで十分素晴らしいことだと思っています。コロナだけでなく、彼女たち自身が背負っている問題により、必ず舞台に立てる保証はありません。とにかく無事に舞台に立ち、ただ戻ってきてくれるだけでいい、そう考えていました。
青柳 2021〜2022年と奇跡のような1年間を過ごしてきたと思っています。彼女たちは決して演劇の技術が高いわけではなく、何か特別な才能や知識があるわけでもありません。舞台から降りて、教室の中で見ればどこにでもいるような普通の高校生です。そんな彼女たちが演劇の全国大会まで進んだわけですから、演劇のおもしろさを感じています。集団創作の手法で、彼女たちと作品をつくることを選んでよかったと思っています。彼女たちと1年間を通して「7月29日午前9時集合」という作品に向き合うことができて本当に幸せでした。この作品をつくり始めて1年が経った今(収録時)でも、稽古場は毎日が新鮮で、飽きることもなく笑ってしまう場面ばかりです。あと少しで終わってしまう寂しさもありましたが、柏木さんの言うように、無事に上演できることを祈っていました。
関連書籍