


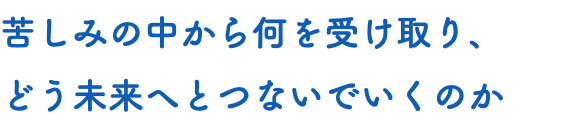
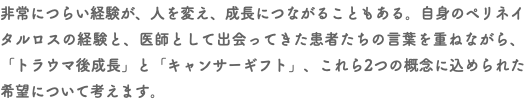
私自身のPTGを振り返って
ペリネイタルロスを経験した私自身にも、PTGを実感する学びや変化がありました。
- 体の健康だけでなく、メンタルヘルスの大切さを意識するようになった。
- 人生において新たな優先順位を見出した。
- どんなに努力しても思いどおりにならないことがある事実を受け止められるようになった。
- 病院で提供されるサポートには限界があることに気づけた。
- 自分のつらい経験を通じて人のために役立てることがあれば、積極的に取り組みたいと思うようになった。
私はたまたま最初の流産を経験する少し前にブログを始めていたこともあり、その後の流産や子宮外妊娠の体験をリアルタイムで書き綴っていました。そして、そうした発信をきっかけに、同じ経験をされた方へのピアサポートを行うようになり、その後、取材や執筆の依頼をいただくことも出てきました。
振り返ると、こうした活動を重ねる中で、自然に「自己開示」や自問自答を繰り返してきました。その積み重ねこそが、自分の中でPTGがしっかりと育まれた理由なのだと考えます。
「キャンサーギフト」とは
キャンサーギフトとは、がんという病気を経験した後に、患者さんが人生において予期せぬ肯定的な側面や恩恵を見出すことを指します3)。
がん経験者が語る「ギフト」とは、具体的には次のようなものです。
- 人生への感謝の深化:日常のささやかな出来事に、より強い感謝を抱くようになる。
- 人間関係の再構築・深化:サバイバー仲間との出会いや、家族・職場の支えを通して、人とのつながりの大切さを再確認する。
- 価値観や目標の再設定:病気を通じて、自分の人生の優先順位や目標が明確になる。
- 個人的な強さや回復力の実感:治療を1つずつクリアする過程で、自分の内なる力を再認識する。
- 新たな使命感や生きがいの発見:経験を通じて、これからの生き方や役割に新しい意味を見出す。
- 精神性や共感力の高まり:精神的な深まりや、他者への共感が強くなる。
お気づきのように、PTGの5つの因子とよく重なります。そのため、キャンサーギフトは「がん」という特定のトラウマ体験を契機としたPTGの一形態、あるいはがん患者のコミュニティーで独自に表現されたPTGの姿と考えることができます。研究でも、がんを含む生命を脅かす病気や慢性疾患を持つ患者がPTGを経験することが確認されています。
私はまだがんを経験していませんが、ペリネイタルロスの経験を通じて「苦しみの中に小さな贈り物を見出す感覚」を味わったとき、キャンサーギフトという言葉を理解できるようになりました。
PTGとキャンサーギフト──その相違点
両者はいずれも「苦しみや困難を経て得られる内的変化や成長」を語る概念ですが、その成り立ちや含意には大きな違いがあります。
特にPTGは、「成長」と「苦痛」の共存を前提とする点が特徴的です。成長があったからと言って苦痛が消えるわけではなく、両者は同時に存在しえます。
つまりPTGは、「苦しみを否定すること」や「前向きであることの強制」ではありません。むしろ、痛みを認めながら、その中で新しい意味や強さを見出す人間の複雑な適応過程を描いているのです。
PTGとキャンサーギフトの比較
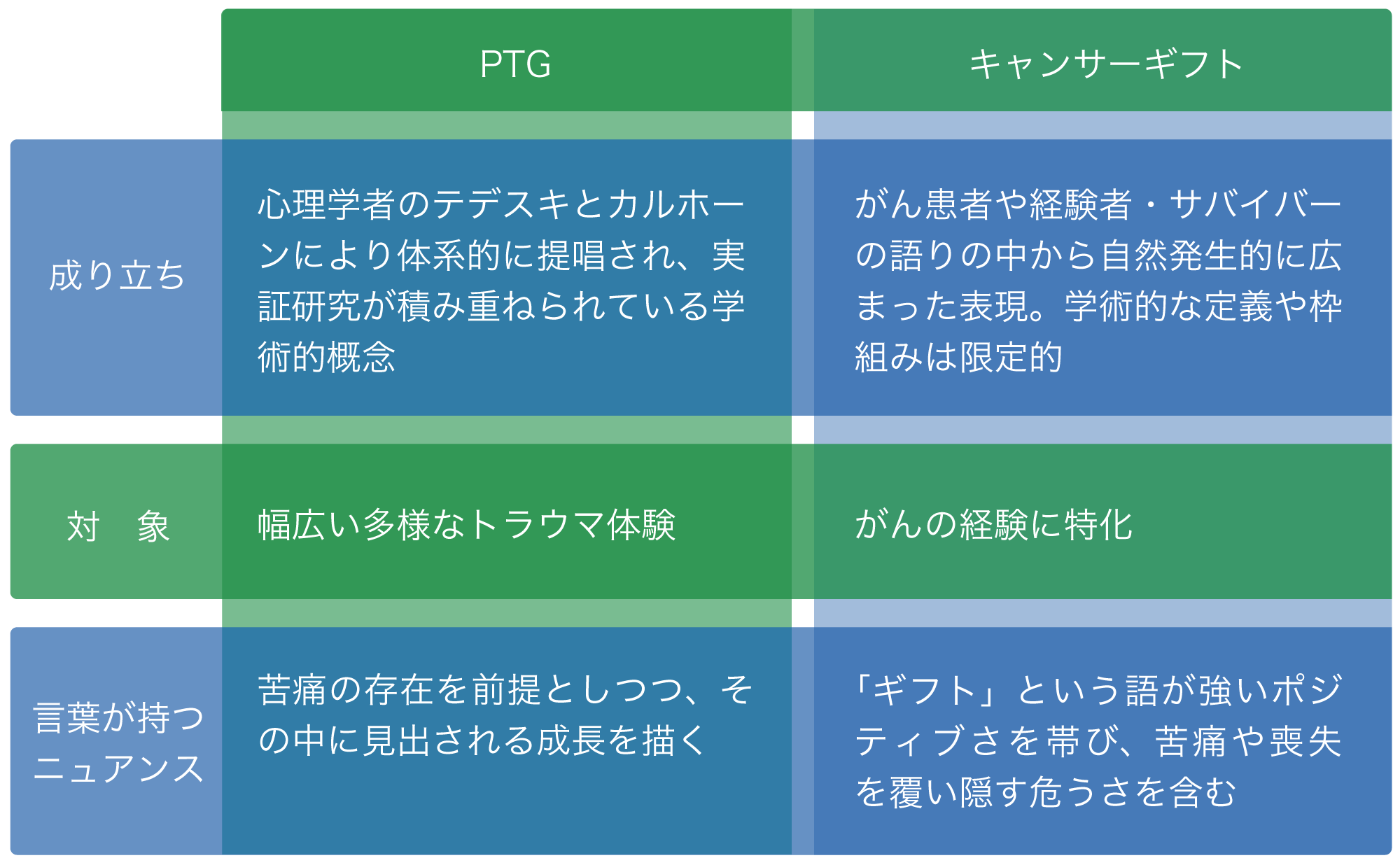
「キャンサーギフト」への批判的視点
「キャンサーギフト」という言葉は、がん経験を希望の象徴として語る際に用いられる一方で、強い違和感や反発を招くこともあります3)。その理由は、がんによる苦痛や喪失を過小評価し、患者の感情を無効化してしまう危険性があるからです。さらに、「ギフト」(贈り物)という言葉自体が強いポジティブな響きを持ち、苦しみを美化してしまう危うさを含んでいます。
がんは、身体機能や生殖能力の喪失、経済的困難、キャリアの中断など、多くの「失う経験」を伴います。そうした現実を「ギフト」と呼ぶことは、一部の患者に「自分の感じ方が間違っているのではないか」と思わせてしまう可能性があります。
この背景には、がんのステージや治療経過による状況の差もあるでしょう。たとえば、早期がんで治療が落ち着き、再発の不安が比較的少ない場合、「ギフト」として語ることのできる人もいるかもしれません。しかし、進行がんで長期の闘病が続く人や、もう治療法がないと診断された人などにとっては、「ギフト」と呼ぶことはきわめて困難なことと思われます。
さらに、社会全体に根付く「前向きであるべき」という風潮が影響し、患者が「ポジティブでいなければ」と感じやすくなります。その結果、苦痛や悲しみを表出しにくくなり、「ギフトを見出せない自分は不十分だ」と自己否定に陥る危険もあります。こうした構造が、患者を孤立させ、必要な支援から遠ざけてしまうのです。
「キャンサーロスト」という補完的視点
こうした批判等を踏まえ、自身もがん経験者である花木裕介氏4)により、「キャンサーロスト」(cancerlost)という概念が提唱されています。がんによる目標や機能、キャリア、人間関係などの喪失を表しますが、花木氏が設立した一般社団法人がんチャレンジャーが実施したアンケートでも、多くのがん経験者がこうした喪失体験を抱え、周囲の反応に苦しめられたと答えています5)。
ただし、「キャンサーロスト」は「ギフト」を否定するものではなく、がん経験にはプラスとマイナスの両面があることを示す言葉です。喪失を認めることは回復や適応の第一歩であり、患者が自分の体験を包括的に受け入れるために大切な視点だと言えます。
逆境からの成長を語るときの注意点
PTGやキャンサーギフトといった言葉は、あくまでも「本人が自発的に感じるもの」であり、他者が押し付けるものではありません。
渦中にいる人に対して、
「この経験にも意味がある」
「人には、乗り越えられない試練は与えられない」
などと声を掛けることは、かえって孤独感や憤りを深める場合があります。「成長」を感じる「タイミング」や「度合い」も人それぞれであり、時間が経ってもそう感じられない人もいます。
そもそも、「必ず成長しなければならない」という前提自体が不必要だということを、私たちは肝に銘じておきましょう。
私自身も含め、医療者等の支援する立場にある人が大切にすべきなのは、次のようなことだと考えます。
- 苦痛や喪失を否定しないこと
- 「成長」の有無にかかわらず、その人の物語を尊重すること
- その時々の段階を見守り、寄り添い続ける姿勢
私自身、「つらい経験を乗り越えたね」と言われることに、かつては強い違和感をおぼえていました。「私は乗り越えたわけじゃない。ただ、受け入れただけ」と、心の中で反発していた時期もあります。それでも、年月を経た今は、「乗り越えた」という表現にも、かつてほどの違和感はありません。
このように、言葉の選び方1つで、相手の心の受け止め方は大きく変わります。そして、その感じ方は、時間の経過とともに少しずつ変化していくこともある──そのことを、知っておいていただければ、と思います。
*
PTGやキャンサーギフトは、苦しみの中から芽生える「気づき」や「変化」を表す言葉です。しかしそれは一人一人異なる体験であり、決して万人に共通するものではありません。大切なのは、本人がどう感じ、その経験にどう意味を見出すかです。周囲は、その心のプロセスを静かに支え、言葉にならない思いさえも尊重していくことが求められます。
「成長」という明るい側面に目を向けながらも、そこに至るまでの痛みや喪失を見落とさず、両方を抱き締める姿勢こそが、医療者をはじめ、支援する側には求められているのではないでしょうか。
●●参考
- Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G.(1996):The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma. J. Trauma Stress, 9(3):455-471.
- Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G.(eds.)(2014):Handbook of Posttraumatic Growth: Research and Practice,Routledge.
- Briggs, B.(2016): The gift of cancer? Perspectives vary widely. Fred Hutchinson Cancer Center.(https://www.fredhutch.org/en/news/center-news/2016/01/cancer-as-gift-perspectives-vary-widely.html)
- 花木裕介(2023):キャンサーロスト: 「がん罹患後」をどう生きるか(小学館新書 456), 小学館.
- 一般社団法人がんチャレンジャー:「サバイバートラック」に関するアンケート(がん罹患経験者対象).(https://www.gan-challenger.org/research/)
サトコ・フォックス|2008年、川崎医科大学卒業。聖マリアンナ医科大学病院および附属ブレスト&イメージングセンター勤務を経て、2018年にスタンフォード大学放射線科乳腺画像部門に研究留学。結婚・出産を機にアメリカに移住。乳腺の画像診断の仕事は続けながら、オンラインで助産師が乳がんについて勉強できる「ピンクリボン助産師アカデミー」を主宰。2024年1月〜2025年8月、医学書院『助産雑誌』にて「「助産師の疑問に答える!実践的おっぱい講座──多角的な「胸」の知識」連載。乳がんに関するオンライン医療相談や、ペリネイタルロス経験者へのピアサポート活動も行っている。医学博士、日本医学放射線学会放射線診断専門医・指導医、日本乳癌学会乳腺認定医。2022年、不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修医療従事者プログラム受講修了



