






text by : Satoko Fox
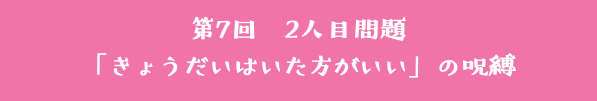
2人目以降の子どもを持てない理由はさまざま
2人目以降の子どもを希望しているにもかかわらず実現しない理由には、不妊・不育といった身体的な事情だけでなく、次のような社会的な要因も大きく影響しています。
- 経済的な負担:子どもを2人以上育てるのが難しい。
- 家事・育児の負担:夫(主に)の協力が得られない。
- 夫婦間の意見の相違:夫もしくは妻が2人目以降の子どもを望んでいない。
- 仕事との両立の困難:家庭と仕事のバランスがとれず、限界を感じる。
- 健康上の問題:自分や家族が病気になった。
- 体力的な限界:年齢や体力の問題で難しい。
- 家庭環境の変化:離婚などで環境が変わった。
こうした理由が絡み合い、2人目以降を持つことが難しい家庭が非常に多いのです。だからこそ、「次の子はいつ?」「1人っ子はかわいそう」といった言葉は、相手にとって大きな負担となる可能性が高いと考えます。
とは言っても、私自身も過去には無神経に友人にそうした言葉をかけたことがあります。そのころの自分を振り返り、とても反省しています。
私の葛藤──「レインボーベビー」には会えず、
「諦める」という選択
喪失後に誕生した子どものことを、雨後の空にかかる虹になぞらえ、希望の象徴として「レインボーベビー」と呼びます。私も「レインボーベビー」に会えることを望んで妊活を再開したものの、なかなか妊娠には至らず、不妊治療を始める決意をしました。
ところが、その矢先に夫から「もうこれ以上子どもは望まない」と言われたのです。その言葉は私にとって大きなショックでした。
しかし、ペリネイタルロスで心身ともに落ち込んでいた私を1年間支えてくれて、夫も疲れてしまったのかもしれません。私より5歳年上ということもあり、いろいろと限界を感じていたのでしょう。
私は大きな岐路に立たされました。
「ここで諦(あきら)めるべきなのか」「夫を説得すべきなのか」「それとも、夫の気持ちを無視してでも進めるべきなのか」と自問自答しました。
そんなとき、不妊治療を経験し、最終的に子どもを授かることのできなかった友人がかけてくれた言葉に救われました。
「諦めるって、実はポジティブなことなんだよ」
「諦める」の語源は仏教用語で、「明らかにする」「つまびらかにする」が本来の意味なのだそうです。さらに、「諦」はサンスクリット語の「真理」「道理」を訳したもの。つまり、「物事の道理を明らかにすることによって、自分の願望が達成されない理由がわかり、納得して断念することができる」と解釈できるのだと4, 5)。
これまで、〈諦めること=ネガティブ〉と信じてきた私にとって、その言葉は目から鱗でした。結果がどうであれ、前に進むための選択肢として「諦める」ことを受け入れる。その考え方が、少しずつ心を軽くしてくれたのです。
ステップファミリーとしての絆と体力の限界
「諦める」に至った理由はほかにもあります。
私の夫はバツイチで、前の奥さんとの間に2人の子ども(私にとってはステップキッズ)がいます。アメリカでは離婚後も共同親権が一般的で、両親がともに子どもと関わる形がとられます。
わが家の場合、子どもたちは、平日はお母さんの家から学校に通い、週末になると私たちの家に来る、というスケジュールです。このような形態は日本ではあまり見られないため、私も最初は戸惑いましたし、子どもたちも環境に慣れるまで大変だったと思います。
ステップキッズと私には血のつながりはありませんが、もう6年間以上、ほぼ毎週末を一緒に過ごしてきたことで、しっかりとした絆があります。一番上が男の子で、3歳離れて女の子、その下に6歳離れて私の娘がいます。年が離れているのですが、子どもたちが成長するにつれて、娘と一緒に遊んだり、面倒を見たりしてくれる機会が増えました。けんかもよくしますが、自然と仲直りしている様子はほほえましく、きょうだいならではの絆を感じさせます。
娘にとっては、「お兄ちゃん、お姉ちゃん、私」という環境で、「1人っ子」という感覚がないのです。何度か娘にも「弟や妹が欲しい?」と聞いてみましたが、「別にいらない」と言われ、こだわっているのは自分だけだと気づきました。
そんな中、私自身も体力の衰えを感じるようになり、41歳で妊活を終了する決断をし、今では納得して過ごしています。
カミングアウトの力
私はこれまで、流産などの経験や家庭内の事情をオープンに話してきました。その結果、「あなたにだから言うね」と、友人から胸の内を打ち明けられることが増えました。
自分の経験を共有することで、相手も自分の気持ちを話しやすくなる。そしてそれが、孤独や心の重荷を少しでも軽くするきっかけになるのだと感じています。
もし妊活や不妊治療を続けるべきかで悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひ私のお話会「レインボーベビーには会えなかったけど」のアーカイブ6)をご覧ください。何かのヒントになることを願っています。
●●参考
1)Satoko Fox:Pregnancy Lossと向き合って~流産・子宮外妊娠~.
3)株式会社ネクストレベル(2021):「本当はもっと子供が欲しいのに…」6割以上が希望人数を持てない! その理由と解決策とは?
サトコ・フォックス|2008年、川崎医科大学卒業。聖マリアンナ医科大学病院および附属ブレスト&イメージングセンター勤務を経て、2018年にスタンフォード大学放射線科乳腺画像部門に研究留学。結婚・出産を機にアメリカに移住。乳腺の画像診断の仕事は続けながら、オンラインで助産師が乳がんについて勉強できる「ピンクリボン助産師アカデミー」を主宰。医学書院『助産雑誌』にて「「助産師の疑問に答える!実践的おっぱい講座──多角的な「胸」の知識」連載中。乳がんに関する情報発信のほか、ペリネイタルロス経験者へのピアサポート活動も行っている。医学博士、日本医学放射線学会放射線診断専門医/指導医、日本乳癌学会乳腺認定医。2022年、不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修医療従事者プログラム受講修了


