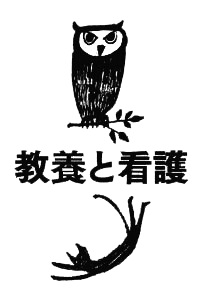本連載は月刊「看護」2025年6月号からスタートした同名連載の再掲です。
>> この連載について
第1回
被災地の現実と被災者支援の変革
酒井 明子
2025.6.5
能登半島の被災状況
まず、能登半島の被災状況を振り返りましょう。2024年1月1日16時10分、石川県能登地方をマグニチュード7.6(暫定値)の地震が襲いました。この地震により多数の家屋倒壊が発生し、死者・行方不明者551名(うち災害関連死321名)の被害をもたらしました1)。死因の約4割が「圧死」、次いで、約2割が「窒息・呼吸不全」、1割強が「低体温症・凍死」でした。そして、死者は、70代以上が約6割を占めました1)。
多くの道路で通行止め等が発生した能登半島では、33地区最大3,345人(2024年1月8日時点)が孤立状態に陥りました1)。また、能登6市町において、発災前と比較して最大約7割のエリアで通信が断絶しました。最も深刻な問題は、上下水道が大きな被害を受け、長期にわたって断水が継続し、避難生活が長期化したことです。
そして、地震からの復旧・復興が進む中、2024年9月21日から22日にかけて、追い打ちをかけるように記録的な大雨が発生し、家屋の倒壊や、仮設住宅を含む家屋の床上・床下浸水の被害が発生しました。医療施設や高齢者関係施設についても、倒壊の危険・停電・断水が発生しました。
全国から医療・福祉に携わる職員が被災地に派遣され、医療機関・社会福祉施設への物資搬送なども行われました。被災地内での避難生活により健康状態が悪化する恐れのある高齢者など要配慮者には、広域避難、1.5次避難、2次避難が行われ、命と暮らしを守る支援が展開されました。
被災地で見た現実と被災者支援の実際
1. 被災地で見た現実
災害発生直後を振り返ると、あらためて被災者が漏らした苦しみの声が思い出されます。「震災が発生し、自宅から飛び出した直後、目の前で自宅が崩れ落ち、周辺が砂煙で真っ白になった」「家屋の隙間から人の足だけが見えていて、助けようと引っ張ってもびくともしなかった」「液状化現象で、首まで砂で埋まってしまい、これで自分も死ぬのかと覚悟を決めた」など、生きるか死ぬかという体験の語りです。
道路には至るところに亀裂が走り、主要な道路が寸断され、見渡す限り倒壊した家並みに阻まれ、避難の足も支援の手も止まりがちとなる中、それでも消防団や近隣の住民が協力して被災者を救出し、避難所運営などに奔走しました。
そして、地震が発生から1年以上が経過しているにもかかわらず、数多くの困難が山積した状態と言わざるを得ないのが、今の被災地の現実です。未だに停電・断水が続いている地区や、解消されない避難所があります。さらに、「応急仮設住宅に入れない」「家族を失って深い悲しみに沈んでいる」「職を失い経済的に困窮状態にある」「住まいの再建に悩みを抱えている」「長期避難区域のため故郷に帰りたくても帰れない」など、さまざまな境遇の人たちがいます。そして、今でも災害関連死者数は増え続けているのです。
これまでの災害では体験したことのない現実が、今回の震災発生から現在までずっと被災者の生活に襲いかかっています。では、これほどまでに人間の命と尊厳が危ぶまれる現状に対し、看護はどのように動いてきたのでしょうか。
2. 看護の本質が浮かび上がった被災者支援
「能登の灯」の看護部長たちによる意見交換の場では、人間の尊厳を保持し、命と暮らしを支え、より健康であることを願い、行動した看護の姿が浮かび上がりました。
ある病院では、停電断水状態のためライフラインは途絶し、通信は遮断され、エレベーターは作動せず、手術や透析、検査もできない状態となり、透析患者などの他院への搬送が行われました。道路陥没やヘリ搬送困難などにより、搬送時間が遅れてしまっても、受け入れ先の病院の看護師たちは送り出す側の状況を理解し、到着時間が遅れても温かい言葉で励ましました。さらに搬送による衰弱が見られた高齢者は次の搬送にストップをかけ、ヘリの音を戦争と錯覚し混乱する高齢者のこれまでの人生を思い、安心できるように寄り添い続けたとのことです。
あるスタッフは、断水状態の下で節水と効率的な水の利用を考えながらも、口腔ケアと陰部ケアを丁寧に実施し、何とか平常時の看護を実践し続けようと尽力。患者のために水をなんとか確保するため、自ら重い水を施設に運び入れていました。また、孤立した地元の避難所では不眠不休の活動も行われました。
看護管理者は、情報が錯綜する中、被災専用病棟を稼働させ、入院患者の推移を確認しつつ、転院搬送調整をしたり全国に応援要請を出したりするなど、勇気を持って主体的に判断し行動していました。さらに、災害復興の段階から今後の災害を見すえ、物品を各病棟に分散配置したり、災害時のシミュレーションを行ったりと、災害対策に努めています。
これらの看護の活動は、人間の命と尊厳を保持するために、専門職としての覚悟を固め、社会に向けての責任を果たしたものと言えます。また同時に、病院・地域・社会全体の動きを見すえたマネジメント力や「人間としての力」を発揮したことを示しています。
このように悪戦苦闘した病院看護職や避難所で必死に命を守った看護職の姿、被災地からの重症者を受け入れてくださった県外の施設関係者の姿勢などは、必ずしも報道で大きく取り上げられはしませんでしたが、そこから学べることは多いのです。「能登の灯」で語られた多くの支援者の実践と声を、連載を通して共有することで、能登半島地震における被災者支援とは何か、災害時の看護とは何かに関する議論がさらに深まると思います。