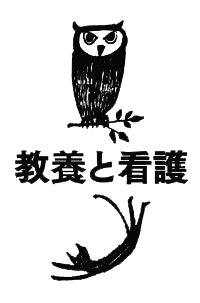第3回
災害支援ナースの体制整備
日本看護協会 常任理事 松本 珠実
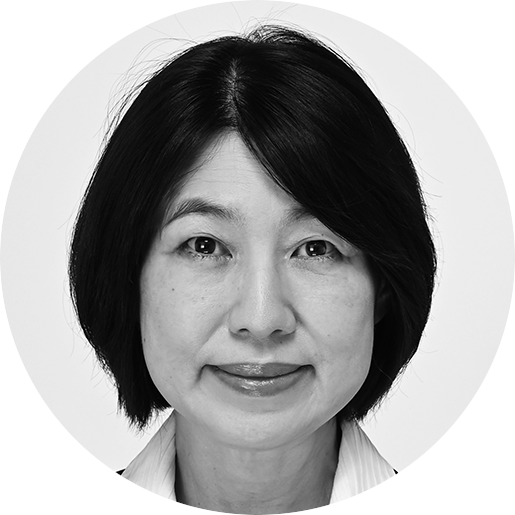
2025.9.1
令和6年能登半島地震においては、被災地における指揮・命令系統の混乱がありました。例えば、活動場所である避難所へ向かったものの、避難所では災害支援ナースが来ることを知らされておらず、再調整が必要となったケースなどです。
これについては、「災害支援ナース活動要領」において、被災都道府県の保健医療福祉調整本部が設置された際には、都道府県看護協会が参加することが原則として明記されました。
また、令和6年能登半島地震発災時に、石川県保健医療福祉調整本部では、県庁の看護職や石川県看護協会、本会が他チームの看護職と連携しながら、被災地の看護ニーズの把握を行い、災害支援ナースの要請や活動内容の調整を行っていました。本部内で、チーム横断的に看護にかかわる情報共有・調整をはかるために、このような機能が不可欠であると思います。
2025年3月31日付けで都道府県知事あて厚生労働省関係局長通知「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について」が発出され、都道府県保健医療福祉調整本部は災害支援ナースとの連絡および情報連携を行うための窓口を設置することが明記されました。加えて、2025年度より、都道府県職員と連携して災害支援ナース等の看護職員の派遣調整を担う看護師等を「災害医療コーディネーター(仮称)」として養成するよう厚生労働省の研修事業が拡大されました。
情報連携や情報の迅速化についても課題がありましたが、2025年4月から災害支援ナースの活動にEMISが使用できる改正がなされています。
本会では、令和6年能登半島地震の経験を踏まえ、2024年9月に内閣府特命担当大臣(防災)と内閣府副大臣、および厚生労働省医政局長にあて「都道府県における災害支援ナースの体制整備に関する要望書」を提出しました。①支援者が安全に活動するための移動手段や宿泊の確保等の平時からの環境整備、②都道府県における災害支援ナースの派遣・活動体制の整備、③保健医療福祉調整本部における看護職の派遣をコーディネートする人材の育成・配置などです。
①については、2025年2月に災害対策基本法の一部改正案として、被災者の援護に従事する者が災害が発生した地域において円滑かつ効率的に活動を行うことができる環境の整備に関する事項が国および地方公共団体の努力義務として盛り込まれ、②と③については、先に述べたように、すでに制度として実現されています。
本会として残された課題としては、まず、災害支援ナース派遣の円滑化があります。2024年度からの災害支援ナースの派遣については、都道府県が協定を締結した医療機関等に所属していることが前提となりました★2。したがって、多くの医療機関等が都道府県と協定を締結する必要があります。また、都道府県に派遣の主体があることから、都道府県が都道府県協会に派遣調整等の業務を委託する、あるいは協定を結ぶなどにより役割を明確化しなければ、県協会がこれまで培ってきた災害支援ナースの派遣調整のノウハウが生かせなくなります。
これらの課題は、都道府県が主として検討する事項となるため、本会からの直接的な働きかけは難しいのが実情です。そこで本会では、都道府県と都道府県看護協会の担当者を対象とした合同会議の開催や、病院団体等との派遣調整会議の開催、学会等での好事例の発表などに取り組んでいます。
その他、EMISの実装の効果を検証して必要な対策を講じること、感染症発生・まん延時の派遣調整にかかる具体化、更新研修のあり方の検討などが課題となりますが、これからも来るべき災害や感染症発生時に災害支援ナースが円滑に派遣できるよう着実に取り組みを進めてまいります。
★2 病院または診療所以外で勤務する看護職や潜在看護職も都道府県の調整により派遣することが可能