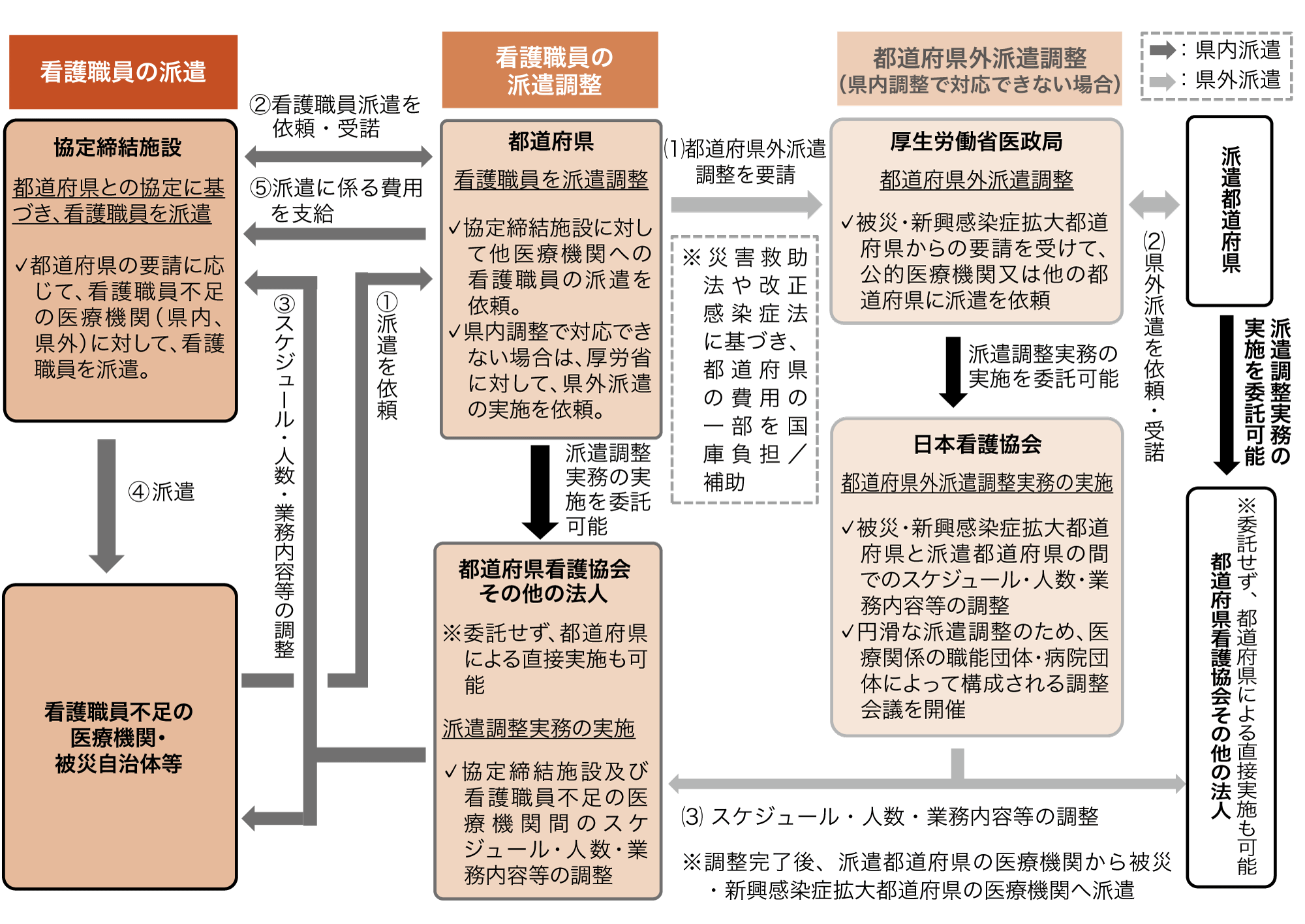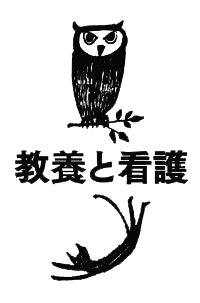本連載は月刊「看護」2025年6月号からスタートした同名連載の再掲です。
第3回
災害支援ナースの体制整備
日本看護協会 常任理事 松本 珠実
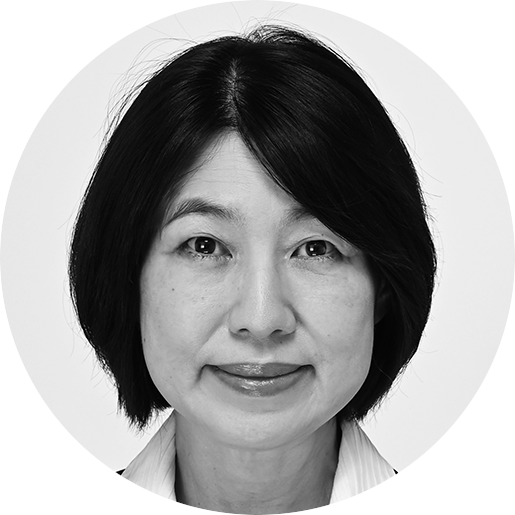
2025.9.1
まつもと・たまみ
1987年4月大阪市に保健師として入庁、1993年4月大阪市立厚生女学院(のち保健専門学校)専任教員、2015年4月国立保健医療科学院生涯健康研究部上席主任研究官、2023年4月大阪市健康局保健指導担当部長、2024年6月より現職。
★1 病院または診療所以外で勤務する看護職や潜在看護職も都道府県の調整により派遣することが可能
災害支援ナースは、1995年に起きた阪神・淡路大震災を契機として誕生しました。その役割は、看護職能団体の一員として、被災した看護職の心身の負担を軽減し支えること、被災地で適切な医療・看護を提供することにあり、2023年度までは、都道府県看護協会(以下:県協会)に登録され、日本看護協会(以下:本会)と県協会が協力しながら派遣調整を行ってきました。
令和6年能登半島地震においては、1月5日から石川県看護協会の調整の下で災害支援ナースの県内派遣が開始され、本会の調整による県外派遣は、1月6日から2月29日まで行われました。その後、2024年4月1日に改正医療法等が施行され、災害支援ナースは法令等に規定され、厚生労働省が主体となって養成・登録・派遣する仕組みとなりました。
本稿では、災害支援ナースの体制にかかる変更点、令和6年能登半島地震での派遣を踏まえた体制整備のあり方と、今後の課題について述べます。
2022年度までの災害支援ナースの養成については、まず、Part1「災害支援ナースの第一歩 ~災害看護の基本的知識~」で、看護専門職の災害時支援者として必要な災害医療と看護の基礎知識を習得すること、および災害支援ナースの役割と活動の実際を理解することを目的として、本会で作成した2日間計12時間のDVD研修を受講してもらっていました。加えて、Part2「各県協会災害支援ナース養成研修」では、看護専門職の災害時支援者として、被災地や被災者に対して有効に機能すること、および災害支援ナースとして他者と協働でき、自律した活動ができることを目的として、1日間6時間の集合研修を受講してもらうことで災害支援ナース研修を修了したものとしていました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、2024年4月に施行された改正医療法において、医療機関に勤務する災害支援ナースは「災害・感染症医療業務従事者」として厚生労働省医政局に登録され、大規模自然災害発生時に加え、新興感染症の発生・まん延時にも派遣されることとなりました★1。
そのため、2023年度からは、災害・感染症等に関する基礎知識および技術を習得すること、および派遣の概要を理解し、実際の派遣時に対応できる技能を習得することを目的に、新たな災害支援ナースの養成が行われ、2025年3月31日現在、研修修了者は8,408名となっています。
研修方法は、各県協会で受講申し込みを受け付け、本会で作成したオンデマンド研修(総論120分、災害各論540分、感染症各論540分)
と、各都道府県の活動体制などを踏まえた集合研修(講義60分、災害演習270分、感染症演習270分)の受講です。演習では、想定される被災状況を基に作成したシミュレーションなどが活用されるよう、本会において企画・指導者研修も実施しています。
災害支援ナースの登録とリスト管理は厚生労働省医政局が行うこととなっており、本会では2024年度よりその業務を受託しています。都道府県看護協会に、研修を受講した人からの、都道府県行政への情報提供と「災害・感染症医療業務従事者」および災害支援ナースの登録(EMIS[広域災害救急医療情報システム]への登録を含む)に関する同意を得た後、研修修了者の名簿を県協会から本会に提出してもらって登録となります。
令和6年能登半島地震は、いわゆる旧の仕組みでの災害支援ナースの派遣調整が行われました。旧の仕組みでは、災害支援ナースの派遣体制をレベル1~3に分類し、レベル1は被災県協会のみで災害時の看護支援活動が可能な場合、レベル2は被災都道府県内のみでは災害時の看護支援活動が困難または不十分であり、近隣の県協会からの支援が必要な場合、レベル3は被災県協会および近隣県協会のみでは災害時の看護支援活動が困難または不十分であり、当該活動が長期化すると見込まれる場合と定めていました。
実際のレベル2・3の本会による派遣調整は、1月3日に石川県から災害支援ナースの県外派遣の要請があり、1月4日に本会から富山県・福井県・新潟県の看護協会に災害支援ナースの派遣を打診し、その後、徐々に範囲を広げ、計27都府県から延べ2,982人の災害支援ナースを派遣するというものでした。災害支援ナースは、寒冷、交通経路の遮断や断水など過酷な状況の中、被災地に派遣され、医療機関5カ所、避難所15カ所、1.5次避難所2カ所において、避難者に寄り添い、被災地の看護職員や関係者と連携・協働をはかりながら看護活動を展開しました。
派遣を要請された各県協会では、本会からの情報等を基に派遣を協議・決定し、県内で派遣要請を行い、候補者の中から調整をした上で、派遣場所や派遣期間を決定して通知する一連の派遣調整業務を担いました。また、派遣元の県協会では、派遣が決定した災害支援ナースに対する事前説明会の実施、支援活動中の後方支援、活動終了後の本人の健康状態の確認、最新の現地ニーズについて次の派遣者へ伝達するなど、きめ細やかな調整が行われていました。
2024年4月以降は、被災都道府県の派遣要請に基づく派遣となり、レベル分類の考え方ではなく、県内派遣か県外派遣かの2択となりました(図表1)。県内派遣は被災都道府県において行われ、県外派遣は被災都道府県からの要請に基づき、厚生労働省を通じた派遣調整が行われます。本会は2024年度以降、厚生労働省からの委託を受け、厚生労働省に代わって災害支援ナースの県外派遣を調整することとなりました。一方、都道府県看護協会は都道府県から派遣調整を委託されているか否か等によって、業務が異なることになります。
災害支援ナースの養成
登録の方法
派遣調整