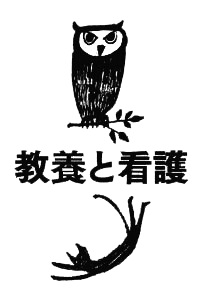本連載は月刊「看護」2025年6月号からスタートした同名連載の再掲です。
第2回
震災時に看護はどう動いたか
「能登の灯」の会からの報告

中村 真寿美
金沢医科大学病院
病院企画室部長
前副院長兼看護部長

澤味 小百合
公立能登総合病院
副院長兼看護部長

中西 容子
金沢市立病院
教育研究開発センターセンター長
前看護部長
2025.7.31
想定外の連続に立ち向かった看護活動── 中村真寿美
令和6年能登半島地震から1年以上が経過しましたが、能登はようやく復旧・復興が始まったばかりです。この震災は、地域医療体制の脆弱さを浮き彫りにしました。当時、筆者を含め、災害対応に奔走した医療機関の看護部長は、それぞれの知見と経験を生かし、困難に立ち向かいました。しかし、災害は一つの医療機関だけではなく、地域全体の問題です。被災地を含むすべての医療機関の間で情報共有・病床調整・看護職員の人員調整をする仕組みがないために、苦慮する経験が多々ありました。
2024年12月、「看護部長としての被災経験を共有しよう」との声が上がり、能登で支援活動に尽力されている酒井明子氏とともに有志10名(石川県内の医療機関の看護部長・元看護部長)で、「能登の灯」の会を立ち上げました。今回執筆した3名もそのメンバーです。本会では、今回の地震における医療・看護の検証を行い、得られた知見を発信し続けることが災害大国日本における被災地の使命と考えています。
「災害は必ず起こるもの」その認識は間違いではなかった
金沢医科大学病院(以下:当院)は、能登半島の入り口に位置する病床数817床、39診療科の特定機能病院です。能登半島周辺では数年前から地震が頻発しており、当院でも「災害は必ず起こるもの」との認識の下、大規模災害訓練や災害看護研修に積極的に取り組んできました。しかし、今回の震災は、われわれの想像をはるかに超える規模でした。初動こそ訓練通りだったものの、「最も能登に近い大学病院」として発災直後の2週間で約200名、3カ月間で600名以上、県内で最多の入院患者を受け入れ、さまざまな想定外に直面しました。
刻々と変化する状況の中、とりわけ、予想を超える入院対応と人的リソースの確保に難渋。元日の出来事でもあり、病院全体が帰省中の多くの能登出身職員の安否を気遣い動揺する中、病院長の「今こそ地域の期待に応えよう」との言葉で地域医療を支える使命感を再認し、職員一丸となって対応に当たりました。
不確実な情報と想定外の連続
地震発生時、当院がある内灘町は、震央(珠洲市)から100km以上離れているにもかかわらず、震度5強の揺れに加え、液状化による道路寸断・断水、1,700戸余りの住宅被害が生じました1)。幸い当院自体の被害は少なく、エレベーターが一時停止し、断水したものの貯水タンクが無事だったため通常診療が可能でした。発災直後から「奥能登(珠洲、輪島の両市)は壊滅的」との言葉が飛び交い、携帯電話での通信が不安定なために刻一刻と変化する能登地区の病院の詳細な状況もつかめず、緊張感の漂う日々が始まりました。
実際の被害は想像を絶するもので、地震・火災・津波・地盤災害・家屋倒壊・道路寸断・通信遮断・断水・停電と、まさに未曾有の災害です。翌日からは、能登全域の病院避難者や傷病者が救急車やヘリコプターで次々と金沢以南に搬送されました。石川県内では、突如として能登北部医療圏(輪島市・珠洲市・穴水町・能登町)と能登中部医療圏(七尾市・羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町)が「最前線基地」、石川中央医療圏(金沢市・かほく市・白山市・野々市市・津幡町・内灘町)と南加賀医療圏(小松市・加賀市・能美市・川北町)が「被災患者受け入れ側」となったのです(図1参照)。

図1 筆者らの病院の所在地
「病院の被害状況、入院・診療機能の状況」「搬送の準備」等の情報が十分に得られず、「手術要」とされていた患者が実際は「手術後」、午後10時到着予定が午前5時に大幅に遅延といった混乱が起きる中で、多数の患者を受け入れました。そして、数日で金沢以南の病院すべてで病床が逼迫し、高度医療機能を維持するためにベッドコントロールが最も深刻な問題となりました。統一的な転院調整システムは存在せず、従来の人的ネットワークを頼りに1例ずつ電話で転院調整を行うのが精一杯でした。
発災から6日目、誰もが広域搬送の長期化を覚悟し、病床逼迫に対応するため非稼働病棟の再稼働を決定しました。同時に、スタッフのメンタルケアや休息の確保、さらには効率的なシフト管理の必要性もいっそう高まりました。病院長と相談し、思い切って私立医科大学病院協会に応援看護師の派遣を依頼したところ、即座に14病院に支援調整をしてもらえました。この迅速な対応により病床と人的リソースの確保ができるようになり、なんとか当面の課題を乗り越えられる手立てを得られたと安堵しました。
こうした状況の中、石川県看護協会の小藤幹恵会長が呼びかけ、金沢以南の看護部長による「能登半島地震ZOOM会議」を開催。小藤会長は能登地区の厳しい状況を涙ながらに語り、1.5次避難所構想などの情報提供も行いました。これを契機に転院調整が進んだことを実感し、「気持ちと情報が人を動かす」と思いました。
平時から有事に備えること
平時に準備していないものを有事に稼働させようとしてもうまく機能しません。当院でも発災後早期に、KDDIの協力を得て能登地区の病院との間で人工衛星を活用したインターネット網を設けたり、金沢の近隣病院間の病床マッチングサイトを構築したりしましたが、これらの整備には多くの時間を要し、当座の被災対応としては功を奏しませんでした。現在は、今後への備えとして人工衛星を活用したインターネット網を介して、能登地区病院への医療支援を継続しています。
経験から得た教訓
次なる大災害への備えとして、インフラのみならず、災害に強い地域医療体制を構築しておかねばなりません。高齢化社会における広域・激甚災害では、避難所生活での持病の悪化や感染症が多く発生し、患者搬送期間も長期化します。
被災地が刻一刻と変化する災害急性期から亜急性期においては、事業継続マネジメント(BCM)として、「最前線基地」と「被災患者受け入れ側」の双方を想定した医療機関連携シミュレーションを行っておくことが重要な災害対策になります。そして、本稿で触れたように①情報ネットワークの構築、②地域全体の病床管理、③人的リソースの確保、この3つが最重要課題であると考えます。
なかむら・ますみ
2013年石川県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程修了。2024年10月より現職。認定看護管理者。