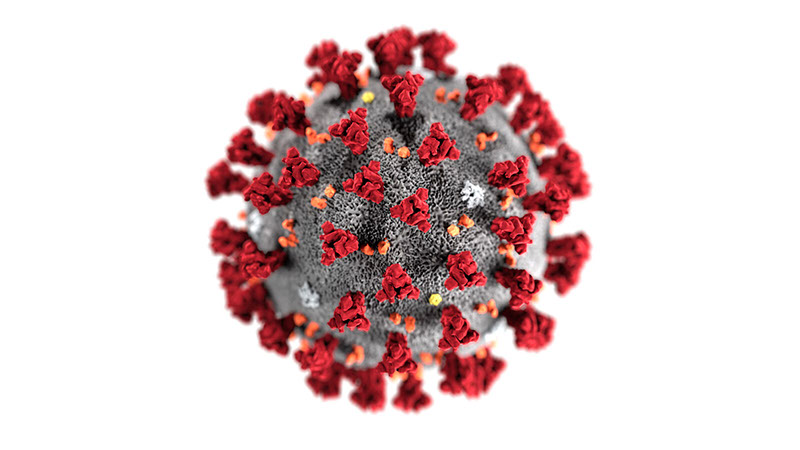マルクス&エンゲルス
最後に、マルクス&エンゲルスを取り上げます。ハート&ネグリ、柄谷のアイデアのもとになっているのがマルクスらです。余談ですが、ラトゥールはマルクス系列の議論をよく批判します。マクロな社会構造ではなく、むしろミクロなローカリティから出発すべきである、つまり微細な人間-非人間のネットワークの動きをゆっくりしっかり地道に明らかにしていくことを説きます。よって、ラトゥールらのANT派は本来、社会構造の議論は嫌いです。「社会」や「構造」という言葉も嫌います。
しかし、私にはマルクス哲学と共通点が多く、彼は、むしろマルクスらの思想にかなり影響を受けているように思われます(事実、もとをたどればマルクス哲学の史的唯物論から派生した、既述の状況論の議論に関しては、彼は肯定的に評価しています)。
大胆な言い方をすれば、ラトゥールこそマルクスらの歴史的発展形であり、かつ私たちと同じ社会構造の舞台の上で演じる演者の一人です。彼の論旨はあたかもANTだけが卓越し一貫した立場になりえるかのようですが、むしろ彼自身も社会構造の舞台に突き動かされている者の一人といえます。
マルクス派のアルチュセールの議論(アルチュセール、1965;今村、1980;1997)からうかがえるように、社会構造とは、そもそもが、身近な人々の行為に浸透しているもの、あるいは、ミクロな人−モノ関係の運動(の連なり)から生まれるものなのです。ここでは詳細には述べませんが、「マルクスは人間中心主義ではないが,人間の立場ではある」(岩佐,2016)という側面はANTにも見受けられるように考えています。よって、私はむしろこれらの理論の結合の道を探りたいと考えていますし、それら複数の異なる諸理論の中核に「交歓」があると考えています。
さて、マルクスらの議論ですが、冷戦終結後や、欧米の施策を見習ってきた日本においては、一時期かなりのアレルギーをもって否定されてきました。とりわけ、彼らの流派は国家権力を強化するにすぎず、経済的競争を避けることで技術発展や自由な経済活動を妨げるものであったという意味付けが多かったのではないでしょうか。いわゆる左派へのさまざまなアレルギーもあると思います。下記で述べる資本主義に代わる「共産主義」という概念も、その言葉を聞いただけで抵抗を感じる人もいるかもしれません。
しかし、興味深いことに、昨今(コロナ問題以前から)、資本主義の限界が叫ばれるようになり、かつての右派、左派という区別を越えて、再び彼らの議論が注目され読み直す運動が世界各国で起きています。彼らのアイデアのポテンシャルはいまだ実現されておらず、未来社会のヒントが眠っていると感じる人が増えてきているからです。
とりわけ、マルクス&エンゲルスが得意とするのは、歴史の議論です。例えば初期の作品にて彼らは、自然と人間との原始的関係、及び人間同士の原初的な家族関係が、資本主義的な民間の体制、そして、国家の源泉になったと主張します。そのうえで、資本制後の社会システムについても論じています。
以下、1845~46年の、つまり100年以上も前に書かれた著作を取り上げますが、100年以上も前に書かれた作品であるにもかかわらず、奇しくも現在の状況と重なる点が少なくありません。
まず彼らは、人間社会の歴史(資本主義の発展までの歴史)は、人間と自然との間の歴史と密接に関係していることを論じます。
例えば、現在のように、人間社会において、特定の立場の人間が他者に力(「威力」)を行使する源泉は、人間が自然に畏服していた原始社会にあると論じます。より正確に言えば、人間同士の力関係は、自然に対する人間の畏服と同時に発生したものではないかと主張しています。自然の力に人間が恐れおののくことと、人間同士の関係において何者かに恐れおののくことはよく似ており、密接に関係するというのです。
また、現在の労働で見られる分業(例えば、雇用主の資本家と被雇用者の労働者、車の部品を作る人とそれを組み立てる人)の源泉は、男女の性行為における分業にあるともいいます。
子作りや性行為において男女が異なる役割を担うことがもとになって、仕事における分業が発展していった。そして、資本制では常識となっている「所有」の概念は、家父長制的に、妻や子供が夫に従属することから始まった。それが次第に、資本家が他人の労働力(労働者)を雇い(所有し)、意のままにすることに発展していったというのです。
ただし、分業や所有は、一方(夫)のみが得をするだけではなく、共同の利害関係によって(相互依存関係によって)成立するものであるとも述べています。他方、この共同利害は、個々人の特殊な利害との間で矛盾を生じさせる。すなわち、家父長制という社会に共通の仕組みによって、年長の男性が先頭に立って家族を護るという共同の利害関係が成立する一方で、個々さまざまに事情の異なるはずの家族関係と捻じれ(矛盾)が生じ、人々はそれに苦しむ。
このような家父長制という仕組みは人間がつくった仕組みにもかかわらず、人間自身を支配する「威力」となります。
そして、この特殊的利害と共同的利害が国家へとつながっていくと言います。人々にごく身近だった特殊的利害と共同的利害が、個々の家族や部族や分業的諸階級の領域を超えることで、次第に普遍化されていき(つまりローカリティから切り離されて)、家族や部族等からは自立した国家が形成されていく。それは、「幻想的な共同性」である。エンゲルスは、「そもそも、普遍的なものというのは共同的な幻想的形態なのだ」と表現します。ただし「幻想」と言えども、それはあくまで家族等の「実在的な土台」の上に位置するものと述べています。
だからこそ、国家と国民との間に不一致が生まれることになります。先に、コロナ対策における国家の方針が、悉く国民の実態とズレてしまうことを述べました。マルクス&エンゲルスの考えをふまえれば、まさしく、「幻想の国家」と「現実の国民生活」との間に距離や分裂が起こるのは、原理的に不可避なのです。
国家が「ほら貴方たちがのぞんでいることでしょう」と示す施策は、(幻想の)普遍利害に基づくものであるにもかかわらず、我々の生活に根付いた特殊的利害として示される。ここに「矛盾」が生じてしまうそもそもの構造がある。マルクス&エンゲルスに言わせれば、民と国家の乖離は今に始まったことではなく、家族関係から国家が形成されていった歴史的経緯によって生じている事柄になります。
「まさしく<各人>諸個人がもっぱら彼らの特殊的な──彼らにとってさえ自分たちの共同的利害とは一致しない利害を、追及するからこそ、──そのものは彼らにとって「疎遠な」、彼らから「独立な」ものとして、それ自身重ねて特殊的でありながら特有の「普遍」利害として、まかり通ることになる。あるいは、民主政の場合のように、彼ら自身がこの[特殊と普遍との]二極分裂の中で動かざるを得ないことになる。」
(マルクス&エンゲルス、1845-46/2002)。※<>等の記号は原文のまま引用
この矛盾を乗り越えるには、あくまで一例ではありますが、既述にあげた寄付の取り組みのように、我々国民同士もまたより積極的なアクションを起こしていく必要があるということになります。国家(と国民の関係)は自ずと限界を有していますから、民が国家に責任を課す、あるいは国家の権力強化だけでは、この矛盾を乗り越えられないのです。
あるいは、国家と国民を仲立ちする地方行政が、国家と国民の隙間を埋める重要な鍵を握ります。中央政府よりもローカルな民に近しく、地方の文化や強みや課題に敏感に動ける立場にあるからです。
現に、コロナ問題を通して、北海道や大阪府など地方行政が、中央政府を先導するような動きが繰り返し報道されました。それはマルクスらの議論をふまえれば当然のことで、地方行政の方が国家よりも民に近く、乖離が小さい関係にあるからです。
ただし、コロナ対策に限らない話ですが、地方行政の中にはトップダウン的で官僚主義的な文化を色濃く残している地域もあり、地方行政と県民市民町民との間で、国家と国民の関係に似た類のズレが生じるケースも少なくありません。そのような限界を超えるべく、地方議員や職員の中には地域の人たちのローカルなコミュニティ創りに参加したりするなどして、この共同利害と特殊利害の隙間を埋める/超えるような活動をしている人たちもいます。
あるいは、前篇にて、ウイルスのような分散型の勢力は集権国家にとって弱点だと述べましたが、そうであるなら、同じ行政でも、よりローカリティに近い地方行政の方が対応がしやすいと言えます──他方、国家の下に地方行政が置かれる現在のような階層構造の下では、このゆえ国家が地方行政に丸投げをし、地方が困るといったようなこともまた起こってしまいます──。
そして、このような地方行政が目立つ動きは、前篇で触れた、地方への分権化の動きを加速させる可能性があります。国政への信頼感が減り、野党も与党もいまひとつ、どこも積極的に支持できず──過去の民主党政権が信頼を得られなかったことに加え、それ以前の疑惑やコロナ問題の対応がうまくいかず自民党も信頼を失っていくようなことがあれば──、その反面、地方行政が活躍していくのならば、地方行政の可能性がますます着目され、世論の後ろ盾を得ていくことでしょう。縦割り的に独立しがちな、異なる地方行政同士の連帯や協働も広がっていく可能性がありますし、その動きを意識的に加速させていく必要があります。
そして、民の水準でもまた、特に日本にて、罰則等の強い規制がないにもかかわらず、このコロナ問題を乗り越えたとなれば、民の自信にもなります。実際、内閣への支持率急落(毎日新聞社2020年5月23日27%、朝日新聞社調査2020年5月25日29%)から、日本国民は、感染がある程度抑制できた成果を、あまり政府の政策に帰属していないことがうかがえます。
日本人は暴動を起こすよりも、自らの意志で自粛や対策をしていくことでこの危機を乗り越えた。政府への不信を逆手にとって、これを契機に民同士が、より自律的に、より連帯する、新しい社会形成に動いていく。その萌芽が垣間見えます。
とはいえ、むろん(アナキズム的に)国政が無くなるようなことはすぐにはありません。国政ならではの役割は当然あり、重要です。したがって、先の途上国-先進国という、従来の固定的な上下階層を超えていく、新しい動態的な関係構築の可能性と同じように、これまでの上下階層関係にある地方と国家ではなく、地方の力が強まっていくことで、むしろより対等に、異なる特異性を持つ存在として、連帯し合う関係を築けばよいのです。
先のマルチチュードの議論と結び付ければ、「民(国民、県民、市民、町民、企業、NPO、任意団体等)」、「地方行政」、「中央政府」の三者がいかに有意義に連帯できるかということです。お互いの得手不得手を理解し合い、相手が持っていない強みとしての特異性を結び合わせて補い合う関係をいかに構築できるか。その柱には、単に利害関係だけでなく、<共>=人類と自然の共生関係がある。
このような関係性の転換こそ、トップダウン-ボトムアップの区別を超えた、特異性同士の「交歓」であり、その回路の構築といえるものです。トップかボトムかという固定された権力的階層関係ではなく、特異性の下、状況に応じて動態的にリーダーシップを変動させる。ある時は県が、あるいは特定の市や小さな町がリーダーシップを発揮する。別の時には、国がリーダーシップを発揮する。
教師と生徒との関係で喩えれば、生徒であっても教師よりもよく知っている趣味の領域となれば、教師がむしろ教わったり手助けされることがあるように、そして当然、教師が得意な領域であれば生徒に教えていくように、場面場面、状況ごとで関係性を変化・運動させていく。変化・運動を前提とした関係性に変えていくのです。権力の固定化こそが、さまざまな限界や問題を生むのであれば、それを状況ごとに変化させていく、状況論的政治学が求められます。
「共生」とは、皆が同じ平等な(フラットな)関係を築くことでは決してありません。むしろ、歴史の中で培われたそれぞれの特異性が生き、互いが生かし生かされ合う関係を形成していくこと、互いの特異性が動態的に結合していく関係性と言えます。対等なのは、どのような立場であっても、各々の特異性を発現していくことのできる権限なのです。
例えば、むしろ分断が進んでしまって、上記のような国際的連帯を築く事が難しければ、アメリカと中国という対立する二つの大国に挟まれた日本こそ、このような国家、地方、民の間の流動的な連帯モデルを示せる潜在的立場にあるともいえます。
歴史的に、中国大陸と欧米から強い影響を受けつつも、独自の文化を築いてきた日本、米の新自由主義政策を導入しつつも福祉国家の伝統が残っている日本にはその可能性が大いにあると思われます。すなわち、東洋の文化と欧米の文化の間、新自由主義と福祉国家の間、海と陸の間…、他にも様々な〝グレーゾーン〟が日本にはあります。また、オリンピックで世界中から注目されやすい今の立場だからこそ、逆手に取って、新世界を生み出す効果的な発信が可能なはずなのです。
さて、マルクス&エンゲルスは、資本主義(へ)の発展において生産と「交通」(Verkehr[独=原語]、intercourse[英訳])の発展が不可分であると述べました。交通は、物流インフラや交易ルートの開発、そして人口を増やす性交、これら複数の意味が含まれた用語です。交通という用語は、資本主義の発展においては、商品の生産と流通に関わるものとして位置付けられます。
しかし、私たちは、上記のように、資本主義の負、あるいは国家と国民の矛盾を乗り越えるような新たな交通の仕組みや流れを構築する機会にいま直面しています。つまり、貨幣、国家(間)、民(間)、さらにはウイルスといったさまざまな特異性が、人類と自然の危機を乗り越えるべく連帯・結合していくシステムを構築していく歴史的な転換期を迎えているのです。
この新たな交通の形こそ、古くて新しいintercourseの在り方、すなわち「交歓」です。交歓とは、一方で生命の誕生、存在(being)そのものへの愛、そして変化へのきっかけづくりと育成をメタファとする点で、父母関係に立ち返るものである一方で、交歓とは、家父長制的な権力的階層構造の負を越えていくものです。
また、異性愛だけでなく同性愛も、同じ愛によって共通するものとみなします。こうした新たな時代性が加わっていくことで、もとのintercourseの概念は新たな姿として再生されます。私たちの生の原点に立ち返りつつ、当時代性を反映し、さらに未来に向かって前進していくような形で再生されます。
さらに、マルクス&エンゲルスは、資本制の先の社会について次のような議論をしています。
「共産主義社会では、各人は排他的な活動領域というものをもたず、任意の諸部門で自分を磨くことができる。共産主義社会においては社会が生産の全般を規制しており、まさしくそのゆえに可能になることなのだが、私は今日はこれを、明日はあれをし、朝は<靴屋>狩をし、<そして昼[には]>午後は(庭師>漁をし、夕方には<俳優である>家畜を追い、そして食後には批判をする──猟師、漁夫、<あるいは>牧人あるいは批判家になることなく、私の好きなようにそうすることができるようになるのである。」
(前掲書)
この箇所は、共産主義に関する記述ですが、我々が一般的に持っているイメージ(国家が国民の自由を権力によって抑圧するイメージ)とは異なり、むしろかなり「自由」な働き方やライフスタイルを提唱していることがうかがえるのではないでしょうか。この意味で、共産主義はいまだどの国でも達成されていないものだと言えます。
つまり、ここで私は、どこか特定の政党を支持しようだとか、どこそこの国を模倣せよと言いたいわけではありません。むしろ、いまだどの国でも達成されていない未来を、国家、政党、地方、学術、企業、NPO……さまざまな枠組みを超えて、共創していく必要があるということを言いたいだけです。
必要なのは、党派や派閥ありきの話ではなく、どのような社会を形成していくのかという中身そのものです。いかなる党派や派閥も、同じ社会構造の舞台に立って演じている点は同様なのです。
興味深いことにこのマルクス&エンゲルスの記述は、コロナ禍を通して起きていっている働き方の変化と重なってきます。在宅勤務が増えることで、家庭生活と労働との区分が曖昧な人が増えていきます。既述のように、都会に住む人が減り地方に分散すれば、農業とデスクワークとを兼業する人や家庭菜園を積極的に行う人なども増えるかもしれません。今以上に、副業や複業をする人も増えそうです。専門性や「一人いち職業」というこれまでの常識が変わっていく可能性があります。
そして、マルクスは、「この運動の諸条件は<眼前の現実そのものに従って判[定]されるべき>今日現存する前提から生じる」(前掲書)とも述べています。共産主義は突如出現するものではない。むしろ、今の「現存する前提」から生じる。この現存する前提はまさしく、現在のグローバル資本主義が相当するでしょう。そして、「無所有」の大衆という現象<が>をあらゆる諸国民のうちに同時的に<現れ>創出」していることが、共産主義の出現の条件となると言います。
「持たざる者=無所有のもの」とは、当時の資本家に対する労働者や貧困者が想定されているかもしれませんが、コロナ現象という現在に照らして再解釈すれば、「経済を停止した者たち=所有を減退した我々自身」と言えるかもしれません。
「つまり、人々がそれに反抗して革命を起こすような威力となるためには、それが人類の大多数をまったくの「無所有者」として、しかも同時に、現前する富と教養──どちらも生産力の巨大な上昇とその高度な発展を前提とする──の世界との矛盾において、創出してしまっていることが必要である」
(前掲書)
すなわち、この「無所有者」と「富と教養」との間の矛盾を、単に「貧困労働者」と「資本家」の関係という、各々別人を置く従来的な解釈ではなく、「経済的な富を求める我々自身」と「経済を停止する我々自身」との間で生じる自己矛盾というように解釈するなら、まさにコロナ禍を通して、人類全体がその矛盾に直面したと言えます。
さらに、マルクスらは、「このことなしには、共産主義は局地的なものとしてしか実存しえず、……略……土着的・迷信的な「厄介事」のままであり続けるだろう」(前掲書)と述べています。つまり、世界規模で資本主義が広がる事、そして、無所有と富の間の矛盾がグローバルに広がる事、これが共産主義の条件だと主張しています。
共産主義は、一国、一地域でやろうとするのでは厄介事にすぎない。また、世界が資本主義を選択しない中で生まれるものでもない。むしろ、資本主義が世界中に広がることでこそ、その条件が整うと。このことは、「共産主義がそもそも「世界史的な」実存としてしか現存し得ない」と述べていることからもわかります。グローバルな資本主義の発展は、「絶対に必要な実践的前提」(前掲書)とさえ述べられているのです。
「共産主義は、経験的には、主要な諸国民の行為として「一挙的」かつ同時的にのみ可能なのであって、このことは、生産諸力の全般的な発展およびそれと連関する世界交通を前提としている」
(前掲書)
「世界交通」すなわち、人やモノが世界の隅々まで移動しまくる社会。まさしく、マルクスらの文言と、現在のグローバリゼーションおよび、それによってリスクが短期間で急速に広がったコロナ問題とが重なってきます。
国民と国家の矛盾、経済活動と感染拡大(生命の危険)の矛盾、自然支配と自然共生の間の矛盾……。マルキストの哲学者アルチュセール(1965)は、「矛盾の重層的決定」という概念を論じています。大きな変革は、複数の諸矛盾が重層的に集積し、それが爆発することによって起こると。
もちろん、繰り返しになりますが、今のところ、共産主義への移行よりも、従来の消費社会が(もしかすると以前以上に)進む、あるいはさまざまな変化はありながらも、そこに回帰する可能性が高そうです。しかし、長期化するほど、この前提が崩れる可能性が高まる。あるいは、他のさまざまな事変を経ながら、徐々に、今回の新型コロナの<共>的経験が私たちの社会の根底にある下部構造に影響を与え変動を起こしていくかもしれない。
いずれにしても、これまでの生活や社会の前提そのものを問い直す必要性に私たちは直面しています。環境問題等これまで蓄積された他の問題をふまえても、私たちは岐路に立っていることは間違いなさそうです。繰り返しになりますが、コロナ問題は、その一つにすぎないともいえるのです。いずれまた、我々の社会の前提を問う、新たな事変が到来します。
私たちは、一体どういう世界秩序を相互的に創りだしたいのかを真剣に考えなくてはなりません。コロナショックが過ぎ去ればそれを次第に忘れていくかもしれない。しかし、すぐにまた、否応なく考えざるをえない状況に直面するはずです。その時、より良い方向に移行可能な諸萌芽をここでできるだけ生み出し、共有し、あちこちの場所や領域に散在させておく必要があります。変化に迫られたときに、急に社会の転換をすることはできませんし、多くの犠牲を伴うからです。
ここで取り上げたマルクス&エンゲルスの共産主義の議論もまた、すでに完成された社会モデルでも、ただ目指していけばいいというものでもありません。これ自体、誰も具体的なものはわからない、未完成の社会像なのです。私たちは、今の時代性、これまでの歴史性をふまえて、どのような社会を望むのかを考え、共創していく必要があります。
(第10回へ続く)