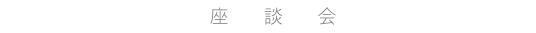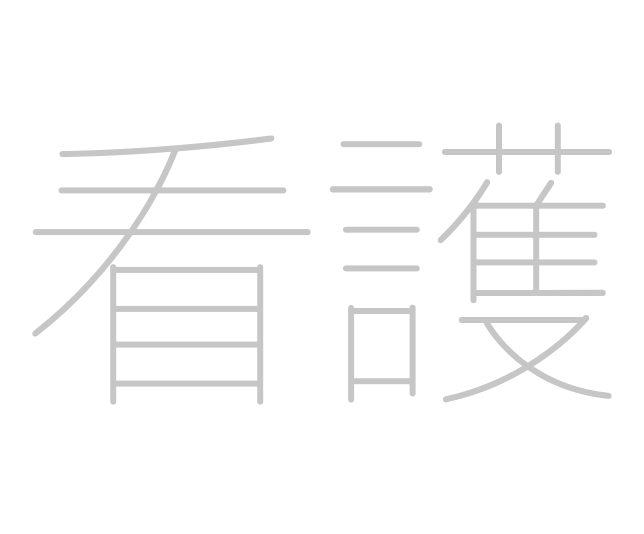
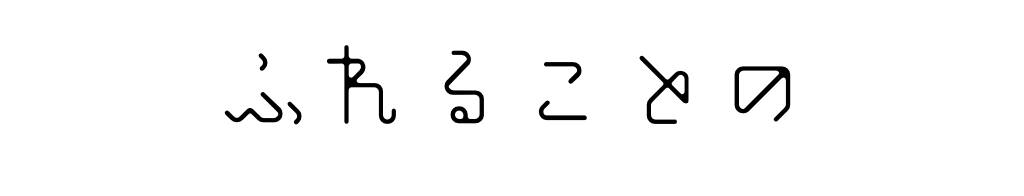




当社では2021年5月に、コロナ禍における看護の状況を医療人類学の視点から検証したNursing Todayブックレット『「コロナ」と「看護」と「触れること」』を刊行しました。看護師が手を使い患者に「触れること」がままならない現状をめぐるその議論をきっかけに、その名も「て・あーて(TE・ARTE)推進協会」の発起人である川嶋みどり氏と、「熱布バックケア」の普及活動に取り組む茂野香おる氏・内山孝子氏をお迎えし、看護職自身の立場から「触れること」のもつ普遍的な意義について語り合っていただきました。(編集部)
「触れること」が “何もしていない” わけではない
川嶋 『看護覚え書き』を著したフローレンス・ナイチンゲールも、機械や薬に頼るのでなく生活行動の援助、つまりきれいな空気や身の周りの清潔さ、暖かい日差しが入る部屋といったさまざまな環境を整えることの重要性を訴えています。そうした前提のもとで自然が健康を回復させるのであり、病気というのは健康への回復過程であるのだと。しかし当時の社会でも、薬を与えたりする行為に比べ、きれいな空気や暖かさ、清潔さを与え整えることは「何もしていない」とする認識が根深かったことを、彼女は批判し嘆いていたのです。それは今も同じですよね。薬や医療行為こそが「医療」であり、看護師が患者のそばにいたり、触れたり、トイレの世話をしたりすることは「何もしない」ことだと受け止められる。こうした看護行為が診療報酬として1円も認められていない事実からもそれは明らかです。
随分以前のことですが、こんなことがありました。ある知り合いの女性が子宮筋腫で入院し、腰椎麻酔で手術を受けた時のことです。術前からの心理的な緊張と術中の体位も影響して、術直後の彼女は緊張から肩がカチンカチンになり、痛みで身動きできず苦しんでいました。そんなとき、一人の看護師が病室にそっと入って来て、ポケットからベビー・パウダーを取り出し手につけてから、何も言わず肩から背中にかけて優しくマッサージをしたのだそうです。
その女性は「こんなに気持ちのいいことはなかった」と言っていました。お腹の手術部位の痛みよりも、神経を集中するせいか背中がすごくつらくなるとも。それを知って柔らかく乾いた手でさすっていただいたことが本当に気持ちよく嬉しかったと。この経験から彼女は、退院したあとに誰か知人が入院するようなことがあれば、すぐにベビー・パウダーを持参して背中をさすってあげるようになったそうです。すごく感心しましたね。後日談で伺ったのですが、この看護師は、小林富美栄先生(元日本看護協会会長、東京女子医科大学教授ほか)だったとのことです。
また、私が教育師長をしていた頃のことです。とても気難しい患者さんで、何を提案しても「ほしくない」「いらない」と不機嫌な顔で拒否されるので足が遠のきがちになると看護師達が話していました。肺がんの末期で呼吸状態がとても悪く、ずっと輸液中なので滴下状態の観察のみで退室してしまうと言うのです。そこで様子を見に、私がそっと部屋に入っていくと、確かにその患者さんはしかめっ面で目を閉じておられました。
私は、まず脈を見ました。内山先生が言われたように3本の指だけで皮膚の温熱や湿りや乾きのほか、脈拍の数で患者の緊張や不安など、いろいろなことがわかるんですね。だから学生にも、とにかくまず触れるとしたら脈をとることが一番だと教えます。患者さんに「脈を見ますね」と言えば、例えば認知症の方以外ならだいたい手をとらせてくれます。なので、私はその気難しい患者さんに対しても、まず黙って脈をとりました。そしてその方にこんなマッサージをしたんです。

脈をとった手を持ち代えて自分の手のひらで支え、静かに鳥の羽で撫でるように静かに遠心的に触れてさする。袖を少しまくって手首から先を出し、求心的ではなく遠心的に、つまり心臓から末梢に向かって静かになでる。それは触れるか触れないかくらいのソフトタッチで、鳥の羽で撫でるように柔らかく静かに触れる。川嶋氏らが音楽療法に取り組む中で見出した技術である。
川嶋 そうしているうちに、患者さんは薄目を開けて怪訝な顔をして私を見ました。知らない看護師が来たという様子だったので「すみません、川嶋です」と話しかけ、「いかがですか、ご気分悪いですか」って聞くと「いやー気持ちはいいけど、あなたの手は温かすぎるよ、冷たくしてほしい」とおっしゃったんです。私はわざわざストーブで手を乾かして温めてきたので、この言葉に驚きました。「あたたかく乾いた手」は、マッサージの基本だからです。続けてその患者さん「そこの魔法瓶に氷が入っていますから、どうぞお使いください」と言うので、洗面器に氷をいれ手を冷やしたうえでまたさすりました。すると「本当に気持ちがいい。もう結構です、ありがとう」とおっしゃいました。ケアを拒否されるどころか、ご自分から提案して下さったのでした。
ナースステーションに戻り記録をしていると、みんなが集まってきて「どうでした先生? 断られました?」って聞くので「そんなことない、ご自身からケアを提案して下さったわよ」と説明すると不思議がっていましたね。私がそういうコミュニケーションをとれたのは、やはり患者さんに触れたから。他の看護師は部屋に行っても輸液の量をちらっと見て点滴の滴数だけ調節し、さっと帰っていく。気難しい人のところに行くのが嫌だという気持ちがそこに表れていたわけです。
他にも印象深いエピソードがあります。私の親友で胃がん末期で亡くなる直前のことでした。会いに行くといつも彼女は「看護って何かしら、看護師って何をする人かしら」と言い「ユニフォームを着ていた時に考えていた看護と、パジャマでベッドに横たわっている時に思う看護は違うの」って言っていました。浮腫(むくみ)がすごく腹水がたまっていてとても痩せており、死が訪れるのは誰の目から見てもあと2、3日という状況でした。せめて背中ぐらいさすってあげようと黙々と触れていると、彼女は突然すごく大きな声で「ああ気持ちがいい、それそれ、それが看護だわ、川嶋さんこれが看護よね」って言ったんです。私の手には彼女のごつごつとした背骨と肋骨がぶつかってきて痛いほどで、その感触と彼女の言葉が今も忘れられません。
しかし、そうした話をいくらしても、今の病院ではあまりに患者に触れなくなってしまっているから、もし入院を経験した人がこの記事を読んだとしても、「そんなこと言うけど、看護師は手でなんか触れてくれなかったよ」って思う人のほうが多いのかもしれません。だから私は、看護行為のもたらす効果を科学的に示す必要があると考えています。
飛躍しますが、2021年に、皮膚を通した刺激が内臓に及ぼす影響を調べた研究者たちが、ノーベル医学・生理学賞を受賞しました(温度受容体および触覚受容体の発見、米カリフォルニア大学サンフランシスコ校のDavid Julius教授、米スクリプス研究所のArdem Patapoutian教授の2氏に授与)。研究の全容は論文を読んでも理解できないかも知れませんが、私は数種類の解説記事から、熱布バックケアのような温熱刺激や、”て・あーて” のように皮膚に触れる看護への科学的裏づけになるのではないかと思いました。
毎日新聞(2021年10月5日)の解説には「温度と接触による受容体の発見」とありJulius教授は、「辛み成分(カプサイシン)により皮膚の神経が熱に反応するしくみを分子レベルで解明」し、Patapoutian教授は、「刺激に反応する内臓や皮膚の細胞のしくみを研究。細胞表面の特定の受容体が圧力を感じると神経細胞を活性化させ、体中のさまざまな細胞にこのタイプの受容体が存在し、血圧を安定した状態に保つといった重要な役割を果たしている」ことを明らかにしたというのです。
とりわけ後者の研究では、この実験結果が明らかになった瞬間(2013〜16)に立ち会った野々村恵子氏(基礎生物学研究所助教)によると、「五感の一つの触覚がどうやって物を認知しているのかという疑問にとり組み、今では、同じ受容体が呼吸や血圧の制御、尿の放出といったさまざまな機能にかかわっていることがわかってきた」と述べています。熱布バックケアや ”て・あーて” によって全身的な変化がもたらされるのは、各臓器の細胞に受容体があってその受容体が温熱をはじめ五感にまつわる刺激で変化するのだというふうに理解すれば、今行っている看護──触れる・温めるケアの科学的根拠に通じるのではないかと思った次第です。