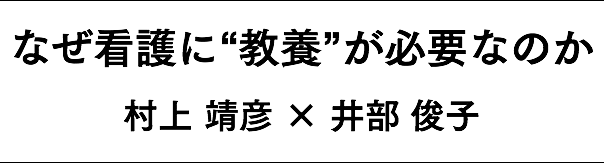◉ むらかみ・やすひこ(大阪大学大学院人間科学研究科 教授)
2000年パリ第7大学にて基礎精神病理学・精神分析学博士号取得、東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位修得退学。日本大学准教授を経て08年より現職。『治療の現象学』(講談社)、『摘便とお花見:看護の語りの現象学』(医学書院)、『障害受容からの自由』(シービーアール)、『仙人と妄想デートする:看護の現象学と自由の哲学』(人文書院:近刊)ほか著書多数。
★お知らせ(5/11):村上先生の最新著書『仙人と妄想デートする:看護の現象学と自由の哲学』(人文書院)が5/10に刊行されました。

◉ いべ・としこ(聖路加国際大学大学院看護学研究科 特任教授/日本看護協会出版会 社長)
1969年聖路加看護大学卒業。聖路加国際病院勤務を経て87年より日本赤十字看護大学講師。聖路加国際病院に復帰し看護部長・副院長を務める。2003年より聖路加看護大学教授、04年より16年3月まで学長。14年より株式会社日本看護協会出版会社長。『看護という仕事』(日本看護協会出版会)、『マネジメントの探究』『プリセプターシップ』(ライフサポート社)、『専門看護師の思考と実践』(医学書院)ほか著書多数。
看護は “医療” でなくなる時に看護になる
井部 村上さんが『摘便とお花見』(医学書院)を出版された時に行った対談で、次のような言葉が印象に残っています。▶ 対談:解きほどかれる看護師の語り(週刊医学界新聞, 第3048号, 2013年10月21日)
「“こんがらがった”看護の日常は、現象学を実現できる題材として非常に魅力的だし、解き明かしたい謎に満ちている」(村上)
「一見ありふれた日常と地続きのような看護に、実は深い意味があることをどう言語化、あるいは概念化していくか、これは大きな課題です」(井部)
今日はこの続きを議論したいと思います。
村上 看護師さんがいる現場はどこを切り取っても、考える材料がたくさんあります。哲学にかぎらず心理学や社会学、教育学などほとんどすべての学問にとっても興味深い、複雑かつ幅の広い世界なのです。それは看護師さん側からすれば、普段何気なく行う実践の中にたくさんの「考える種」があって、その思索にいろんな学問領域が役に立つということですね。
井部 でも看護師たちは、そうは思っていない。患者や家族から感謝され、いくらか自分を立て直してまた明日の仕事に向かうことはあるにしても、自分たちの経験から「自家発電」ができていない。村上さんのような人が常に周りにいて「そこは面白いね」と言ってもらわないと、なかなかその意味を見出せないのかと思います。
村上 もしかすると、看護の面白い部分、大事な部分が見えにくいからかもしれません。看護師さんは、働く上でのルールが大変厳しい中でも、自発的に「隙間」をつくっておられますよね。そこでちょっとした工夫をしたり、患者さんや家族の調整をしたり。特にエキスパートの方は自発的かつ自由に、ある意味「自家発電」をされているなと思います。しかもそれは、何かの学問領域に乗っかるような作業ではないところが面白い。
井部 「隙間」というのはとても魅力的ですね。でもそのような言葉をつけられるのは、やはり村上さんのような特別な作法を身につけた人たちなのです。
村上 どうでしょうか。たとえ言葉を与えなくても、看護師さんたちは実際にそれをやっておられますし、その中で自己実現されていると思います。仮に言葉を与えることが必要だとしたら、それは“教養”やリベラルアーツといったものが看護にどう関係するのかを確かめる、1つのきっかけかもしれないですね。
井部 社会学者の吉田民人さんが「看護学は文科系でもなければ理科系でもない。それらを融合した新たなジャンルの学問だ」というようなことをおっしゃったことがありました(日本看護系学会協議会ニュースレター, 2002)。文理の融合だからこそ言語化する力もまだ十分開発されておらず、学問が体系として確立されていない。
村上 医療の言葉で語られていながら、でも実はちょっとそこではないところに看護というものがあるのではないでしょうか。それがまだ言葉になっていないからこそ、僕らには考えたいことがたくさんあり非常に魅力的なのです。僕と付き合いのある多くの看護師さんが「看護は医療ではない」とか「医療でなくなる時に看護になる」とおっしゃいますが、全くそのとおりだと思います。
看取りのケアは「楽しい」?
村上 僕は今は訪問看護ステーションでフィールドワークをしているのですが、訪問に出る看護師さんは生き生きとしていますね。患者さんの生活と看取りをどうサポートしていくかという視点なので、以前に病院の看護師さんたちから聞いたお話と全く違うし、見ていても違います。
井部 村上さんはそこで、どのように佇んでいるのですか?
村上 慢性期で状態が安定している患者さんのケアに一緒について、たまにシーツを持ったりもしています。ここまでに5人の訪問看護師からインタビューを取ったのですが、そのうちの1件をもとに書いた原稿を発表したらクレームが来たんです。ある訪問看護ステーションの所長さんから「私たちはそんな看護はしていません!」というお怒りのメールをいただいてしまった。でもむしろ幸運なことだと思ってインタビューをお願いし、その方が5人目になったのです(笑)。
井部 「そんな看護はしていません!」ってどういう内容ですか?
村上 20年の病棟経験があり、最近在宅に移られた看護師さんで「在宅での看取りは本当に楽しい」とか「医療者にとっても、患者さんやご家族にとっても楽しい経験」というふうに「楽しい」という言葉を何回か使われました。これに対してその方は「私はよかったと思ったことも楽しいと思ったことも一度もない。いつもずっと悩み続けて、逡巡しながらの毎日です」という長いメールを送ってくださったわけです。
井部 よほどそのことを訴えたかったのですね。
村上 でもそのおかげで、すごくいいインタビューが取れました。「楽しい」という言葉があった訪問看護ステーションの看取りは高齢者が多く、メールをくれた方のほうでは若年のがんと神経難病の方をたくさん看ておられたのです。経験されてきた内容が大きく違う。後者のインタビューでは、お子さんを残していく若いお母さんたちに付き添う経験が多かったから、当然それは「楽しい」とか「よかった」という経験ではないですよね。
井部 よくわかります。看護師の立場からすると私たちは病気や人の死について「楽しい」とか「面白い」などと言ってはならないような、強い規範に縛られているように思います。現場では感激したり、大笑いしたくなるようなユーモアを感じる場面もあるのですが、普通はそれに気づいてはいけないという自己抑制がかなり強く働きます。「普通」じゃない人たちは「看取りは楽しい」って突き抜けることができるのですが、経験を積んでいないとそれができず、自分自身を苦しめます。