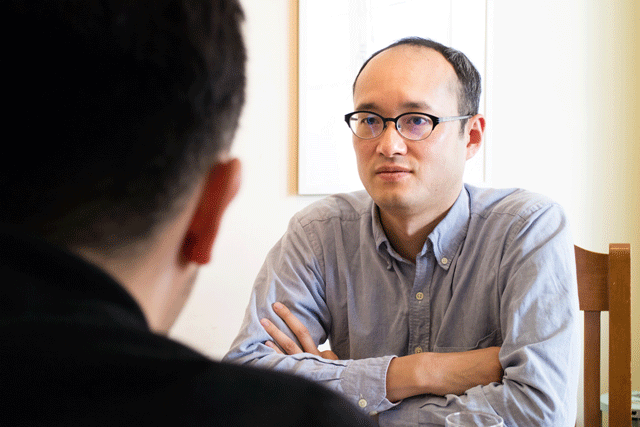特集:ナイチンゲールの越境 ──[情報]
対談:ドミニク・チェン × 孫大輔
ウェルビーイングを考える

たとえば「トランプ大統領は私のヒーローだ」という考え方の多くは、彼が主張するような極端で強い言葉に自身の価値観を外在化させており、自己生成というものができていないがゆえに強固です。だからそれを否定する者は否定し返すといった反応しかできない。逆にリベラルと呼ばれる人もまた然りで、トランプを支持する者はすべて女性蔑視で差別主義者だと言わんばかりに画一的に否定する。でも自己生成ができる人ならば、自分が保守かリベラルかは関係なく、話している相手が保守だろうと何であろうときちんと話を聞くことができるはずです。
僕らのような情報技術者には、SNSなどのサービスを支える技術がこうした問題を助長しているかもしれないことへの反省や危機感があります。だからこそ、社会全体のウェルビーイングにテクノロジーがどのように貢献できるかを考える必要があるのです。
一つの例ですが、サンフランシスコのベンチャーがつくっているSpireというデバイスがあります。僕も今ベルトに付けていますが、圧力センサーが腹部の微妙な動きをとらえて呼吸の状態をトラッキングしてくれる機器です。自身の呼吸の深さをリアルタイムでモニタリングできるので、いま自分がどれくらい緊張しているか、集中ができているか、ストレス度はどうかなどを知ることができます。
身につけたセンサー自体が振動したり、ランプを点灯させて「いま息が乱れているよ」などと教えてくれるので、そこで深呼吸して気持ちを整えることができます。履歴も残されるから過去にいつどこで緊張していたかなどもすべてわかります。
孫 なるほど。自分がいつどれくらい緊張していたかなんて、気づかないものですよね。
チェン そうなのです。僕はこうした個人レベルのログと解析を、家族や同僚、学校や職場といった集団で、数値やグラフ以外の形式で上手にシェアする方法があればいいのではないかと考えています。たとえばここにいる3人が今同じオフィスで働いていて、僕の呼吸はすごくいい状態だけど他の誰かの息が少し荒いことがわかったとすれば、部屋の照明の色を変化させることで、さりげなく全員にその場の雰囲気を伝えることができます。
孫 空気の可視化ですね。
チェン そうです。お互いの心理的な空気を気持ちよく忖度できれば、ちょっと気に掛けたり、思いやりの行動が生まれる。「もしかしたら孫さんが緊張しているのかもしれない。ちょっとランチにでも誘ってみようかな」というふうにね。でも、そういうことを全部スマホのディスプレイ上に指し示すという方法は選びたくない。それでは目的が外在化されてしまうから。人々の「気に掛ける」という探索行動のきっかけをつくることを大事にし、個々のイルビーイングを掬い上げることで、集団のウェルビーイングが高まるしくみをつくりたいのです。
さらに極端なことを言えば、このアイデアを国民全体に広げると、さまざまな社会属性ごとの苦しみや痛みのエビデンスを浮かび上がらせることができます。たとえばシングルマザーたちが相対的貧困に陥っていることを、経産省や総務省の統計が示した数字から理解するよりも、苦痛のデータとしてうまく社会で共有することによって、ファクトだけでなくエンパシーに基づいた社会合意を形成できるかもしれません。
他者の痛みを今よりももっと社会で共有できるようになれば、フィルターバブルのような状況下でも価値観を超えて、他人のことを「助けてあげなきゃ」と思える感情が自然に生成されるでしょう。実際にオーストラリアでは、行政がメンタルヘルスを身体の健康と同等にとらえることを一般通念化しようとしており、たいへん感銘を受けました。だけど日本の社会では不思議なことに「精神科にかかっている」と人に言った瞬間に不穏な空気が流れ始めますよね。本人もそれを知られたくないと思いがちです。でも、こうした苦痛を共有しようとする姿勢は、喜びの共有と同じかそれ以上に重要だと僕は思います。
たとえば僕の子どもが生まれてまだよちよち歩きだった頃、彼女が転びそうになった瞬間、自分自身が痛みを覚えたのです。おそらくミラーニューロンの働きかなという気はしますが、僕以外の人にはそれが発生しません。自分がエンパシーもシンパシーもいっぱい注いでいる大事な子どもが感じた痛みの感覚を共有できた体験が、いま話した考えのきっかけになったのです。
孫 痛みの共有ということで言えば、「言語ゲーム」で有名な哲学者のウィトゲンシュタインが有名ですね。彼は「他人の痛みがわかる」とはどういうことなのか、徹底的に考えました。他人の感覚は直接に経験できないし、検証することができないので、理解することは不可能とも言えます。しかし「言語ゲーム」の考えに則れば、経験の類似性、人間としての共通性が痛みの感覚の理解を支えていると彼は考えました。これは医学教育の世界でも「医療者の共感を育むことができるか」という大きなトピックになっていて、いま私が関心を傾けている事柄の一つです。チェンさんの取り組みは「痛みの可視化」という意味で、医学教育にも応用できる可能性を十分に持っていると思います。