特集:ナイチンゲールの越境 ──[情報]
対談:ドミニク・チェン × 孫大輔
ウェルビーイングを考える
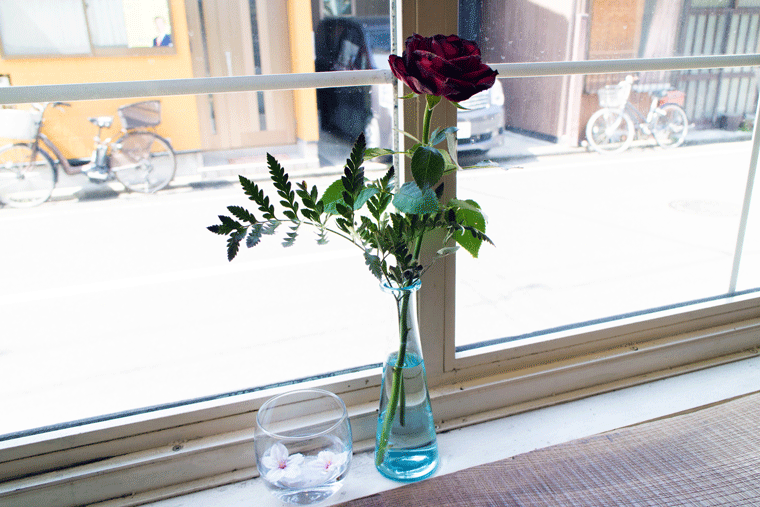
目的から自由になる
チェン 先ほど話したRISTEXでのプロジェクトでの議論を通じて浮き彫りになったことですが、健康に対する強迫観念や義務感からの解放を考える時に「無目的性」というものが、すごく大事な概念になるのではないかと思います。たとえば一緒に研究を進めている慶應義塾大学と港区が運営する「芝の家」というコミュニティスペースは、子どもから高齢者まで学生でも社会人でも誰もが自由に出入りして交流できる場所です。日常的にいろんなイベントがゆるく行われていたりするのですが、この取り組みがユニークなのは、事業として「この町をこんなふうに変えよう」といったゴールや目標を掲げていないところです。集まりたい人が集まればいい。トップダウンに目的が設定されていない。無目的性の価値というのがそこにあります。
編集部 当サイトでも「芝の家」を拠点にした「音あそび実験室」という催しをご紹介しています(「ケアする人のためのワークショップ・リポート第2回」井尻貴子)。コヒロコというミュージシャン・ユニットと近所の子どもたちやその親が集まって、楽器などに触れながら文字どおり、ただ「遊ぶ」だけの時間です。うまく演奏するとか楽曲をマスターするなどの目的があるわけではありません。たとえば子どもたちのようす次第で、おやつを食べながらボーッと過ごすだけの場合もあるそうです。
チェン まさそういった場所や時間のとらえ方の先に、真のウェルビーイングというものがある気がします。なんらかの目的性に振り回されている限りそこへは辿り着かない。こういう議論を今後どのようにやっていくべきなのでしょうか。たとえば医師として患者さんに「無目的になってください」とは言いづらいですよね。
孫 僕はちょうどこの、谷中・根津・千駄木あたりの地域の強みを活かした健康づくりを実践する「谷根千まちばの健康プロジェクト」(まちけん)という活動に関わっていて、そこで「まち歩き」というフィールドワークを行ってます。医学生、看護学生、薬学生、心理学の大学院生のほか、医師や管理栄養士などの医療専門職もそこに参加し、医療目線だけで地域を見るのではなく、地域での人々の暮らしを知る中から地域の魅力と課題を発見しようと考えています。ぶらぶら歩いて偶然の探検を楽しむこのまち歩きは、まさに「無目的」ですね。
ふつう医療従事者が患者に「歩行」を勧める場合は「1日に1万歩以上、週2,000キロカロリー以上の身体活動をする人には、そうした運動を行わない人に比べて神経疾患を1.3倍ぐらい予防できる」といったエビデンスの話になりますが、これは非常に目的的かつ管理的な発想です。もし本人に「いや、自分は健康にならなくてもよい。不健康なままで行きたい」と言われたら強制することはできません。健康増進を目的化すると、どうしてもそういう側面が生じます。
19世紀のパリにはフラヌール(遊民紳士)と呼ばれる人たちがいたそうです。金持ちで暇を持て余していた彼らはカフェなどに潜んで街行く人を窓から眺めたり、外をぶらぶら歩いたりしながら、そこから詩や文学作品などを生み出していました。シティウォーキングはそのように文化地理学や文化人類学に大きく貢献してきたのですが、ウェルビーイングや健康などについて論じられることはほとんどありませんでした。
こうした無目的な散策で得られる楽しさ、つまりそうした文化的要素と健康を融合させることでウェルビーイングを高めるという発想が医療者にあれば、専門家として統計的な合理性を唱えるだけではなく、たとえばその地域の街歩きマップをつくったり、それをアプリにしてツールとしての使い勝手を考えてみたりすることも仕事の範疇になってきますよね。
チェン 統計やエビデンスというものは、すべて外在的な目的を支える情報ですよね。どれも自分の中で生成されていない価値に従うものです。これに対し、孫さんが言うように趣味や趣向が持続性をもたらすのだと考えると、自己生成される価値観の重要性が浮かび上がってきます。ただ、それだけではこれまでの西洋的な考え方を超えられません。今の社会はそこに明らかな限界があるのです。だから先ほどの共話のようなかたちで、他者とともにその価値を生成していかなければならない気がしています。
先ほども少し触れましたが、今インターネット社会を襲っている最大のイルビーイング(ill-being:ウェルビーイングの欠如)はフィルターバブルという現象だと考えています。アメリカではそれがほとんど末期症状のようなかたちで起きているのです。自分と同じ意見を持たない者を全否定してしまうことによって、社会の分断がどんどん進み紛争や戦争を生み出すきっかけをつくってしまいかねません。
