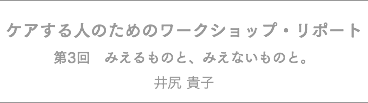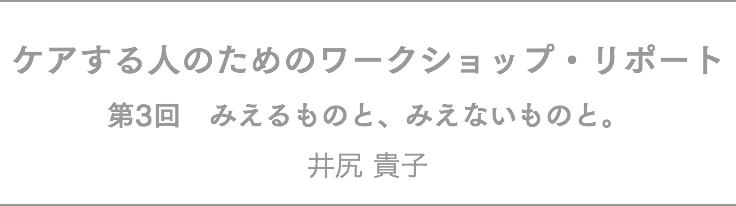ズレた状態を楽しむ
このワークショップを主催している「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」は、こうした「目の見える人と見えない人が対話しながら美術を鑑賞するワークショップ」を、都内を中心に、全国で開催している任意団体だ。2012年6月に団体としての活動をスタートさせ、これまでにのべ100回ほどのワークショップを開催してきたという。代表の林建太さんに、話をうかがった。
── 主な活動について教えてください。
ほぼ毎月1回、全国の美術館などで鑑賞プログラムを開催するのが基本的な活動ペースです。規模は小さくても、誰でも参加できる場が定期的にあることが大事だと思っています。
継続的な活動の中で美術館と連携関係をつくりたいと考えていますので、同じ美術館で何度も開催させていただくこともありますし、初めての美術館にも積極的に出向いています。また最近は、美術館だけでなく小学校や美術大学などの授業に伺うことも増えてきました。学生の皆さんと一緒に、鑑賞やコミュニケーションについて考えることはとても面白いです。
── これまでに、たくさんのワークショップをされていますが、特に印象に残っている出来事やエピソードがあれば教えてください。
活動を始めたばかりの頃は、こちらの意図とは違う動機を持った方が参加されることがしばしばありました。たとえば、「視覚障害者の方の手伝いをしにきました」という晴眼者の参加者や、「説明を聞きにきました」という視覚障害者の参加者などです。
こちらとしては、晴眼者も、視覚障害者も、一参加者として対話しながら一緒に作品をみていくということを想定していましたが、少し違ったのですね。
でも、そうした参加者の声を聞くことは「あれ? そもそも自分たちがつくりたいのはどういう場だろう?」ということを改めて考える機会になりました。うまくいったことよりも意図が伝わらなかったり、齟齬が生じたりしたときに考えたことの方が印象に残っています。
── 活動のなかで大切にされていることは、どんなことでしょうか。
できるだけ「ズレた状態」を大切にしたいと思っています。日常生活の中では人と人の間にある認識のズレ、身体のズレは齟齬や行き違いを生むことが多いので、ズレは少ない方がよいのですが、ワークショップの場ではそのズレについて話してみることで何か発見できるのではと思っています。
たとえば身体のズレとは視覚障害者と晴眼者の間だけにあるのではなく、目の見えない人同士の間にも、見える人同士の間にもズレがあるのだと思います。でも普段は気がつかないんですね。
なので、そもそも自分は何を見て、何を感じているのか、自分一人では気づけない実感をみんなで発見するような場にしたいです。そのためにはまず主催者の自分自身が、自分の意図や考えに凝り固まらないように気をつけたいです。なかなか難しいことですが。

言葉を交わし情景を生み出す
林さんは、「ズレ」を大切にし、そこから生まれるものをみんなで一緒に楽しむことを意図している。
確かに、「ズレ」は普段の生活においては、問題視されることが多い。解消すべき課題とされたり、なるべく触れないほうがよいこととして、ないかのようにやり過ごされたりした経験が、私にもある。でも、と思う。そのズレは、そうすることで「断絶のタネ」となってしまったりする。本当は、そこから始まる関係を生み出す「創造のタネ」であるかもしれないのに。
晴眼者も、視覚障害者も、実は一人ひとり、まったく違うようにこの世界を捉えているのかもしれない。このことに向き合うのは、怖いような気がする。だからか、私たちは普段、何の気なしに「私たちは同じ世界に生きている」ということにしてしまいがちだ。
同じ世界に生きている、でもその世界の捉え方はひとりひとり違う、かもしれないのに。そして、「同じ」ということにしてしまいがちだからこそ、すこし「違う」ものが現れたとき、極端な反応をしてしまうことがある。違うとして拒んだり、必要以上に気を使ったり。そこでは、対等な関係、対話は生まれにくい。
ズレだけではない。林さんは、最初の説明で「言葉にできないことも、そう話してほしい」といっていた。これも、特徴的なことだと思う。普段の生活では、言葉にできないことは、そう言葉にすることも控えられ、伝わる機会をもたない。なかったことになってしまう。
いま、私はそれが何なのかうまく言い表すことができないけれど、何かを感じている。その状態を自覚し、うまく言えないけどということも自覚したうえで、言葉を尽くそうとする。尽くしても尽くしきれないことがあるということに、ときに絶望しながらも、伝えようとする。そのとき、その伝わらなさを共有したところから、それでも、とはじまることがあるように思う。そうして生まれる関係は、互いの感覚や感情が異なろうとも、尊重し合える関係となるのではないだろうか。
ワークショップでは、最後に、感想を共有する時間がもたれた。グループのメンバーからは、こんな感想が語られた。
「おもしろかった。人の話もおもしろいし、口にすることで自分の考えが客観的に捉えられる」
「別世界に来たような感覚」
最初「なるべく声をかけないでほしい」といっていた女性に、ナビゲーターが問いかける。「わりと積極的に参加いただいて。どうでした?」
そう、この女性も、はじめこそ口数が少なかったが、途中からは自然と輪に加わり、発言ししていた。「よかった。ほかの人の発言をきいて、そういう見方があるんだ、というのもおもしろかった」と彼女は笑った。
そして、そのほかの人も。
「美術館は静かにみないといけない感じがしていた。しゃべること自体が新鮮。みんなにわかりやすく伝えようとすると、いつもとは違う見方をしている自分がいる。ふだん見過ごしているところも、説明しないとわかってもらえないということがわかった」
「目が見えなくなって2年くらいなんですね。その前は、一人で美術館にいくこともあった。そのときとは全然違う体験でした。言語情報から情景ができあがっていく、という体験がはじめてで、おもしろかった」
「美術が苦手で、一人だと、短時間でぱっ、ぱっとみてしまう。じっくり見て言葉にすることでドアがどんどんひらいていく感じがして、楽しかった」
私も、とても楽しかった。
そのとき、その場で、その人たちと一緒に作品と向き合う。言葉を交わし、みえるものとみないものを探り、織り合わせていく。その作業は、うまくいかないことも含めて、それでも楽しく、そのとき現れる情景はとても記憶に残るものになるように思う。
*リポート中の発言は、個人が特定されないよう、一部編集させていただきました。発言そのままの記録ではないことをご了承ください。
林 建太(はやし・けんた)視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ代表。1973年東京生まれ。1995年より介護福祉士として訪問介護事業に携わる。2012年より「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」発足。全国の美術館、博物館、学校などで視覚障害者と晴眼者がともに美術鑑賞をする鑑賞プログラムを企画運営している。 視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ障害の有無、見え方、考え方などさまざまな違いを持った人が、さまざまな視点を持ち寄り、ことばを交わすことで一人では出会えない新しい美術の楽しみ方を発見することを目指している。誰もが気軽に感じていることや印象、経験や考えを自由に語り合う、そんな美術鑑賞の場をつくっている。 https://www.facebook.com/kanshows/
戻る
第1回:からだを使って、新しいコミュニケーションの回路をひらく
〜 佐久間 新 さん(ジャワ舞踊家) >>
第2回:音であそぶ、音とあそぶ「音あそび実験室」
〜コヒロコ (音楽ユニット) >>
第3回:みえるものと、みえないものと。
〜 視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ >>
連 載

page 3

『ソーシャルアート-障害のある人とアートで社会を変える-』
(たんぽぽの家編)
障害のある当事者、福祉施設スタッフ、アーティスト、プロデューサー、音楽家、ダンサー、演出家など、アートを通して誰もが幸せに生きることを実現する環境や社会のあり方を問う、25の実践を紹介。第6章のコラム「すべての人に美術館を開く」を井尻さんがご執筆されています。
コメント:
(毛利悠子《From A》2015-2016年)