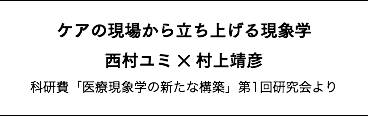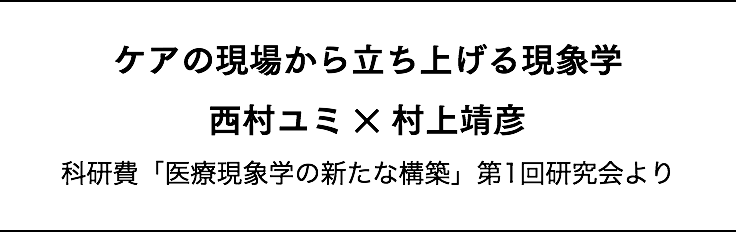質疑応答 page 2

質疑:言葉で掬いきれない「身体性」をどのように拾うのか
発言者C 私は看護系大学の博士課程で現象学を学んでいます。かなり研究の実践的なレベルでの話ですが、言葉と実践と身体の連動について考えるときに、例えばインタビューで身振りや手振りといった身体性をどのようにデータとして記録するのかについてお考えがあれば聞きたいです。
村上 インタビューでの身振りや声のトーンなどはよく覚えていて、データを読めば僕自身はもちろんわかる。でもそれだけがポイントではなく、言語だけで書き起こされたテキストの中に、すでに身体が書き込まれているということなのです。僕の考えでは本人が自覚しているかしていないかは関係なく、自分のやっていることに全部気づきがなくても構わない。ぐちゃぐちゃの語りで自分が何をしているのかわからないままであったとしても、そこに身体的なものはすでに書き込まれていると思います。
西村 質問者の疑問は、インタビューから文字起こしをしてもジェスチャーや身振り・手振りはそこに残らないじゃないか、ということだと思います。私の場合、象徴的な身振り・手振りはインタビュー中にメモし、インタビュー自体の記録はICレコーダーに任せます。例えば患者さんの動作を示すようなときはかなり大きな身振りをしますよね。
もう一つは村上さんと同じく、語り言葉の中にも身体性を見て取ることができると思っています。例えば、動作に関する語りで「ああするとよかった」「こうするとよかった」というような表現があります。これは、見て判断をして「ああする」「こうする」という行動が生まれる以前に、患者さんに出会うことにおいて、すでに私たちの身体性が駆動させられている、と言えるインタビューデータなのです。つまり、語りの順序や、その動詞がどんなふうに他の言葉や事象と結びついて語られているのかを見ることが、身体性を分析する手掛かりになります。私たちは二人ともそういうところをかなり意識して分析をしていますね。
村上 そうですね。
榊原 西村さんのご本の中に、看護師さんが「病棟に溶け込めない」と言った後ですぐ「溶け込まない」と言い直したところがありましたね(『看護実践の語り』p.47)。細かな動詞の表現で「め」と「ま」しか違わないのですが、身体的なかかわりや実践への構えというものがたったそれだけで表れていて、そこを分析されたのは素晴らしいなと思ったのです。
西村 溶け込めない=溶け込むことをさせてもらえない、というある種の受動性が語られた直後に、溶け込まない=自分からそうしない、という能動的な意思を表す語りが続く。そういう両義的な経験が、言い換えられた言葉には表われています。たった一文字の言葉の違いが、こういう分析を可能にしてくれます。
榊原 そうですね。単なる言い間違いととらえて読み飛ばすこともあり得るし、データをカテゴリー化してしまうとこの辺が抜け落ちてしまう。こういうところに言葉と身体性、実践が表裏一体になっているのがわかります。
「突き刺さる」経験と「個」の広がり
守田 個別事例でないと他者が触発されない、という村上さんのお話がありました。そうでないと「突き刺ささらない」というのは本当にそう思います。一方で、看護の実践にとっての個別事例の重要性を、現象学の学問的普遍性として成り立たせることも重要です。これについてはいかがでしょうか。
村上 個別のものを分析することによって、ある形をつくり出す。経験の個別性から形や構造の個別性へと転換するのが現象学の役割かなと思います。もう一つは、それでも分析できないポイントのようなものがやはりある。それを最終的に支えるのが「突き刺さるもの」なのかもしれません。研究にとってもこれは大切で、僕には本などに載せていないような重要なデータもあります。たとえば訪問看護先でインタビューをしたとき、予後告知の話になった際に机の脇に家族写真が置かれていました。笑っている6人の子どもがすごく痩せた母親を囲んでいる写真でしたが、ある瞬間それが僕の目に留まりました。それを見た看護師が「最近こんなことがあって...」と、その痩せた母親の話を始めたのです。予後告知とはなんの関係のない話題でしたが、僕がたまたまそのテーブルの前に座り写真を見たことによって、その方にとってすごく意味のある重要な語りを聞くことができたのです。こういう部分は分析のしようがないのですが、すごく大切で消してしまうことはできないのです。
守田 分析ができないのは、そこで経験されている状況の全体が、ということですか?
村上 そうです。語り自体は分析できますが、その時はたまたまステーションでお話を伺い、そこにあった写真にたまたま僕の目が向いただけなのです。僕の研究室でインタビューしていたらそれはあり得なかった。そういう偶然の要素に「突き刺さる」ことが支えられていたりもする。もちろん実践の個別性にもそういう部分があるのです。
西村 たしかに私たちにとって「個」は具体的な事象ではあるけれど、しかし、あまりその「個」を強調しすぎる必要はない気がするのです。なぜかというと、そこではその写真を村上さんだけでなく複数の人が見ているのだし、村上さんは他の場所へ行けばまた違うものに関心を向けていた可能性もあるのだから。そう考えるとやはり個別の問題ではなく複数の人の関心やその場の状況、それも共有するというよりは、自覚する手前、つまり一人ひとりの個別性が意味を持つよりも手前で行われている、私たちの身体的な営みであるというふうに見ることができます。個であると同時に状況に対する応答であったり、それらが他者と分かち持たれている可能性ですね。これは他者も同じように考えているというよりも、そういう個を超えた経験が潜在的になされているからこそ、私たちの他者に対する理解が成り立っているのだと思います。
普通の言葉
大熊(由紀子) 長年ジャーナリストをやってきた立場からの感想ですが、もう少し「わかる」言葉で議論していただけないものか、と思いました。ドイツに行った哲学者が「あちらでは女中が哲学用語をしゃべっていたりする」と言っていましたが、日本ではおそらくそれらを輸入したときに難しい言葉にしてしまう伝統があるのではないかなと思います。村上さんの『摘便とお花見』とか『妄想デート』などは本当にパッとわかりますが、「側面的普遍」と言われると、いろいろと解説をしていただかなければわからない。新聞で言えば見出しになるような概念があれば、看護さんや患者さんの間にもっと広まっていくのかなと思うのです。私としては、ジャーナリストの分野と現象学が地続きじゃないかなと考えているので、私が教えるジャーナリズムを学ぶ博士課程の院生さんとの間に、何か学問的な架け橋のようなものをつくっていただけると嬉しいです。
榊原 大熊先生には、今後3年間のプロジェクトのとても大きな課題を示していただいたような気がします。現象学的看護研究では、たとえば先ほどの「溶け込めない、溶け込まない」のように、その人が実際にしゃべった言葉が見出しになればストレートに伝わると思えます。しかしそれがどう成り立っているのかを議論し始めると、途端に難しくなってしまうわけです。その議論をどこまで「普通の言葉」で語れるかというのも一つの課題かなと思います。
今日はみなさん、どうもありがとうございました。
(2016年8月2日 於・東京大学本郷キャンパス法文二号館一番大教室)
page 1 2
トップ | ディスカッション 前編 | ディスカッション 後編 | 質疑応答