
他者からみた「私」
一方、こうした「独我論」と対立する考え方の「相互承認論」はどうでしょうか。「相互承認論」は「独我論」とはまったく正反対に、「我思う」ということ自体が、実はとても「疑わしい」と考える立場です。デカルトの考えのなかにはこうした「他者」との共通感覚が前提となっているところもあるので、ある意味ではデカルトは「相互承認論」の創始者でもあると言えるわけです。ただし「相互承認論」を前面に展開したのは、やはりヘーゲルです(また、この考えをもとに「社会科学」を成立させたのはマルクスであると言えるでしょう)。
ヘーゲルはとても現実的な物の見方をする人で、確かにデカルトは「思う我」という「主体」を発見したけれども、そうした発見は人間の成長過程の一部であり、人類の歴史的展開の一コマなのだと考えました。つまり「独我論」を否定するのではなく“そういう考えもある”とみなしたのです。人類の英知の一部分として「独我論」を組み込んでしまうわけです。
わかりやすく言えば、10代になって「自我」の目覚めというものを経験するのと同じようなことをデカルトは主張したのだ、とヘーゲルは解釈しました。今で言う「中二病」みたいなものとしてヘーゲルは独我論を位置づけてしまうわけです。
今でも独我論を主張している大人(哲学者)もたくさんいますから、そういう人たちからみれば、こうしたヘーゲルのものの見方には反発もあることでしょうが、まあ、ヘーゲルの言い分もちょっと聞いてみてください。
ヘーゲルが考えるような「相互承認論」は、自分が「思う」ことが「自分」に起源があるとはせずに「他者」からやってきたと考えます。ここが「独我論」と決定的に異なります。
言葉と思考と我
そもそも「独我論」のようなことを考えたりできるようになったのは、親から生まれ育ち、次第に言葉を覚えて、他人とコミュニケーションがとれるようになった結果なのではないでしょうか。その「いのち」が「思考」を開始するためには、「私」だけではなく「他者」が必要である、ということです。
「独我論」の言う「私」という「存在」の独特さ、固有さはわかるとしても、その「私」は独我論が言うようには簡単には単独で成立しないように思います。要するに、親や周りの人たちとのやりとりがあって初めて「独我論」も誕生するのです。
そもそも、この世に生まれたときからまわりに他人(人間)がいない場合、つまり、人間どうしの関係をもつことなく育ったとき(たとえば狼に育てられるような場合)、その個体は「思考」を持たないため、独我論は決して生まれてはこないでしょう(思考のない独我論、というものがそこに存在するかもしれませんが、それは証明しようがありません)。
「我思う」ということを考える際には、必ず「言葉」を使っていますが、この「言葉」は、「我」がつくりだしたものではなく、歴史的、文化的に多くの人たちを経由して「我」に利用されたものでしかありえません。「言語」とはそういうものなのです。冷静に考えれば、この世のあらゆる事象がすべて一人の人間の「思考」によって生み出されたと考えるのは、あまりにも非現実的です。この点に目をつぶる独我論は、やはりどうしても独善的に見えてしまいます。こうした拡がりがすべて、独我論者の言うようにある個人の「思考」だけによって生み出されるなんていうことは、果たしてあり得るでしょうか?
しかも現実社会においては、人は一人で生きているのではなく、相互に認め合い、助け合って生きています(ヘーゲルは相手との闘争や戦争さえも「相互承認」の一類型とみなすので、相互に争い、戦い、戦争を行うことも人間的なものである、ということになります)。独我論者もまた、たとえば大学教授という立場に基づく社会関係をもち、家族をもち、さらにはそうした考えを多くの人に知ってもらうために本さえ書いています。そうなると「独我論」とは、あくまでもこうした前提を理解したうえで行っている「知的ゲーム」のようなものではないかという気もしてきます。
そうであれば「我思う、故に我在り」は、やはりただ一人「デカルト」だけを指すのではなく、「人類」「人間」全般があてはまりうると考えるべきではないのか。ヘーゲルならきっと、独我論のことをそう位置づけることでしょう。
まとめると、「相互承認論」においては「独我論」はあくまでも変種扱いされ、逆に「独我論」においては「相互承認論」は関心の対象外とされてしまいます。こうした相矛盾した考え方がデカルトに端を発して生まれ現在に至っています。しかし、この二つの自他認識の基本構図は、だからといって単なる「対立」した考えではありません。強いて言えば、「独我論」をつきつめると、本当の意味で「他者」と向き合うことになり、他方「相互承認論」をつきつめると、どうにも捨て去ることのできない「自分」につきあたる、そうした力があるように思われます。
つまり、こうした「~論」というのは「自己主張」を目的としているのではなく、そこで語られないものを発見し、広い意味での「他者」を見つけ出して、対話が困難なそれら「他者」との対話を試みようとする「仕掛け」のようなものなのです。私たちは「独我論」から「他者」を学び、「相互承認論」から「自己」を学ぶべきなのです。
人間の思考の不思議さ
どうでしょうか? ヘンテコな話かもしれませんが、つきつめて考えると皆さんのなかにも、この二つの考え方が(あいまいな形かもしれませんが)潜んでいるのではないでしょうか。
「相互承認論」は、現在でも社会科学や社会福祉学の基盤にある考え方となっていますが、少し厄介なのは必ずしも「独我論」が否定されるものではないことです。「相互承認論」もときに行き過ぎると、相手への依存や無理解を生むことがあります。相手と自分との違いに鈍感になり、あたかも自分が「人間」や「人類」または「国」や「社会」の正しい考えを背負っているかのように思い込み、相手がそうではない場合に、排除したり差別したりすることが発生してしまいます。「独我論」は、こうした考えに歯止めをかけることができるかもしれません。
なんとなく「相互承認論」のほうが、世間的にはまっとうに見えるかもしれませんが、「他者」にばかり目がいってしまい「自己」を見失ってしまいそうなときがあることを、決して忘れてはなりません。
実は、看護の学生に「独我論」と「相互承認論」のどちらを支持するか、という質問を投げかけたことがあります。そうすると意外にも、どちらかに偏らずだいたい支持者の数が半々になりました。言い換えれば「独我論」にも、良し悪しはありますが少なからず一定程度の人が引き付けられていることがわかります。
そして、少なくともこうした「独我論」に関心をもつ看護学生がけっこういるという現実を知ることがとても大事であるように思います。ソクラテス(第1回)のところで述べたように、「世話(ケア)」すべき「魂」はまず「自分」にあると考えることは、看護においても大切だからです。他者への世話(ケア)を通じて自分の魂を磨いているのです。
こういう議論は、看護の現場からはかなり離れてしまっているように思われるかもしれません。しかし私は、看護職の方々が医療チームで他職種の人々とどのように仕事を進めるのか、またどのように患者と向き合うのかについて考えることと「独我論」と「相互承認論」という二つの考え方は決して無関係ではないと思います。
しかし繰り返しますが、「独我論」と「相互承認論」は直接、医療の現場における仕事や患者との関係などを具体的に改善する処方箋のようなものではありません。にもかかわらず、私はこの二つの考え方が、いずれも人間が考え出したもののなかでも、とりわけ根本的な概念であると思われて仕方なく、それを皆さんにも是非知っていただきたいと思い、お話ししてみました。医療や看護とは一体何なのか、そこにかかわっている自分、患者、医者、それぞれの人との関係性を「独我論」と「相互承認論」といった考えをふまえて、あらためて見つめなおしてみてはいかがでしょうか。
次回は、20世紀を代表する哲学者の一人、ミシェル・フーコーをとりあげます。彼は「相互承認論」を基盤とした考え方の一つである構造主義の影響を強く受けて研究者としての道を歩みますが、晩年には、実践的な「自己への配慮」という形で自分の生き方を追求しました。こうした思考の歩みは、今回とりあげた「独我論」と「相互承認論」との奇妙な相互関係から説明ができるかもしれません。どうぞ、次回もお楽しみに。
◉ 参考文献
永井均『<魂>に対する態度』勁草書房、1991年
永井均『ウィトゲンシュタイン入門』ちくま新書、1995年
永井均『<子ども>のための哲学』講談社現代新書、1996年
永井均『これがニーチェだ』講談現代新書、1998年
滝浦静雄『「自分」と「他人」をどうみるか』NHKブックス、1990年
柄谷行人『倫理21』平凡社、2000年
柄谷行人『探究I・II』講談社学術文庫、1986、89年
東浩紀『動物化するポストモダン』講談社現代新書、2001年
大澤真幸『文明の内なる衝突』NHKBooks、2002年
(第6回へつづく)
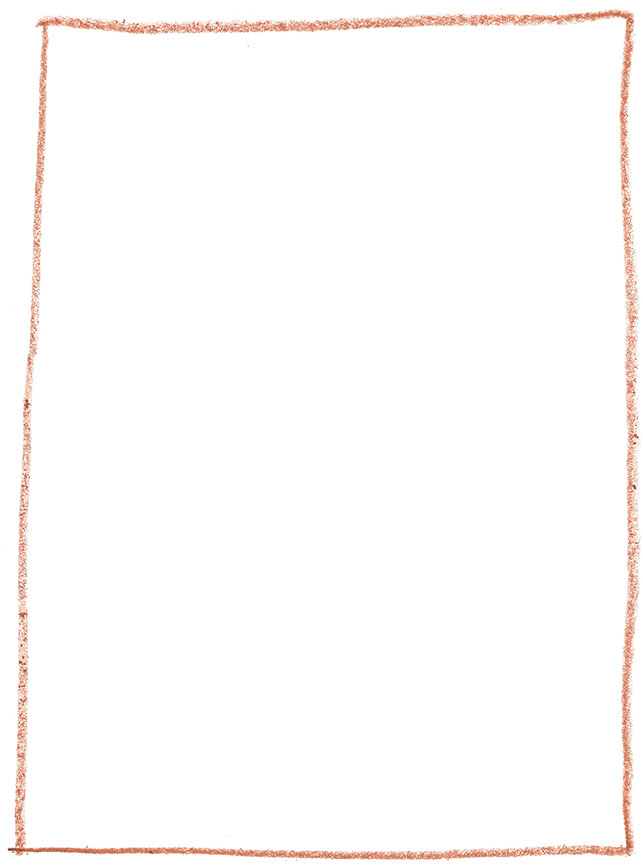
韓流ドラマ「冬のソナタ」が名作である理由
少し古い作品で恐縮ですが、かつて「ヨン様」ことペ・ヨンジュンが主演の「冬のソナタ」というドラマが日本で放映され、社会現象的な人気を博したことがありました。実はこの作品を支えている設定の要こそ、「独我論」と「相互承認論」の絶妙な交錯なのです。
ペ・ヨンジュンは最初、チュンサンという、かなり影のある高校生として登場します。そしてチェ・ジウ演じるユジンは彼に惹かれ、そして二人は恋人どうしとなります。
ところがチュンサンは交通事故で記憶を失ってしまいます。こともあろうにチュンサンの母親は彼に別の記憶を移植するよう医者に要求し、その手術は成功します。チュンサンに、とても快活な「ミニョン」というまったく別の人格が与えられるのです。
母は息子のためを思って、チュンサンは事故で亡くなったことにし、息子を留学させ、別の人生を歩ませます。
しばらく時が流れて、ユジンは建築デザイン会社で働いています。そこで、かつての恋人とそっくりのミニョンと出会います。もちろんミニョンはユジンのことをまったく覚えていません。
そのうち次第にミニョンに惹かれていくユジンですが、自分が愛したのはチュンサンであることにこだわり、ミニョンとは距離をとります。しかし、ミニョンにふれるにつれ、ユジンはそこにチュンサンの魂を見つけ出していくのです……。
是非とも作品にふれてほしいので詳細は省きますが、このようにユジンは、「チュンサン」という「魂」を「ミニョン」に発見します。ここには、「魂」というものが、ある種の「独我論」的構成をもっており、そのために、別の人格となりえることが示されているとともに、他者からの、特に「愛」を伴った他者関係からの働きかけによって、独我論的な「魂」がゆるぎないものとして発見されます。
コ ラ ム
page 1 2