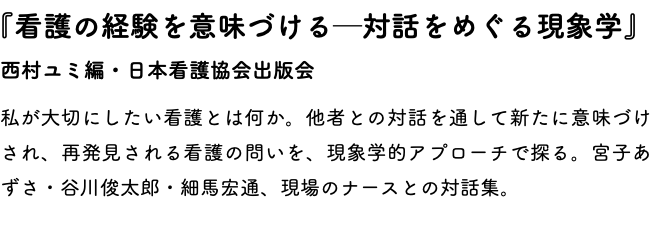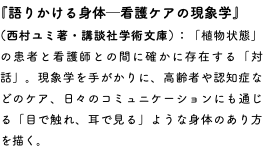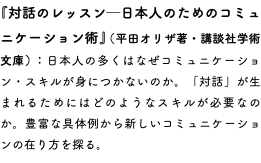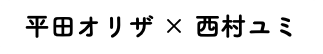

2019年4月23日に開催された弊社トーク・イベントの全内容です。ゲストの平田オリザさんは劇団「青年団」●1を主宰されている劇作家であり教育者、西村ユミさんは現象学的アプローチで看護ケアの有り様を追究されている看護師であり研究者、教育者。「演劇」と「看護」というこの2つの世界は、どちらも「身体」と「コニュニケーション」という重要なキーワードに向き合う分野です。この対談では、演じる者と観る者/ケアする者とされる者とのあいだで繰り広げられる、言葉を超えたコミュニケーションの世界に分け入ります。
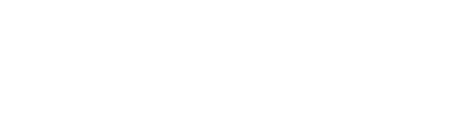
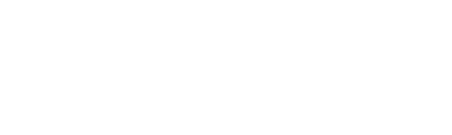
●3:糖尿病劇場
日常的な糖尿病診断や療養指導を再現した後に、聴衆である参加者とディスカッションを行う医療者向けの教育手法。2009年西東京臨床糖尿病研究会に始まり、日本糖尿病学会学術集会で知られ、全国に展開している。
● ● >
役割を演じるのは悪いことじゃない
平田:演劇と看護は一見関係がないようですが、僕はそうでもないと考えています。医療は人類が発生した2〜3万年前からあるものだと思うんです。動物はたぶん長生きしたいとは思っていないので、人類が死や弔いを意識していたということは、逆にいうと人類は長生きしたいと思っていたのではないか。それで、加持祈祷や呪い、密教のように祈りで人を驚かせて元気にさせるとか、それから薬草とか、そういうものがあった。
この加持祈祷みたいなものは、お祭りなどと非常に密接な関係があったので、人類は最初の頃、ほとんど祈りと医療は同じだったと思うのです。医療の初期段階では長生きしたいし、幸せになりたいからお祭りをやったり、神に祈ったりしていたと思うので、そもそも演劇と看護のつながりは強いものだと思っているんです。
西村:実は私、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター●2(現大阪大学COデザインセンター)に在籍していた当時、平田さんの「演劇ワークショップ」の授業に出席していました。私自身は「現場力と実践知」という身体ワークショップの授業を提供していたのですが、この授業は演ずるというよりも、ある状況に思わず身体が応答してしまって、それが表現になるというような、ダンスのスタイルの1つかもしれませんが、そういったことを学生たちと行っていました。
私たちが普段、気がついていない身体の営み、例えば後ろ向きにものすごくゆっくり歩くことが、前に向かって歩くこととどう違うのか、について3時間にわたってやるとか。そんな経験を一方でしながら、他方で平田さんの演劇の世界に入り、私たちが普段、意図的にしていることと、意図せずにしていることってどう違うんだろうと考えようとしていました。
演劇ワークショップでは、日常的に意図せずに身体が思わず動いてしまう振る舞いを、平田さんたちは自覚的に再現し、なおかつそれが自然に見えるという、すごく難しいことをされているなと思っていました。私などは意図的にやるとすごくぎこちなくなって、あからさまに演じていることが見えてしまうんですけれども。演劇は身体について気づくきっかけになるだけではなくて、それを組み直していくようなことをされているのかなと思いました。そのあたりのことは、一緒に仕事をしている頃には質問できなかったので、今日改めて聞いてみたいなと思っています。
平田:いきなり結論めいたことになっちゃいますが(笑)、というか、よく自分の著作の最後のほうに書くことなのですが、不登校の子たちはよく「本当の自分はこんなんじゃない」って言うんです。また「いい子を演じるのに疲れた」とも。僕は演劇人だから「お前ら本気で演じたこともないのに“いい子を演じて疲れた”なんて言うなよ」ってからかうんです(笑)。真面目な子ほどそう思い込んでしまう。
大学の授業では一般学生が対象なので、「いやいや、みんなそれぞれの社会的役割を演じているんだよ」「演じることは別に悪いことじゃないんだよ」ということを教えていて、それが大阪大学での最大のミッションだと思っています。「そうとわかって楽になりました」っていう子は結構います。阪大生は真面目だから、本当の自分を見つけようとする。「“本当の自分”なんてないよ」っていつも言うんだけど、「でもあります!」みたいな反論をしてくる子も結構いる(笑)。
西村:平田さんに反論している学生を私も見かけたことがあります(笑)。
平田:ああそう(笑)。それでね、「え?じゃあ、君のいう本当の自分って何?」って聞くと、「頑固な自分です」「うん、そうだね」みたいな(笑)。あと、いま就職すること自体は以前より楽になったんだけれども、就活で自分探しをやるようになって、あれでみんな参っちゃうんですよね。自分に合う仕事というものにこだわるんだけど、そんなものあるわけないないでしょ?
今の学生たちは平成生まれで、日本という国が低成長になってから育っていますから、なかなか上向きの変化を実感できない。大きな企業や組織に入ってしまうとなおさらです。それで「これは自分に合った仕事ではない」って思ってしまうんだけれども、「そうは言っても、君が入る部署は20〜30人で構成されていて、生物に例えれば、君が入ったことによって20分の1の細胞が入れ替わっているんだから、その組織は相当大きな変革をきたしているはずなんだよ」とよく学生たちに説明しています。
例えば「本当に自分に合ったパートナー」を見つけられるかって考えたら、地球上にいる異性の35億人をチェックしないといけないわけですよ(笑)。それをやった後に、自分がセクシャルマイノリティだったと気がつく場合もあるわけです。そうすると、さらにあと35億人チェックしないといけない(笑)。実際にそういうことはできないので、「まあ、こいつでいいか」っていうふうに、私たちは人生を営んでいるはずなんですよね。仕事もそうで、自分も変わるけれども、仕事の対象も変わるっていうことです。そこがなかなか実感しにくい世の中になっているんだろうなと思うんですね。
相手の立場には、立てない
西村:私は、病院で看護実践がどのように成り立っているのかを調査する仕事をしているんですが、病院ではだいたい1セクション(病棟)に20〜30人の看護職がいます。春に新人が入ってきて、途中でも人が入れ替わります。一見その病棟は細胞(看護師)が入れ替わっても、変わらずそれまでの病棟のあり方を維持しているように見えるのですが、1人が入れ替わると、その新しい人の質問やちょっとした戸惑い、動きなどが病棟全体を変えていく。いつもは誰もそんな質問をしないのですが、新しい人はルーチンがわからないので聞く。で、質問されたほうは「そんなこと自分で考えてごらんなさい」って厳しい応答をして(笑)、言われたほうも驚く。
でも、その質問はいい刺激を与えていて、そこは病棟が変化する入り口でもありますね。そして質問をしなくなった頃には、知らない間にここは自分の病棟だと認識し、いろいろなものが見えてくる。たとえ質問をしたとしてもルーチンの中での質問なので、過激ではなく、簡単に受け入れられるわけです。
平田:今はどこでもコミュニケーションの問題が切実なので、僕は医療系や福祉系の大学に呼ばれることが多いのですが、3〜4年生くらいの、つまり現場に出る前後で学校を辞めちゃう学生が一定数いて、その子たちは「患者さんの気持ちがわからない」って言うんですよ。だから「本当の自分じゃない」と言われた時と同様に、その子たちには「いやいや、患者の気持ちはわからないに決まってるじゃん」って言うんです(笑)。
「だって、君、患者さんじゃないでしょう? 障害者でもないでしょう? わかるわけないじゃん。でもね、20年も生きてきたんだから、とてつもなく悲しかったこととか、とんでもなく寂しかったことはあるんじゃないの? そこから類推していくしかないんじゃないの?」ってよく言うんです。
もう1つ、「冷静になって考えてみよう。ベテランの看護師さんが、何人も患者さんを抱えていて、その1人ひとりと同化して同情していたら身が持たないでしょう?」「だから、大人は少しずつ接点を見つけてコミュニケーションをとっているんだよ。『子育て大変ですね、うちも大変だったんですよ』とか、『母親の介護大変らしいですね、今、うちの親戚が大変なんですよ』とかね」と話したりします。
この2つのセリフは、まったく同化していないんですよ。だって「うちも大変だったんですよ」って、その人はもう子育てが終わってますからね。それから「うちの親戚が大変なんですよ」って自分のことじゃなくても、何か接点があればコミュニケーションは成り立つんです。
コミュニケーションのうまい人は、その接点を見つけてコミュニケーションをとっているんだけれども、真面目な子、看護や介護に進もうと思うような子ほど「相手の立場に立ちなさい」って教えられて育てられてきている。でも現場に行ったら相手の立場になんて立てないから「私は看護に向いていない」って折れてしまう。だから、ちょっと適当なほうがいいんだけれども、看護で適当っていうのも心配なので、そこをどうするかですよね。
西村:私、「相手の立場に立ちましょう」って、今日の授業でも……。
平田:あ〜言った?(笑)。気をつけてください、相手の立場には立てません(笑)。
西村:ただ、それは「相手を理解しようと努力をする指針」として伝えています。
平田:そうですね。演劇の話に戻すと、いじめのロールプレイを小中学校でよくやるんですけれども、これも経験の浅い先生ほど「いじめられた子の気持ちになってごらん」ってすぐ言うんですよ。だけど、いじめられた子の気持ちがわかるなら誰もいじめないでしょう。いじめられた子の気持ちがわからないから、いじめちゃうんだし。
日本のいじめ問題の深刻なところは、いじめている側にいじめているという意識が希薄なところです。だから「いじめられた子の気持ちになってごらん」と言っても「俺はいじめてないもん」って話になっちゃうんですね。でも、いじめっ子側にも親や兄弟、友だちなど、他の人から何かをされて嫌だった経験はあるんですね。
「ほら、1週間前にA君から何かされて嫌そうにしていたのと、さっきのBちゃんは似てるよ」って言うと、ちょっと会話の回路が開けてくる。もちろん小学生だったら「違うもん、あれはAが絶対悪いんだもん。さっきの僕は遊んでただけだもん」などと反論する。でもそう言ってくれれば教員としてはチャンスです。「そうかなあ、先生から見たらすごく似てたけど……。じゃあ、AちゃんとBちゃん、そして君にとってのいじめといじりと遊びはどこがどう違ったんだろう?」って問いかけることができる。
いじめられた子の気持への同情とか同化を強いると、オールオアナッシングになっちゃうんです。医療系でもよくロールプレイをやるじゃないですか。これ、本当に指導がうまくいかないと、オールオアナッシングになっちゃうので、もう少し揺れの部分があるといいですね。
例えば、私、日本糖尿病学会の方たちとお付き合いがあるのですが、すごく大きな学会で、15,000人くらい会員がいる。医師、看護師、ケースワーカー、栄養士、そしてご家族、患者さんなどステークホルダーも多く、例えば医師が栄養士の立場に、看護師がご家族の立場に立つロールプレイをよくやるそうです。だけど、ただ立場を入れ替えるだけなら、それは教科書でも学べますよね。それで、学会の中に「糖尿病劇場」●3というロールプレイをやっている先生たちがいて、すごく人気があり、学術集会でやっても毎回満席で立ち見も出るほどです。
西村:はい、聞いたことがあります。すごい人気です(笑)。
平田:そんな彼らが僕のところで学ぶようになってから、劇の内容がだんだんと込み入ったものになってきました。「おじいちゃんが糖尿病で、娘さんはシングルマザーで、お孫さんと3人暮らし。娘さんは働きに出ていて、普段はおじいちゃんとお孫さんがずっと一緒にいる。ある日、お孫さんが大好きなおじいちゃんのためにケーキを焼いてくれました。さあ、このケーキ、どうしましょう?」みたいにね(笑)。
観ていた糖尿病分野の医療従事者の方たちも、すごく納得し共感して「これだよね、困るのは」って(笑)。今どき、お菓子をバクバク食べている患者はいないし、いてもノウハウが確立しているから指導すればいい。本当に困るのはこういうときだよねって。つまり、人間が本当に困るのはどういうときなのか、ということを考えるのには演劇は非常に有利だと思います。
演劇がもたらす、自分を見つめ直す時間
西村:実は、7年前にうちの大学(首都大学東京)でも演劇ワークショップの授業を始めました。最初は、私が平田さんに刺激を受けて提案したのですが、その後は同僚の先生が方が、色々なアイディアを出して新たなスタイルのワークショップに発展させてくれています。意外と効果的なのですが、学生は嫌がるんです(笑)。演劇という言葉に抵抗を示しちゃうんですよね。
平田:そうですね。
西村:無理にやらせてはいけないんですが、看護職、理学療法士、作業療法士、放射線技師が参加者で、急性期の医療場面についてシナリオを書くところから2日間かけて行っています。1日目は自分たちの職種を演じ、2日目はほかの職種に自分たちがやっていることを教えて演技の指導をしながら、自分たちはほかの職種を演じる。
面白かったのは、ほかの職種の参加者を指導して演じてもらった劇を見ていると、「私たちだったらそういうふうには演じない。違う」って言うんです。指導したようには演じられないのと、看護職はこういうふうに動く、というある種の先入観があるのだけれども、相手は違う職種なのでそのようには動いてくれないんです。
「違うのに…」と思いながら、他方で「あの動きはまずいよ」となる(笑)。まずいと思うのは、私たち教員が無意識に描いてしまっている看護職の像があって、気づかない間にそれを学生たちに伝えているわけですね。教えられた側も、知らない間に教えられたことは自覚されないままに伝わるので、大切なことを言語化しないままに共有している。あるいはそれが、考え方や実践の前提となっていく。
その前提を共有した者同士で議論すると、時々、患者さんに対して無理な方向にケアの方針が向けられることがあります。例えば「糖尿病にはこういうふうな食事療法がベストだ」と思ってしまい、知らない間にそれを患者さんにも向けてしまっていることがあります。そのような状況に陥っていることに気づいた時は、私たちの期待と先入観を見直そうと指導しています。 むしろ、ワークショップによって気付かされたりします。
平田:これも、さまざまなところに書いてきたことですが、僕は大阪大学に呼ばれたときに、医学部出身の副学長から「医師や看護師は、昔は病気を治してあげれば誰からも感謝された。貧乏でも誇り高い商売だったけれども、今は医療が高度化しすぎて、そもそも何をもって治したというのか、誰にもわからなくなっている」と言われました。もう余命いくばくもない人にケーキを食べることを我慢させることが、本当に「治す」とか「延命」と言えるのかということです。
患者さんもいろいろで、1分1秒でも延命したいのか、痛みを緩和したいのか、家族と一緒にいたいのか、それぞれに違った希望があると思います。もしかすると1人でひっそり死にたい人もいるかもしれないし、相反する複数の気持ちがあったり、ご家族みんなの希望がバラバラだったり。それに医療の高度化で治療法がいくらでも出てきているけれど、いろいろ試してみるわけにもいかず、どれか1つを選ばなければなりません。
しかも説明義務の原則があるから、患者さんにもその原則は納得してもらわないといけない。いろいろな気持ちの中で何を選択していくかにおいて、これからはコンピュータがたくさん手助けしてくれるでしょう。「この症状だったら、過去の統計からこの治療法が一番いいですよ」という回答は出してくれる。だけど、その回答が患者さんの望む治療法なのかどうかは、まだ人間しか判断できないんですよね。そこがポイントだと思うんです。つまり、医療が高度化すればするほど医療コミュニケーションが必要になってくるという大きな課題が待ち受けている。
西村:そもそもですが、患者さんが前もって持っていた望みを私たちが確認し、それを実現するというのはちょっと違うんじゃないかと思っています。今日の授業でもそんな話をしたのですが、相手とかかわる中で自分が大切にしていたこと、自分がこうしたいと思うことが生まれてくる、つくられてくる、と考えるほうが事実に近いのではないかと。もちろん、患者さんには「治りたい」という切実な思いはあるけれど、われわれ看護師などさまざまな人と接する中で、希望というものががつくられたり、生まれたりするのではないでしょうか。
実は先日、こまばアゴラ劇場に行ってみました。大変お尻の痛い劇場で(笑)、それは冗談ですが、そこで平田さん原作の「思い出せない夢のいくつか」を拝見しました。劇中のやりとりを見ていると、一歩間隔を置いて次の言葉が出てくる感じで、何かが生まれてくることを待っているようでした。とても不思議な印象です。現実の会話だと、もっとパッパッと次の言葉が出てくるのですが、いつもの自分たちのリズムとは違う。そこに自分自身のことでも普段は気づかない、見過ごしてきた何かに気づく瞬間があるように思いました。
平田:劇場は非日常の空間だとよく言われるのですが、それはお化け屋敷みたいなものではなく、僕はよく「プロテスタントの教会」に例えるんです。要するに、自分を見つめ直すとか、自分の身体や言葉を見つめ直す時間を提供しているんじゃないかと思うんですね。まさに今おっしゃったように「普段はもっとしゃべる」みたいなことに気がつく。
とにかく今の社会は情報が溢れていて、誰もがしゃべらないといけないし、聞かなければいけない。僕はこれを「都市のストレス」と呼んできました。そもそも、演劇やお祭りには、単調な日常からくるストレスを解放する役割がある。人間は「過剰」を抱えた生き物ですので、例えば冬に雪で閉ざされた村なら、雪解けとともに春祭りをやったり、夏の一番厳しい時期に盆踊りをやったりして、単調な生活のどこかで発散をする必要がある。
でも現代社会はそれとは逆に、日常生活のほうが情報過多で「過剰」になってしまっている。しかもその中で「本当の自分」を見つけることが強迫観念にもなっているので、もうわけがわからない。
例えば、ブランド信仰ってありますよね。手取り20万円くらいのOLさんが、ボーナスが出ると40万円ぐらいのバッグを買っちゃったりして、ローン地獄に陥るような話をよく聞きます。バッグは毎日手に持つもので、背負ったり肩にかけたり、自分に合った大きさや、好みの色、形、耐久性などの要素がとても個人にとっては重要で身体性が高いものなんですけど、一方で「来年のミラノではどんなバッグが流行る」かとか「カンヌで叶姉妹がどんなバッグ持っていた」とか(笑)、そういう自分自身とは直接関係のない情報がものすごくたくさん入ってくるわけですよ。そうすると、自分の身体が何を欲しているのかがよくわからなくなってしまう。
つまり、ずっと座って何かを見るという経験が、今はほとんどなくなっていて、残っているのは禅の修行か劇場かっていうくらい(笑)。芸術家がつくるある1時間、そういう時間が大切なんじゃないかということなんです。
あるいは、最近は動物園の入場者が右肩下がりだそうで、むしろ水族館のほうに人気がある。みんなそこへ何をしに行くのでしょう。まさか、水族館に勇気や元気をもらいに行く人はあまりいない(笑)。つまり要するに、彼らは外の喧騒をシャットアウトしてクラゲを見たりしている。まさに禅や教会と似た空間なんだと思います。今の時代はそっちのほうが求められているんじゃないでしょうか。
西村:私は「あ、美味しそう」と思いながら見ていますが……(笑)。
平田:それは珍しいと思います(笑)。
● ● >
●1:青年団
平田氏らが1982年に結成した劇団。日本語と日本人の生活様式を起点に、新たな言文一致の劇言語と緻密な空間を創造することに定評がある。本拠地はこまばアゴラ劇場(東京都目黒区)。今後は兵庫県豊岡市に拠点を移す。
●2:大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
2005年4月、大阪大学の掲げる教育目標「教養」「デザイン力」「国際性」のうちの「デザイン力=柔軟な想像力」の育成を目的に設置された。2016年6月に名称変更。